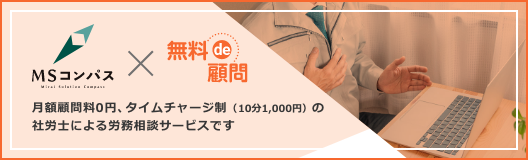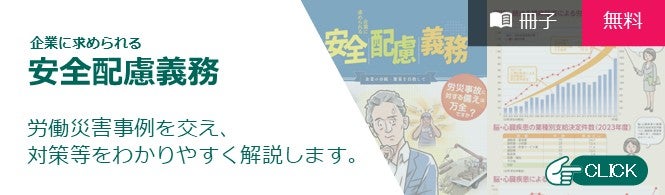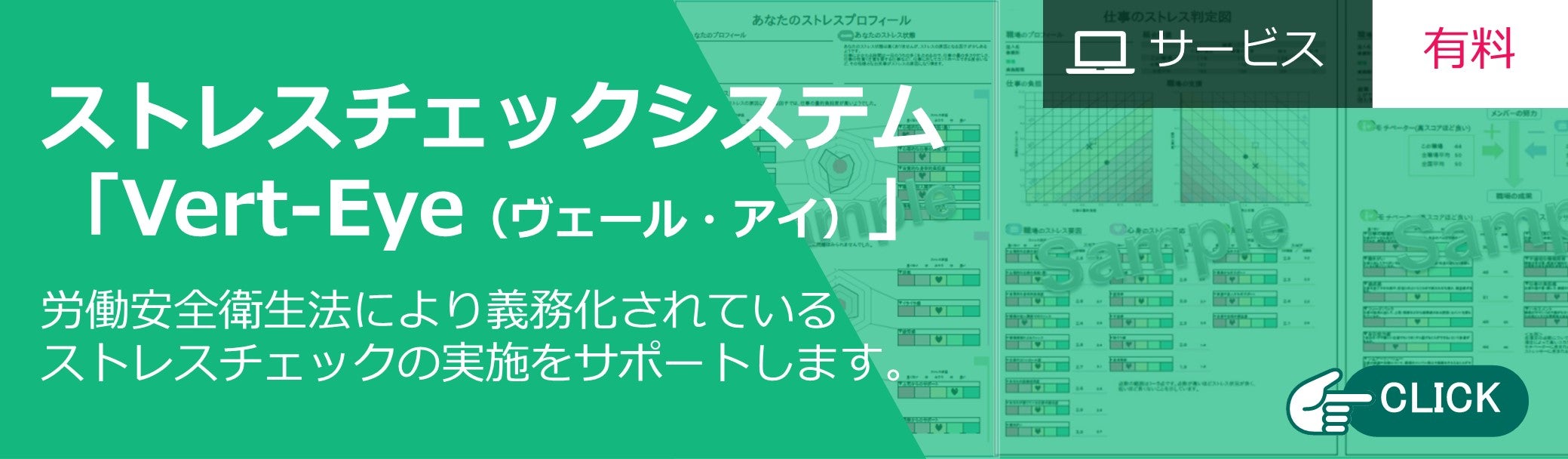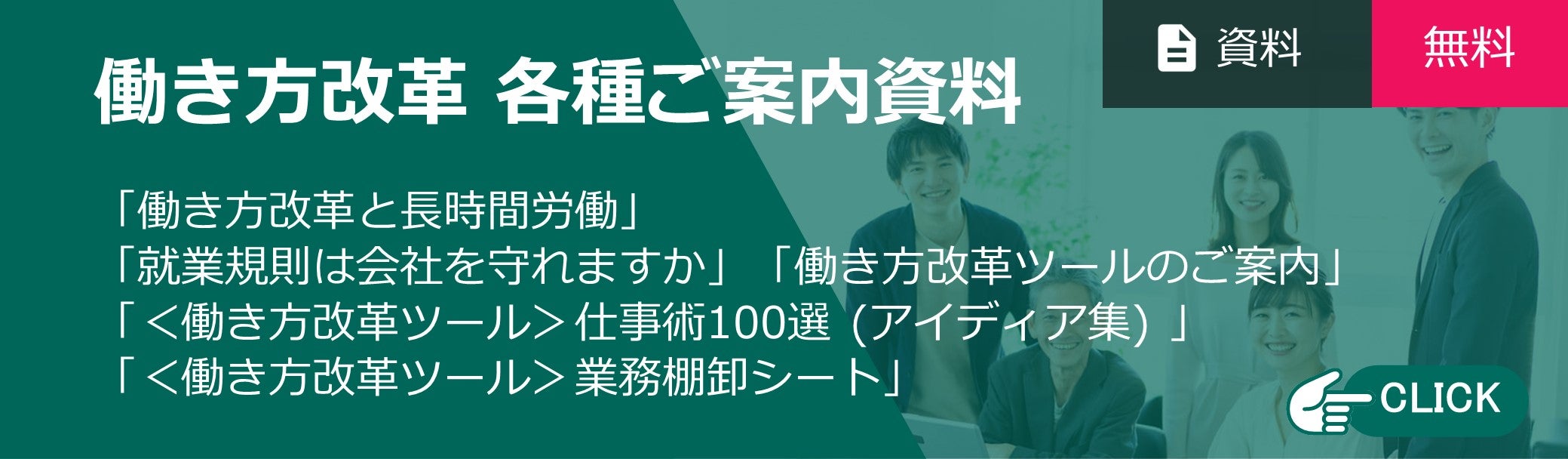【2026年】企業経営に関する法改正をまとめて紹介
公開日:2025年11月17日
法改正
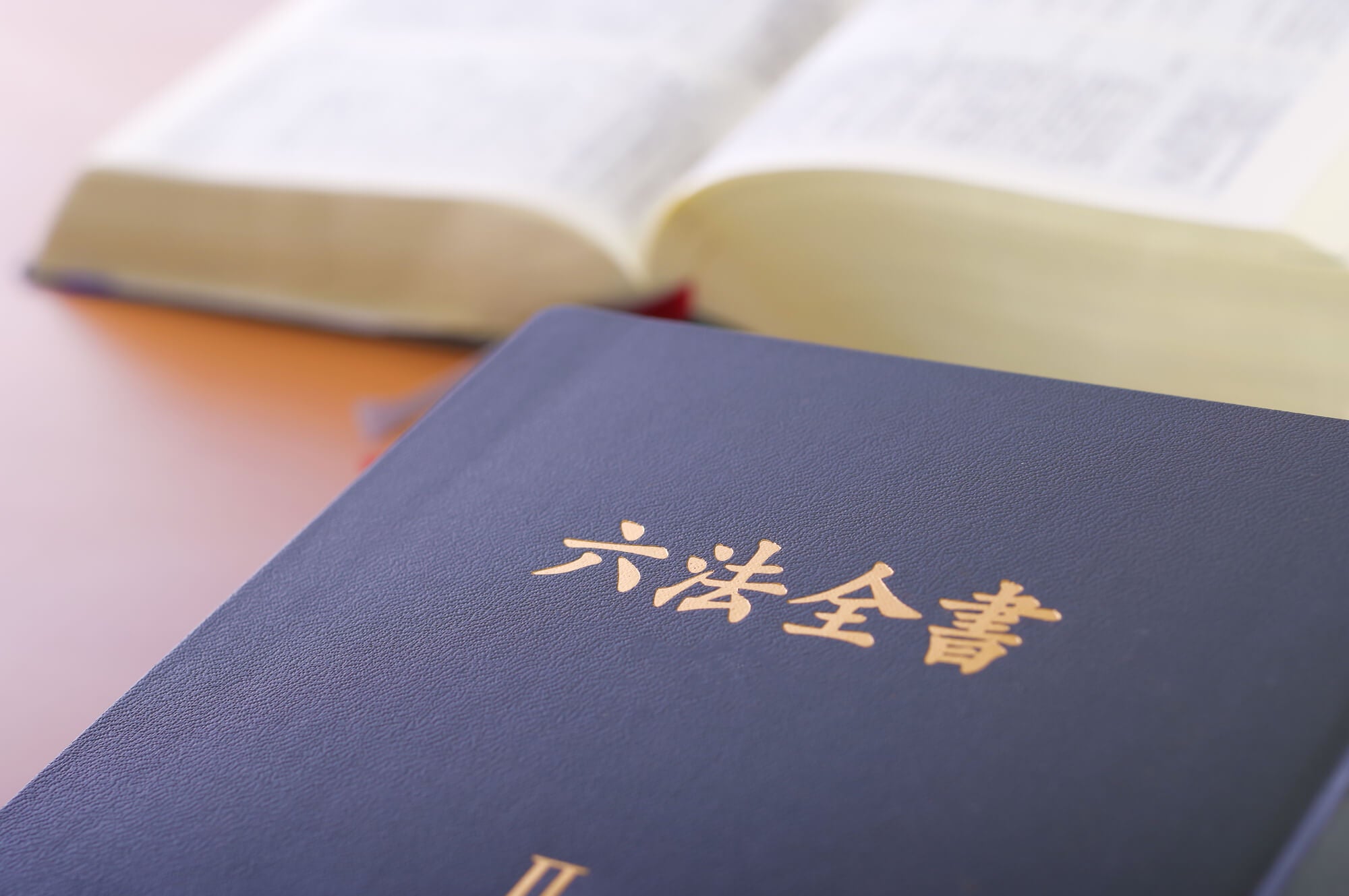
2025年には労働や事業に関するさまざまな法改正が行われ、その多くは2026年に施行される予定です。企業の運営に大きな影響を与える内容も多いため、できるだけ早い段階から改正のポイントをおさえておくことが大切です。
この記事では、2026年に施行される法改正について、特に企業経営と関連が強いものをピックアップしてご紹介します。
年金制度改正法の施行
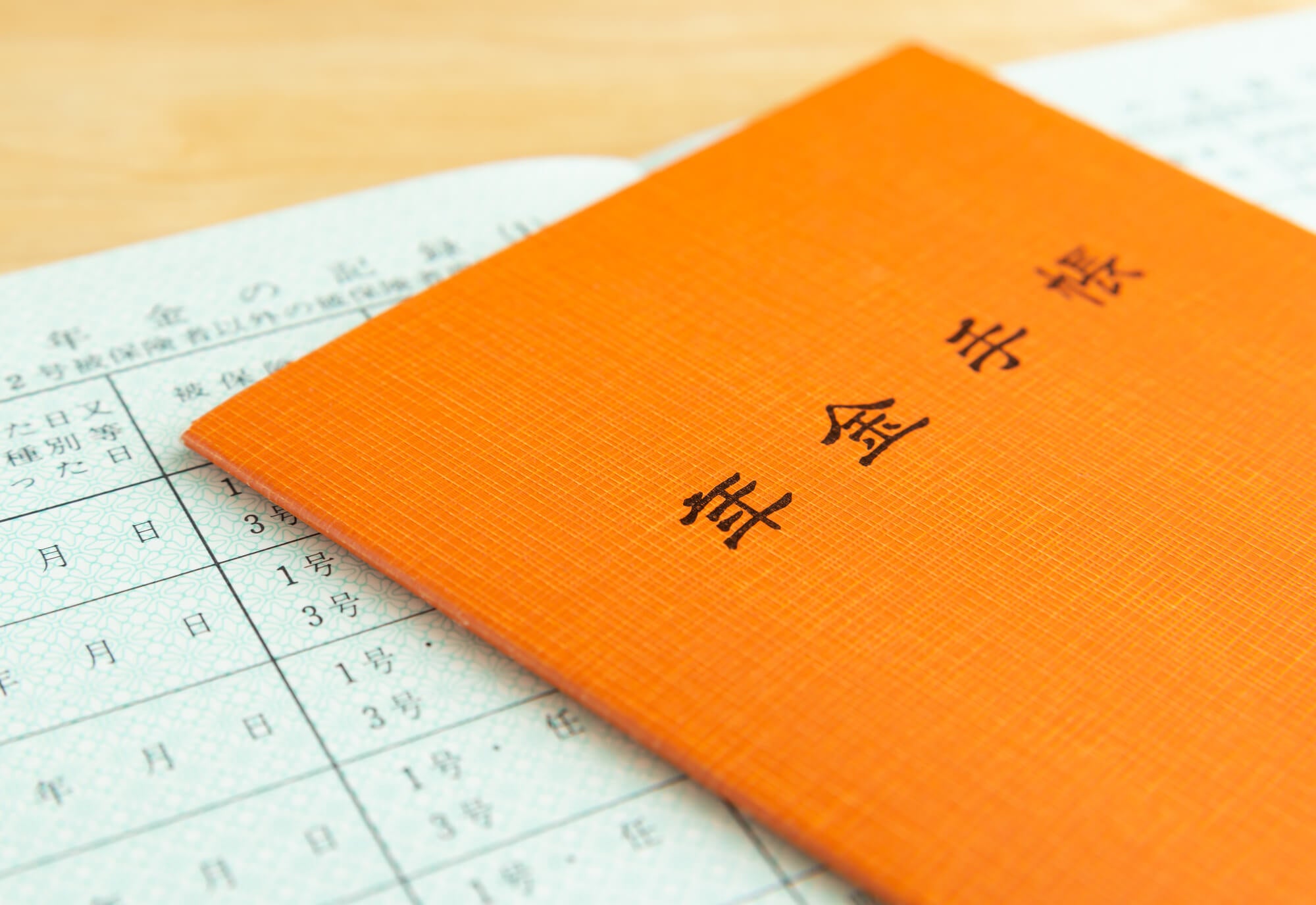
2025年6月13日に年金制度改正法が成立したことを受け、2026年4月1日からは新たな年金制度が施行されます。改正の主なポイントとなるのは、以下の6つです。
【改正のポイント】
・被用者保険の適用拡大等
・在職老齢年金保険の見直し
・遺族年金の見直し
・厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
・将来の基礎年金の給付水準の底上げ
・私的年金制度の見直し
ここでは、改正の具体的な内容について解説します。
【関連記事】
厚生年金保険について解説しています。
被用者保険の適用拡大等
改正後は社会保険の適用対象が拡大され、より幅広い人が加入できるようになります。具体的には、中小企業の短期労働者等を新たな対象としており、大きな変化としては2025年10月に導入が予定されている「賃金要件の撤廃」が挙げられます。
これまで、短期労働者については「従業員51人以上の企業等」で働く「給与の月額が88,000円以上」「かつ週の勤務が20時間以上」「雇用期間2か月以上」の方が加入対象となっていました。改正後は月額88,000円以上の要件が撤廃され、より多くの短時間労働者が加入できるようになります。
また、企業要件も2027年から2035年の間に段階的に撤廃され、最終的には従業員10人以下の企業で働く短期労働者も対象となる予定です。なお、個人事業所については、現行法では常時5人以上を使用する場合は、法律で定められた17業種に限って社会保険の適用対象となっていました。
改正によって、2029年10月からは非適用業種(農業・林業・漁業・宿泊業・飲食サービス業等)が解消され、新たに設立される場合には被用者保険の適用事業所となります。
在職老齢年金保険の見直し
働く意欲のある高齢者が、年金を減額されにくくするために、在職老齢年金の見直しが行われます。一定収入のある厚生年金受給者の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を「50万円から62万円に」引き上げることとなりました。
これにより、新たに20万人が年金を全額受給できるようになり、高齢者の働き控えの緩和が期待されています。
遺族年金の見直し
遺族厚生年金の男女格差を解消するとともに、子どもが受け取りやすくすることを目的として、遺族年金の改正も行われます。18歳未満の子がない20~50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とすることで、男女差解消を図る仕組みです。
ただし、配慮が必要な場合は、5年目以降も給付が継続されます。それに併せて、有期給付の収入要件は廃止され、年金額は増額されることとなりました。
また、2028年4月からは、父・母と生計を同じくしている子どもも、遺族基礎年金を受け取れるようになります。これにより、例えば夫の死亡後に妻が収入要件を超えるほどの稼ぎがあったとしても、子どもは遺族基礎年金を受け取ることが可能となります。
厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
厚生年金等を計算する際の「標準報酬月額」については、上限額が「65万円から75万円へ」段階的に引き上げられることとなりました。これにより、現役時代の賃金に見合った年金が受け取れるようになります。
将来の基礎年金の給付水準の底上げ
公的年金制度の所得再分配機能の低下により、基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させる措置を講じる旨の規定が追加されました。これは、経済の推移に合わせて、基礎年金の水準が下がってしまうことを防ぐための措置です。
現行の給付水準では、将来的に経済が好調に推移する場合は、年金の水準もおおむね維持されます。一方、経済が好調に推移しない場合には、基礎年金の水準が低下してしまう点が問題視されてきました。
そこで、2029年に予定されている次の財政検証によって、給付水準の低下が見込まれる場合は、必要な法制上の措置がとられることとなります。
私的年金制度の見直し
私的年金については、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限が、70歳未満までに引き上げられる予定となっています。また、企業型DCの拠出限度額も拡充される予定であり、これらは公布から3年以内に実施される見込みです。
また、企業年金の運用の見える化(情報開示)を行うため、厚生労働省が情報を集約して、公表するという取組も盛り込まれています。こちらは、公布から5年以内に実施される予定です。
企業型確定拠出年金について解説しています。
改正労働安全衛生法の施行

2025年5月に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号)が成立し、その多くは2026年4月1日に施行されることになっています。改正の主なポイントは次のとおりです。
個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
2026年4月1日からは、既存の労働災害防止対策に、個人事業者も取り込むための措置が実施されます。具体的には、注文者が講ずべき措置を定め、「職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約」の履行に必要な整備を行うものとされています。
また、改正法には、個人事業者自身がそれぞれ講ずべき措置や、業務上災害の報告制度等を定めるとの内容も盛り込まれています。ただし、個人事業者が講ずべき措置や業務上災害の報告制度等の一部は、2027年1月1日に施行予定です。
また、注文者が講ずべき措置については、一部が公布日に施行されているものの、残りは2027年4月1日に施行予定となっています。
【関連記事】
労働災害の判例と労働災害発生状況、企業に求められる安全配慮義務や労働災害が企業に与える影響と対策について、事例を交えながら分かりやすく解説しています。
職場のメンタルヘルス対策の推進
職場のメンタルヘルス対策の強化措置として、「ストレスチェック」の義務化対象の拡大が挙げられます。具体的には、努力義務となっていた「労働者数50人未満の事業場」についても実施が義務化されるという内容です。
ただし、施行は公布から3年以内に政令で定める日となっています。
化学物質による健康障害防止対策等の推進
化学物質による健康障害防止対策としては、3つの措置が盛り込まれています。1つめは、化学物質の譲渡等実施者に課せられた「危険性・有害性情報の通知義務」の違反に、罰則を設けるというものです。
これは、公布後5年以内のうち政令で定める日に施行される予定です。2つめは、化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認めるというものであり、2026年4月1日に施行されます。
ただし、代替を認めるのはあくまで成分名のみであり、人体への作業や応急の措置等は対象となりません。3つめは、有害物質を扱う作業者にサンプラーを装着して検査する「個人ばく露測定」について、作業環境測定の一つとして位置付けるというものです。
作業環境測定士等による適切な検査の担保を図るための措置であり、2026年10月1日に施行される予定です。
機械等の労働災害の防止の促進等
2026年4月1日からは、ボイラーやクレーン等に係る製造許可の一部や、製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲が拡大されます。これまでも、民間活力の活用と言う観点から、検査制度の民間への移管が進められており、今回の改正でさらに取組が推進される形です。
また、2026年1月1日からは登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件が強化され、検査基準への遵守義務が課されます。
高齢者の労働災害防止の推進
60歳以上の就労者が増加するとともに、労働災害の死傷者における60歳以上の割合も高まっていることを受け、高齢者の労働災害防止の推進が行われます。具体的には2026年4月1日から、高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を、すべての事業者の努力義務とするというものです。
必要な措置については明示されていませんが、厚生労働省がまとめている「エイジフレンドリーガイドライン」によれば、「安全衛生管理体制の確立」「職場環境の改善」「健康や体力の状況把握」「健康や体力に応じた対応」「安全衛生教育」等が取組として挙げられています。
中小受託取引適正化法(旧:下請法)の施行

2026年1月1日には、従来の下請法が「中小受託取引適正化法(取適法)」に名称を変え、新たに施行されます。取適法の主な改正ポイントは、以下のとおりです。
【改正のポイント】
・用語の変更
・適用対象の拡大
・禁止行為の追加
・面的執行の強化
・その他
【関連記事】
下請法改正のポイントについて解説しています。
用語の変更
取適法では実態をより適切に表現するために、下請事業者を「中小受託事業者」へ、親事業者を「委託事業者」に呼称が変わります。また、下請代金は「製造委託等代金」、下請代金支払遅延等防止法は「製造委託等に係る中小事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」へと名称が変わります。
適用対象の拡大
従来の下請法では、適用対象として「資本金による区分」のみが用いられてきました。取引の内容に応じて、一定以上の資本金を持つ会社を「親事業者」、一定以下の資本金を持つ会社を「下請事業者」とし、その条件に該当する場合のみ下請事業者を保護するという仕組みです。
今回の取適法の施行により、新たに「従業員数による区分」が加わり、より幅広いケースで適用されることとなりました。具体的には取引内容に応じて、従業員300人超あるいは従業員100人超の会社から、それ以下の規模の事業者へ委託する際も適用対象となります。
また、対象取引に「特定運送委託(軽貨物ドライバーへの発注等)」が加わり、取引内容の面でも適用対象が拡大されることとなりました。
禁止行為の追加
従来の下請法では、委託事業者(親事業者)側に対し、さまざまな義務と禁止行為が定められていました。例えば、受託事業者に責任がない状態での「受領拒否」「減額」「返品」「支払遅延」の禁止や、支払期日を定める義務等です。
さらに、取適法の施行によって、新たに「協議に応じない一方的な代金決定」と「手形払い」が加わりました。これにより、委託事業者には4つの義務と11の遵守事項が課されることとなります。
面的執行の強化
従来、事業所管轄庁に対して与えられていたのは「調査権限」のみでした。取適法では、新たに指導・助言権限が付与され、「面的執行」が強化されることとなります。
また、「報復措置の禁止」に関する情報提供先にも、従来の公正取引委員会および中小企業庁長官に、事業所管轄庁が加わります。報復措置とは、受託事業者が委託事業者の不公正な行為を告発したことを理由に、何らかの不利益な取扱いが行われることを指します。
改正により、万が一委託事業者から報復措置が行われた時に、中小受託事業者が申告しやすい環境が確保される仕組みです。
その他
その他の改正ポイントとしては、製造委託の対象物品への「金型以外の型等」の追加が挙げられます。また、書面交付義務については、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メール等の電磁的方法を選べるようになります。
労働基準法の大幅改正の見通し

厚生労働省では2024年1月に、「労働基準関係法制研究会」を開催し、2025年1月には労働基準法の改正案をまとめた資料が公開されています。その内容は、2026年の「労働基準法改正」に反映され、2027年4月から施行される見通しとなっています。
【改正(予定)のポイント】
・14日以上連続勤務の禁止
・法定休日の特定義務化
・勤務間インターバル制度の義務化
・有給休暇時の賃金策定におけるルールの明確化
・副業・兼業者の割増賃金算定に関するルールの見直し
・法定労働時間の週44時間の特例措置廃止
14日以上連続勤務の禁止
現行の労働基準法では、法定休日として「1週間のうち少なくとも1日の休日」を設けることが義務付けられています。しかし、業務の都合等で難しい場合には、「4週間で4日の休日」の変形休日制を導入することで、週休1日に縛られない特例も認められています。
そのため、場合によっては休日を連結させる等の方法で、長期の連続勤務も可能です。こうした極端な連勤による負荷の発生を防ぐため、改正案では「連続14日以上の勤務禁止」が盛り込まれる見通しとなっています。
具体的には、変形休日制の特例を「2週間で2日の休日」に変形し、事実上の連続勤務の上限を13日までとする提言がなされています。
法定休日の特定義務化
現行法における法定休日は、必ずしも曜日が定まっているわけではありません。そのため、働くリズムが保たれにくくなるとともに、法定休日と法定外休日の区別が曖昧になってしまうという問題が生じます。
その結果、休日労働による割増賃金の取扱いもグレーになってしまう恐れがあるため、改正後は法定休日の特定義務化が盛り込まれる見通しです。
勤務間インターバル制度の義務化
「勤務間インターバル制度」とは、勤務の終了時刻と翌日の始業時刻の間に、少なくとも「原則11時間」のインターバルを確保するという制度です。労働者の休息時間を十分に確保し、労働災害や健康被害を防止するための取組であり、2019年から努力義務として導入されています。
しかし、2023年1月時点での導入企業割合は6.0%となっており、実施はなかなか進んでいないのが現状です。こうした状況を受け、法労働基準関係法制研究会では勤務間インターバル制度の実質的な義務化が提言されています。
ただし、義務化にあたっては、「インターバル時間を短くする」「一定の経過措置を設ける」等の緩和措置も検討されています。
有給休暇時の賃金算定におけるルールの明確化
現行法において、年次有給休暇取得時の賃金算定の方式は、「平均賃金方式」「通常賃金方式」「標準報酬日額方式」の3通りを選ぶことができます。一般的に、月給制で働く労働者については、どの方法を選んでもそれほど大きな差額は生まれません。
しかし、日給制・時給制で働く労働者については、平均賃金方式や標準報酬日額方式を用いると賃金が大きく減額されてしまう恐れがあります。そのため、改正後は原則として「通常賃金方式」のみを採用する方向性が検討されています。
副業・兼業者の割増賃金算定に関するルールの見直し
副業・兼業者の賃金の算定については、事業主が異なる場合でも労働時間を通算して計算することとなるため、法律上は割増賃金が発生することとなります。このため、企業が副業・兼業を許可するには、「自社以外の業務時間についても1日単位で細かく把握しなければならない」という負担が生じます。
こうした制度の仕組みが、企業による副業・兼業受け入れの大きなハードルになっていると考えられており、改正後は労働時間の通算ルールを適用しない方向性が検討されています。
まとめ
2026年にはさまざまな法改正が施行される予定であり、企業経営に影響を与えるものも少なくありません。特に年金制度や労働安全衛生、業務の受託・委託に関するルールは大きく改正されるため、内容を正しく把握しておく必要があります。
また、2026年には労働基準法の大幅な改正も予定されています。施行自体は2027年以降と考えられますが、早めに対応するためにも事前に動きをチェックしておきましょう。
2025年に実施された法改正のポイントについてまとめて解説します。
【参考情報】
2025年10月13日付 厚生労働省 「年金制度改正法が成立しました」
2025年10月13日付 厚生労働省 「社会保険の加入対象の拡大について」
2025年6月30日付 厚生労働省 「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」
2025年10月13日付 厚生労働省 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」
厚生労働省 「高年齢労働者の労働災害防止対策について」
2023年6月13日付 厚生労働省 「エイジフリーガイドライン」
公正取引委員会 「2026年1月から「下請法」は「取適法」へ!」
2025年5月付 公正取引委員会 中小企業庁 「下請法・下請振興法改正法の概要」
2025年1月8日付 厚生労働省 「労働基準関係法制研究会報告書」
2025年10月13日付 厚生労働省徳島労働局 「法定労働時間」