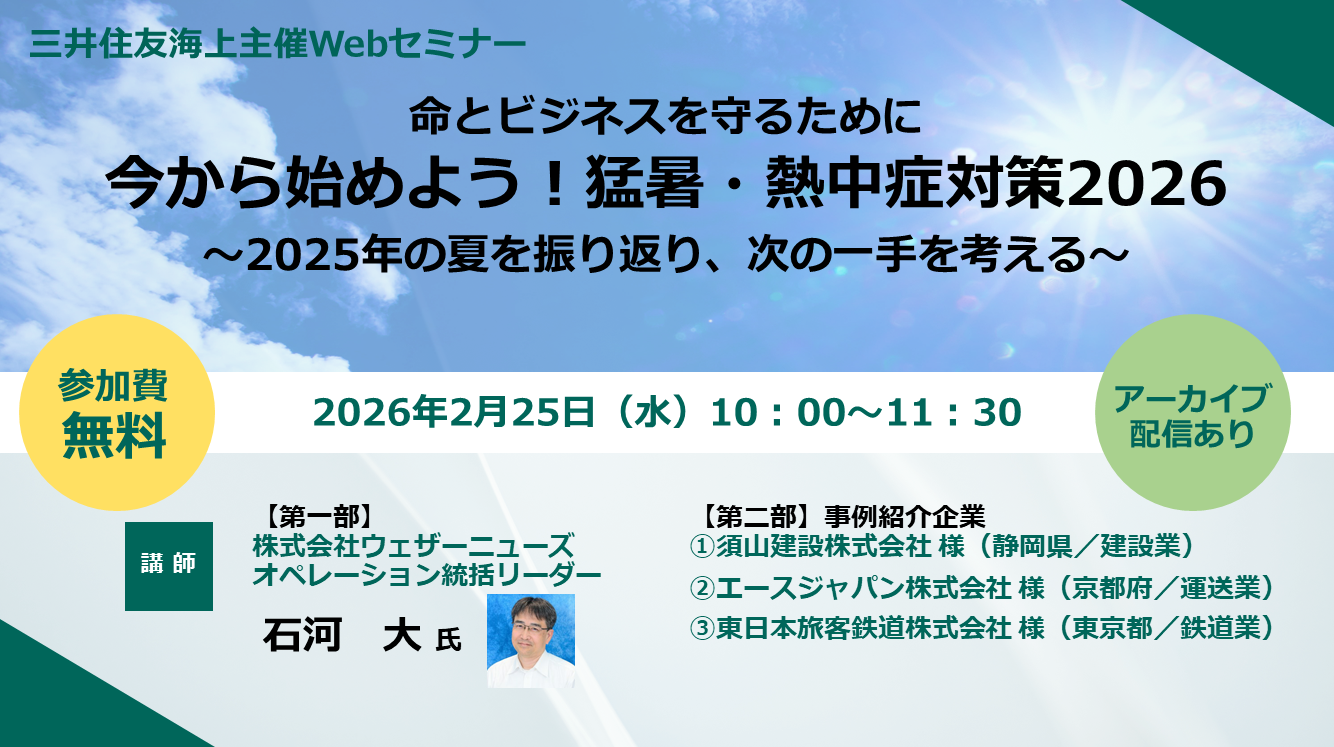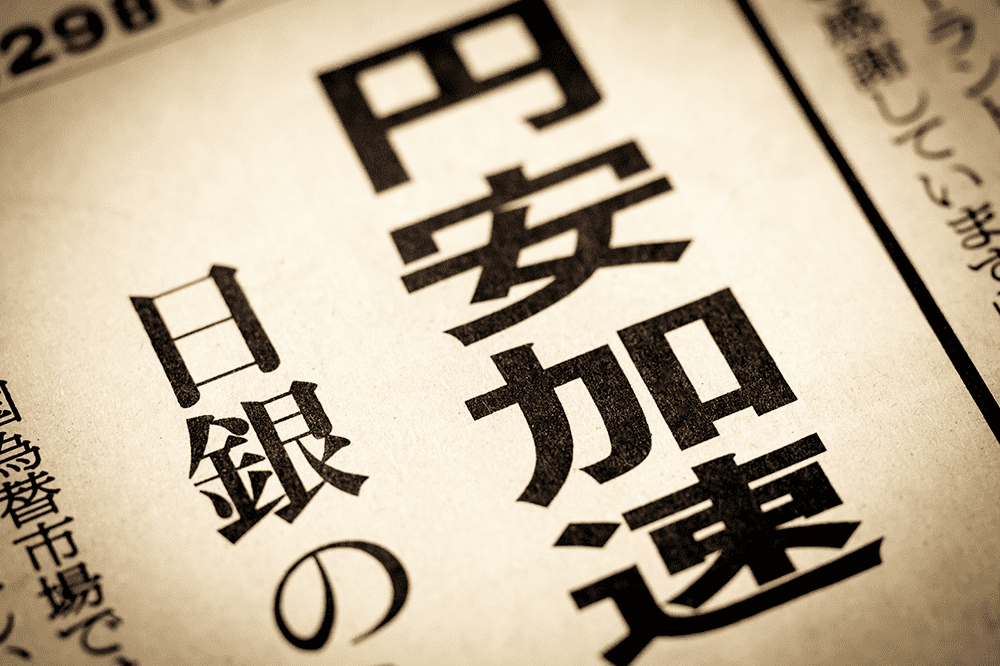今考える「勤務間インターバル制度」の導入と活用
公開日:2023年10月18日
人事労務・働き方改革
.jpeg)
【要旨】
■勤務間インターバル制度は、働き方改革関連法(2018年成立)に伴う法改正で努力義務とされたが、国内企業での導入率は低く、企業の多くがその必要性を感じていません。
■一方、直近では、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」に記載され、自民党より推進に向けた緊急提言が行われるなど、普及・拡大に向けた動きが加速しています。
■制度導入のメリットとして、労働時間の削減だけでなく、従業員のワーク・ライフ・バランスの確保や休養(睡眠)時間の確保が挙げられます。
■制度の効果的な活用にあたっては、①他の施策と同時展開、②外部発信によるセルフブランディングを企図し進めていくことが望ましいです。
勤務間インターバル制度をめぐる動き
(1) 勤務間インターバル制度の導入状況
勤務間インターバル制度は、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設ける仕組みです。(図1)。2018年に成立した働き方改革関連法において、労働時間等設定改善法の改正により、事業主の努力義務となりました。
.png)
しかし、国内の導入率は芳しくなく、厚生労働省の令和4年就労条件総合調査によると5.8%となっています。また、「導入予定はなく、検討もしていない」が80.4%でした。「導入予定はなく、検討もしていない」と回答した企業へ理由を聞いたところ、「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じない」が53.5%と多数を占めました。一方、「当該制度を知らなかった」が21.3%となっています。政府では、2021年改正の「過労死等の防止のための対策に関する大綱」において、以前よりあった目標を改定し、周知・導入拡大に努めています。
.png)
(2) 海外(欧州)の状況
国内ではこのような状況ですが、EUでは既に義務化されています。EU労働時間指令(1993年制定・2000年改正)では、「24時間につき11時間の休息期間付与」が義務とされ、各国の法律に基づき運用されています。ギリシャやスペインでは基準を超える12時間、ドイツやフランスでは11時間とされています。また、インターバル時間を遵守できない場合には代替日に繰り越すことができる、としています。また、EUを脱退したイギリスでも同様の法律があり、11時間の休息付与と代替措置が定められています。
(3) 国内における動き
国内と海外(欧州)で、大きく状況が異なりますが、昨今、国内において大きな動きが出てきており、普及・拡大に向けた動きが加速しています。また、働き方改革関連法は5年後に見直すとの“見直し条項”があることから、次回改定での義務化の議論もあります。以下、直近の動向をいくつか紹介します。
①「脳・心臓疾患の労災認定基準」への追加(2021年)
「脳・心臓疾患の労災認定基準」の改定により、労働時間以外の負荷要因として「勤務間インターバルが短い勤務」が追加され、勤務間インターバルが短い期間の程度(時間数、頻度、連続性等)や業務内容等が考慮されることとなりました。
②上限規制が猶予されている事業・業務における、義務化(2022年)
現在、働き方改革関連法(2018年成立)において、上限規制の適用を猶予されている医師について、2024年4月の適用開始にあわせ、9時間の勤務間インターバルが義務化されることになっています。また、バスやタクシー運転手などの自動車運転業務においては、改善基準告示の改正により、現在よりも1時間長い9時間の勤務間インターバルが義務化され、違反した事業者は行政指導の対象になります。また、9時間の義務化にあわせ、11時間以上の確保が努力義務とされました。
③人事院での検討開始(2022年)
2022年1月より人事院において、一般国家公務員の柔軟な働き方を検討する為、「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」にて、勤務間インターバル制度についても検討がされています。7月の中間報告では“引き続き検討”となっていますが、導入となれば、民間に先行する男性育休と同様に、社会全体に広がるきっかけになると見られているため、動向が注目されています。
④「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」への記載(2022年)
2022年6月に政府より出された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」において、「人への投資と分配(多様性の尊重と選択の柔軟性)」の項目で、「勤務間インターバル制度の普及を図り、長時間労働の是正を図る」と記載がなされました。
⑤自民党推進プロジェクトチーム(PT)による緊急提言(2022年)
2022年11月、自民党の雇用問題調査会・勤務間インターバル推進PTにおいて、制度推進のための提言をまとめ、厚生労働大臣へ提言書を提出。2023年度予算へ反映されました。
.png)
導入におけるメリット
(1) 労働時間の削減
(2) 安全配慮義務の履行
2つ目は、安全配慮義務の履行です。安全配慮義務とは、労働契約法第5条に定められている、使用者(企業)が従業員の健康や安全に配慮する義務です。十分なインターバル時間を確保できず、長時間労働が継続すれば、メンタル不調や過労死のリスクが高まることになります。
企業全体では超過勤務の機会が少ないと回答している企業であっても、超過勤務の実態のある従業員がいるのであれば、企業として勤務間インターバル制度を導入し、その意義を社内発信することで、企業としての責務を果たすことにつながります。
(3) 従業員のワーク・ライフ・バランスの確保
3つ目は、ワーク・ライフ・バランスの確保が挙げられます。従業員の生活時間の確保につなげることで、仕事と生活との調和が図ることに寄与します。ワーク・ライフ・バランスというと、育児や介護を行う従業員が注目されがちですが、病気の治療や趣味、自己研鑽等もすべて「ライフ」であり、対象はすべての従業員です。ワーク・ライフ・バランスが維持されることで、従業員はいきいきと働くことができ、仕事へのモチベーションにもつながります。また、ライフにおけるインプットがワークにおけるイノベーションや個人の成長につながることも期待されます。さらには、職場の活性化やワーク・エンゲージメントの向上が、従業員の採用や定着の面でも、効果的であるところは知られているところです。
(4) 休養(睡眠)時間の確保
そして、4つ目は休養(睡眠)時間の確保が挙げられます。睡眠不足は、従業員個人のメンタルヘルス不調や生活習慣病等につながり、万一不調をきたせば、組織における円滑なコミュニケーションや業務遂行を阻害することにつながります。前掲のバスやタクシーなどの自動車運転業務では、睡眠不足に起因して大事故につながることもあります。
これら不調や睡眠不足に起因する事故等の予防・改善には、毎日の適切な睡眠時間の確保と睡眠の質の維持が大切です。睡眠は上限規制のように月単位で管理とはいきません。可能な限り、毎日、同じサイクルで個人に適した睡眠時間を確保することが肝心です。企業は、従業員に継続してしっかり睡眠をとらせることで、従業員の健康を守り、労災等の防止やプレゼンティーズム(※)による生産性損失の低減、中長期的な疾病の予防、組織の活性化等が期待できます。
昨今の勤務間インターバル制度普及に関する論議の中では、睡眠時間の確保をその根拠とする論調が強くあります。OECDの調査(2021年版)によると、日本人の平均睡眠時間は7時間22分と、加盟国30カ国中最下位となっており、日本全体では、15兆円の経済損失になるとの試算(米国・ランド研究所)も出ています。また、2022年に慶應義塾大学の山本勲教授が従業員の睡眠時間と企業の利益率に正の相関があることを発表し(図2)、企業における従業員の睡眠時間の確保に資する取り組みについて、関心が高まっています。
(※)プレゼンティーズム:出勤しているものの、健康上の影響から、自覚の有無にかかわらず本来の能力を発揮できていない状態
.png)
制度導入における課題点と対応策
ここからは、制度導入における課題点と対応策について紹介します。なお、導入にあたっては厚生労働省の「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」も参照ください。
(1) 経営層・管理職、従業員の理解
まずは、経営層の理解が進まなければ、当然のことながら制度導入には至りません。経営層への説明については、①ワーク・ライフ・バランスや健康経営、生産性の観点からもメリットがあること、②企業の状況に応じて制度設計が可能であり、多くの従業員の負担になるものではないこと、③コストもかからず、まだ導入率も高くないので会社のPRに活用できる、といった点の説明が良いでしょう。
その上で、勤務間インターバル制度の意義や自社で導入する目的を整理し、経営層から管理職・従業員へ発信し浸透を図ることが望ましいです。また、従業員の睡眠確保を目的とする場合、従業員が会社が意図したように睡眠に時間を充てないことも懸念されるので、健康経営を進める中で、定期的に研修等を実施し、従業員の意識と行動の変容を促したいです。
(2) 制度の基本設計の検討
次に制度の基本設計についてです。まず、「インターバル時間をどうするか」「インターバル時間確保のため翌日の始業時間を超えた場合の取り扱いをどうするか」などが検討課題となります。前述の通り、法的拘束力はない為、自社の状況を確認の上、検討・決定する必要があります。
まず、インターバル時間については、2022年就労条件総合調査では、10時間22分が平均とされています。一方で、所定労働8時間・休憩1時間の企業において、インターバル時間を10時間22分と設定した場合、1日あたり4.5時間程度の残業が可能となります。月20日勤務で計算した場合、月の時間外労働は90時間となり、過労死ラインの80時間を超えます。設定においては、導入目的をふまえて検討ください。なお、導入企業の中には、全員一律とせず職種などにより分けているケースもあります。
次に、インターバル時間の確保により、翌日の始業時間を超えた場合の取り扱いです。9時始業・インターバル時間12時間としている会社で、前日22時まで業務を行った場合をイメージください。翌日は10時開始となるが、9時から10時の勤務時間の取り扱いについて、①重複部分を勤務したものとみなす、②所定労働時間の始業を繰り下げる(終業は変更しない)、③所定労働時間の始業・就業ともに繰り下げる、が考えられます。2018年の調査では、①重複部分を勤務したものとみなすが回答の半数を占めていました。この点については、極力、管理が煩雑にならない方法を検討ください。
.png)
(3) 緊急時の対応等
勤務間インターバル制度の導入にあたっては、緊急時の対応についての不安から導入が見送られるケースもあります。また、夜間も含めて常時顧客対応が必要なケースやシフト勤務で前日の勤務状況で翌日の勤務予定が変更になると業務に支障が出るケースなども考えられます。
この点については、適用除外ルールを設定することで導入へのハードルを下げることが可能です。一方で、適用除外ルールを作りすぎると、制度が骨抜きになってしまい、本来の目的を達成できなくなる可能性があるため、制度開始後は徐々に適用除外を減らしていくことにも取り組むべきです。
また、適用除外ルールについては、「管理職は除外する」といった役職・職種での線引きも可能ですが、健康経営やワーク・ライフ・バランスを制度導入の目的とするのであれば、管理職も含め、全員を対象とすることが適切です。
(4) 就業規則の変更・勤怠システムの改定
次に、制度導入に伴う就業規則の変更や勤怠システムの改定についてです。この点については、導入企業の中でも状況が分かれるところですが、導入時においては、対応不要と考えられます。運用する中でルールを変える必要が出てくることも想定されるため、一定の期間をトライアル期間とし、状況確認した上で、就業規則や勤怠システムに反映するのが良いです。
制度導入している企業で、就業規則の変更や勤怠システムの変更を行っていない企業の意見としては、前者では制度開始後に問題があれば制度設計の変更が容易なことや遵守できなかった場合に懲戒等の取り扱いが導入の趣旨にそぐわないといったことが挙げられています。また、後者では、費用面や担当者の負荷が挙げられており、エクセルシートにて管理している企業事例もあります。
(5) 多様な働き方の実現との調整
新型コロナウィルスの流行をきっかけに多くの企業で、働く場所や時間にとらわれない多様な働き方の実現に向けた環境整備が進みました。リモートワークにフレックス勤務など、それ自体は歓迎すべきものですが、制度導入に際しては、「働き方が縛られる」「自由な働き方を阻害する」といった意見が挙がることも考えられます。
例えば、「育児を行っている従業員が、夕方から家事・育児の為に中抜けし、子どもを寝かしつけた後に業務を再開し、22時に終了。翌朝は、6時から始業。」といった場合を考えてください。インターバル時間は8時間ですが、会社ルールで8時間超となっていれば、このような働き方は、できないことになります。
適用除外とすることも考えられますが、従業員の健康や安全配慮義務を考慮し、働き方を是正していくことが望ましいです。企業においては、在宅勤務で従業員の働き方が多様となり、個々の労働時間を管理しきれない状況も考えられる中、個々の従業員の健康を守り、メンタル不調や過労死を予防するセーフティーネットとして制度運用していくべきでしょう。
制度をどのように活用していくか
最後に、ますます注目がされるであろう勤務間インターバル制度ですが、企業として、より高い効果を生むためにどのように活用すべきか、ポイントをお伝えします。
(1) 他の施策と同時展開
勤務間インターバル制度は、シンプルな制度であるものの企業や担当者側の理解が進んでないがゆえに、不要と判断されてしまうか、あるいは導入しても活用されないままとなっているケースもあるのではないかと考えます。
健康経営優良法人認定制度(大規模法人部門・中小規模法人部門)ではワーク・ライフ・バランス(労働時間削減に関する取り組み)項目の設問に設定されており、健康経営に取り組む企業の中にも、導入している企業は一定数ありますが、例えば従業員の睡眠改善とセットで取り組んでいるといったケースは多くはないのではないでしょうか。しかし、制度導入や見直しをきっかけとして、健康経営や働き方改革のテコ入れに活用できる可能性は大いに秘めています。制度単体で考えるのではなく、健康経営の枠組みの中で、睡眠施策などの健康施策や他の人事施策とセットで取り組むことにより、相乗効果を生み出すことができるでしょう。
(2) 外部発信によるセルフブランディング
そして、もう一つは外部発信によるセルフブランディングです。勤務間インターバル制度は従業員の労働環境改善につながる取り組みなので、ぜひ、情報開示を通じて、自社のイメージアップに活用ください。
勤務間インターバル制度の導入は、2022年のトピックスであった男性育休に比べて他社との差別化に有効であると考えます。理由として、男性育休の取得率は直近で13.97%ですが、勤務間インターバル制度の導入率は5.8%と、まだまだ希少価値が高いです。また、男性育休は一連の法令改定の中で、企業の社内環境整備が義務とされていますが、勤務間インターバル制度は任意の取り組みに位置付けられます。そして、男性育休の取得が男性従業員の状況に左右されるのとは異なり、勤務間インターバル制度の従業員への浸透や活用促進は企業主導で進めることができます。
このように、勤務間インターバル制度の導入や付随する取り組みの発信は、目に見える形での他社との差別化につながります。従業員の採用や定着に課題のある企業にとっては、効果的といえます。採用に苦労している特に中堅・中小企業はぜひ検討・導入ください。また、大企業においても、人的資本経営に関する開示が進む中で、新たなトピックスの一つになり得るでしょう。
<参考文献・HP>
① 勤務間インターバル制度 導入・運用マニュアル―職場の健康確保と生産性向上を目指して― (厚生労働省、2020年)
② 令和4年就労条件総合調査(厚生労働省、2022年)
③ 厚生労働省・雇用政策研究会資料アフターコロナに向けたウェルビーイングと生産性の両立(厚生労働省/慶應義塾大学 山本勲教授、2022年)
④ 働き方・休み方ポータルサイト(厚生労働省)
MS&ADインターリスク総研株式会社発行の健康経営インフォメーション2023年3月(No.5)を基に作成したものです。