カスタマーエクスペリエンス(CX)とは?意味と重要性、向上させるための方法を紹介
公開日:2025年9月1日
経営に関する全般
その他

近年のマーケティングでは、顧客の多様化やチャネルの細分化等により、従来とは異なるアプローチが求められるようになっています。そのなかでも、特に注目を集めているのが、「カスタマーエクスペリエンス(CX)」を意識した戦略の重要性です。
この記事では、カスタマーエクスペリエンスがなぜ重要なのか、基本的な意味とメリットについて解説します。その上で、カスタマーエクスペリエンスを向上させるための方法も詳しく見ていきましょう。
カスタマーエクスペリエンス(CX)とは?

「カスタマーエクスペリエンス(CX)」とは、日本語で「顧客体験」あるいは「顧客体験価値」を意味する言葉です。主にマーケティング分野で用いられる用語であり、顧客視点で商品・サービスを利用した時の体験価値を示します。
単に商品・サービスを購入してもらうだけでなく、カスタマーエクスペリエンスではそこに至るプロセスや、購入後のサポートまでを対象に捉えます。そして、購入や利用の「体験そのものの価値」を向上させるというのが基本的な考え方です。
なお、ビジネスの分野で「CX」と言う時には「コーポレート・トランスフォーメーション」を指すこともあります。こちらは、「企業変革」を意味する別の用語であるため、混同しないように注意しましょう。
合理的な価値と非物質的な価値
カスタマーエクスペリエンスは、「合理的な価値」と「非物質的な価値」の合計値で決まると考えられています。合理的な価値とは商品・サービスの基本的な機能・性能、あるいは価格のことです。
つまり、商品やサービスが持つ基本的な価値のことであり、誰がどのように販売しても価値の度合いは変わりません。また、企業同士の開発競争等によって、コモディティ化(一般化)しやすいという側面も持っています。
一方、非物質価値とは、感覚的な価値や心理的な価値といった感情面における価値を指します。例えば、「居心地の良い空間でリラックスできた」「求めていた商品を快適に探せた」といった価値のことです。
合理的な価値と比べて数値化が難しく、価値を感じる度合いにも個人差が大きいため、非物質的価値の追求は合理的な価値と異なるベクトルでの企業努力が必要です。しかし、商品・サービスの差別化を図る上では、特に重要なテーマと言えるでしょう。
カスタマーエクスペリエンスの具体例
商品の購入プロセスにおいて、カスタマーエクスペリエンスがどのように変化していくのか、一つの具体例をもとに見ていきましょう。ある家電製品の購入を検討する顧客A(成功例)と顧客B(失敗例)がいたと仮定します。
顧客Aは魅力的な広告を見て商品への関心を深め、店舗の家電製品コーナーへ足を運びます。そして、丁寧な接客を受けられたことで購買意欲を高め、気持ちよく購入に至りました。
その後、不具合が生じても手厚いサポートを受けられたことで、かえってその企業に好印象を持つようになります。製品を通じて企業への信頼性を高めた顧客Aは、その後、関連商品も同じ企業で買うようになっていくという具合です。
一方、顧客Bは広告を見て店舗に足を運ぶも、接客がどこか機械的であったことで、購買意欲が低下してしまいます。自分でいろいろな商品と比較し、何とか購入に至るものの、さらにその後のサポート体制に不満を抱くようになります。
その結果、ついにはその企業に対するイメージそのものも損なわれてしまうというケースです。このように、同じ商品を扱う場合でも、アプローチの質によってカスタマーエクスペリエンスには大きな差が生まれてしまいます。
顧客との接点を最大化するために、オンラインとオフラインを含むさまざまなチャネルを統合する戦略である「オムニチャネル」の概要やポイント等について解説しています。
ユーザーエクスペリエンス(UX)との違い
CXと類似した言葉に「ユーザーエクスペリエンス(UX)」があります。UXとは、ユーザーが各プロセスで得る個別の体験のことです。
例えば、「問い合わせ対応が良かった」「レジでの対応がスムーズだった」等の具体的な経験を指します。それに対して、CXは企業の商品・サービスの利用者がプロセス全体を通じて得られる体験を指します。
つまり、UXはCXの一部であり、UXの積み重ねがCXを左右していくと考えると良いでしょう。
カスタマーエクスペリエンスの向上がもたらすメリット

カスタマーエクスペリエンスの向上をめざすことで、企業はどのようなメリットが得られるのでしょうか。4つのポイントに分けて見ていきましょう。
顧客離れの予防
カスタマーエクスペリエンスを向上させることで、顧客に良質な体験を提供できるようになり、購買プロセスでの離脱を防げるようになります。オンラインでの快適な案内や情報収集、リアル店舗での良質な接客等、各プロセスで顧客との関係を深められるため、途中で他の商品・サービスに移行されてしまうリスクが軽減されるのです。
また、購入後も自社のファンとして良好な関係を保てるため、CLV(1人の顧客が企業にもたらす生涯価値)の損失も防止できます。
リピート率の向上
カスタマーエクスペリエンスの向上は、企業と顧客との信頼関係が深めることにつながります。購入後も自社のファンとして良い印象を持ち続けてもらえるため、関連製品や新商品の購入といったリピート率の向上が期待できるのもメリットです。
新規顧客に対する販促と比べ、既存顧客によるリピートは広告・宣伝コストを抑えられるのが特徴です。そのため、より効率的な売上の向上につなげやすくなります。
既存顧客による宣伝効果
自社と既存顧客との関係性が向上すれば、口コミ等でプラスの宣伝効果を生み出すこともあります。近年では、SNS等を通じた個人の発信も、消費行動における重要な判断材料になるケースが増えています。
消費者庁の調査によれば、消費者の情報の入手先に関する過去5年の動きとして、インターネットサイトやSNSを活用する割合が大きく増加しているデータが示されています。既存顧客によってポジティブな評価が発信されれば、大きな宣伝効果が期待できると考えられるでしょう。
ブランドイメージの構築
顧客との関係を大切にすることで、企業や商品・サービスそのもののブランドイメージも向上していきます。「顧客を大事にする企業」「ニーズを柔軟に受け入れてくれるブランド」といったイメージが構築されれば、新規顧客の獲得時にもプラスの影響が生まれます。
ESGの取組における課題や事例について解説しています。
カスタマーエクスペリエンスが特に重視される理由

近年のビジネス環境において、カスタマーエクスペリエンスの向上がなぜ重要とされる背景には、市場のいくつかの変化が関係しています。ここでは、3つのポイントから、カスタマーエクスペリエンスの重要性について解説します。
ニーズや価値観の多様化
カスタマーエクスペリエンスが重視される理由として、顧客のニーズや価値観の多様化が挙げられます。現代では、情報技術の進歩や販売チャネルの拡大によって、顧客のニーズが多様化・細分化されています。
特にSNSの影響は大きく、若い世代では周りと同じような画一的な体験よりも、個人に合わせた独自の体験の価値が高まっているのが現状です。また、経済産業省の「消費者理解に基づく消費経済市場の活性化研究会報告書」では、「所有と体験についての意識」調査において、「多くの物を所有することが幸せだ」という回答が37.3%であったのに対し、「物を所有するより、得られる体験にお金をかけたい」という回答は69.2%というデータが示されています。
このデータからも、消費者の価値観は、「所有から体験へ」とシフトしている状況がうかがえるでしょう。ニーズや価値観の多様化に適応するためには、単に商品・サービスを流通させるだけでなく、独自性と付加価値のある体験を提供する必要があるのです。
製品・サービスのコモディティ化
技術の進歩により、商品・サービスの品質・機能はコモディティ化が進んでいるのが現状です。多くの商品・サービスでは、既に一定以上の高品質が実現されているため、単体で差別化を図るのは難しくなっていると言えるでしょう。
そうした中で自社の商品・サービスを選んでもらうためには、カスタマーエクスペリエンスに着目した新たな価値の提供が重要と考えられます。
DXの急速な進展
DXの進展に伴い、さまざまな企業がオンライン空間でのサービス提供を実施しています。それにより、顧客体験の概念そのものが、従来とは大きく変化しているのも現状です。
対面のみを前提とした販売システムから、オンラインの活用も想定したハイブリッドなプロセスへと移行する中で、販売・流通を担う企業に大きな転換が求められていると言えるでしょう。その結果として、カスタマーエクスペリエンスへの注目度が高まっている側面もあります。
カスタマーエクスペリエンスを向上させるための5つのステップ
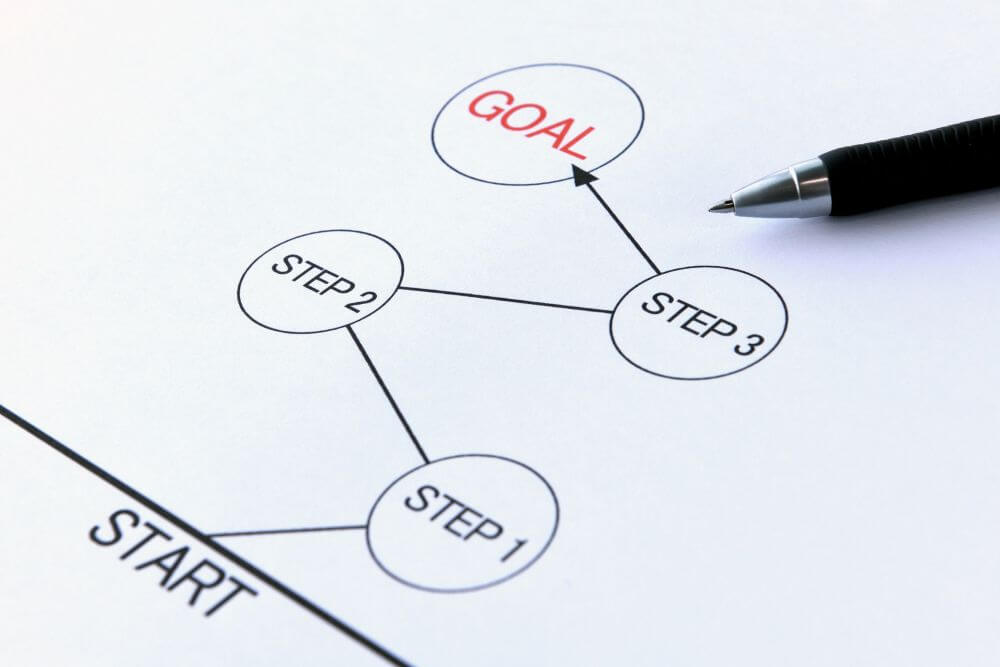
カスタマーエクスペリエンスの向上をめざすにあたり、企業はどのような手順で取組を進めるべきなのでしょうか。ここでは、5つのステップに分けて見ていきましょう。
1.ペルソナの策定
まずは、自社のターゲットを正確に把握するために、「ペルソナ」の策定を行う必要があります。ペルソナとは、自社が提供する商品・サービスの典型的な顧客像のことです。
ペルソナはマーケティングにおいて、新規顧客の獲得やエクスペリエンス向上の戦略を考える上で、基礎となる重要な要素です。ペルソナを設定する時には、年齢や性別、収入、家族構成、性格、価値観、ライフスタイル、消費傾向、趣味といった多様な項目に目を向け、実在の人物のように描く必要があります。
企業が想定するターゲットにとらわれず、既存の顧客データや市場調査の結果も踏まえ、客観的に検討することが重要です。
2.カスタマージャーニーマップの作成
「カスタマージャーニーマップ」とは、顧客がどのようなルートで購入・利用へ至るのかを描いた経路のことです。最初のタッチポイントから育客、購入、アフターサポートまでを細かく描き出し、具体的なシナリオとして共有するのが主な目的です。
プロセス全体を明らかにすることで、各場面やプロセス間における課題を分析しやすくなり、どの部分でカスタマーエクスペリエンスを向上できるかを発見できるようになります。カスタマージャーニーマップには決められたフォーマットはありませんが、場面ごとに「顧客の行動」「顧客の心理」「顧客とのタッチポイント」「課題」を洗い出していくのがポイントです。
3.戦略の策定・現状とのすり合わせ
続いて、ペルソナとジャーニーマップをもとに、具体的な戦略を策定していきます。カスタマーエクスペリエンスの戦略を立てる上では、「一貫性」と「パーソナライゼーション」がキーワードとなります。
一貫性とは、どのタッチポイントにおいても、一貫したイメージを訴求できる状態のことです。カスタマーエクスペリエンスでは、情報収集から接客、アフターサポートまでを幅広く設計するため、個々のアプローチで方向性がブレてしまうケースも少なくありません。
「自社として顧客に何を届けたいのか」「どんな体験を提供したいのか」を明確にした上で、ある程度の統一感を持たせることが重要です。パーソナライゼーションとは、顧客一人ひとりに合わせてカスタマイズされた体験を提供できるようにすることです。
顧客それぞれの属性や行動履歴等のデータを収集・分析し、各タッチポイントへ柔軟に反映させることで、スムーズに購入プロセスを進んでもらいやすくなります。その上で、ビジネスモデルや商材、市場によって適した戦略は異なるため、幅広く意見を集めることも大切です。
戦略が見えてきたら、現状と照らし合わせながら、実現可能性や必要なリソースを細かく検討しましょう。
4.社内オペレーションの整備
カスタマーエクスペリエンス戦略を実行するためには、柔軟かつきめ細かなアプローチが求められるため、円滑な社内オペレーションを整えておく必要があります。ここでは、顧客向けと社内向けの2方向に分けて、整備の方法を見ていきましょう。
顧客向けシステムの整備
顧客向けのシステム整備としては、WebサイトやWebコンテンツを整えたり、ECアプリを運用・改善したりするのが基本です。例えば、WebサイトやアプリのUIがわかりにくければ、それだけでも顧客体験価値が下がり、途中で離脱されるリスクが高まります。
既に顧客向けのオンラインサービスを提供している場合は、使い勝手や見やすさに問題がないかを細かくチェックしましょう。また、Webサイトやアプリは、顧客のデータを集める際にも重要なツールとなります。
「どのような経路で自社サイトに訪問したか」「どの時間帯が効果的か」「どの広告が集客につながっているか」等を細かく分析するためにも、データの取扱いがしやすいシステム構築をめざしましょう。
サイバーリスクの実態について解説しています。
社内向けシステムの整備
社内向けのシステム整備は、スムーズに戦略を実行できる体制を確保するために行います。具体的には、データ共有・管理の効率化や、取り扱うチャネルの整理、社内リソースの一元管理等が重要度の高い施策です。
例えば、複数の販売チャネルを扱っていて仕組みが煩雑になっている場合は、統合して管理をしやすくするのも一つの方法です。また、顧客データを一元管理するために、CRM(Customer Relationship Management)システムを導入するのも有効です。
その上で、施策の実行に必要なリソースを確保するために、単純作業の効率化や人員の拡充等にも目を向ける必要があります。カスタマーエクスペリエンス戦略は長期的なスパンを見越した計画であるため、安定して運用できるように土台作りは丁寧に進めましょう。
5.施策の実行・定期的な見直し
外部環境や顧客のニーズは絶えず変化していくので、カスタマーエクスペリエンスを向上させるには、戦略を柔軟に見直し続けなければなりません。そのため、施策を実行するにあたっては、定期的に効果測定を行い、有効性を検証することが重要となります。
戦略を策定する段階で、継続的な効果測定とプランの見直しを前提とし、ゆとりのある実行体制を構築しておきましょう。例えば、費用についても初めからすべてリソースをつぎ込むのではなく、途中で他の施策へ移行できるよう、予算にゆとりを持たせておくことが大切です。
DCXとは

DCXとは「デジタルカスタマーエクスペリエンス」の頭文字をとった用語です。デジタル上におけるカスタマーエクスペリエンスを意味し、CXよりもさらに一歩細かく踏み込んだ概念にあたります。
これまでも見てきたように、顧客の消費行動においては、デジタルを活用される機会が多くなりました。DXの促進によってデジタルサービスも多様化しており、近年特に重要となっている考え方です。
具体的には、オンライン広告やメルマガ配信の質、購入サイトの操作性、オンラインサポートの充実度等が、顧客体験を左右するポイントとなります。DCXを向上させれば、例えば顧客が商品・サービスで不利益を被った時も、インターネット上ですぐに対応することができます。
迅速な対応を行えば、かえって企業に対する信頼度を高められる可能性もあるでしょう。現代のカスタマーエクスペリエンスは、DCXと切っても切り離せないほど密接な関係にあると言えます。
カスタマーエクスペリエンス戦略の一環として、デジタルサービスの拡充にも力を入れ、さまざまな角度から顧客との接点を改善していくことが重要です。
まとめ
顧客のニーズや価値観が多様化する現代では、単に優れた商品・サービスを開発するだけでなく、カスタマーエクスペリエンスに目を向けた戦略が求められます。顧客一人ひとりにあった体験を提供することで、商品やサービスのみならず、自社に対するイメージを向上させられる可能性もあります。
カスタマーエクスペリエンスを向上させるには、まずペルソナとカスタマージャーニーマップを策定し、丁寧に戦略を立てていくことが大切です。顧客データや市場の動きを丁寧に分析しながら、自社ならではの強みを活かせる戦略を構築しましょう。

















