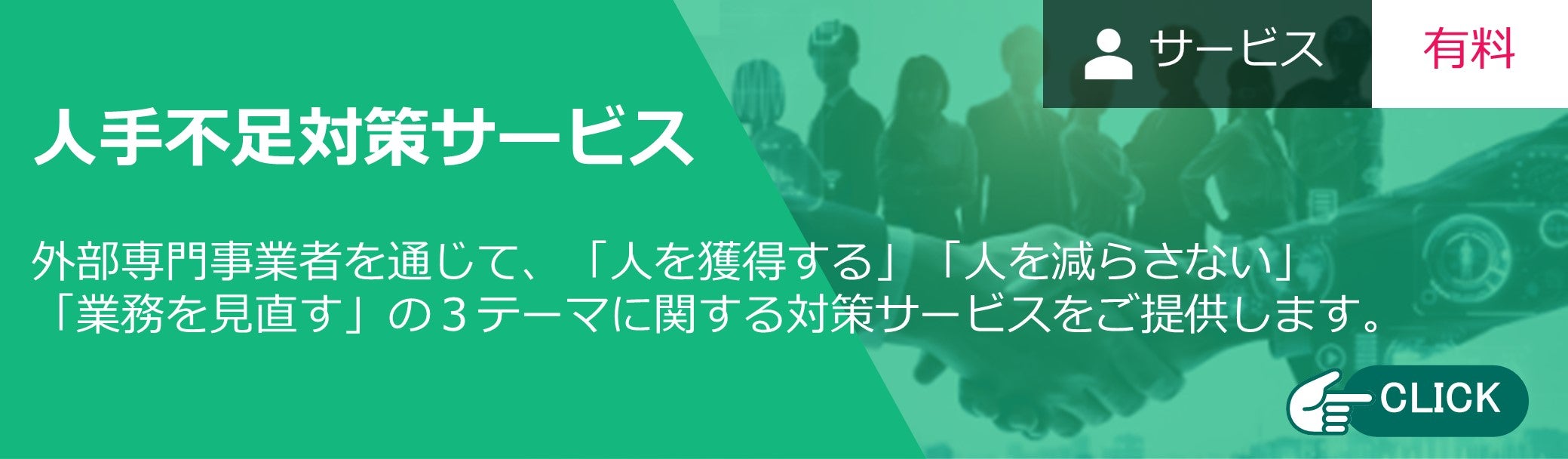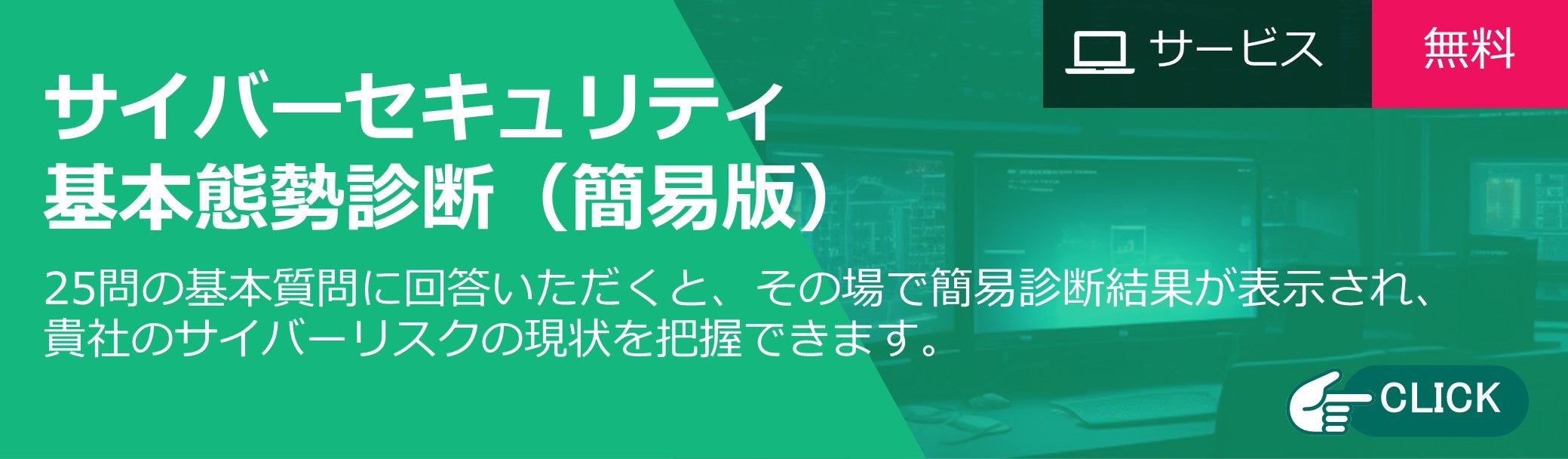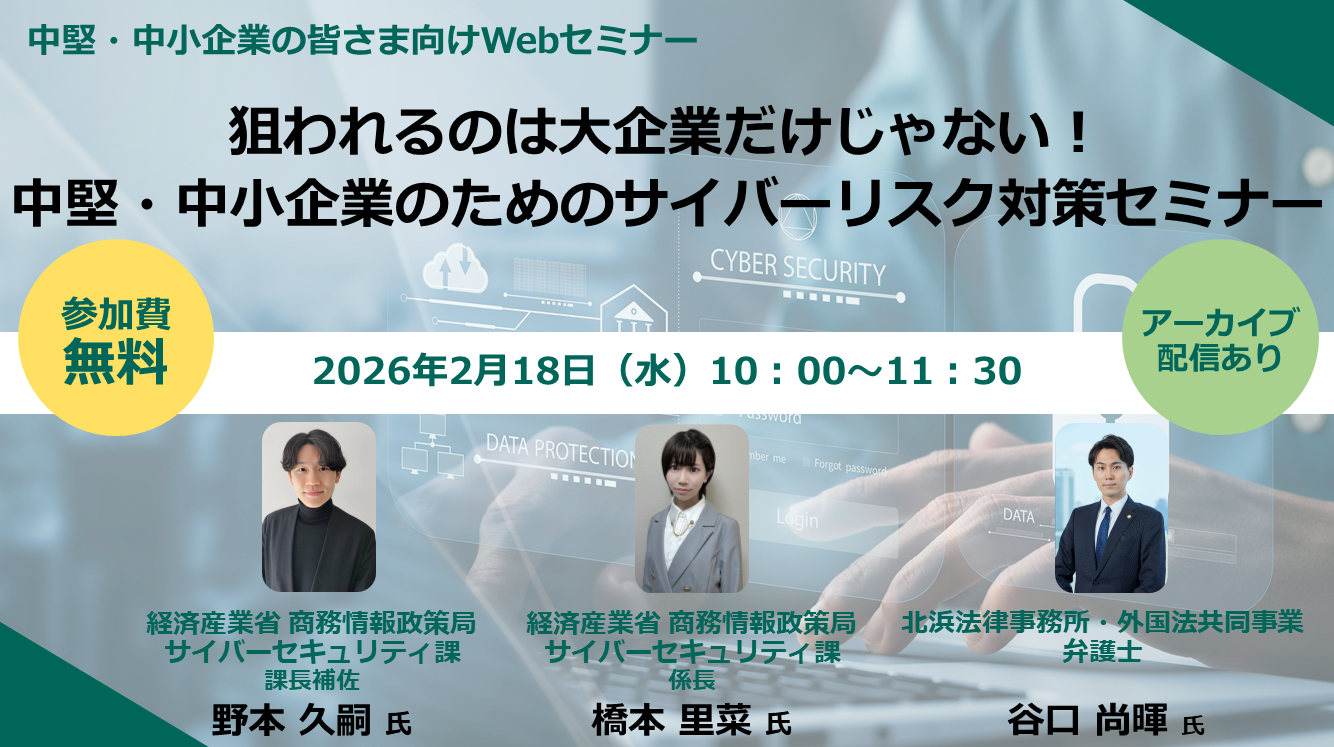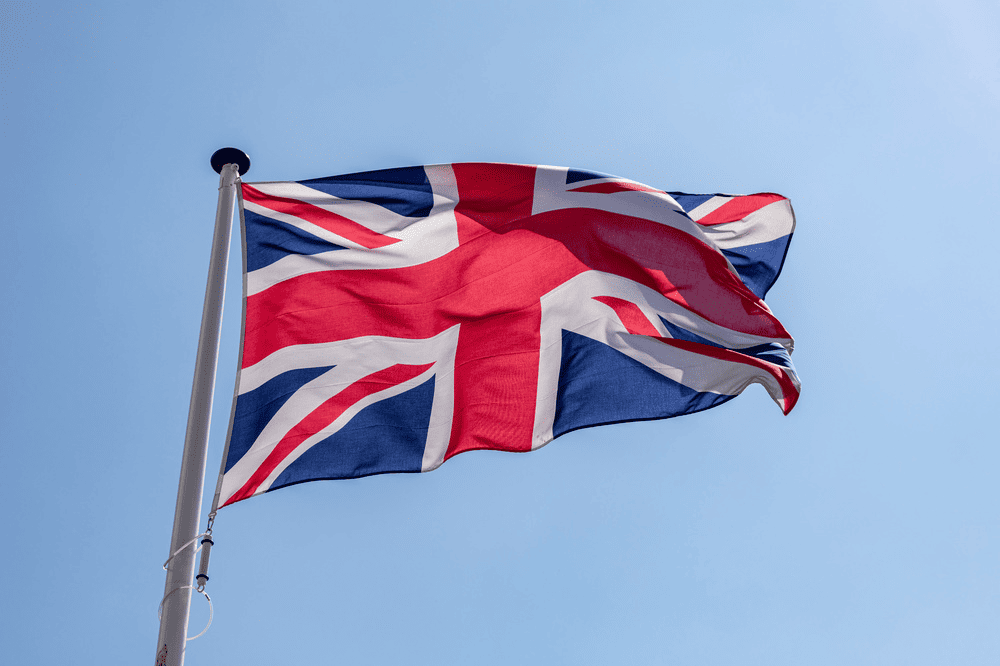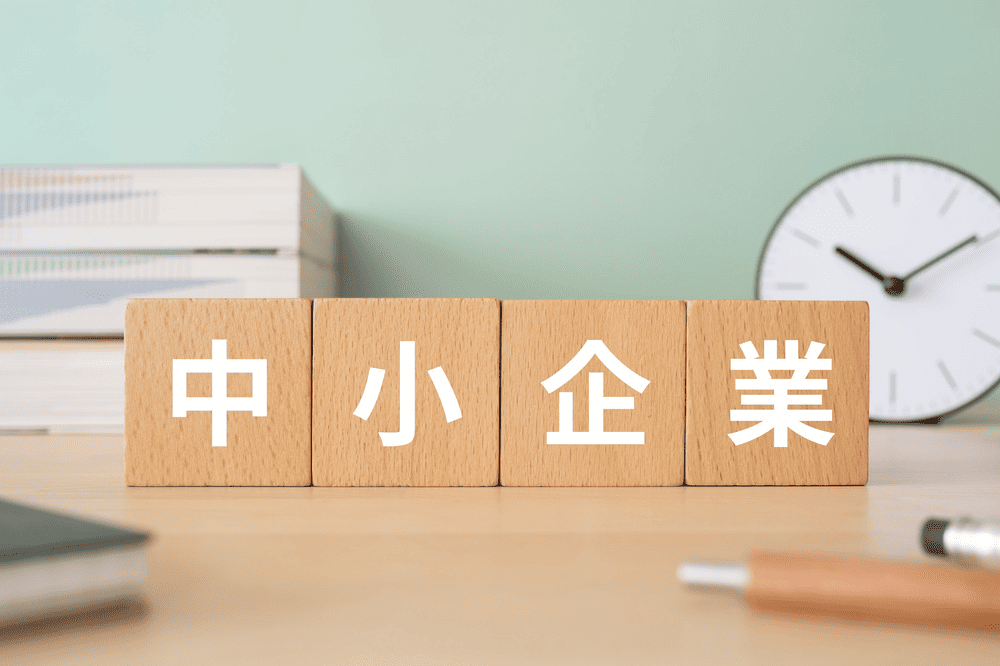給与デジタル払いとは?基本的な仕組みと導入のメリット・デメリットを解説
公開日:2025年5月26日
サイバーリスク

2023年の法改正により、給与の一部または全額のデジタル払いが認められるようになりました。電子マネーを使った支払いが可能となり、給与受取の柔軟性が高まったことで、多様な場面での活用が期待されています。
今回は給与デジタル払いの仕組みと基本的なルール、導入するメリット・デメリットについて解説します。また、導入時に把握しておくべきリスクについても詳しく見ていきましょう。
給与デジタル払いの概要

給与デジタル払いとは、電子マネーを使って従業員の給与を支払う仕組みのことです。賃金の支払方法としては、長らく現金払いや銀行等の金融機関口座への振込等に限定されてきました。
しかし、2023年4月に施行された改正労働基準法施行規則により、給与の新しい支払方法としてデジタル払いが加えられました。ここではまず、給与デジタル払いの概要について解説します。
企業の初任給引上げについて解説しています。
従来の給与支払方法
従来の給与の支払方法は、労働基準法において、通貨によるものが原則とされてきました。これを「賃金支払の5原則」と呼び、以下の5つのルールが定められています。
「賃金支払の5原則」(労働基準法第24条)
1. 通貨を用いて支払う
2. 労働者へ直接支払う
3. 全額を支払う
4. 毎月1回以上支払う
5. 一定の期日を定めて支払う
なお、一つ目の通貨払いの原則については、労働基準法施行規則7条にて、従業員の同意があれば本人名義の銀行口座や証券口座に振り込むことが例外的に認められてきました。例外とはいえ、現在では金融機関口座への振込のほうが主流と言えるでしょう。
2023年の改正では、ここに新たな例外事項である「第二種資金移動業の口座を用いた給与支払(=給与デジタル払い)」が加えられました。金融機関口座を用いる際と同じように、従業員の同意を得る必要はありますが、一定のルールに則ればデジタル払いも可能となっています。
給与デジタル払いと従来の方法との違い
給与デジタル払いでは、残高上限が100万円以下に制限されます。そもそも、第二種資金移動業自体が100万円相当額以下の送金を扱うサービスであるため、上限を超える金額をやりとりすることはできません。
上限を超過した部分については、あらかじめ従業員が指定した金融機関の口座へ送金される仕組みとなっています。また、企業がデジタル払いを取り入れたとしても、すべての従業員に適用しなければならないというわけではありません。
受取方法は個人で選べるので、従業員にとってはあくまでも選択肢が一つ増えるといったイメージになります。また、振込手数料については、デジタル払いのほうが金融機関口座への振込よりも安くなるケースが多いとされています。
給与デジタル払いの基本的な仕組み

給与デジタル払いは、指定資金移動業者の口座を介して行われる仕組みとなっています。資金移動業者とは、厚生労働省の審査を受け、内閣総理大臣によって資金移動業者登録簿に登録された業者のことです。
2025年4月現在、第二種資金移動業者には82の事業者が登録されており、金融庁の「資金移動業者登録一覧」で確認することができます。そのうち、給与の支払いに利用できる指定資金移動者は4社のみ(PayPay株式会社・株式会社リクルートMUFGビジネス・楽天Edy株式会社・auペイメント株式会社)となっているため注意が必要です。
中小企業が給与デジタル払いを導入する時の流れ

中小企業が給与デジタル払いを採用する時には、以下のようなステップを踏むのが一般的です。
1. 労使協定の締結
2. 就業規則・給与規程の見直し
3. 従業員への周知
4. 給与デジタル払いを希望する人の同意書を得る
5. 給与システムの仕様を確認
6. 運用開始
前述のように、デジタル払いの制度を導入するには、雇用主と労働者の間で労使協定を結ばなければなりません。さらに、デジタル払いに関する以下の事項を従業員に説明した上で、個別に同意を得る必要があります。
■受取額は1日あたりの払い出し上限額以下の金額とする
■口座の上限額は100万円以下
■口座残高の現金化も可能(月1回は口座からの払い出し手数料なし)
■口座残高は少なくとも10年間は払戻しが可能
さらに、万が一に備えて、トラブルが起こった場合の対応も共有しておくことが大切です。不正取引が行われた時には、口座所有者に過失がなければ損失額の全額が補償されます。
しかし、従業員にも過失がある場合は、補償の有無や度合いはケースバイケースになるため注意が必要です。また、資金移動業者ごとに通知期間(少なくとも30日以上)が設定されているので、不正取引に気づいたらすぐに問い合わせを行うことが大切です。
なお、資金移動業者が破たんした場合には、第三者である保証機関から弁済が行われる仕組みとなっています。従業員からの同意を得る際には、これらの注意事項も丁寧に共有しましょう。
このほかに、就業規則や給与規程等の改定が必要かどうかもチェックしておくと良いでしょう。
ユーザとシステム会社の間における責任の範囲の基準について解説しています。
給与デジタル払いを導入するメリット・デメリット

給与デジタル払いを採用するかどうかは、メリットとデメリットの両面を適切に把握した上で判断することが大切です。中小企業が給与デジタル払いを導入するメリット・デメリットをご紹介します。
給与デジタル払いのメリット
デジタル払いを併用すれば、金融機関口座を持たない従業員への給与支払も可能となります。アルバイトをする高校生等の若年層や、口座の開設審査が通りにくい外国人労働者等にも、雇用の機会を設けやすいのがメリットです。
また、単発のアルバイトや副業といった幅広いケースに対応できるため、多様な人材を活用することもできます。企業が積極的な姿勢を示すことで、福利厚生の柔軟性がアピールされるため、自社のイメージアップにもつなげられるでしょう。
さらに、企業側からすれば、振込手数料の削減につながるのも重要な利点です。
給与デジタル払いのデメリット
一方、給与のデジタル払いには、いくつかのデメリットも存在します。一つ目は、金融機関口座への送金や現金化に手間がかかってしまう点です。
デジタル決済は民間サービスでは広く普及しているものの、公共料金や家賃の支払いには対応していないケースも多いです。給与をデジタル払いで受け取る場合は、家賃等の支払いにそのまま充てられない可能性があるため、従業員の負担になる恐れもあるでしょう。
二つ目のデメリットは、先ほども触れたように振込金額の上限が設定されている点です。制度上の上限は100万円と規定されているものの、実際の上限額は決済サービスによっても異なります。
例えば、資金移動業者の厚生労働大臣第00001号に指定されている「PayPay株式会社」では、一つのアカウントで保有できる上限残高が20万円となっています。既に残高を保有している場合は、上乗せされて計算されるため、例えばもともと10万円の残高を持っている従業員には給与を10万円分までしか振り込めません。
超過分は、本人名義の金融機関口座に自動送金される仕組みなので、サービスごとの上限を企業・従業員ともに正しく理解しておく必要があります。
そして、三つ目のデメリットは、振込方法の併用による事務負担の増加です。給与の受け取り方は従業員ごとに要望が異なります。給与デジタル払いを希望しない従業員もいれば、給与の一部のみをデジタル払いにしてもらいたいという従業員もいるでしょう。
デジタル払いを導入する場合、基本的には従来の振込方法との併用が前提となります。複数の方法を処理する必要が生まれるため、運用や管理の手間が増大してしまうのがデメリットとなります
【関連記事】
福利厚生のメリットと注意点について解説しています。
給与デジタル払いとサイバーリスク

給与のデジタル払いを導入する上では、運用上のリスクも想定しておく必要があります。国家公安委員会の「犯罪収益移転危険度調査書」では、資金移動業者を介したサイバーリスクの多様化が指摘されています。
例えば、不正入手された口座情報を利用して他人になりすまし、残高を増額させた上で現金化するといった手口です。従来は入金額が比較的に少額であったスマホ決済アプリも、給与のデジタル払いによって取扱金額が大きくなるため、リスクはさらに高まると考えられます。
口座アカウントの乗っ取りやフィッシング詐欺、リスト型攻撃等のターゲットになるリスクもあるため、利用する資金移動業者は慎重に見極めることが大切です。
【関連記事】
サイバー攻撃の被害と対策について解説しています。
サイバー攻撃を受けた後の取組について解説しています。
給与デジタル払いに関するQ&A

ここまでの内容を踏まえ、給与デジタル払いに関するQ&Aを確認しましょう。
労働者が給与デジタル払いを希望した場合、雇用主は必ず応じなければならないのか?
給与のデジタル払いを取り入れるかどうかは、従業員だけでなく企業側にも選択する権利があります。導入の可否を決めるにあたっては、企業と労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結しなければなりません。
その上で希望する労働者の同意を得て実施する流れとなるため、従業員が求めたとしても、企業側に導入が強制されるわけではありません。
同意書に記載すべき項目は?
給与のデジタル払いを実施する際には、従業員ごとに個別で同意書を書いてもらう必要があります。同意書には、「デジタル払いで受け取る賃金額」や「資金移動業者口座番号」のほかに、上限が超えてしまった時の措置に必要な「指定代替口座情報等」も記載してもらいましょう。
なお、厚生労働省ではデジタル払いに関する同意書の様式例が公開されているので、作成時の参考にしてみるのも一つの方法です。
給与デジタル払いが認められている指定資金移動業者とは?
2025年4月現在、給与のデジタル払いに利用できるとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者は「4社」となっています。具体的には、PayPay株式会社(サービス名:PayPay給与受取)・株式会社リクルートMUFGビジネス(サービス名:COIN+(スタンダード))・楽天Edy株式会社(楽天ペイ給与受取)・auペイメント株式会社(サービス名:au PAY 給与受取)の4つの事業者によるサービスの利用が認められています。
なお、受取上限額はそれぞれ異なるので注意が必要です。参考までに、PayPay株式会社では20万円、株式会社リクルートMUFGビジネスでは30万円、楽天Edy株式会社では10万円、auペイメント株式会社では10万円となっています。
指定資金移動業者が万が一、破たんした時の対応は?
万が一指定資金移動業者が破たんしてしまっても、賃金の受取に用いる口座の残高は、保険会社などの第三者保証機関から速やかに弁済される仕組みとなっています。具体的な弁済方法は資金移動業者ごとに異なるので、万が一のリスクに備えて事前に確認をしておきましょう。
まとめ
給与のデジタル払いは、従業員と企業側の双方にとってメリットのある選択肢です。従業員側からすれば、自身の給与を柔軟な形式で受け取れるため、利便性の向上が期待できます。
企業側からしても、「多様な人材を活用しやすい」「振込手数料を抑えやすい」といった利点があるため、今後も徐々に普及していくことが予想されます。ただ、導入には一定の手続を踏む必要があり、全従業員に強制することもできません。
給与の支払方法が増えれば、事務負担も大きくなってしまうため、企業規模や従業員のニーズ等を踏まえて慎重に判断することが大切です。まずは、福利厚生の取組として、自社の従業員へアンケートやヒアリングを行ってみると良いでしょう。