従業員満足度(ES)とは?モチベーションによる影響と改善方法を解説
公開日:2024年5月20日
その他
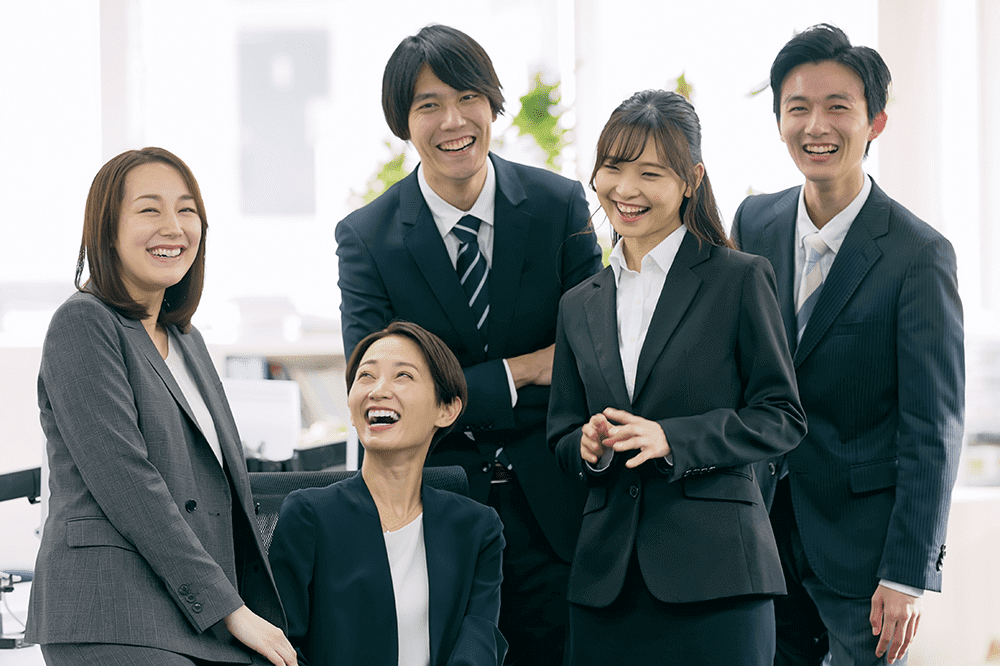
働き方の多様化等の影響によって、リモートワークで仕事に取り組む機会が業種や職種によっては増えています。自社で働く従業員の状況を把握するために、従業員満足度(ES)を定期的にチェックし、適切な対応を行っていくことが大切です。
従業員満足度の低下に対して、有効な改善策を取れないままでいると、離職率の増加や生産性の低下等につながるので注意しましょう。この記事では、従業員のモチベーションが低下することの影響や具体的に改善していくための方法等を解説します。
従業員満足度(ES)とは

従業員満足度を把握するには、まず基本的な意味を理解しておく必要があります。企業において重視されている理由も含めて解説します。
従業員満足度の意味
従業員満足度(ES)とは、「Employee Satisfaction」のことであり、労働環境や待遇等の要素から従業員の満足度を測るための指標です。企業においては従業員が満足している部分と不満に感じている部分を把握した上で、必要な改善策に取り組んでいくことが求められます。
従業員満足度が低い状態だと、離職率の増加や提供するサービスの質が低下するといった事態を招きやすくなるため、経営課題の一つとして捉えられる部分があるでしょう。社内アンケートや面談等を通じて、従業員満足度をチェックしていくことが大切です。
重視されている理由
厚生労働省の調査によれば、「従業員と顧客満足度の両方を重視する」企業は、「顧客満足度のみを重視する」企業に比べて、売上高営業利益率、売上高ともに増加傾向にあるとされています。また、人材確保の面でも従業員満足度を重視する企業のほうが、人材をうまく確保できている傾向が見られます。
従業員にとって働きやすい魅力的な職場は、従業員の仕事に対するモチベーションを高めるだけでなく、生産性の向上や人材確保に効果があることが調査結果からわかるため、多くの企業が重視していると言えるでしょう。経営課題の一つとして、顧客満足度を高めていくとともに、従業員満足度についても注目していく必要があります。
従業員満足度が低いことで生じる影響
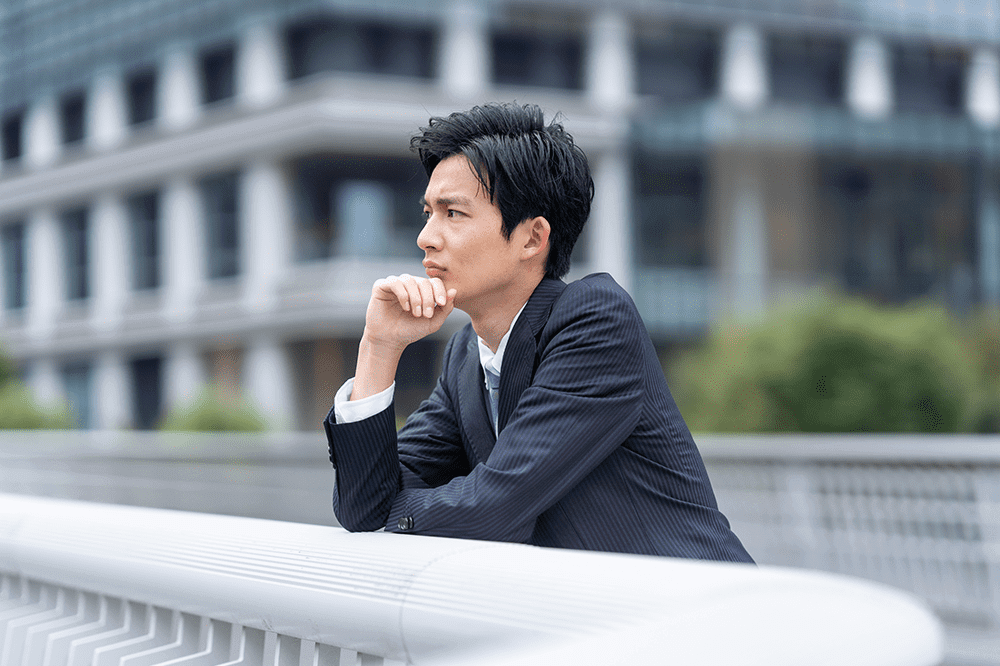
従業員満足度が低い状態が続いてしまえば、企業にとってマイナスの影響が生じる可能性があります。どのような影響が生じるのかを解説します。
離職率の増加につながる恐れがある
従業員満足度が低い状態が続けば、従業員の離職につながる恐れがあります。厚生労働省が公表している「平成30年 若年者雇用実態調査の概況」では、初めて勤務した会社をやめた主な理由として以下のものが挙げられています。
初めて勤務した会社をやめた主な理由(3つまでの複数回答)
・「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」
・「人間関係がよくなかった」
・「賃金の条件がよくなかった」
・「仕事が自分に合わない」
上記のように、労働環境や待遇面での不満を理由として、退職しているケースが多いと言えるでしょう。また、人間関係に悩みを抱えて退職するケースもあるので注意が必要です。
同僚や上司とのコミュニケーションが取りづらい場合は従業員満足度が低くなり、離職につながるケースがあります。離職率の増加が気になるときは、上記のような不満を従業員が抱えていないかをチェックし、早めに対応していくことが大切です。
製品の品質やサービス低下につながる
従業員満足度が低下し、離職率が高まることによって企業は人手不足に陥る場合があるでしょう。日本商工会議所と東京商工会議所が取りまとめた「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」の調査結果(複数回答)では、人手不足が事業にもたらす影響について挙げられています。
人手不足の影響を既存の従業員で補っていると回答した企業が77.2%となっていますが、一方で「事業運営の具体的な支障が生じている(納期遅れ、品質・サービスの低下等)」という回答が21.6%です。また、「事業の拡大(新規顧客や新規市場の開拓)を見送った」と答えた企業も18.7%となっており、経営に少なからず影響を与えていることがわかります。
顧客に提供する製品の品質やサービスが低下すれば、企業そのものに対する信頼性も低くなる恐れがあるでしょう。むやみに顧客からの信頼を損なわないためにも、従業員満足度の維持や向上に努めていくことが重要です。
従業員満足度を構成する要素

自社の従業員満足度を把握するには、どのような要素が関係しているのかを押さえておく必要があります。従業員満足度をチェックする方法も含めて解説します。
金銭的な報酬
従業員満足度を調査する上で、金銭的な報酬に関する要素が挙げられます。具体的には、給与や賞与、退職金等の直接的な報酬に加え、社会保険や福利厚生等の間接的な報酬に分けられます。
企業によって給与水準や福利厚生等は異なりますが、従業員が自社の待遇にどの程度満足しているかを定期的に確認することが大事です。調査方法としては、全従業員に対するアンケート調査や個別に確認していく聞き取り調査が主な方法だと言えます。
調査項目や調査回数が多いほど、より詳しい結果を得られますが、回答に時間がかかり過ぎては従業員の負担になるため、調査の実施時期や内容を精査してから取り組みましょう。また、どのような目的で調査を行うのかを従業員に対して丁寧に説明し、協力を得ていくことも大切です。
非金銭的な報酬
従業員満足度に影響する要素には、非金銭的な報酬に関するものも含まれます。具体的には、仕事へのやりがいや仕事を通じて自己の成長につながっているかという点、企業のビジョンに対する共感、組織風土、対人関係等が挙げられます。
前述の金銭的な報酬は従業員満足度を数値で判断しやすいですが、非金銭的な報酬については数値化しづらいため、個別面談等を通じて従業員から直接話を聞く機会を設けるようにしてみましょう。従業員の希望や意見を聞き、一緒になってキャリアパスを考えていく姿勢を取ることが大事です。
従業員満足度を高めるメリット

従業員満足度を高めることによって、企業は次のようなメリットを得られます。
従業員満足度の向上で得られるメリット
・従業員の意欲が向上する
・業績・生産性の向上につながる
・人材確保の効果に期待できる
それぞれのメリットについて、ポイントを解説します。
従業員の意欲が向上する
従業員満足度を高める取組を実施すれば、従業員の労働意欲を向上させることが期待できます。「この会社でずっと働きたい」という意識が強まれば、勤続年数が長くなり、キャリアアップに対しても前向きな気持ちになれるでしょう。
従業員のモチベーションが高まれば、離職率の低下等につながり、人材の定着といった部分で企業が抱える経営課題の解消につながるはずです。
業績・生産性の向上につながる
働くことに対する従業員のモチベーションが高まれば、業務効率の改善や生産性の向上も期待できます。従業員満足度を高めるための取組は、全従業員を対象とするものなので、結果として企業業績の向上にもつながっていくでしょう。
業務の効率化や生産性の向上は、自社の顧客に対して製品やサービスの質を保つだけでなく、職場における働き方を見直す機会となります。企業にとって業績アップに向けた良い循環を生み出すでしょう。
人材確保の効果に期待できる
自社の従業員にとって働きやすい労働環境を提供することは、企業イメージの向上にもつながります。魅力のある企業となることで、採用活動においても良い効果をもたらすでしょう。
企業イメージが高まれば、新たな人材の確保に期待できます。人手不足の課題に悩みを抱える業種ほど、従業員満足度を高めることで得られる効果は大きいと言えるでしょう。

従業員満足度を改善するために行う具体的な方法として、以下のものが挙げられます。
従業員満足度を改善する方法
・適正な人事評価制度の構築
・柔軟な勤務形態の整備
・キャリアパスの明示・人材育成
・従業員目線で継続した取組を行う
それぞれの方法について、ポイントを解説します。
適正な人事評価制度の構築
従業員満足度を高める取組として、人事評価制度の見直しが挙げられます。自らの仕事が適正に評価されていないと感じた時、従業員満足度は低下しやすい傾向が見られます。
職種やスキル、成果等に応じてきちんと評価される人事評価制度の構築を検討してみましょう。また、在宅勤務や時短勤務等、勤務形態に応じてそれぞれ評価基準を設けることも大切です。
柔軟な勤務形態の整備
働き方が多様化している労働市場において、柔軟な勤務形態を採用するほうが企業にとって人材確保を行いやすいと言えます。在宅勤務や時短勤務等、働く側の視点に立って柔軟な働き方ができる環境を整えることが大切です。
勤務形態が柔軟であれば、これまで採用候補から漏れていた人材にもアプローチを行いやすくなり、人材確保の課題解決にもつながっていくでしょう。
キャリアパスの明示・人材育成
従業員に長く働いてもらいたいと考えるのであれば、自社で働き続けることによって、どのようなキャリアパスを描けるのかを明示する必要があります。将来的にさまざまなスキルアップが図れる企業であれば、他社への転職を考える必要性が低くなり、結果として人材が定着しやすい環境を整えられます。
また、自らの将来に対してキャリアプランを描きやすくなるため、従業員満足度も高くなりやすいでしょう。定期的な個別面談の実施やキャリア支援等を通じて、人材育成に力を入れていくことが大切です。
従業員目線で継続した取組を行う
従業員満足度を高めるための取組は、実施したからといってすぐに成果が出るものばかりとは限りません。そのため、短期的な施策と中長期的に取り組む施策を分けて、継続して実施していく必要があります。
定期的に実施する従業員満足度に関する調査結果等を踏まえ、従業員とのコミュニケーションを重視しながら、全社的な取組として進めてみましょう。
【関連記事】
ワーク・エンゲージメントを高める職場づくり
従業員がイキイキと働き続けるために効果的な「ストレスチェック制度」の活用について解説します。
まとめ
従業員満足度は自社で働く従業員が、労働環境や待遇等にどれくらい満足しているか、あるいは不満に感じているかを測るための指標です。従業員満足度が高い企業は従業員のモチベーションが高く、結果として生産性が高くなる傾向が見られます。
また、人材確保の面でもプラスの効果を期待できるため、自社の状況を把握した上で改善のための具体的な取組を進めていくことが重要です。魅力ある職場づくりの施策を実施し、従業員とのコミュニケーションを大切にしながら進めていきましょう。
【物流業界向け関連記事】

















