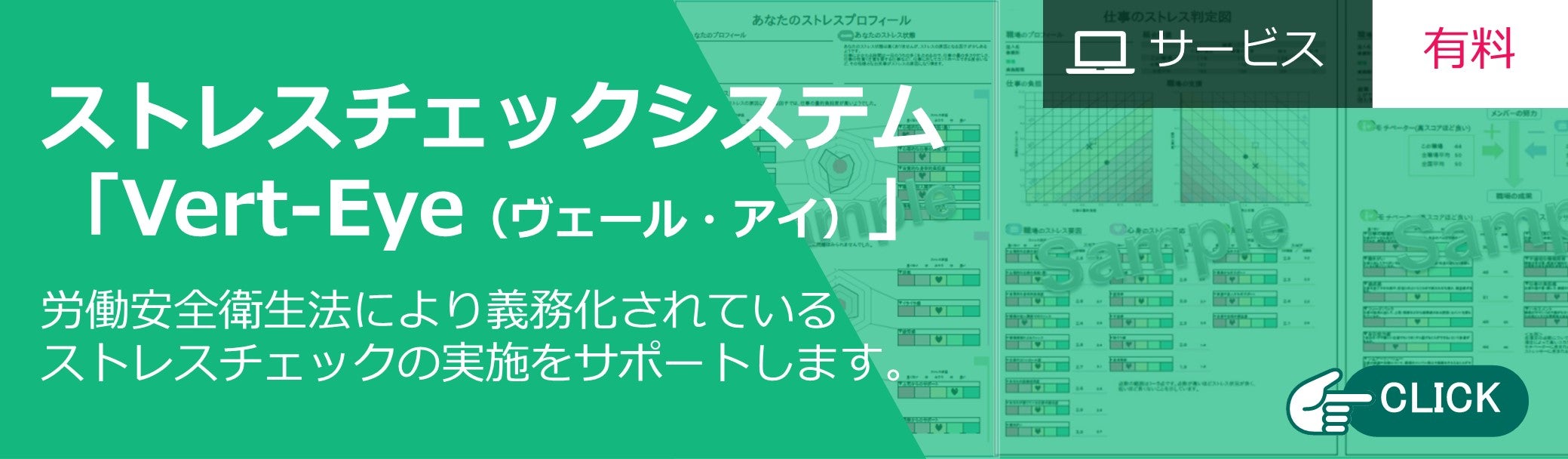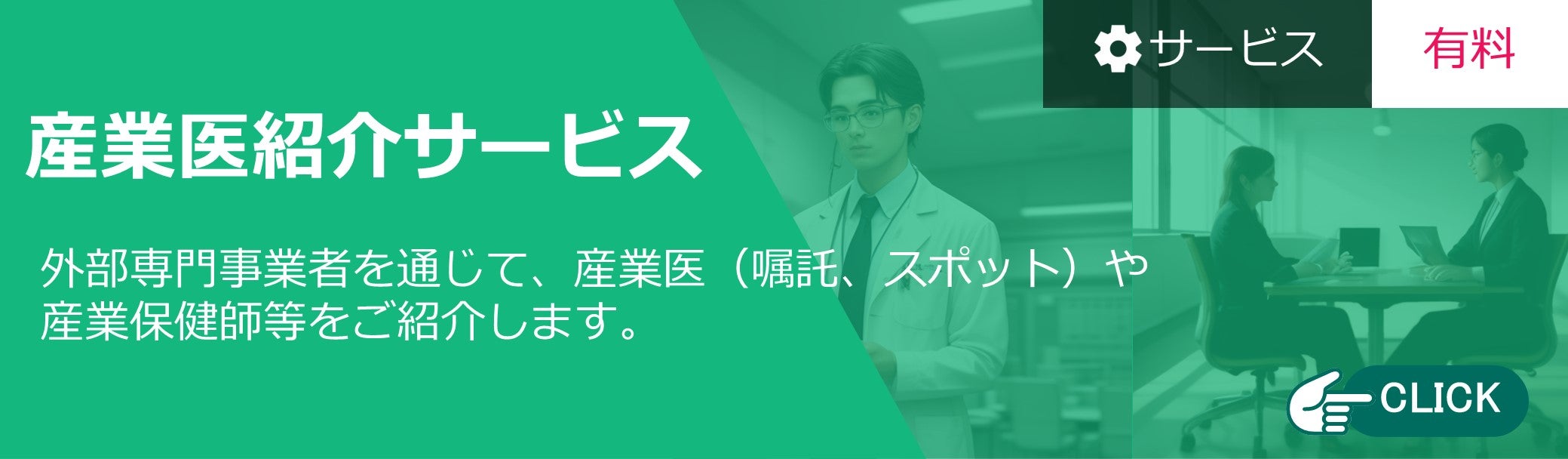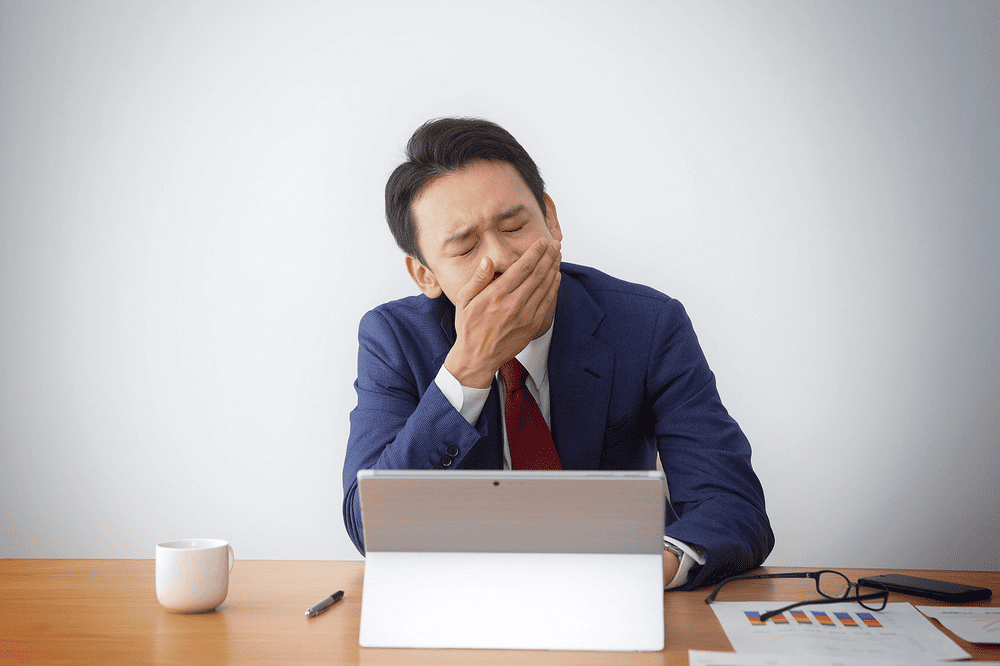フェムテックとは?基本的なとらえ方と課題解決のポイントを解説
公開日:2025年5月19日
健康経営・メンタルヘルス

近年、ビジネスの分野で「フェムテック」という言葉を耳にする機会が増えました。フェムテックとは、女性が抱える健康の悩みや課題に対して、テクノロジーを用いて解決へ導く商品・サービスを指します。
今回はフェムテックがなぜ注目されているのか、基本的なとらえ方や重要性に触れながら解説します。また、実際にどのようなサービスが扱われているのか、フェムテックに関する実例も詳しく見ていきましょう。
フェムテックとは

フェムテック(Femtech)とは、「Female(女性)」と「Technology(テクノロジー)」を掛け合わせた造語です。健康やライフスタイルに関する女性特有の悩みを、テクノロジーによって柔軟に解決していく考え方を指します。
科学技術の進歩により、現在ではテクノロジーによって、生理や不妊、妊娠・出産に伴う健康課題、更年期障害といった女性特有の健康問題を解決する幅広い手法が開発されています。そのなかでも、特にITを用いてアプローチする手法を「フェムテック」と呼んでいます。
フェムテックに関する商品やサービス等が多くの企業で開発、提供されており、女性のメンタルヘルスにとって良い影響をもたらしていると言えるでしょう。フェムテックをうまく活用することで、女性が抱える健康課題の解消やより良い働き方の実現につながっています。
規模別・業種別の女性管理職割合から見える、女性管理職の割合が上昇しない要因・課題について解説しています。
フェムケアとの違い
フェムテックと類似した言葉に「フェムケア(Femcare)」があります。フェムケアは「Female(女性)」に「Care(ケア)」を組み合わせた言葉であり、女性の健康やウェルビーイングを向上させるための商品・サービスのことです。
例えば、フェムケアの代表例としては次のようなものが挙げられます。
・オーガニックコットンの生理ナプキン
・ナプキン一体型パンツ
・洗って何度も使える月経用吸水ショーツ
・デリケートゾーン専用の洗浄剤やオイル
・更年期症状緩和・改善のサプリやアイテム
・妊娠中や産後のQOL向上を目的としたアイテム
・セクシャルウェルネス関連商品
・授乳期の衣類
・産後ケア商品
・骨盤ケア商品
それに対して、フェムテックは具体的な商品というよりも、IoTやAIを用いて女性が抱える悩みを解決していくのが特徴です。例えば、フェムテックの製品やサービスとしては、次のようなものが挙げられます。
・月経周期管理アプリ
・オンライン診療・処方
・更年期サポートアプリ
このように、両者の目的は共通していますが、アプローチが異なるものと捉えると良いでしょう。
フェムテックの市場規模
2024年に行われた株式会社矢野経済研究所の調査によれば、2023年のフェムケア&フェムテックの市場規模は約750億円となっており、年々増加している傾向が見られます。メディアによって注目度が高まっているのに加え、ドラッグストア等でもフェムケア商品売り場が普及し、関連商品の売れ行きは伸びています。
一方、フェムテック関連のサービスについては、認知度こそ高まってきているものの、アプリ等の普及にはまだ課題が残されているのも実情です。そこで、内閣府の「女性活躍・男女共同参画の重点方針2024」では、女性の健康課題を解決するためにフェムテックの活用が明記される等、国レベルでの取組が進められています。
フェムテックが注目されている3つの理由

フェムテックが注目されている理由には、社会情勢のさまざまな動きが関係しています。ここでは、3つのポイントに分けて、フェムテックが注目される背景を見ていきましょう。
女性の健康問題を取り上げやすくなった
近年では働き方改革の一環として、2016年に女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が施行されるなど、女性の活躍を後押しする動きが強まっています。働く女性が増えたことで、それまで見落とされがちであった女性特有の健康課題が着目され始めているのが、フェムテックが注目される一因と言えるでしょう。
経済産業省が2024年2月に取りまとめた「女性特有の健康課題による経済損失の資産と健康経営の必要性について」という資料によれば、女性の健康課題による経済損失(欠勤や離職、パフォーマンスの低下など)は、約3.4兆円と試算されています。参考として男性特有の健康課題による損失額も記載されていますが、こちらは1.26兆円となっており、両者には大きな違いがあることがわかります。
このように、女性の健康上の課題を解決し、働きやすい環境を整えていくことが、日本経済にとっても良い影響をもたらしていくと考えられているのです。
健康診断の種類や対象者、注意点等を詳しく解説しています。
【関連記事】
健康経営におけるメンタルヘルス不調者の低減に向けた取組について解説しています。
テクノロジーが進歩してきた
フェムテックの注目度が高まっているもう一つの要因は、テクノロジーそのものの進歩にあります。IT技術の発達により、アプリやAI等の開発が進んだことで、現在では健康分野についても有益なサポートが行える環境が整えられつつあります。
アプリを用いた健康管理やオンライン診療、細やかな健康相談等が可能となり、誰でも手軽にサービスを利用できるようになりました。その結果、フェムテックという用語は知らない方でも、関連するサービスに触れる機会は増えつつあります。
フェムテックに関心を持つ企業や自治体が増えた
女性の働きやすさ向上の取組として、福利厚生の一つにフェムテックを導入する企業も増えてきています。具体的な事例は後述しますが、検査や治療の費用を負担したり、健康問題に関するセミナーを取り入れたりと、さまざまな形で課題解決の取組が実施されています。
また、自治体においても、フェムテックを活用した支援サービスを導入するケースが増えています。官民一体となって取組が進められるなかで、女性の健康問題を前向きに考える機会が広がり、個人レベルでもフェムテックへの関心が高まっていると言えるでしょう。
【関連記事】
ワーク・エンゲージメントを高めるための職場づくりについて解説しています。
フェムテックで解決できる課題

フェムテックの活用により、具体的にはどのような課題が解消されるのでしょうか。ここでは、「働く女性を支える」という点にフォーカスして、フェムテックの効果を見ていきましょう。
生理に関する悩み
生理に関するアプローチは、フェムケアの分野で早くから発展してきました。生理痛やPMS等の心身の不調、肌トラブルの解決のために、さまざまな製品やサービスが開発されており、既に広く利用されています。
一方、フェムテックの分野においても、生理周期や体調を記録できる月経管理アプリが徐々に利用され始めています。生理周期が予測できることで、次の生理を事前に把握しやすくなり、柔軟に対策を講じられるようになるのが大きな効果です。
働く女性にとっては、どの周期で体調に変化が起こるかがわかるため、仕事量の調整等に活用できるでしょう。さらに、アプリには生成AIを活用した相談チャット機能が搭載されているものもあり、生理やPMSの悩みを相談することもできます。
それ以外のサービスとしては、オンライン診療や処方が挙げられます。忙しくてなかなか婦人科を受診できない方でも、オンラインで診療を受けられ、必要があればピル等を処方してもらうことも可能です。
妊娠・出産に関する悩み
妊娠・出産は身体・精神ともに負担が大きく、働く女性にとってはキャリアにも影響を与える重要なライフイベントです。フェムテックにおいては、妊娠・出産に関する悩みを解決する方法として、専門医へのオンライン相談サービスの活用が期待されています。
自宅にいながらでも産婦人科医や保健師、助産師等に相談可能なため、ちょっとした体調の変化であれば、通院をしなくても対処できる場合があります。産休に入る前の不安を解消し、無理なく仕事と体調管理を両立する上では、役立つ仕組みと言えるでしょう。
また、妊娠中の体調を記録、管理できるアプリもさまざまな種類のものが運用されています。妊娠週数における胎児の発育状況や、母体の健康状態に合わせて、医師や助産師からアドバイスを受けられます。
更年期障害に関する悩み
更年期障害は、女性ホルモンの急激な減少によって引き起こされる症状の総称であり、日常生活に支障をきたすこともあります。泌尿器や生殖器系の症状だけでなく、頭痛やめまい、不眠、神経系の異常といった幅広い影響をおよぼすことから、特に大きな経済損失を引き起こす要因ともされています。
また、一般的に45~55歳ごろに起こりやすいとされていることから、職場で中核を担う人材に生じる可能性もあるでしょう。フェムケアの分野では、既に吸汗性や速乾性のあるインナーの着用、保温性の高いショーツ、吸水ショーツ、サプリメントといった多様な商品が普及しています。
一方、フェムテックの分野においても、アプリやオンラインサービスを通じて、症状や対策等のスムーズな情報提供が実現されています。更年期障害は一時的な体調不良やメンタルヘルスの不調と混同されることも多く、自覚が難しいのが特徴です。
情報収集が円滑化されることで、人には相談できないような悩みを抱える方も、スムーズに自身の状況を把握できるようになるでしょう。その結果、適切な対策を打てるようになり、日常生活への影響を最小限に抑えられるのが重要な効果です。
フェムテックを課題解決につなげるポイント

ビジネスの分野において、実際にフェムテックを課題解決につなげるためには、どのような取組が求められるのでしょうか。ここでは、中小企業がフェムテックを活用する上で、重要となるポイントを解説します。
自社の現状を把握する
フェムテックを自社に導入する際には、まず実態を的確に把握する必要があります。経済産業省のレポートでは、女性従業員側に確かなニーズがある一方で、企業側は「何をすべきかわからない」というミスマッチが指摘されています。
そのため、まずは自社で働く女性従業員がどのような働き方をしているのか、どのような健康課題を抱えているのかを知ることが第一歩です。しかし、健康に関する悩みはデリケートであり、当事者の声を拾い上げるのは容易ではありません。
そこで、従業員の能動的な動きが必要な方法だけでなく、健康診断等の受動的なアプローチも活用するのがポイントです。また、専用の相談窓口を設置し、プライバシーに配慮した状態で悩みに関するデータを収集するのも良いでしょう。
加えて、従業員の健康管理等を効果的に行うためには、医学的な専門知識も必要なため、産業医を置くことも検討してみましょう。産業医の指導を受けることで、職場の健康意識の向上や作業環境の改善等につながるアドバイスを受けられるはずです。
意思決定権者の理解を図る
男性従業員の割合が多い企業では、女性の健康課題に対する認識が遅れてしまいがちです。特に、管理職に男性が多い場合は、どうしても男性に多い健康課題(喫煙・メタボ等)にばかり着目されやすいと言えるでしょう。
そこで、取組に先んじて管理職向けの研修を行うなど、意思決定や伝達に関わる重要なポジションを中心に意識改革を進めることが大切です。例えば、「社内メルマガ等による情報提供」「外部講師によるセミナーの開催」のように、組織的な施策を実行しながらフェムテックを活用する土台づくりを行いましょう。
健康診断や健康情報の活かし方について解説しています。
全社的な取組として推進する
フェムテックは特定の部署だけで推進するものではなく、全社的な取組として進めていく必要があります。場合によっては勤務体制や休暇のあり方にも影響を与える可能性があるため、全体の足並みがそろわなければ不公平感が生まれてしまうでしょう。
そして、企業全体で取組を進めるには、やはり経営陣が率先して自社における女性の働き方や健康課題を認識しなければなりません。主体的に情報をキャッチし、取組のロードマップを作成していくことで、従業員からの理解が得やすくなります。
自社にノウハウがなく、取組の方向性が見えない場合は、外部の専門家のサポートを受けるのも有効な方法です。
ウェルビーイングの基本的な意味や注目されている理由、企業経営への活かし方について解説しています。
フェムテックに取り組む企業の事例を紹介

フェムテックの活用を考える上では、具体的なサービスの仕組みを理解することが大切です。ここでは、経済産業省がまとめている「フェムテック等サポートサービス実証事業」から、特徴的なサービス提供を行う企業の事例をご紹介します。
事例1:PMS・更年期等の心の不調とうまく付き合うためのアプリ活用
ある大手生活用品メーカーは、PMSや更年期障害等に起因する「心の不調」に焦点を当て、上手に付き合っていくことを目的としたアプリを開発しています。これまで、精神的な不調には個人の気質も関わることから、状況に応じた対処が難しいのが課題とされてきました。
そこで、アプリでは「個人の考え方のくせ」に着目し、傾向を個別に把握した上で改善を促す仕組みが導入されています。アプリを活用すれば、一人ひとりが自らの考え方の習慣を理解し、それに合わせて認知行動療法に基づいたセルフケアプログラムを実践できるという仕組みです。
アプリを活用することで、ネガティブな思考ルーティンが改善され、精神的な不調に対する負担を軽減できる効果が期待されています。
事例2:生理痛体験研修プログラムの開発
あるスタートアップの企業は、VR体験デバイスを用いた生理痛体験研修プログラムを開発しています。具体的には、EMS(電気的筋肉刺激)技術によって腹筋を刺激することで、男性でも疑似的に生理痛を体験できるという仕組みです。
生理痛は多くの女性が経験する一方、個人差があることから、つらさや業務への影響が共有されにくいのが現状です。男性従業員からすれば、たとえ女性の健康を支援するポストに就いても、実態としての理解は難しいと言えるでしょう。
そこで、同社では女性の健康や活躍を推進する取組の一環として、VRデバイスを活用した研修プログラムの提供に力点が置かれています。
事例3:更年期オンライン診療の実施
あるスタートアップの企業は、医師・医療従事者による医療チームを構築し、更年期障害を対象としたオンライン診療サービスを提供しています。従来、更年期障害の診療報酬は低く、医師側にとっては持続可能な経営を行うことが難しい状態にありました。
その結果、診療窓口が不足してしまい、更年期障害の受診率が上がらないという実情につながっています。そこで、オンラインで更年期症状に対する包括的な医療ケアを可能にするために生まれたのが本サービスの仕組みです。
オンラインで医療従事者とも連携を図ることで、医師側の診療の負担を軽減するとともに、患者側に対しても受診のハードルを下げるのが狙いです。
事例4:健診データ等を活用したセルフケアアドバイス&カウンセリングサービスの実施
医療統計データサービスを扱うある企業は、健診等で集積した医療ビッグデータを活用し、月経・PMSに関するアプリとカウンセリングサービスの開発を行っています。大きな特徴は、月経・PMS症状と健診結果の関連性を膨大なデータから分析し、「なりやすい症状」や「症状に応じたアドバイス」をパーソナライズして提供できる点にあります。
月経やそれに伴う症状は個人差が大きいことから、個別の体質に合わせたアプローチが行えるのは、重要な利点と言えるでしょう。本事業では、ユーザーにアプリを通じて自身の症状を細かく認知してもらい、そこから適切なセルフケアとカウンセリングによるメンタルケアにつなげていくまでを一連のプロセスとして扱っています。
企業が福利厚生として活用すれば、従業員自身のリテラシー向上から適切なケア、効果測定までをまとめて行える仕組みとなっています。
まとめ
女性の社会進出が実現されるなかで、女性特有の健康課題やそれに伴う経済損失への注目度も高まってきています。特に月経や妊娠・出産、更年期障害による仕事への影響は、従業員本人はもちろんのこと、企業にとっても無視できない課題と言えるでしょう。
社内へのフェムテックの導入は、女性の健康課題を解消に導く有効打となり得ます。一方で、取組を進めるためには、経営層や管理職に就く男性からの理解が欠かせません。
フェムテックの仕組みやサービスの具体例、企業における実践例等を参考にしながら、社内の意識改革に着手してみてはいかがでしょうか。
【参考情報】
2025年4月11日付 内閣府男女共同参画局 「女性活躍とフェムテック」
2024年2月5日付 厚生労働省 2023年度第7回雇用政策研究会 「職場における女性特有の健康課題」
2024年11月1日付 株式会社矢野経済研究所 「フェムケア&フェムテック(消費財・サービス)市場に関する調査を実施(2024年)」
2024年6月11日付 内閣官房すべての女性が輝く社会づくり本部 「女性活躍・男女共同参画の重点方針2024 (女性版骨太の方針2024)」
2024年2月付 経済産業省ヘルスケア産業課 「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」
2025年4月11日付 経済産業省 「新しい当たり前をつくり女性が働きやすい社会を」
2024年3月26日付 厚生労働省 雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会(第3回) 「今、働く女性が求めている健康支援策とは?」