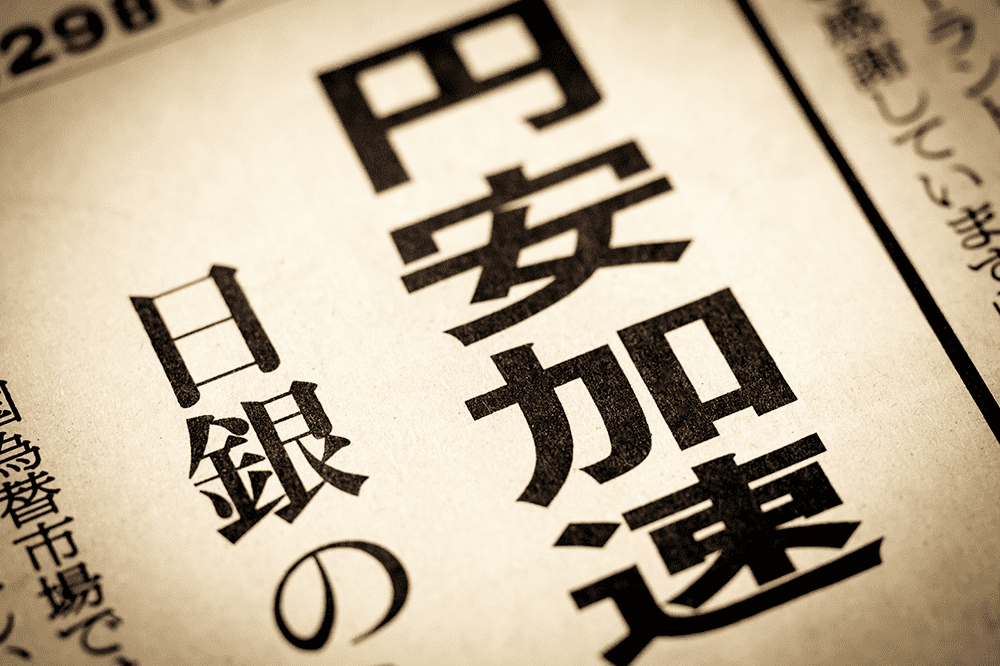ガソリン暫定税率廃止とは?想定されるメリットとリスク、今後の見通しを解説
公開日:2025年11月10日
助成金・補助金

ガソリン暫定税率とは、1974年に導入されたガソリン税の一種です。当初は臨時的な措置として導入されたものの、名称を変えながら現在まで存在してきましたが、2025年は廃止に向けて大きな動きが生まれました。
この記事では、ガソリン税の基本的な仕組みを解説した上で、ガソリン暫定税率の現状や今度の見通しについて詳しくご紹介します。また、個々の企業がとるべき対策についても確認していきましょう。
ガソリン税の基本的な仕組み

ガソリンの暫定税率廃止について知る上では、ガソリン税の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。一般的に「ガソリン税」という時には、揮発油税・地方揮発油税、暫定税率を指します。
しかし、実際のガソリン料金には、ほかにもいくつかの税金が加算されています。まずは、ガソリンに関する税金の仕組みを確認しておきましょう。
揮発油税と地方揮発油税
主なガソリン税には、国税である「揮発油税」と、地方税である「地方揮発油税」の2つがあります。揮発油税とは、ガソリン等の揮発油にかかる税金であり、「1リットルあたり24.3円」と決められています。
地方揮発油税は、特定の国税を国から地方自治体に譲与する「地方譲与税」の一部であり、税額は「1リットルあたり4.4円」です。これらの揮発油税・地方揮発油税を合計すると、税額は「1リットルあたり28.7円」となります。
暫定税率
暫定税率とは、1974年のオイルショック後に導入された増税措置のことであり、ガソリン税に上乗せする形で設定されています。もともとは、急激な燃料価格の高騰に対処しつつ道路整備財源を確保するため、特定財源として導入されました。
「暫定」という名称のとおり、本来は一時的な措置として導入されたものであるものの、名称や仕組みを変えながら現在まで残っています。税額は1979年までに現在の水準へと引き上げられ、「1リットルあたり25.1円」となっています。
ガソリン価格の全体像
上記のように、揮発油税・地方揮発油税、暫定税率を合計すると、2025年9月現在におけるガソリン税は、「1リットルあたり53.8円」となっています。実際のガソリン代には、さらに「石油石炭税」(1リットルあたり2.04円)、「地球温暖化対策税」(1リットルあたり0.76円)が加わり、最終的に消費税が課される仕組みとなっています。
そのため、ガソリンの本体価格によっても若干の違いは出ますが、小売価格の4割程度を税金が占めているのが現状です。
【関連記事】
企業におけるコスト削減の方法について解説しています。
暫定税率のこれまでの流れ

前述のように、ガソリンの暫定税率は臨時の課税措置として導入されたものの、さまざまな変遷を経て現在も残っています。過去には実際に廃止が実行されたこともあり、暫定税率については多様な見方が存在していると考えられます。
ここでは、暫定税率のこれまでの動きについて、特に重要性が高いトピックを整理しながら見ていきましょう。
暫定税率の導入~一時廃止
ガソリンの暫定税率は、1974年に「2年間の臨時措置」として導入された税制措置です。「第7次道路整備五箇年計画」の財源不足と、高度経済成長期のインフラ需要増、オイルショックによる財政悪化等を理由に、道路特定財源として導入されました。
当初はあくまで臨時的な制度として取り入れられたものの、その後は延長を繰り返し、現在に至るまで数十年にわたって維持されています。2008年にはねじれ国会の影響で一時廃止されるものの、法案の再可決によりわずか1か月で復活し、ガソリン価格が乱高下する事態に陥りました。
一般財源化と名称変更
その後、暫定税率は2009年に道路特定財源から一般財源へと切り替わり、使途が柔軟化されます。一方、2009年の衆院選では、暫定税率の廃止をマニフェストに掲げた民主党の大勝により、暫定税率廃止への動きが強まります。
しかし、財政状況の厳しさによって方針を切り替えざるを得ず、暫定税率は「当分の間税率」と名称を変えて維持されることとなりました。名称が変更されても、実質的な仕組みは変わらず、税負担にも特に変化はありませんでした。
そのため、変更後のネーミングはあまり浸透せず、現在でも一般的には「暫定税率」や「旧暫定税率」の名称が使用されています。
トリガー条項の導入と凍結
暫定税率が実質的に維持されたことで、代わりの措置として2010年の税制改正で導入されたのが「トリガー条項」です。トリガー条項とは、ガソリン価格が「3か月連続」で「1リットル160円を超える」場合、上乗せ部分にあたる25.1円の課税を停止するという制度です。
また、発動後に「3か月連続」で「1リットル130円を下回る」状態が続いた場合には、上乗せ分の課税が再開します。このように、決められた価格要件を引き金に発動される仕組みであることから、トリガー条項という名称がつけられました。
これにより、家計を圧迫するほどの価格高騰が起こった時には、柔軟に負担軽減措置を実行できるようになりました。しかし、翌年の2011年3月に起こった東日本大震災により、トリガー条項はわずか1年で凍結されることとなります。
震災の状況下でトリガーが発動されれば、さらなる混乱を招く恐れがあると判断されたのです。さらに、復興財源の確保も必要になったことから、4月にはそのまま凍結が決まりました。
2022年には与党2党と国民民主党の3党で凍結解除の協議が持たれるも、法改正や事務負担増の問題から、2025年現在に至るまで解除はされていません。
ガソリン補助金制度の導入
2021年には原油価格の高騰や円安に伴い、ガソリン代が急激に上昇し、秋には1リットルあたり160円を超えました。こうした状況を受け、政府はガソリン等に対する補助金制度を導入します。
当初は、全国平均ガソリン価格が1リットル170円を超えた部分について、1リットル5円を上限に元売りへ補助金を支給する期間限定の措置として採用されました。しかし、その後も世界情勢の混乱や円安によってガソリン価格が高騰し、延長・拡充が続けられた結果、現在では「定額1リットルあたり10円」の補助金が支給されています。
暫定税率廃止の動き

度重なる議論を経て、2025年にはガソリン暫定税率廃止を巡る大きな変化が生まれています。ここでは、2025年10月現在における、ガソリン暫定税率廃止の動きについて解説します。
2025年11月1日に廃止の見通し
2025年6月には、野党超党派による暫定税率廃止法案が国会に提出されました。法案は衆議院で可決された一方、参議院では否決され、いったんは廃案となります。
しかし、参院選での与党過半数割れによって事態が変化し、7月30日には暫定税率廃止が与党2党と野党4党によって合意されました。実施の時期は明言されていないものの、2025年中のできるだけ早い時期に行うという内容で合意が行われています。
その後、8月1日には野党7党により、改めてガソリン暫定税率廃止を求める法案が衆議院に提出されました。その内容は2025年11月1日から暫定税率を廃止し、補助金を段階的に拡充していくというものです。
2025年10月現在においては、まだ期日こそ確定されているわけではないものの、廃止に向けた動きは急加速していると言えるでしょう。
暫定税率の廃止で想定されるメリット

それでは、実際に暫定税率が廃止されると、家計や経済にはどのような影響が生まれるのでしょうか。廃止によって期待されているメリットを2つのポイントから見ていきましょう。
家計負担の軽減
まず期待されているのは、家計負担の軽減です。暫定税率の廃止によってガソリン代が下がるため、自家用車を使う世帯では支出の削減につながります。
仮に1リットルあたりのガソリン代が税込170円であるとすると、暫定税率が廃止されれば、消費税の軽減分も含めて1リットルあたり142円まで下がります。これは、現行のガソリン代から見て、約15%の値下げに該当する金額です。
また、環境省のデータによれば、2022年度における1世帯あたりの自動車用燃料の平均支払金額は年間7.1万円です。そのため、年間ベースで見れば、ガソリン代だけでも1万円近くの負担軽減につながると言えるでしょう。
ただし、自家用車の有無や居住地域によっても影響は異なります。また、後述するようにガソリン補助金の打ち切りが考えられるため、実質的に10円分の値下げは相殺される可能性が高いです。
物流・公共交通における経費削減
物流や公共共通の分野においては、燃料費の価格が経営状態に大きな影響を与えます。例えば、公益社団法人全日本トラック協会の『経営分析報告書 令和5年度決算版』によれば、燃料油脂費が営業費用全体の14.9%を占めているとされています。
燃料油脂費が削減されれば、経済を支える運送業や公共交通機関の経営状況にプラスの働きをもたらすため、大きな経済効果が生まれる可能性もあるでしょう。また、輸送費等の低下により、物価の高止まりを抑制する作用も期待されています。
ただし、燃料油脂費のほとんどは「軽油費」であり、軽油はガソリン暫定税率廃止の対象とはなっていない点に注意が必要です。現在、軽油についての見直しも論議されているものの、今後の動き次第では、影響が限定的になる可能性も十分にあり得ます。
暫定税率の廃止で想定されるリスク

暫定税率の廃止には、メリットだけでなくデメリットもあると考えられています。ここでは、現在想定されているマイナス面の影響について解説します。
財源不足の発生
暫定税率の廃止がなかなか実現しなかった背景には、やはり財源不足の課題が存在します。政府の8月時点の試算によれば、11月からの暫定税率廃止とそれまでの段階的な引下げ、さらに軽油・重油も同水準の引下げを行った場合、年度内に約6,000億円の財源不足が生じるという見込みです。
さらに、年間で見れば、ガソリン税のみで1兆円程度、軽油引取税も含めると1兆5,000億円の減収が見込まれています。代替となる財源について、現時点では明確な見通しが立てられておらず、インフラ整備等の財源不足が問題視されているのが現状です。
新税創設や補助金廃止の可能性
暫定税率の廃止により、現在行われているガソリン補助金は終了するものと考えられます。資源エネルギー庁の資料においても、定額引下げ措置の期間は「いわゆる『ガソリンの暫定税率』の扱いについて結論が得られて、それが実施されるまでの間」と明記されています。
現在は1リットルあたり定額10円の補助が行われているため、暫定税率の廃止による実質的なガソリン代の軽減分は、「1リットルあたり15.1円+消費税」となる点に注意が必要です。また、不足する財源の代替として、新たな税金制度が創設される可能性もあります。
いずれにしても、現時点で恒久的な財源の見通しは立てられていないため、与党を中心に2025年11月1日の廃止は現実的ではないという見方も強いです。さらに、最終的なガソリン価格には国際的な原油価格の変動も影響するため、仮に暫定税率を廃止しても、経済全体への恩恵は短期にとどまってしまう可能性もあると指摘されています。
国際的な流れへの逆行
ガソリン税の減税は、カーボンニュートラルをめざす国際的な流れに逆行すると見られる恐れもあります。現代の国際社会では、ガソリン依存による地球環境への負担を抑制する動きが強まっており、OECD加盟国の多くがガソリンに高い税を課している状況です。
財務省のデータによれば、OECDに加盟する35か国のうち、2024年第3四半期時点における日本のガソリン小売価格は34位、税負担額は32位、税負担率は29位となっています。国際的な比較においては、日本のガソリン税は現状でもかなり低いのが実情と言えるでしょう。
暫定税率が廃止されれば、結果としてガソリンの消費を促し、カーボンニュートラルの動きから乖離してしまう恐れもあります。そのため、地球環境への影響はもちろん、諸外国との関係性やエネルギー安全保障の確保にも配慮しなければなりません。
ガソリン暫定税率廃止に備えて企業がすべきこと

これまで見てきたように、ガソリン暫定税率の廃止は具体的なタイミングこそ固まっていないものの、このまま実行されるとの見方は強いです。ここでは、廃止の動きに備え、個々の企業がどのような取組を進めるべきなのか、3つのポイントに分けて整理しましょう。
今後の動きは細かくチェックしておく
2025年10月時点における現状は、与野党が合意形成を図っている段階であり、まだハッキリとした動きが示されていません。しかし、廃止に向けた議論は活発化しており、野党法案のとおりに11月1日から導入されるケースも十分に考えられます。
実際に廃止が発表されれば、その前後はガソリンの買い控えや、急激な需要の増加が起こることも予想されます。業務に自動車を使用する場合は、前後の流通の混乱も踏まえて、早めに手を打っておくことが重要です。
一方、廃止が先延ばしになる場合も、補助金の仕組みや金額等に動きが見られる可能性はあるでしょう。また、実際に廃止が実行されてからは、代替の財源として新たな税制や法案が策定される場合もあります。
そのため、まずは今後の動きに引続き注目し、政策の変化を見逃さないようにすることが重要です。
コストの見える化を行う
社用車を用いている場合は、各車が普段からどの程度の燃料を消費し、どのくらいの経費につながっているのかを把握しておくことも大切です。先ほどご紹介したように、家計レベルで見ても年間で1万円近くの変化が生まれる可能性もあるため、企業経営には大きな影響が起こると考えられます。
例えば、30台の社用車が1台あたり平均で月間100リットルのガソリンを消費していると考えると、暫定税率の廃止によって一月あたり約5万円(=15.1円×3,000リットル+消費税)の経費削減効果が生まれます。
年間で見れば約60万円の経費削減につながるため、その分をどのように投資するかなど、経営戦略にも幅が生まれるでしょう。そのため、まずは車両ごとにコストを調べ、廃止後のメリットを数字で把握しておくのがおすすめです。
事前にコストの違いを計算しておけば、廃止後のメリットを最大化するための戦略を立てやすくなるでしょう。
【関連記事】
企業におけるコスト削減の方法について解説しています。
複数のシナリオプランを用意しておく
戦略を立てる上では、複数のシナリオプランを用意しておくことも大切です。暫定税率廃止が11月1日に行われるケースだけでなく、やや遅れて年内に実施されるケース、あるいは年内に行われないケース等も想定し、どのように舵を切っていくのかを明確化しておくと良いでしょう。
さらに、暫定税率が廃止された後に、代替となる税金が導入されるリスクに備えることも大切です。例えば、走行距離課税等が導入された場合に備え、営業ルートの見直しを図り、より効率的なプランを組み立てるのも一つの方法です。
また、社用車の利用実態を踏まえて、低燃費車やEVへ車両の買換えを行ったり、法人向けカーシェアの併用を検討したりするのも良いでしょう。その上で、従業員へのエコドライブの徹底を図るなど、地道な取組を重ねていくことが重要となります。
まとめ
2025年10月現在、ガソリン暫定税率の廃止はどのタイミングで行われるかが定まっていません。8月時点での野党法案では11月1日の実施が求められているものの、現在はまだ細かな動きを調整している段階です。
しかし、廃止の動きそのものはこのまま進んでいくと考えられているため、それに伴う影響を事前に想定しておくことが大切です。個別の企業においても、燃料費の見直しやコストの見える化、複数のシナリオプランの準備等、事前にできることがいくつかあります。
自社への影響を丁寧に見極め、廃止が実行された際にすぐ動けるよう、柔軟なプランを立てておきましょう。
【参考情報】
2025年10月13日付 財務省 「自動車関係諸税・エネルギー関係諸税に関する資料」
2025年10月13日付 千葉県石油協同組合 「ガソリンと税金のおはなし」
2025年10月13日付 総務省 「地方譲与税について」
2025年5月20日付 経済産業省資源エネルギー庁 「エネこれ」
2025年10月13日付 経済産業省資源エネルギー庁 「燃料油価格定額引下げ措置」
2025年10月13日付 環境省 「家庭部門のCO2排出実態統計調査 家庭のエネルギー事情を知る」
2025年3月付 公益社団法人全日本トラック協会 「経営分析報告書(概要版)―令和5年度決算版―」
2025年10月13日付 独立行政法人経済産業研究所 「経済を見る眼 ガソリン税の暫定税率廃止は正しい選択か」