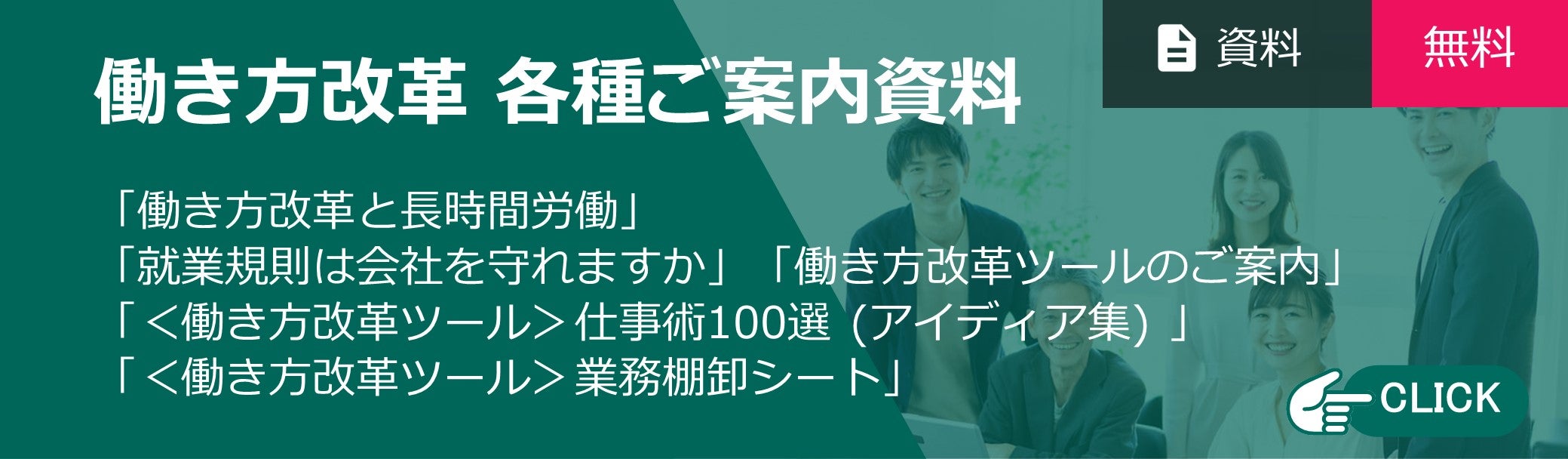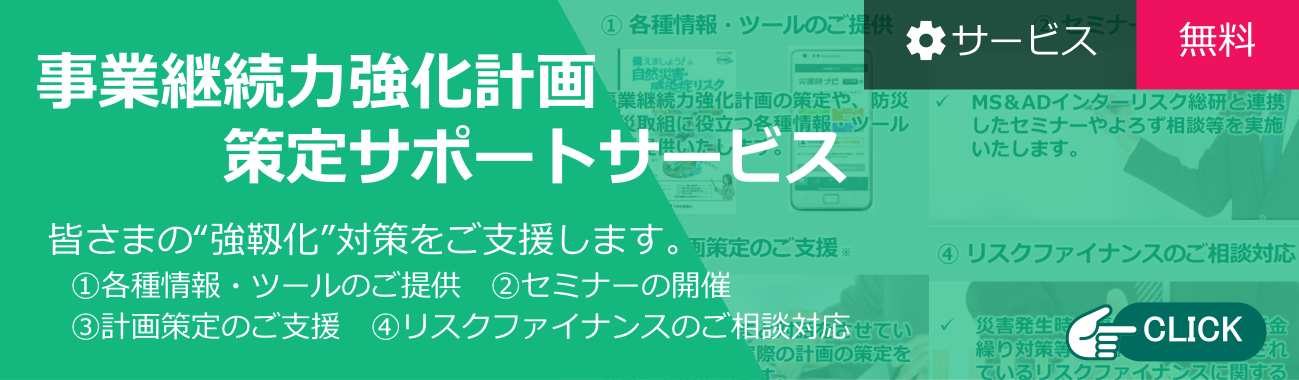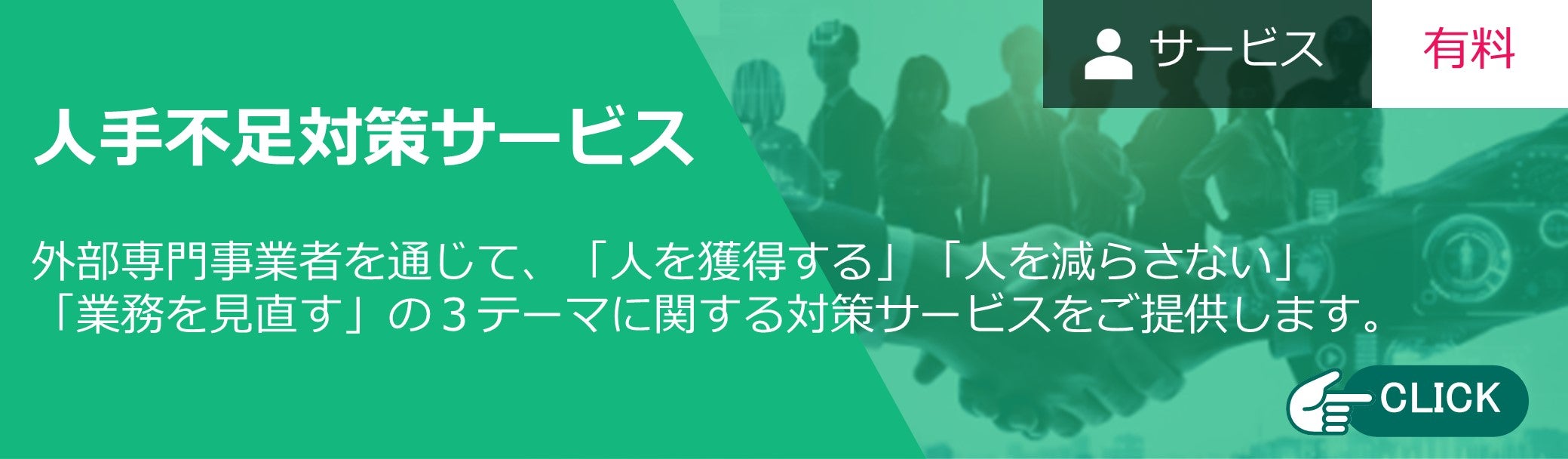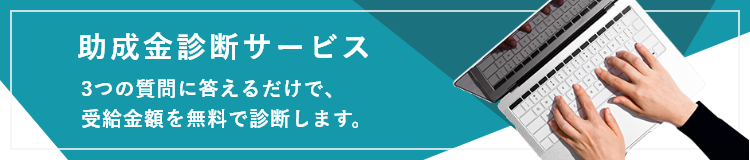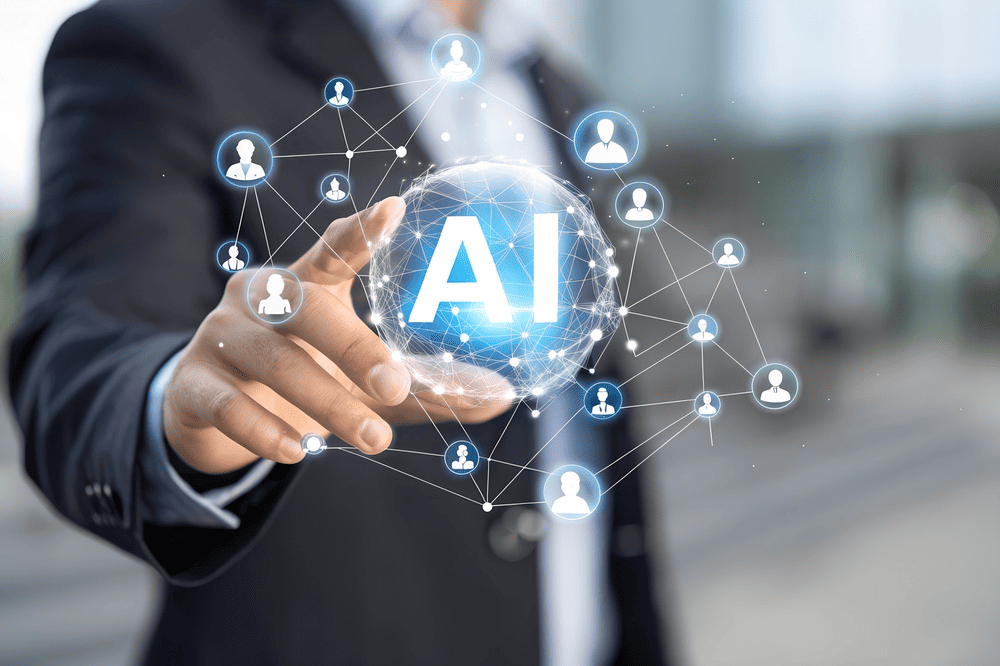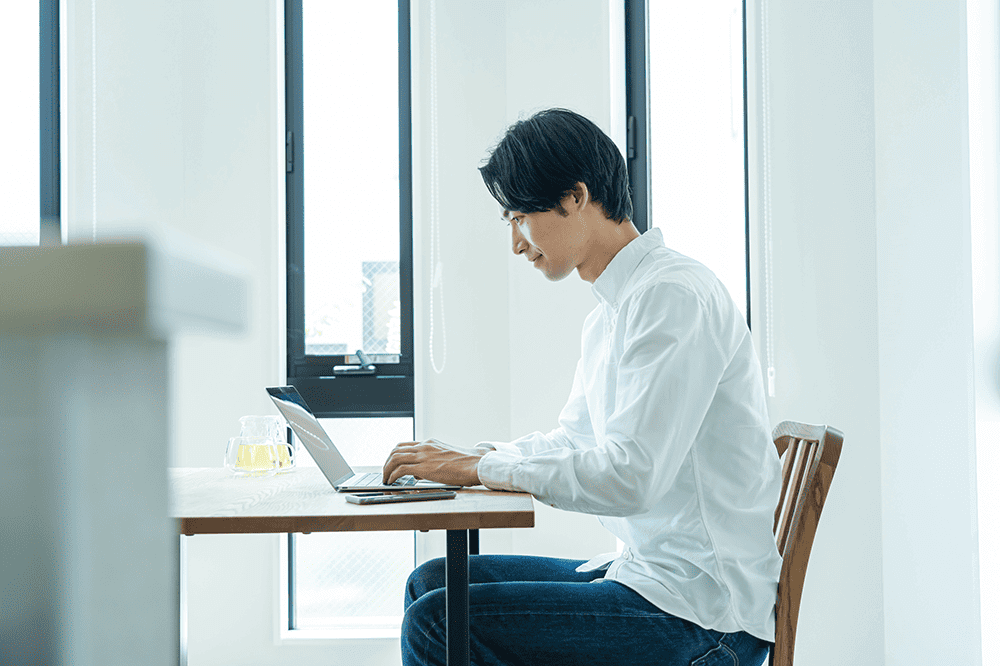ビジネスケアラーとは?企業に与える影響と取り組むべき施策、活用できる助成金制度を解説
公開日:2025年9月29日
人事労務・働き方改革
人手不足

少子高齢化により、家族間での介護は年々増加しています。近年では家族構成の変化や共働き世帯の増加から、現役世代が介護を担い、「ビジネスケアラー」となるケースもめずらしくありません。
今回は、社会問題としてのビジネスケアラーの実情や課題、企業経営に与える影響について詳しく解説します。その上で、個別の企業がどのように対処すべきなのか、取組の方向性と活用できる助成金制度を通じて見ていきましょう。
ビジネスケアラーの現状と今後の見通し

少子高齢化の進行に伴い、ビジネスケアラーの数はますます増加しています。ここでは、データをもとにビジネスケアラーの現状と今後の見通しを確認してみましょう。
毎年約10万人の介護離職者が発生
経済産業省の将来推計の調査によれば、2025年時点において、家族介護者の合計は約795万人(年齢階層別人数割合と将来推計人口の掛け合わせにより算出)となっています。その数は過去10年で200万人近く増加しており、そのうち307万人がビジネスケアラーとなっているのが実情です。
さらに、データによると、介護者が家族介護にかける平均時間は推計で1日2時間あまりとされています。現役世代の可処分時間が損なわれれば、仕事のパフォーマンスにも悪影響をおよぼし、モチベーションの低下や心身の不調を引き起こすこともあるでしょう。
さらには、そのまま離職に至ってしまうケースもめずらしくはありません。実際のところ、直近の数年では毎年約10万人の介護離職者が発生しており、経済的にも大きな損失につながっています。
2030年には介護者の約4割がビジネスケアラーに
経済産業省の推計によれば、2030年には家族介護者が833万人となり、その4割にあたる318万人がビジネスケアラーとなる見通しが示されています。また、この数値は「仕事が主な者」のデータであり、介護を主としながら仕事を続ける者も含めた「有業者全体」では、438万人にものぼると推計されています。
さらに、今後も女性の雇用促進や高齢化の加速によって、ビジネスケアラーの数は上振れする可能性もあると指摘されているのが現状です。推計では、2040年まで毎年10万人の介護離職者が発生する状況が続くと示されており、国としての対策は急務と言えるでしょう。
2030年における経済損失は9兆円以上に
ビジネスケアラーによる経済損失の要因としては、主に次の4つが挙げられます。
・両立困難による労働生産性の損失
・介護離職による労働損失
・介護離職に伴う育成費用の損失
・代替人員の採用に関するコスト
例えば、介護発生前後における仕事の質に関するアンケート調査では、介護のスタートとともに平均で約3割の低下が見られていると回答されています。特に部長や役員クラスのパフォーマンス低下が顕著であり、介護に伴う管理職者の労働生産性の損失は深刻な課題です。
これらの影響を推計すると、2030年における家族介護に起因した経済損失は、合計9兆1,792億円にものぼるとされています。
ビジネスケアラーの増加が企業経営に与える影響

ビジネスケアラーの増加は、社会全体はもちろん、個々の企業経営にも大きな影響を与えます。ここでは、個別の企業において想定されるリスクを2つの観点から見ていきましょう。
仕事と介護の両立による労働力の損失
個別の事情によって度合いは異なりますが、自社の従業員が介護を抱えれば、一定の労働力を損失するのは避けられない事実です。経済産業省では、ビジネスケアラーの発生に起因する「個別の企業の経済損失額」が試算されています。
それによれば、従業員が仕事と介護の両立が困難となることに起因する損失額(労働生産性損失額+介護離職者発生による損失額)は、次のとおりです。
・大企業(製造業・従業員数3,000名)
年間6億2,415万円(労働生産性損失額:5億5,407万円+介護離職発生による損失額:7,008万円)
・中小企業(製造業・従業員数100名)
年間773万円(労働生産性損失額:686万円、介護離職発生による損失額:87万円)
前述のように、家族介護による生産性の低下は誰にでも起こり得るため、各企業が自社のリスクとして認識しておく必要があります。
中核人材の離脱による戦力の低下
一般的に、家族介護が必要となるのは、親が後期高齢者に差し掛かるタイミングと考えられます。子の年令からすると、ビジネスケアラーになりやすい年齢層は、ちょうど企業の中核を担う40~50代と重なってしまう点にも注意が必要です。
自社にとって重要な管理職者が、仕事と介護の両立を迫られる可能性も十分にあり、生産性の低下や離職に伴う戦力の損失は大きなリスクと言えるでしょう。
企業が仕事と介護の両立支援を行う重要性

ビジネスケアラーの増加に伴い、各企業には仕事と介護を両立できるような体制の整備が求められています。ここでは、企業が両立支援に取り組む重要性について、3つの観点から解説します。
選択的週休3日制のポイントについて解説しています。
人材不足へのリスクマネジメントにつながる
早い段階で介護と仕事を両立できる仕組みを構築すれば、将来的な人材不足のリスクマネジメントにつながります。現代ではほとんどの従業員がビジネスケアラーになる可能性を抱えており、いつ生産性の低下や急な離職は発生するかは予測できません。
一方で、人材不足への対策は一朝一夕に行えるものではなく、丁寧な計画と下準備が必要です。それだけに、将来的なリスクに備えるには、まだビジネスケアラーが発生していない段階から、介護との両立を踏まえた体制づくりを行うことが重要となります。
従業員との関係性向上につながる
仕事と介護の両立支援は、従業員との関係性向上にもつながります。企業が働きやすい環境づくりを行えば、従業員満足度やエンゲージメントが向上し、社内の生産性向上にも結びついていくでしょう。
特に、介護離職の予防に力を入れれば、個人のキャリア形成に対する企業の真剣な姿勢も示せます。従業員に安心してもらい、「自社で長く働きたい」と感じてもらえれば、定着率の向上につながるのもメリットです。
また、職場の環境整備が行われれば、現時点で介護と仕事を両立している従業員のサポートも充実します。そのため、健康経営の観点からも、特に効果的な取組となるでしょう。
【関連記事】
育児・介護休業法の改正点について解説しています。
中長期的な企業価値の向上につながる
ビジネスケアラーへの支援は、人的資本経営の実現にも直接的につながる取組です。近年ではビジネスケアラーへの注目度が高まっていることもあり、人材戦略の一部として取り入れれば、自社の信頼性を高める要素にもなり得ます。
その結果、取引先や株主といった、外部のステークホルダーとの関係性向上につながるのが大きな利点です。また、企業価値の向上という点を踏まえれば、多様な人材の登用等によって、競争力の強化やイノベーションの創出が期待できるのも重要なポイントと言えるでしょう。
さらに、柔軟な業務体制を構築することは、「BCP(事業継続計画)」の強化にもつながります。例えば、普段からリモートワークで業務が回る体制を整えておけば、災害時等に事業がストップしてしまうリスクも軽減できます。
ビジネスケアラーの支援に向けて企業が考えるべき課題

ビジネスケアラーの支援を行う上では、企業が直面しやすい課題を把握しておき、対策を考慮することが大切です。想定される主な課題を3つのポイントに分けて見ていきましょう。
従業員の状況把握が難しい
介護は出産や育児と異なり、明確なスタートラインがありません。そのため、従業員自身が負担を自覚しにくく、気づかないうちに疲弊してしまう面があります。
また、キャリアへの影響を懸念し、プライベートな事柄の開示に消極的な従業員も少なくありません。そのため、企業がサポート体制を築こうとしても、実態の把握そのものが難しいのが大きな課題となります。
効果的な支援体制を整えるには、リアルタイムかつきめ細かな状況把握が必要不可欠です。そのためにも、定期的なアンケート等を実施するとともに、企業と従業員との日ごろからの信頼関係が欠かせない土台となります。
将来の予測が難しい
要介護になる原因はさまざまであり、年令に関わらず急激に訪れる可能性があります。いつ誰が介護の当事者になるかの予測は難しく、終わりのタイミングも決まっていないため、どの程度の支援が必要であるのかを計算しづらい面があります。
また、家族構成等によっても状況が変わるため、仕事と介護の両立については極めて個別具体性が高いことを認識しておかなければなりません。必要なサポート内容やタイミングはそれぞれに異なるため、画一的な仕組みを取り入れるだけでなく、柔軟にカバーできる体制を整えることが重要です。
精神的な負荷の想定が難しい
介護に伴う精神的な負荷は、個別の家庭環境や状況によっても異なり、目に見えないため事前の想定は難しいと言えます。身体的には無理のないサポート体制を築いたとしても、目に見えないストレスやプレッシャー等で負荷が増大し、調子を崩してしまうこともあるでしょう。
従業員とその家族のあり方によって、多様なトラブルが想定されるため、福利厚生でできるだけ幅広くカバーすることが重要です。同時に、それぞれの困りごとを細かくくみ取れるような仕組みを作り、課題を取りこぼさないための配慮も求められます。
企業に求められる取組

ビジネスケアラーの支援に向けて、企業は具体的にどのような取組を進めるべきなのでしょうか。おおまかな方向性として、4つの施策をご紹介します。
相談しやすい環境づくり
ビジネスケアラーの支援にあたっては、何よりもまず相談しやすい環境づくりが土台となります。求められるサポートは個別に異なるため、従業員の状況を細かく把握するためにも、円滑な情報共有の仕組みが欠かせません。
具体的には、「社内の窓口を設ける」「定期的なアンケートを実施する」といった取組が挙げられます。また、企業の規模によっては、外部の専門家による相談先を利用できるようにするのも良いでしょう。
その上で、プライベートな悩みを打ち明けてもらうためには、信頼できる上司による個別面談も丁寧に行うことが大切です。いつでも相談できる雰囲気・関係性づくりが、1人で悩んだ末の介護離職から従業員を守ることにつながります。
利用できる制度の周知
従業員に対しては、家族の介護を抱えた時に備えて、利用できる制度を事前に周知しておくことも大切です。例えば、ビジネスケアラーが利用できる公的制度としては、「介護休暇」や「介護休業」があります。
介護休暇とは、家族介護のために、「年5日まで(対象家族が2人以上なら10日まで)」、1日単位もしくは時間単位で休みがとれる制度です。有給・無給は会社の規定によって異なりますが、「介護施設探し」「ケアマネージャーとの打ち合わせ」にも活用できる利便性の高い仕組みとなっています。
また、介護休業は対象家族1人につき「通算93日まで」休業できる制度です。休業期間中は「賃金の67%相当額」の給付金が支給されるため、経済的な損失も一定程度カバーできるのが特徴です。
まずは、これらの仕組みを研修等で事前に周知し、いつでも利用できるようにしておくことが重要となります。また、企業独自の福利厚生制度を設けている場合は、その仕組みや利用条件もわかりやすく提示する必要があります。
【関連記事】
介護手当や在宅介護で利用できる介護保険サービスについて解説しています。
個別の状況に応じた柔軟な勤務体制の構築
介護との両立をしやすくするため、リモートワークやフレックスタイム制を導入し、柔軟な勤務体制を構築するのも有効な方法です。その上で、単に仕組みを取り入れるだけでなく、実際に利用しやすい環境づくりも進めるとよいでしょう。
具体的には、「オンラインツールの導入」や「申請しやすい制度の構築」、「人員のゆとりの確保」等の準備が必要です。
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)を活用しよう

ビジネスケアラーの支援を行うためには、業務体制の改善や人員確保といった施策が必要であり、ある程度のコストもかかります。そこで、厚生労働省では、仕事と育児・介護を両立できる職場環境づくりを目的とした「両立支援等助成金」が取り扱われています。
ここでは、両立支援等助成金の具体的な仕組みや申請方法等をご紹介します。
基本的な仕組み
両立支援等助成金とは、仕事と育児・介護等を両立できる職場の環境づくりに取り組む中小企業を対象とした助成金制度です。目的に応じていくつかのコースが設けられており、仕事と介護の両立支援については、「介護離職防止支援コース」を活用できます。
介護離職防止支援コースの助成内容は、「介護休業」「介護両立支援制度」「業務代替支援」の3つに分かれています。
介護離職防止支援コースの内容
■介護休業
1.従業員が介護休業を取得し、職場復帰をした場合に40万円/人の支給
■介護両立支援制度
2.介護両立支援制度の対象制度を1つ導入し、その制度が利用された場合に20万円/人の支給
3.介護両立支援制度の対象制度を2つ以上導入し、1つ以上利用された場合に25万円/人の支給
■業務代替支援
4.介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用、派遣で受け入れた場合に20万円/人の支給
5.介護休業取得者の業務代替者に手当を支給した場合に5万円/人の支給
6.介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給した場合に3万円/人の支給
※1~3は、それぞれ1事業主5人まで
介護休業を利用するためには、「介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知」と、「労働者との面談実施、プランの作成・実施」、「連続5日以上の介護休業の取得」が条件となっています。また、介護両立支援制度を利用する場合も、「介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知」と、「労働者との面談実施、プランの作成・実施」は必須条件です。
その上で、以下のいずれかの制度を1つ以上導入し、実際に利用してもらった時に支給対象となります。
介護両立支援制度
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度
・在宅勤務制度
・フレックスタイム制度
・法定期間を上回る介護休暇制度
・介護サービス費用補助制度
なお、業務代替支援は、介護休業で抜けてしまう人員の補完として、新規採用や既存メンバーでのカバーリングを行った時に助成金が支給される仕組みです。
支給申請の流れ
介護離職防止支援コースを利用するには、まず就業規則等への明文化と、従業員への周知を行う必要があります。その後、実際に介護の必要が生じた従業員に対しては、面談を行い、一緒に介護支援プランを作成します。
その後の手続は、介護休業の場合と介護両立支援制度の場合と分かれるので注意が必要です。介護休業の場合は、業務の整理・引継ぎを行った上で、介護休業を連続5日以上取得させてから職場復帰をしてもらい、継続雇用をして3か月が経過した後に申請を行う必要があります。
介護両立支援制度の場合は、業務体制の検討を行ったのちに、実際に制度を利用してもらい、1か月の継続雇用後に申請を行います。業務代替支援では、対象となる行為(新規雇用や手当支給)が行われた事実を持って支給申請を行えば受給可能です。
両立支援等助成金の条件や内容は、毎年細かく変化しているため、最新の情報をもとに手続を進める必要があります。厚生労働省から、支給申請の手引きが公開されているので、事前にチェックしておくと良いでしょう。
まとめ
少子高齢化の進行に伴い、ビジネスケアラーの増加は日本社会の大きな課題となっています。それとともに、個別の企業においても、労働力・生産性の低下や重要な人材の離職を招く大きなリスク要因となっています。
ビジネスケアラーに対する支援は、自社の組織を安定させるだけでなく、従業員エンゲージメントや定着率の向上、対外的なイメージの向上にもつながる重要な施策です。まずは自社の現状を丁寧に把握し、どのような環境整備や施策が必要になるのかを検討してみましょう。