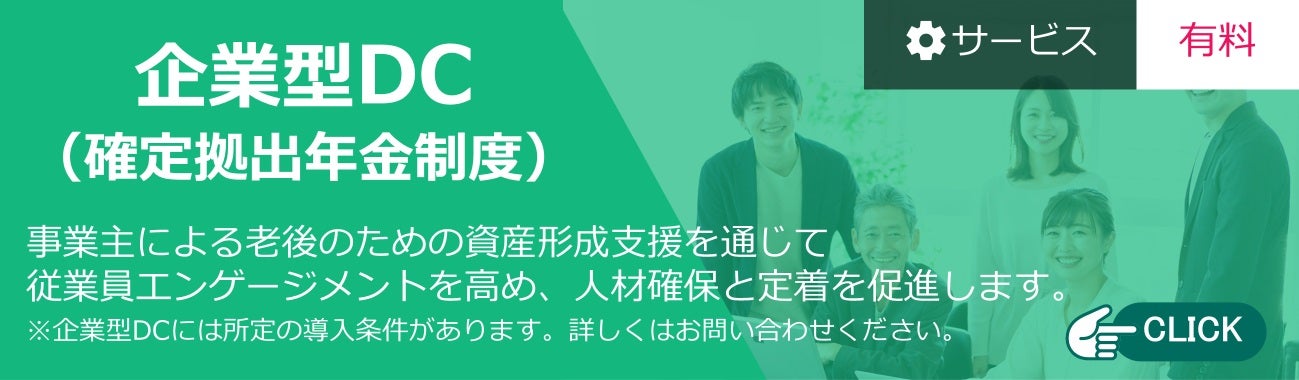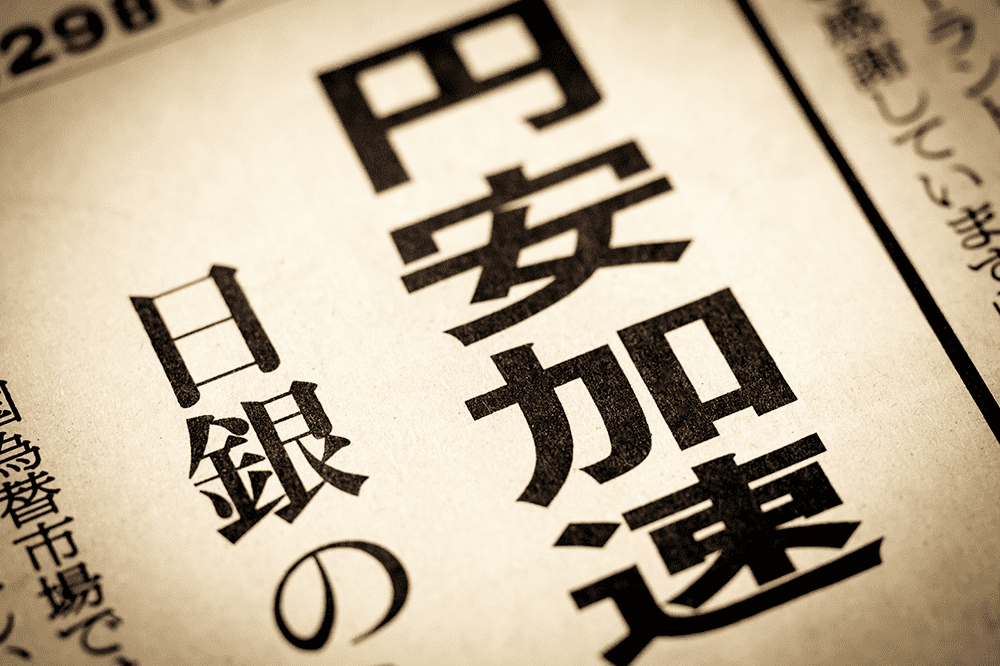企業型確定拠出年金(企業型DC)のメリット・デメリット、導入方法をわかりやすく解説
公開日:2025年8月4日
人手不足

企業型確定拠出年金とは、企業が導入する退職金制度の一種です。「確定拠出」という名称が示すように、拠出金が確定されているのが特徴であり、その掛金を運用しながら年金資産を形成していく仕組みです。
今回は企業型確定拠出年金の特徴や導入するメリット・注意点、導入方法等をわかりやすくご紹介します。
確定拠出年金制度とは

企業型確定拠出年金は、「確定拠出年金制度」の一種です。確定拠出年金とは、拠出された掛金と運用益の合計額によって、将来の給付額が決まる年金制度を指します。
将来受け取れる年金額が決まっている「確定給付企業年金」とは異なり、加入者自らが年金資産の運用を行い、その成果によって年金額が変わってくるのが大きな特徴です。また、大きなメリットとして、「運用益がすべて非課税になる」という点が挙げられます。
一般的な投資信託等では、運用益に20.315%の税金がかかるのに対し、確定拠出年金の利益には課税が免除されるため、利益が大きくなりやすいと言えます。一方、確定拠出年金では、原則として60歳まで積み立て資産を引き出すことができません。
定年退職を迎える60歳以降に、積み立ててきた年金資産を一時金(退職金)、もしくは年金の形式で受け取ることとなります。この点は、途中で解約可能な積み立てタイプの保険商品等と大きく異なるので注意が必要です。
なお、確定拠出年金には、企業型と個人型(iDeCo)の2種類があり、両者を併用することも可能です。
企業型確定拠出年金(企業型DC)
企業型確定拠出年金とは、「企業型DC」とも呼ばれており、企業が導入するかどうかを検討するのが特徴です。企業が導入を決めると、従業員も自動的に加入するのが一般的ですが、個人の意思で加入を判断できる選択型のタイプもあります。
掛金の拠出は企業が毎月一定の金額を積み立てて行い、拠出金は一般的に役職等に応じて決められます。ただし、掛金の上限額は最大年間660,000円(月額55,000円)となっており、それ以上の金額を拠出することはできません。
なお、他の企業年金を利用している場合は、最大年間330,000円(月額27,500円)が上限となります。また、掛金そのものは企業が負担しますが、資産の運用は従業員自らが行うため、受け取れる金額はその成果で変動します。
個人型確定拠出年金(iDeCo)
「個人型確定拠出年金」は、「iDeCo(イデコ)」の名称で広く知られており、国民年金基金連合会が実施する制度です。掛金は「加入者個人」が負担するのが特徴であり、その点が企業型確定拠出年金との大きな違いです。
個人型確定拠出年金の運営主体は国民年金基金ですが、国民年金第1号被保険者だけでなく、厚生年金の被保険者も加入することができます。企業年金等に加入していなければ、最大年間276,000円(月額23,000円)まで掛けられ、全額が所得控除されるため、個人で行える所得税・住民税の節税対策として注目されています。
企業型確定拠出年金のメリット

企業側のメリット
企業側のメリットとしては、主に以下の4つのポイントが挙げられます。
・退職金の積み立て不足の心配がない
・退職給付債務が発生しない
・掛金が全額損金扱いとなる
・福利厚生の充実を図れる
退職金の積み立て不足の心配がない
従来の確定給付型の企業年金では、実際に退職金を支払う時に備えて、企業が計画的に積み立てを行わなければなりません。それに対して、企業型確定拠出年金では、掛金を拠出した時点で企業の負担が確定するため、積み立て不足は発生しないのが特徴です。
毎月の掛金の拠出そのものが退職金の支払いとなるため、退職金積み立てに関する悩みが解消されやすいのがメリットとなります。
退職給付債務が生じない
「退職給付債務」とは、退職給付会計(企業の退職金や企業年金に関する会計基準)において、企業の債務として計上しなければならない金額のことです。退職一時金や退職年金は企業の債務として扱われ、年金資産等の差額は貸借対照表に「退職給付引当金」として計上しなければなりません。
退職給付債務は、全従業員についての期末時点において将来発生する退職後の支払総額を予測計算し、市中金利等を考慮して支払総額を現在価値に割り引いて求めます。企業型確定拠出年金を導入していれば、毎月の拠出によって給付義務を果たしたことになるため、退職給付債務は発生しません。
このように、退職会計上の手続や考え方がシンプルになるのが大きなメリットです。
【関連記事】
役員退職金の税金や支給事例について解説しています。
掛金は全額損金算入できる
企業型確定拠出年金の掛金は、全額損金算入することができます。企業の支出として扱われるため、法人税等の節税対策につながるのがメリットです。
福利厚生の充実を図れる
退職金制度の確立によって、福利厚生の充実を図ることができるのも、企業型確定拠出年金を導入する重要な目的です。退職金制度を整えることは、企業が従業員の老後にも目を向けているという明確な意思表示になります。
福利厚生の一環として取り入れることで、既存の従業員満足度の向上を図れるだけでなく、人材採用における競争力の強化も期待できます。
従業員側のメリット
企業型確定拠出年金を導入する際には、従業員にも仕組みを説明した上で、合意を得なければなりません。導入にあたっては、従業員にどのようなメリットがあるのかも丁寧に整理しておくことが大切です。
ここでは、従業員視点でのメリットを3つに分けて見ていきましょう。
【関連記事】
福利厚生制度の概要や注意点について解説しています。
所得税・社会保険料の負担軽減につながる
確定拠出年金の掛金は、社会保険料の算定の対象外となります。そのため、給与として受け取るよりも、社会保険料負担の軽減につながるのが重要なメリットです。
また、後述するマッチング拠出(従業員も上乗せして拠出できるタイプ)を取り入れる場合、従業員の拠出分は所得控除の対象となるため、所得税の負担も軽減されます。さらに、前述のように運用して得られた利益は非課税となるため、手取りが大きくなりやすいのも利点です。
iDeCoより掛金の上限が多い
同じ確定拠出年金制度である「iDeCo」と比べると、企業型確定拠出年金は掛金の上限が多いのも特徴です。最大で月額55,000円まで掛けられるため、法人税や所得税の節税効果も大きくなりやすいと言えます。
柔軟な利用・運用が可能
掛金の運用(金融商品の選択や資産配分の決定等)については、従業員個人で決めることができます。どのようにリスクをとるかを自分で選択できるので、運用スキル次第では大きなリターンが得られる可能性もあるでしょう。
また、選択型企業DCを選べば、従業員個人で加入するかどうかを判断することも可能です。企業型DCへの加入を選択しなかった場合、掛金分は給与として支払われるのが基本であるため、投資に消極的な従業員がいるケースでも問題なく導入することができます。
企業型確定拠出年金のデメリット

企業型確定拠出年金には、いくつか注意しておかなければならないポイントもあります。ここでは、導入にあたって検討すべきデメリットについて、企業側・従業員側のそれぞれの立場から見ていきましょう。
企業側のデメリット
企業側のデメリットとしては、主に以下の3点が挙げられます。
・運用コストの増大
・制度の見直しの手間の発生
・投資教育の努力義務
運用コストがかかる
退職金制度そのものを新たに導入する場合は、掛金を拠出するためのコストがかかる点を正しく理解しておく必要があります。実態にそぐわない掛金を無理に捻出しようとすれば、経営状況を悪化させてしまうリスクもあるため、資金設計は慎重に行わなければなりません。
また、企業型確定拠出年金を運用する上では、運営管理機関に支払うコストも発生します。さらに、制度構築等で外部のサポートを受ける際には、コンサルティングの依頼料等もかかるため、トータルコストを的確に把握した上で導入を検討することが重要です。
既存の制度を見直す必要がある
退職金制度を導入する際には、さまざまな制度の見直しが必要となります。例えば、退職金制度を設ける際には、就業規則に適用される従業員の範囲、支給要件、計算・支払いの方法、支払い時期等を記載しなければなりません。
また、既に他の退職金制度を利用している場合は、状況に合わせて既存の制度の見直しを図る必要があります。その上で、従業員に仕組みやメリットを説明し、適切な形で同意を得なければなりません。
導入時にはさまざまな手続が求められるため、ある程度の人的リソースが必要になる点も理解しておきましょう。
従業員への投資教育が求められる
確定拠出年金を導入する企業には、従業員に対する継続的な投資教育の努力義務が生じます。制度の加入時はもちろん、その後も定期的に投資教育を続け、適切な運用が行えるようにサポートする必要があります。
トラブルを避けるために、社内に専門的な知識・スキルを持つ人材がいなければ、外部(運営管理機関や企業年金連合会等)の講師を招いて適切な教育の場を提供することも大切です。そのため、導入時には投資教育を行うためのコスト、労力も計算に入れておく必要があります。
従業員側のデメリット
続いて、企業型確定拠出年金の導入にあたり、従業員に説明しておくべき留意点を確認しておきましょう。
60歳まで現金化はできない
確定拠出年金は「年金」という名称がつけられているように、年金資産の形成を行うための制度です。積立金は原則60歳になるまで現金化ができず、途中で脱退した場合でも、支払われるのは60歳以降となるため注意が必要です。
例外として、脱退一時金の支払いが認められるケースもありますが、細かな要件が定められているため、基本的には認められないと考えておく必要があります。教育資金や療養費といった急な出費に対応するためのものではないため、その点は事前の説明で十分に理解をしてもらわなければなりません。
元本割れのリスクがある
拠出金をもとに資産運用する仕組みであるため、元本割れのリスクが存在します。企業が運用の責任を負う確定給付企業年金と比べると、従業員が背負うリスクは大きくなるため、仕組みの違いは丁寧に説明する必要があります。
また、運用方法によってもリスクの度合いは異なるため、自分の価値観に合わせて適切な運用指図を行ってもらうことが重要です。投資教育によってきちんとリスクとリターンの関係性を理解してもらうなど、継続的なサポートを続けましょう。
企業型確定拠出年金の導入方法
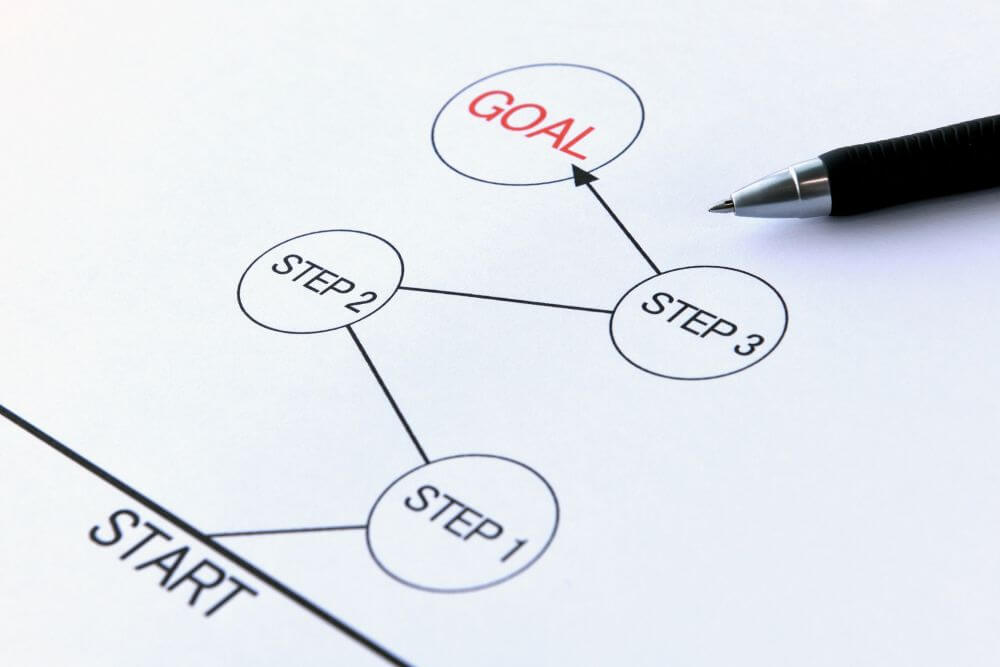
自社に合った導入パターンを選ぶ
企業型確定拠出年金にはさまざまな導入パターンがあるため、自社に合った方法を見極めるのが第一歩となります。具体的には3つのパターンに大別できるので、それぞれの仕組みと特徴をおさえておきましょう。
パターン1:給与に上乗せして掛金を拠出する
今回ご紹介したように、既存の給与に加えて、企業が全従業員に「前払い退職金」の形で拠出金を負担する方法です。拠出金を負担した時点で、企業は退職金を支払ったということになるため、従業員の退職時に資金不足が発生するリスクがないのがメリットです。
また、掛金はすべて企業が負担するため、全額損金に算入することができます。
パターン2:選択型DC
選択型DCとは、従業員が自ら加入するかどうかを選択し、自身の給与の一部を原資として拠出する方法です。企業からすれば、総額の人件費は変わらないため、金銭的な負担を抑えながら導入できるのがメリットとなります。
また、加入するかどうかは従業員が任意で選択するため、導入も比較的にしやすいと言えるでしょう。一方、従業員側からすれば、企業が新たに退職金を負担してくれるわけではないため、給付という意味合いではややメリットを感じにくい点もあります。
ただし、拠出した掛金は所得税・住民税の計算時に控除されるため、節税効果が期待できるのは利点です。
パターン3:マッチング拠出
「マッチング拠出」とは、企業側の負担額に加えて、従業員個人でも拠出額を上乗せできる方法です。運用の原資が増えるとともに、従業員の掛金は全額が所得控除の対象となるため、大きな節税効果が見込めるのがメリットです。
また、選択型DCでも、企業からの掛金に従業員の拠出金を上乗せすることはできます。ただし、マッチング拠出の上限額は、企業が設定した掛金額を超えることはできないため、もともとの掛金設定をどのように行うのかがポイントとなります。
制度設計
導入するパターンを見極めたら、現在の制度と照らし合わせながら、細かなシステムの変更・調整を行います。具体的には、「運営管理機関や資産管理機関の選定」「運用商品の検討・情報収集」「選択肢の用意」、「従業員への説明の準備」等を進めます。
社内への説明・合意形成
おおまかな制度が固まったら、従業員に制度の周知を行い、合意形成を図ります。企業型確定拠出年金の導入時には、制度設計の段階で労働組合(あるいは従業員の過半数を代表する者)に意見を求める必要があるため、丁寧に話し合いの場を整えましょう。
労使協議の経緯は、申請時に厚生労働省(地方厚生局)へ提出する必要があるため、記録を残しておくことも大切です。その上で、選択型DCやマッチング拠出を導入する場合は、個別に詳しい内容のすり合わせを行うと良いでしょう。
トラブルを避けるためには、すべての対象者に仕組みをきちんと理解してもらえるまで、丁寧に説明を行うことが重要です。
必要種類の準備・申請
企業型確定拠出年金を導入する際には、管轄の地方厚生局に申請して承認を得る必要があります。その方法は2通りあり、「独自に企業型年金規約を作成して申請する(単独型DC)」「既に承認されている企業型年金規約のプランに加入し、規約の変更を申請してもらう(総合型DC)」のどちらかを選ぶこととなります。
単独型DCを選ぶ際には、管轄の地方厚生局に必要な書類や手続を確認する必要がありますが、総合型DCの場合は代表企業の案内に沿って準備を進めます。中小企業の場合は、さまざまな手続を自ら進めなければならない単独型DCよりも、既に仕組みが整備されている総合型DCのほうが導入しやすいと言えるでしょう。
なお、確定拠出年金は退職金制度であるため、前述のように内容を就業規則に記載する必要があります。必要書類の準備と並行して、就業規則の変更も進めましょう。
システム設定
厚生労働省からの認可が下りたら、運用管理のためのシステム設定を進めていきます。まずは、企業型確定拠出年金の専用口座を開設しましょう。
専用口座からは、従業員自身で運用状況の確認や見直しが行えます。口座を開設したら、従業員にユーザーIDとパスワードが付与されるため、取引画面からログインし、画面内容を確認しながら実際に運用設定をしてもらうと良いでしょう。
導入後の運用管理
導入後は定期的に投資教育を行い、スムーズな運用をサポートすることが大切です。総合型DCであれば、代表企業がサービスとして投資教育のテキスト配布やe-ラーニングコンテンツの準備、セミナー講師の派遣等を行っているケースもあるので、積極的に利用するのも有効です。
なお、従業員が転職・離職をする場合は、移管あるいはiDeCoへの加入手続を行ってもらえば、年金資産を持ち運ぶことができます。そのため、転職・離職をする従業員に対しては、別途で丁寧に移管手続の説明をすることも大切です。
まとめ
企業型確定拠出年金は、企業が取り入れる退職金制度としてさまざまなメリットを備えています。拠出金額は全額損金算入できるため、法人税の節税をしながら、福利厚生の充実を図れるのは大きな利点と言えるでしょう。
一方、導入にあたってはいくつか注意しなければならない点もあり、デメリットも周知した上で従業員との合意形成を図る必要があります。納得を得た状態で導入を実現するためにも、まずは経営者や経営層自身が仕組みを正確に理解し、丁寧に準備を進めましょう。