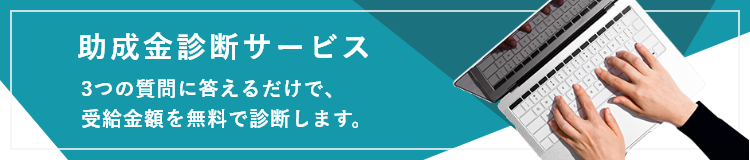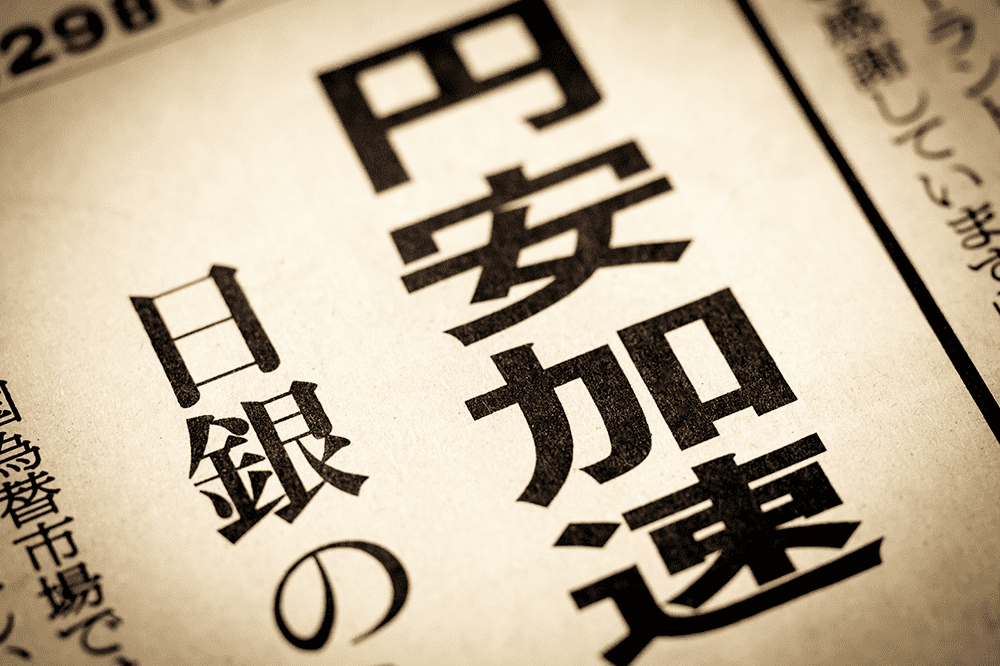資金調達とは?主な五つの方法やポイント・注意点等を解説
公開日:2024年3月22日
更新日:2025年4月28日
助成金・補助金

企業が事業を継続するには、資金調達が非常に重要です。必要なタイミングで資金を調達できなければ、事業を拡大させるチャンスを逃すだけでなく、企業や事業の存続さえ危ぶまれてしまう恐れもあります。
資金調達の方法を把握し、実現しやすい環境づくりを実施しておくことは、経営の安定性を向上させる基本であると言えるでしょう。この記事では、資金調達の基本的なポイントや種類、注意点等を解説します。
資金調達とは
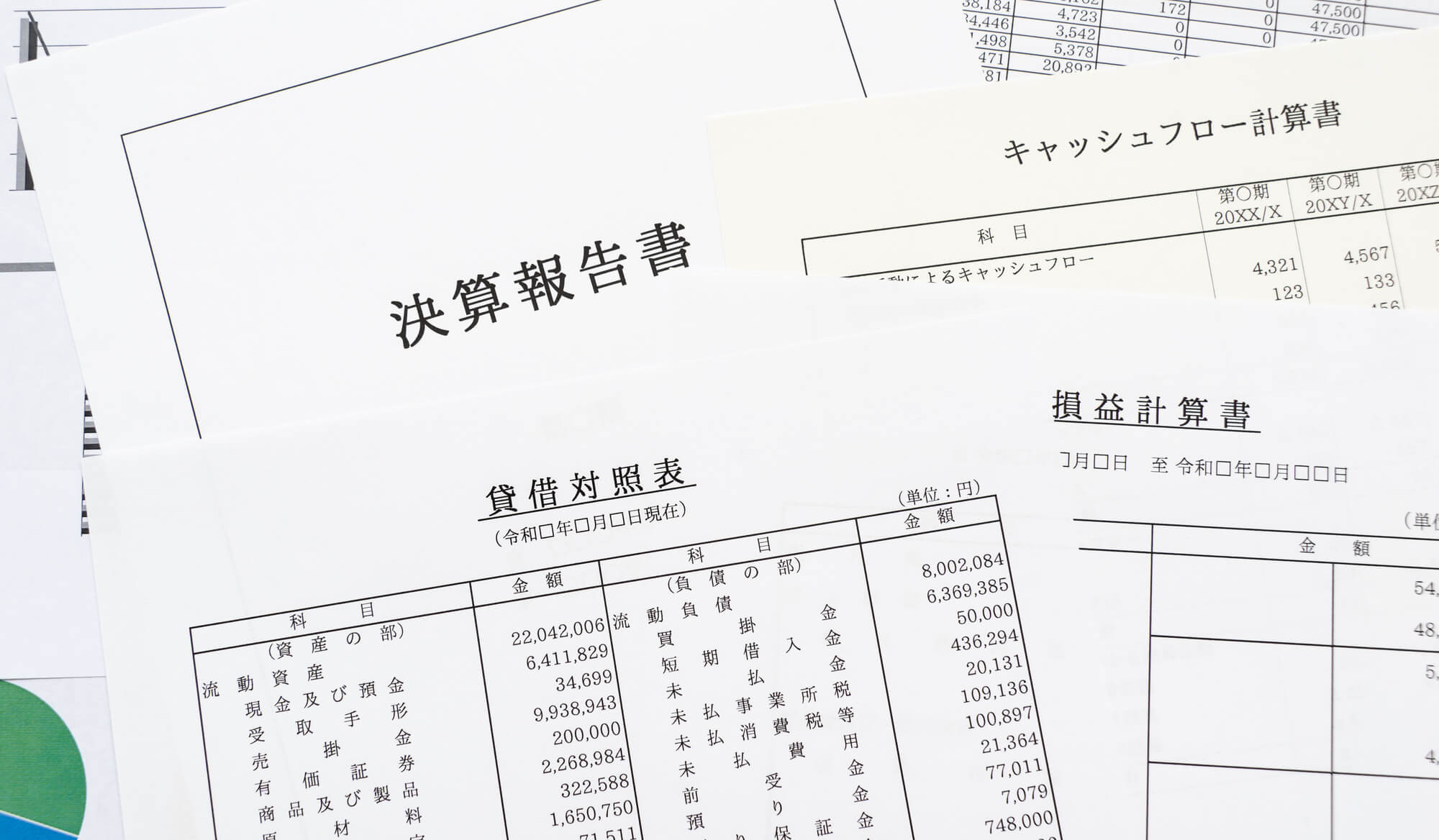
企業において、資金調達は経営戦略や事業計画を左右する重要な土台となります。ここではまず、資金調達の必要性と、融資と出資の違いについて解説します。
資金調達の必要性
企業における資金調達の基本的な目的は、設備資金や運転資金を調達することにあります。設備資金は主に、土地・建物・機械・備品・車両の購入等の用途で使われる資金を言います。
一方、運転資金は事業を継続するために必要な手元資金、原材料や商品の仕入れに使われる資金です。どの程度の資金が必要であるかは、企業規模や資金を求めるタイミングによって異なるため、具体的な金額は適切なファイナンス戦略に基づいて割り出さなければなりません。
また、資金調達には、手持ち資金を安定的に確保して「資金ショートを防ぐ」という目的もあります。資金調達が円滑に行われないまま事業を拡大すれば、キャッシュフローが悪化して必要な支払いが行えず、最悪の場合は事業の存続そのものも危ぶまれます。
事業の撤退や倒産のリスクを低下させる上で、資金調達は企業における最重要課題と言っても過言ではありません。
融資と出資は何が違う?
資金調達の方法には、大きく分けて「融資」と「出資」の2種類があります。融資とは、金融機関や公的機関から事業用の資金を借り入れることです。
融資では締結した契約に沿って、利息を上乗せした金額を返済していく必要があります。中小企業向けの融資制度にはさまざまなものがあり、状況に応じて資金繰りを考えていくことが大切です。
例えば、国が100%出資している日本政策金融公庫では、高い成長性が見込まれる事業を行う方向けの「新事業育成資金」や廃業等の経験がある方向けの「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」等、利用者のニーズに合わせたさまざまな仕組みが用意されています。
一方、出資とは、ベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家等から、株式と引き換えに資金供給を受ける資金調達方法です。
融資とは異なり、返済の義務がないのがメリットである一方、発行株式総数や持株比率によっては経営権そのものを保持できなくなるリスクもあります。経営の独立性という観点で見れば、メリットだけでなくリスクも踏まえた慎重な判断が必要と言えます。
資金調達の主な方法五つ

資金調達の方法はさまざまなものがありますが、主な方法として次の五つが挙げられます。
1. デットファイナンス:負債を増やす
2. エクイティファイナンス:資本を増やす
3. アセットファイナンス:資産の現金化
4. 補助金や助成金の利用
5. クラウドファンディングの活用
それぞれの特徴の違いを解説します。
1. デットファイナンス:負債を増やす
「デットファイナンス」とはいわゆる融資のことです。基本的に返済期限が設定され、金融機関に返済を行う時は利息が発生しますが、支払利息は損金算入ができます。
出資のように貸し手が経営に介入するリスクがないため、経営の独立性を保ちやすいのが大きなメリットです。また、デットファイナンスを行う利点の一つに「レバレッジ効果」が挙げられます。
借入れによってより大きな設備投資が可能になれば、自己資本に対する利益率の向上が期待でき、企業の大きな成長につながる可能性があります。さらに、公的機関を含めて借入先の候補が多いため、金利や返済期限等を柔軟に比較しながら、適したプランを見つけやすいのも特徴です。
一方、融資を受けるには担保や連帯保証が必要な場合があり、経営状況によっては融資そのものが認められない可能性もあるため、借入れ条件や審査内容には注意が必要となります。また、過度な借入れは返済時のキャッシュフローを悪化させる恐れがあるため、申込みの時点で慎重な経営判断が求められます。
なお、2024年3月には事業性融資の推進等に関する法律(事業性融資推進法)が閣議決定し、6月に可決・公布されました。新たな制度として「企業価値担保権」が創設されました。これは、不動産等の有形資産のみならず、企業のノウハウや技術、顧客基盤といった無形資産も担保として活用できる制度です。
独自なノウハウやブランドを活用した新たな形での融資が受けられるため、特に事業再生や事業承継、スタートアップといった幅広い分野での活用が期待されています。
企業価値担保権について解説しています。
2. エクイティファイナンス:資本を増やす
エクイティファイナンスとは、資本を増やして資金を調達する方法であり、代表的なものとして株式の発行による出資の獲得が挙げられます。前述のように返済の必要がないのが大きな特徴である一方、出資者が経営に関与するリスクも想定されるため、株式総数や持株割合には細心の注意が必要です。
エクイティファイナンスにはさまざまなアプローチが存在します。そのうちの一つが、新たに株式を発行して特定の第三者に引き受けてもらう「第三者割当増資」です。
通常と比べて株式発行や募集の手続がスムーズであるため、比較的に短期間での資金調達が行えるのがメリットです。また、それ以外にも未上場の企業が活用できる「ベンチャーキャピタル(VC)」や、エンジェル投資家からの出資等も、エクイティファイナンスの代表例と言えます。
3. アセットファイナンス:資産の現金化
「アセットファイナンス」とは、不動産等の企業が保有する資産から生み出されるキャッシュフローを返済原資として、資金の調達を行う方法を言います。具体的な方法としては、企業が保有する不動産をSPC(特別目的会社)に譲渡し、売却と同等の効果を得る「流動化ファイナンス」があります。
負債を増やさずスピーディに資金調達が行えるのが特徴であり、審査の判断は企業の信用度にも依存しないため、活用の可能性が幅広いのがメリットです、また、遊休不動産をSPCが開発して収益物件化し、ファイナンスの健全性を保つ「開発型ファイナンス」といった方法もあります。
4. 補助金や助成金の利用
国や自治体が実施する補助金や助成金等の制度を活用することも、資金調達の一種であると言えます。制度の種類はさまざまなものがあるため、幅広い業種で利用することができます。
例えば、中小企業が活用できる代表的な補助金として挙げられるのが、「事業再構築補助金」です。もともとはコロナ禍でダメージを受けた企業の支援を目的に立ち上げられた制度ですが、現在ではポストコロナ時代における環境変化に対応するため、新規事業への挑戦やグリーン成長戦略を後押しする仕組みへと変化しています。
それ以外にも、中小企業の革新的なサービスや生産プロセスの開発を支援する「ものづくり補助金」、事業承継による経営革新を支援する「事業承継・引継ぎ補助金」等、さまざまな制度が運用されています。ただし、補助金や助成金を申請するためには、多くの書類を用意しなければならないため、必要に応じて外部の専門家のサポートを受けるようにしましょう。
また、申請期限や要件等が定められているので、事前にチェックしておくことが大切です。
キャリアアップ助成金の概要、申請時の流れや注意点等について解説しています。
各種補助金の特徴や活用方法について解説しています。
5. クラウドファンディングの活用
クラウドファンディングは、インターネットを通じて不特定多数から直接的な資金調達を行う方法です。金融機関では融資が難しい事業や単発のプロジェクトであっても、賛同や共感が得られれば資金調達が行える可能性があり、活用の幅が広いのが特徴と言えます。
一方、必ずしも資金が集まるとは限らないため、取り扱う内容や情報発信の方法には工夫が必要です。なお、クラウドファンディングには、目的に応じたさまざまな種類があります。
代表的な方法とされるのは「購入型」であり、これはリターンとして商品・サービスを提供する方法です。また、「寄付型」はリターンを必要としない方法であり、社会貢献性が強い事業やプロジェクトで用いられます。
それ以外にも、事業者が小口資金を募って大口化し、借り手企業に融資する「融資型」、個人投資家から資金を募る「株式投資型」、売上に基づいて分配金をリターンする「ファンド型」、自治体が活用できる「ふるさと納税型」等があります。
シーン別の資金調達方法

資金調達をどのような方法で行うかは、資金が必要なタイミング等によっても違ってきます。ここでは、シーン別の資金調達方法について解説します。
起業時の資金調達方法
スタートアップの企業であれば、過去の実績がない状態であるため、金融機関から融資を受けにくい部分があるでしょう。そのため、不特定多数の人たちから出資を募ることができるクラウドファンディングや、補助金・助成金等を活用してみると良いでしょう。
起業して間もない頃は、経営基盤が不安定であり、企業としての信用がまだ築けていないため、個人投資家等からの出資を受けるのは難しいと言えます。自社の取組に興味を持ってもらうことで資金を集めたり、一定の要件を満たせば返済の必要がない助成金等をうまく活用したりしていくことが大事です。
中小企業や非上場会社の資金調達方法
中小企業や非上場会社の場合、日本政策金融公庫や金融機関からの融資を受けるほうが無難です。特に日本政策金融公庫は、中小企業や小規模事業者向けの融資が充実しており、用途に応じて自社に合ったものを選びやすいのが特徴です。
また、非上場会社であればベンチャーキャピタルの利用も検討してみると良いでしょう。ベンチャーキャピタルとは、未上場の企業の株式を取得して、上場時に売却することで利益を受け取る投資団体を指します。
融資だけでなく、出資も含めて幅広く検討してみましょう。
赤字補てんの資金調達方法
企業業績が悪化している状態であれば、アセットファイナンスや補助金・助成金等を活用してみましょう。業績が良くない状況で負債を増やせば、さらに経営が難しくなってしまうため、返済負担のない資金調達方法を優先することが重要です。
また、経営が悪化すればどんどん資金調達の選択肢が狭まってしまうため、そもそも資金ショートを起こす前に早めにスタートを切らなければなりません。それには、「キャッシュフロー計算書」と「資金繰り表」を作成し、出入金の状況をリアルタイムで管理することが肝心です。
キャッシュフロー計算書は現在の現金を把握するための書類であり、資金繰り表は過去の実績と将来の収支予測を踏まえ、資金不足に陥らないようにするための書類です。現金ベースで企業の現況をつかむだけでなく、融資の審査を受ける際にも必要な書類となるため、規模の小さな企業でも作成するメリットは大きいと言えます。
資金調達の際に金融機関がチェックするポイント

資金調達を行う時は、金融機関が融資の際にチェックするポイントからも、気を付けておく点がいくつかあります。どのような点をチェックされるのかを解説します。
明確な経営計画を立てているか
金融機関に提出する書類は、自社の強みや成長戦略、企業価値を将来的にどのように高めていくのか、説得力のある説明を行う必要があります。場当たり的な説明では、経営計画の脆弱さを見抜かれてしまうため、さまざまな角度から自社の経営を振り返ることが大切です。
経営計画を取りまとめる際は、良い点だけを書き出すのではなく、現実的な視点に立って事業を行う上で発生するリスクや対応策についても考えておきましょう。自社の現況をありのまま伝えると同時に、今後の事業展開を伝えていくことが大事です。
資金調達のタイミングは適切か
資金調達は適切なタイミングで行わなければ、せっかく集めた資金を有効活用できなくなります。また、業績が悪化してから融資を受けようとしても、思うように資金を集められないケースもあるでしょう。
資金調達は基本的に、事業を拡大させたり軌道に乗せたりするタイミングで行うことが大切です。また、市場が拡大している時にも資金調達を検討してみることが大事だと言えます。
ビジネスパートナーと信頼関係を築けるか
資金調達をスムーズに行うためには、ビジネスパートナーとの良好な信頼関係を長期にわたって築いていくことが大切です。例えば、週次で財務状況の報告を行ったり、月1回程度は近況を伝えたりする関係になっておくことで、資金調達が必要な時に相談しやすくなるでしょう。
その上で、金融機関等もビジネスパートナーの一種として捉え、良好な関係を構築していくことが大切です。特に金融機関からの評価では、財務諸表等の計算書類の質も重要なポイントとなります。
例えば、正確なキャッシュフロー計算書や資金繰り表があり、返済計画まできちんと盛り込まれていれば、金融機関からの協力を得られやすくなるでしょう。
資金調達を行う際の注意点
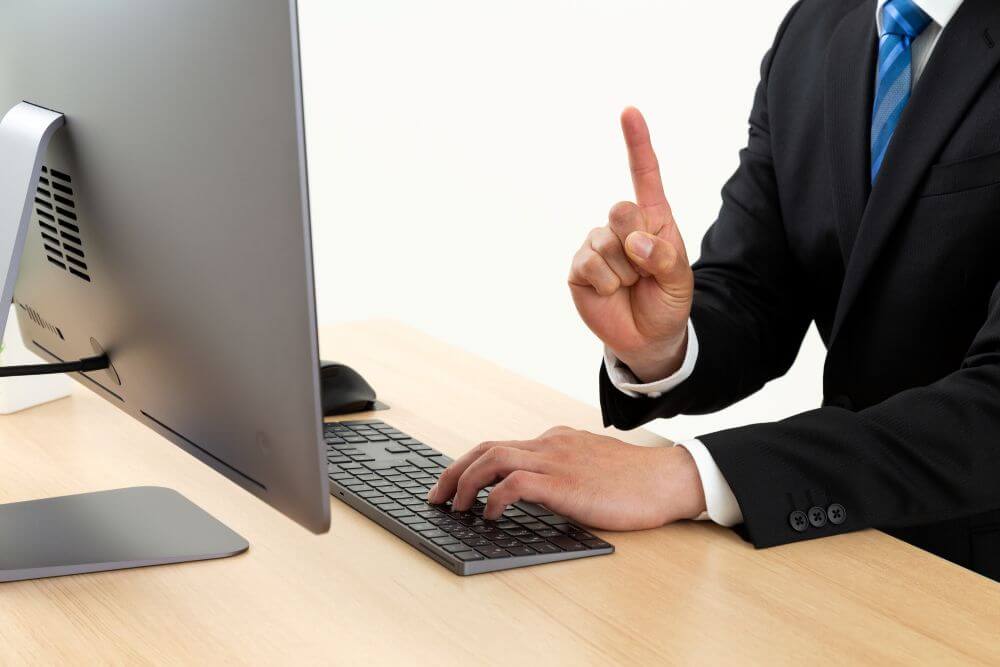
資金調達を行う時は、事前に見直しておきたいポイントがあります。スムーズに資金調達を進めるための注意点を解説します。
キャッシュフローの見直しを行う
返済が必要なデットファイナンスを行った場合には、利息の負担や毎月の返済に支障がないかといった点を十分にチェックしておく必要があります。年間の資金需要を確認した上で、資金繰りが厳しくなってしまわないように、キャッシュフローを見直すことが大切です。
そのためには、繰り返しになりますが、キャッシュフロー計算書や資金繰り表の正確な作成が第一歩となります。資金繰り表については、収支の予測をどの程度正確にできるかどうかがカギとなりますが、不確定要素のある予算はやや厳しめに計上するのがコツです。
また、不確定な部分が明らかになったタイミングでこまめに予算の修正を行い、リアルタイムの状況を反映させていくことが大切です。
【関連記事】
補助金申請~入金までのスケジュールや補助金フローの全体像等について解説しています。
借入資金の返済計画を立てておく
金融機関が融資を行う時は、企業の将来性や返済に支障がないかといった点をチェックします。そのため、融資を受けた後の業績予測等に問題がないかを確認しておきましょう。
調達した資金で事業を成長させるのは基本ですが、取引先に偏りがあったり、リスクがあったりしないかを確認しておくことが大事です。当初の予測よりも業績が悪化した場合のことも想定して、返済計画を立ててみましょう。
無理のない返済計画を立てるには、事業計画や財務計画を定期的に見直していくことが重要です。また、財務上の問題で自ら経営改善計画を策定するのが難しい場合は、国が運営する経営支援制度の活用を検討してみると良いでしょう。
例えば、各地の中小企業活性化協議会が運営する「経営改善計画策定支援等事業」では、国が認定した税理士等の専門家で構成される認定機関によるサポート制度が扱われています。計画策定支援に必要となる費用の2/3は協議会が負担してくれるため、経営を立て直すきっかけとして役立つケースもあるでしょう。
株式の希薄化への対処法を立てておく
エクイティファイナンスによって新たな株式を発行した場合、既存株主の所有割合が減少することを念頭に置いておく必要があります。経営権が希薄化すれば、安定的な経営に支障が出てしまうからです。
資金の調達方法やタイミングに問題がないかを検討した上で、ファイナンス戦略を捉えていくことが大切です。また、新たに株式を発行する際は、株主と事前にコミュニケーションを緊密に取っておくことも心がけましょう。
まとめ
企業が安定的な経営を行い、事業を成長させていくには資金面での戦略をきちんと立てておくことが大切です。資金調達方法はさまざまなものがあるので、資金の用途やタイミング等を精査し、ベストな選択を行っていく必要があります。
いざ資金が必要な時に動こうとしても、準備に十分な時間が掛けられずに、思うように資金調達が進まない場合があります。日ごろからキャッシュフローをよく確認して、金融機関や出資者等と緊密なコミュニケーションを取っておきましょう。
【参考情報】
2024年2月2日付 中小企業庁 「中小企業を支える資金調達」
2025年2月19日付 中小機構 「J-Net21 起業マニュアル 資金調達方法」
2024年3月13日付 経済産業省経済産業政策局産業資金課 「スタートアップ・ファイナンス研究会」
2025年2月19日付 三井住友銀行 「融資とは?出資やローンとの違い、メリットや注意点を分かりやすく解説」
経済産業省 「エクイティ・ファイナンスに関する基礎知識」
2025年2月19日付 日本政策投資銀行 「アセットファイナンス(不動産)」
2025年2月19日付 三井住友銀行 「ストラクチャード・ファイナンス」
2025年2月19日付 経済産業省 「ミラサポplus」
2025年1月10日付 経済産業省 「事業再構築補助⾦第13回公募の概要」
2015年4月24日付 中小企業庁 「小規模事業者の構造分析」
2016年7月1日付 中小企業庁 「中小企業白書」
中小企業庁 「中小会計要領の手引き」
2025年2月19日付 中小企業庁 「経営改善計画策定支援」