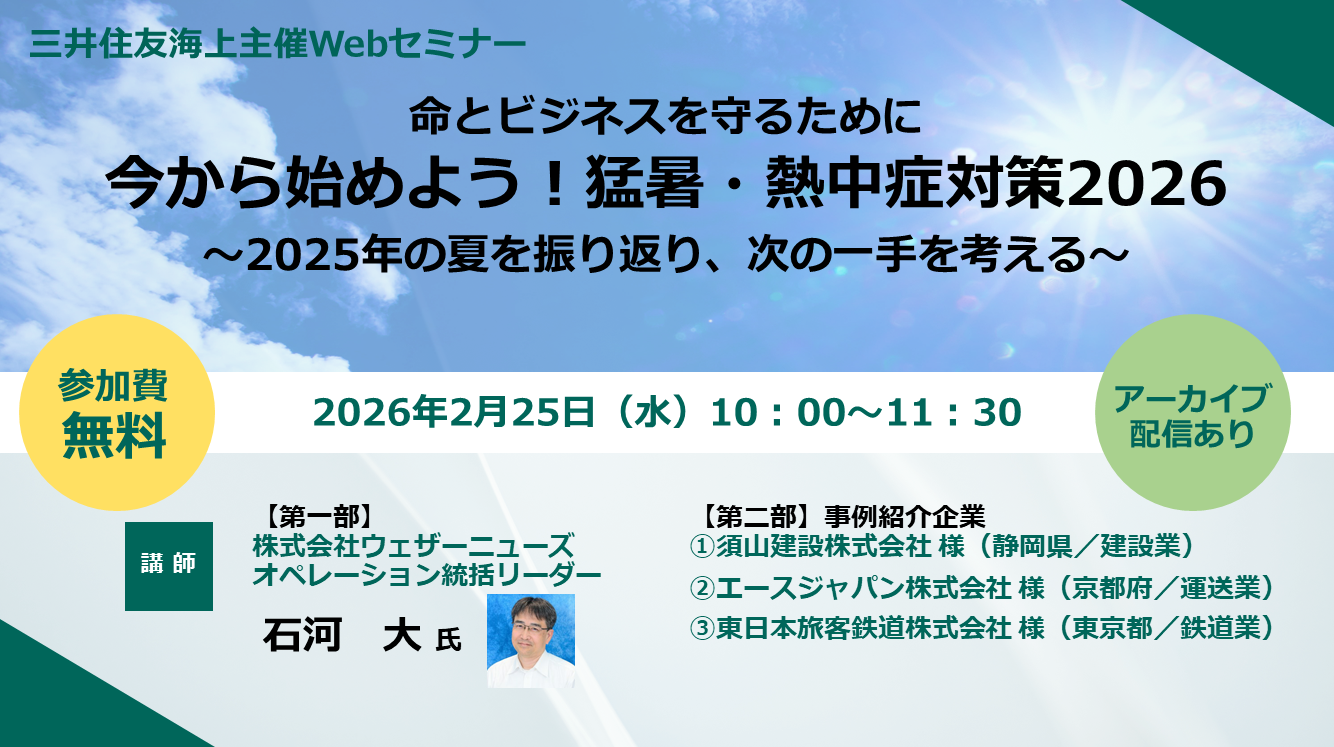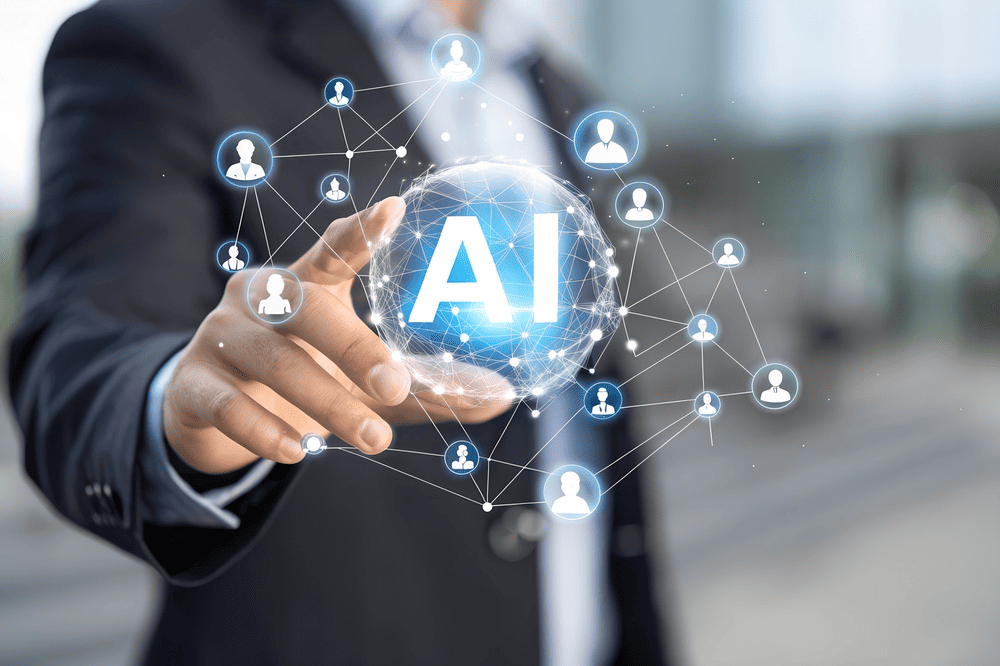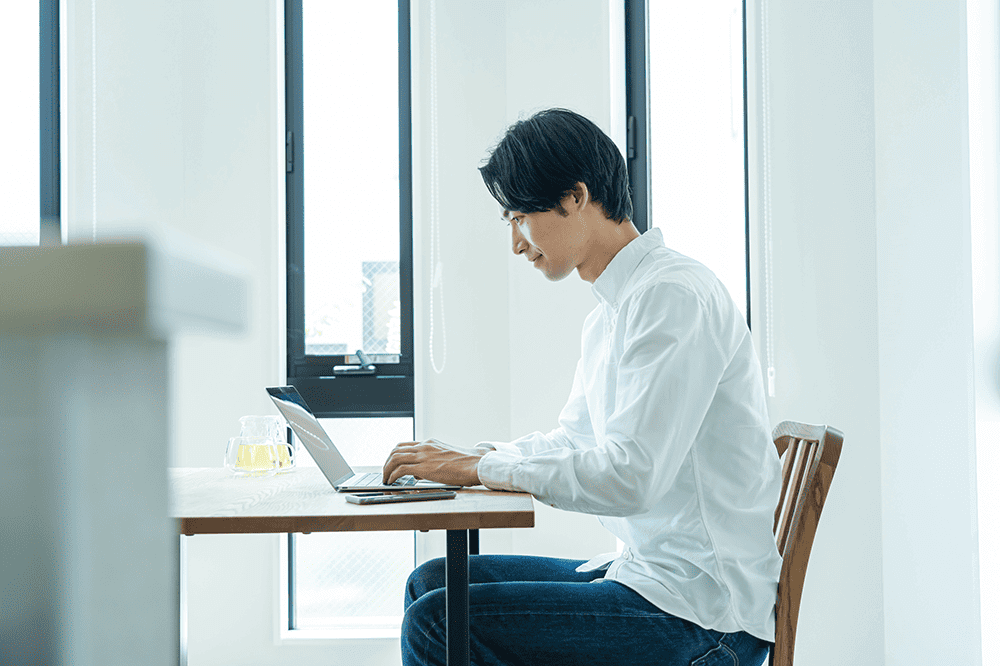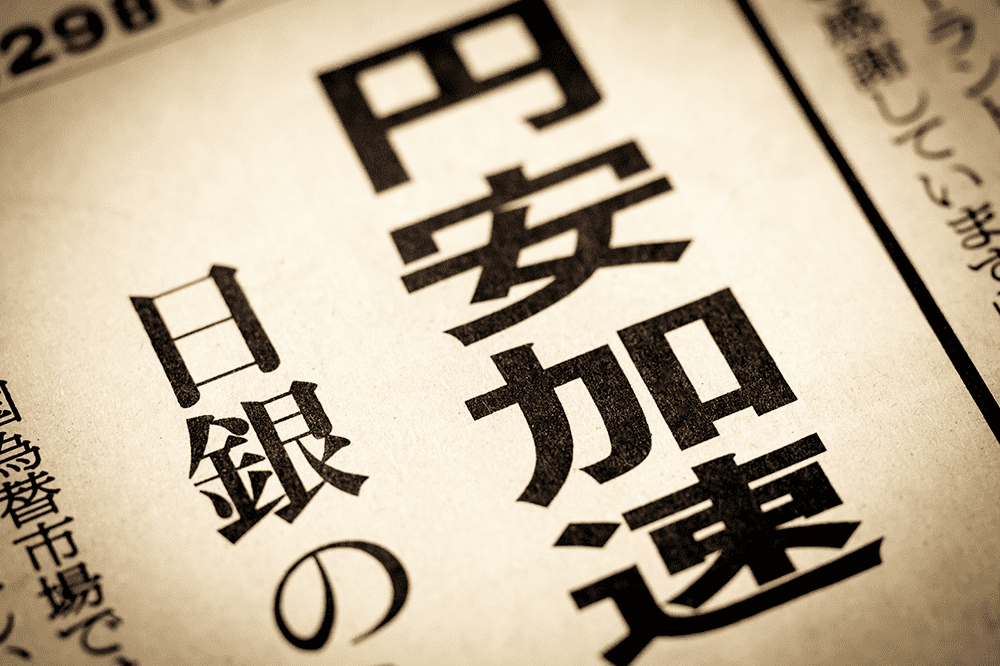産休 (産前産後休暇)と育休の手続きについて解説
公開日:2025年5月7日
人事労務・働き方改革
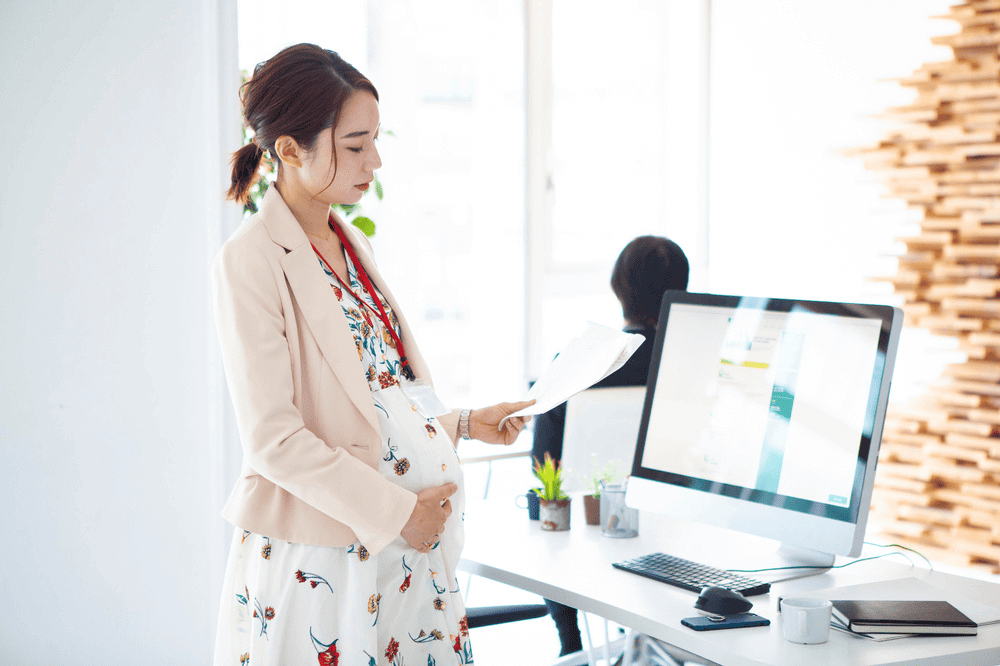
女性の労働者がいる場合、妊娠・出産のために産休・育休を取得することがあります。この時に会社はどのような手続きをしなければならないと定められているのでしょうか。 この記事では、産休・育休について、会社が行わなければならない手続きについて解説します。
産休・育休の手続きとは?
まず産休・育休の手続きとはどのようなものか確認しましょう。
産休・育休とは
産休・育休とはどのようなものか改めて確認しておきましょう。
産休とは、出産予定日の前(産前)と出産をした後(産後)の休業のことをいい、産前産後休暇と呼ばれることもあります。産休は、出産に伴う母体の保護を目的とする制度で、労働基準法65条以下に規定されています。
育休とは、子の育児のための休業のことをいいます。育休は、職業生活と家庭生活との両立を目的とする「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下:育児・介護休業法)」に基づく制度で、育児・介護休業法5条以下に規定されています。
なお、2022年の育児・介護休業法の改正より子が生まれてから8週間以内に、最大4週間の育休を2回に分割して取得することができる制度が、上記の育休以外にも認められています(育児・介護休業法9条の2)。この休業のことを、産後パパ育休と呼んでいます。
【関連記事】
育児・介護休業関連の法改正について解説しています。
産休の要件
労働者が産休を取得するための要件は次のとおりです。
産前の休業
産前の休業の要件は労働基準法65条1項に規定されている次の二要件です。
●6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性
●会社に対して休業を請求したこと
産前の休業については労働者から会社に対して休業を請求することが要件となっています。
また、母体の保護という目的があるので、妊娠をしている本人のみであり、男性側には産前休業は認められません。
産後の休業
産後の休業の要件は、労働基準法65条2項で次の二つを規定しています。
●産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。(本文)
●産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障のないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。(但書)
産後の休業について産後6週間までは「就業させてはならない」とのみ規定しており、労働者がこの期間に復職を希望しても認められません。
産後6週間を経過すると、本人が請求し、医師が支障がないと認めることを要件に復職が認められます。産後の休業についても母体の保護を目的とするものなので男性が取得することはできません。
育休の要件
育児休業の取得について定める育児・介護休業法5条1項は次のように定めています。
「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(中略)をすることができる」
そのため、満1歳に満たない子がいる労働者が会社に申し出をすれば、育児休業を与えなければならないのが原則です。ただし、次の二つの例外が認められています。
1.一定の場合に労使協定を結ぶ(育児・介護休業法6条1項)
例外の一つは一定の場合に労使協定を結ぶことによる例外です。
育児・介護休業法6条1項・育児・介護休業法施行規則8条は、次の三つの場合で過半数労働組合・過半数代表者との間で労使協定を結んだ場合には育休を付与しなくても良いとしています。
●雇用されてからの期間が1年未満の労働者
●1年以内に雇用関係が終了する労働者
●週の所定労働日数が2日以下の労働者
育休の対象外にする場合には、有効な労使協定がなければ育休を制限できないので、注意が必要です。
2.有期契約の労働者
もう一つは、有期契約の労働者について、養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないことが要件となります。
この要件について、書籍やインターネット上の記述で同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていることを要件とする記載があるのですが、同要件は2022年4月の改正によって削除されているので注意しましょう。
産休・育休の期間
産休・育休の期間は次のとおりとなっています。
産休の期間
労働基準法で認められている産休休業期間は次のとおりです。
●本人からの請求により出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)
●出産から8週間(ただし出産後6週間経過後に本人が働くことを望んでいて意思が支障ないと認める場合には就業させることができる)
育休の期間
育児・介護休業法で認められている育休の期間は次のとおりです。
●後休業の翌日から、子が満1歳の誕生日を迎える前日まで
●保育所に入所できない場合には、子が満2歳の誕生日を迎える前日まで
産休・育休に関するペナルティ
産休・育休を請求したにもかかわらず、休業をさせなかった場合、懲戒処分や解雇をした場合には次のようなペナルティがあります。
産休に関する刑事罰
産休についての労働基準法65条に違反した場合のペナルティとして、労働基準法119条1号で6か 月以下の懲役又は30万円以下の罰金が規定されています。産休の請求をしても与えない、産後休業の期間に働かせた場合には刑事罰に処せられる可能性があります。
解雇制限等に違反した場合のペナルティ
65条所定の期間、その後30日に解雇をした場合、その解雇は無効とされます(労働基準法19条)。その規定に違反して解雇を行った場合には、労働基準法119条1号で同じく6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が規定されています。
また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下:男女雇用機会均等法)9条3項は、労働基準法65条所定の産休・育休を申請したことを理由とする解雇等の不利益処分を禁じています。
男女雇用機会均等法違反の場合、違反の事実を公表することができる旨が規定されています(男女雇用機会均等法30条)。
行政指導の対象となる
産休・育休に関する規定に違反した場合、労働基準監督署から立ち入りや報告を求められるなどの行政指導を受けることがあります。
産休・育休のスケジュール
労働者が産休・育休を取得する場合、各種手続きを行う必要があります。
そのため、産休・育休から復職するまでのおおまかなスケジュールを確認しておくことが望ましいです。おおむね産休・育休から復職までの流れは次のとおりです。
1.労働者から妊娠の報告を受ける。出産予定日がいつか、産前休業を取得するか、いつから取得するかを確認する。
2.産前産後休業取得者申出書を年金事務所に提出する
3.出産後に育児休業の取得をするかどうか開始予定日・終了予定日について確認
4.復職後の条件や希望(時短勤務にする・パート契約に変える)について話し合う
妊娠・出産や復職については、一度決定した後にも事情が代わることもあるので、その時の状況に応じて柔軟に変更することもありますが、おおむね上記の流れで手続きをすすめていくことを頭に入れておきましょう。
産休・育休の手続き一覧
労働者が産休・育休を取得する手続きには次のようなものがあります。
労働者が産休に入るときの手続き
労働者が産休に入るときの手続きとして次のものがあります。
産前産後休業取得者申出書の提出
社会保険に加入している労働者が産休に入る場合、産前産後休業中の一定期間は事業主分も含めて社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されます。その手続きを行うために、産前産後休業取得者申出書を年金事務所等に提出します産前産後休業取得者申出書は、日本年金機構のホームページで取得が可能です。
労働者が出産をしたときの手続き
労働者が出産をしたときの手続きとして次のものがあります。
出産手当金の申請
出産後は強制的に産後休暇となります。その間労働をしないので、会社も給与を払う必要がありません。
出産手当金は、出産による休業で給与の支給を受けられない場合に健康保険から支給されます。出産の日以前の42日間と出産後56日間の会社を休んだ日を対象に、休業1日につき標準報酬日額の2/3を支給するものであり、収入のない労働者には大きい支給となります。
出産手当金の支給には、「健康保険出産手当金支給申請書」という書類を全国健康保険協会や健康保険組合に提出します。健康保険出産手当金支給申請書には、医師や助産師に記入をしてもらった上で、会社が事業主証明を行い、会社が提出するのが一般的です。
出産育児一時金について
健康保険による出産時の補助の制度として、出産育児一時金があります。
妊娠85日(4か月)以後の出産を対象に、50万円 が支給されることになっています。
多くのケースで医療機関が制度の利用をしていることがあるのですが、小規模な医療機関や助産院等では制度の利用ができず、手続きが行われていないことがあります。
そのため、利用について確認してあげると良いでしょう。
健康保険被扶養者異動届
健康保険被扶養者異動届の提出が必要です。生まれてきた子どもが自社の労働者の扶養に入る場合、健康保険被扶養者異動届を全国健康保険協会や健康組合へ提出します。健康保険被扶養者異動届は、加入している健康保険のホームページからダウンロードができます。
給与所得者の扶養控除(異動)申告書の変更(h4)
所得税に関する手続きとして、労働者本人が「給与所得者の扶養控除(異動)申告書の変更」をする必要があります。これは年末調整に影響する手続きとなるので、労働者に手続きをするように促す必要があります。
労働者が育児休業をする
労働者が育児休業をする場合の手続きには次のものがあります。
社会保険料の免除の手続き
産休と同様に、育休中も社会保険料の免除があります。この場合の手続きも会社が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出することで行います。
休業については予定よりも早く終了する場合もあれば、延長することもあります。この場合にも延長・終了をする旨の育児休業等取得者申出書の提出が必要となります。
育児休業給付金
育児休業をしている労働者が雇用保険の被保険者である場合で、一定の要件を満たせば、育児休業給付金の支給があります。
育児休業給付金を受けるための要件は次のとおりです。
●休業開始前の2年間に被保険者期間(11日以上勤務した日がある月)が12か月以上ある
●休業開始前の給与の8割以上の金額が支給されていない
●休業中の就業が10日以下または80時間以下である
手続きは育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書をハローワークに提出して行います。
労働者が復職する
労働者が復職する場合には次の手続きが必要です。
育児休業取得者申出書終了届の提出
もし当初の予定よりも早く復職した場合には、育児休業等取得者申出書終了届を提出します。
書類は日本年金機構のホームページで取得が可能です。
社会保険料の報酬月額変更届
育休が終わって復職する場合で、時短勤務をするような場合、従来よりも給与が下がる こともあります。この場合でも、当初は社会保険料が従来の標準報酬月額をもとに計算されており、負担が大きくなります。
社会保険では、3歳未満の子供を養育している場合、復職後3か月間に支給されていた給与の平均額が従来の標準報酬月額と比較して1等級以上差がある場合、4か月目から標準報酬月額に改定することが可能です。
その手続きには、育児休業終了時報酬月額変更届を年金事務所・健康保険組合に提出します。申請書は日本年金機構のホームページで取得が可能です。
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特定申出書の提出
前項の育児休業終了時報酬月額変更届によって標準報酬月額を下げることによって、社会保険料は低く抑えることが可能です。
しかし、社会保険料が下がると、将来受け取れる厚生年金の額もまた下がります。そこで、3歳までの子どもを養育する期間、従来の標準報酬月額が反映される反映される特例が設けられています。
手続きには「養育期間標準報酬月額特例申出書」を年金事務所に提出して行います。申請書は日本年金機構のホームページで取得が可能です。
企業独自の復職に関する届け出
以上の公的な手続きのほかに、企業独自の復職に関する届け出がある場合には、その届け出を行ってもらいます。

日本社会保険労務士法人 社会保険労務士 山口 友佳
2009年、SATOグループ 「日本社会保険労務士法人」設立とともに入所。2010年社員に就任。労務相談部門責任者として中小企業、大企業に対する労務コンサルティングを担当。就業規則諸規程のコンサルティング、判例に基づいた実務的なアドバイス等、経験多数。