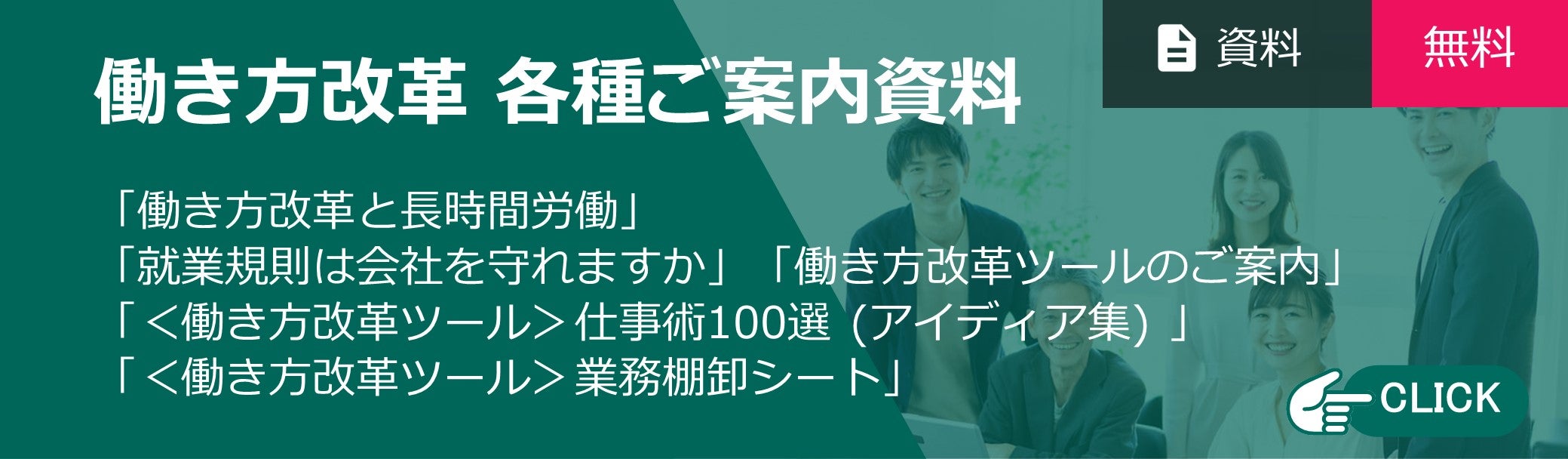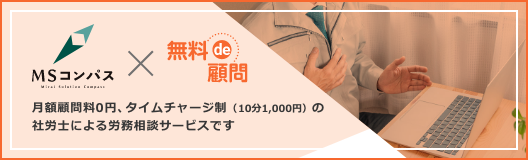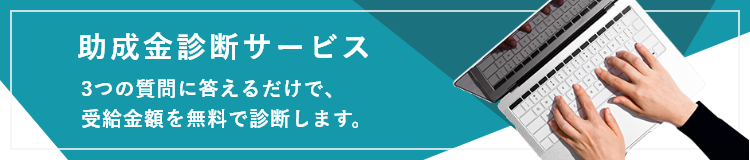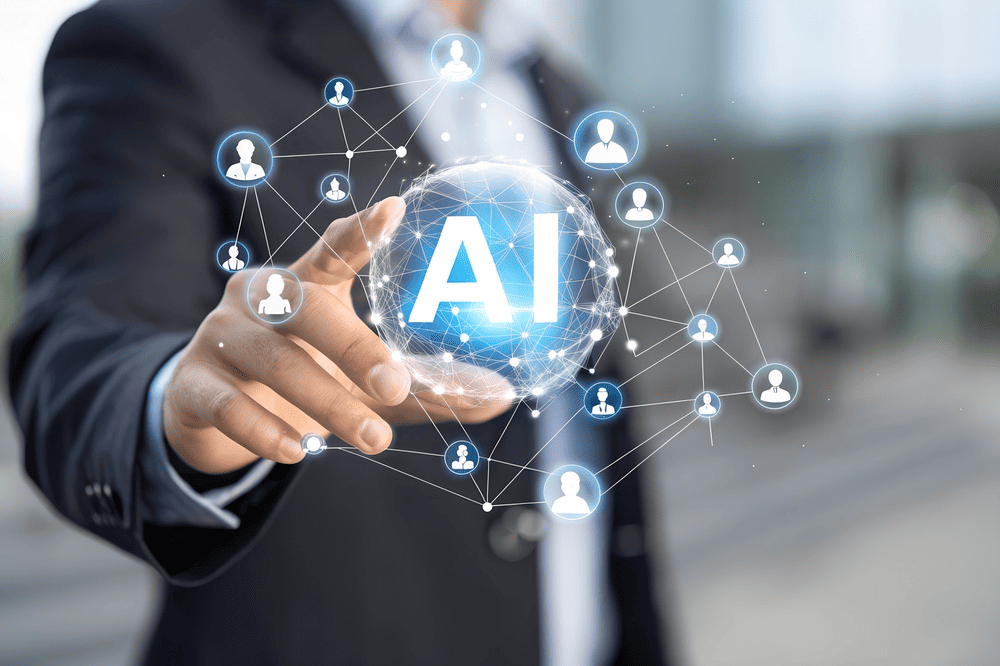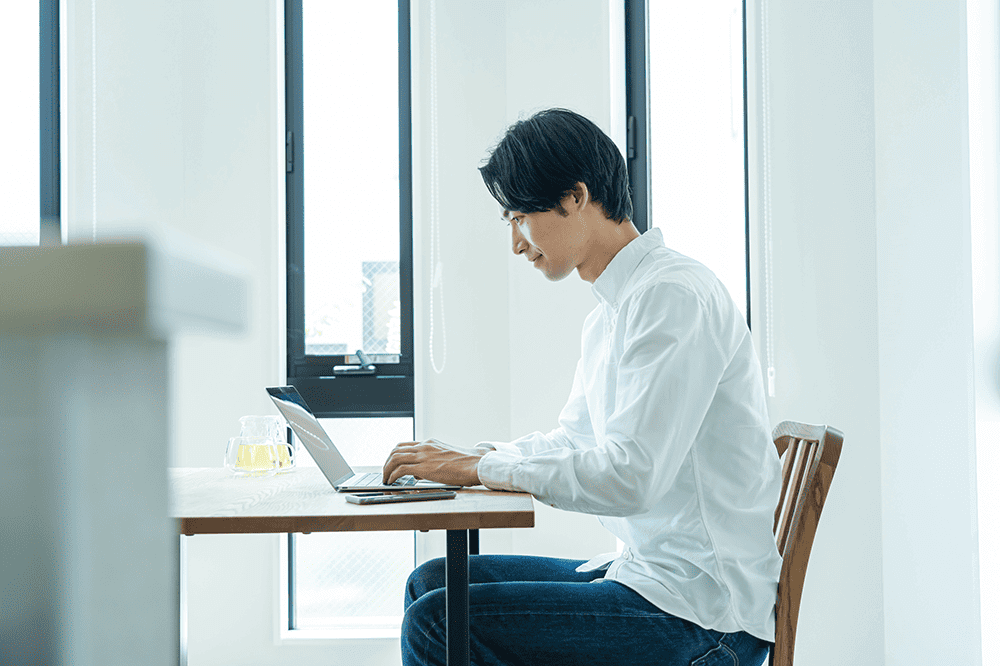企業が男性育休を進めるためのポイントを解説!共育プロジェクトの概要も要チェック
公開日:2025年10月6日
人事労務・働き方改革

男性育休に関する考え方は、近年急速に変化しつつあります。法改正や制度の拡充によって、男性従業員の育休取得を推進する企業が増えており、社会的な関心も着実に高まってきていると言えるでしょう。
この記事では、データに基づいて男性育休に関する現状を解説した上で、自社で取得を推進するために必要な取組をご紹介します。また、男性育休の取得について、望ましい成果を上げている企業の事例も詳しく見ていきましょう。
男性の育休に関する現状

男性の育児休業について、まずは国が打ち出している方針や施策と、現状を確認しておきましょう。
男性の育休に関する国の取組と変遷
男性の育休が可能になったのは、それほど最近のことではありません。1992年4月1日の育児・介護休業法の施行により、既に平成初期の段階では男性の育休取得は可能とされていました。
しかし、一方で取得率は長らく1%程度の状況が続いており、2010年代に入ってからも数%程度と伸び悩んでいました。社会的にも、男性が育児のために休みを取るという価値観はあまり普及しておらず、制度が存在していてもほとんど利用されていなかったというのが実情です。
しかし、2020年代に入ると、働き方改革の推進等によって育休に関する制度が大きく変革していきます。2022年4月1日には、法改正によって育休のための雇用環境整備や個別の周知・意向確認の措置が義務化されると、10月1日には後述する「産後パパ育休制度」が創設されました。
また、2023年4月1日には、一定規模以上(従業員数1,000人超)の企業に対して、育休取得状況の公表が義務付けられました。さらに、2025年4月1日からは、一定規模以上(従業員数300人超)の企業に対して、男性育休取得率の目標設定と公表が義務付けられ、男性育休の取得を後押しするルールが次々と確立されています。
現行の育休制度は2種類
2025年現在、男性の育休に関しては、大きく分けて2種類の制度が設けられています。
通常の育児休業
1つめは、子どもの1歳の誕生日の前日まで(原則)を上限に、労働者が希望する期間にわたって取得可能な、いわゆる通常の育児休業制度です。配偶者が専業主婦や育児休業中でも取得でき、両親ともに取得する場合は子どもが1歳2か月になるまで延長することも可能です。
育児休業期間中は原則働くことができず、最初の180日間は賃金の67%(その後は50%)が支給されます。その間、社会保険料や雇用保険料は免除されるため、手取りで比べると休業前の8割相当が支給されることとなります。
産後パパ育休
2つめの産後パパ育休とは、2022年10月1日から導入された比較的に新しい制度です。主に、出産直後の配偶者をサポートすることを目的としており、「子どもの出生後8週間以内に28日間まで、2回に分けて分割取得できる」のが特徴です。
産後パパ育休の大きな特徴は、労使の合意があれば、休業中でも働けるという点にあります。また、分割取得も認められているため、長期での休業が難しい方でも比較的に利用しやすいのがメリットです。
なお、産後パパ育休と育児休業を組み合わせて利用することも可能であり、両者を組み合わせれば、最大で4回に分けて休みを取得できます。従来の制度と比べると、スケジュールの柔軟性が高まったのが大きな変化と言えるでしょう。
男性育休の取得率が大きく向上
近年、男性育休の取得率は大きく向上しています。長く1ケタ代であった取得率は、2020年に10%を超えると一気に伸び始め、2024年度には40.5%と飛躍的に上昇しました。
前年度と比べると10%以上も上昇しており、法改正や国の施策が大きな成果につながっていることがうかがえます。なお、育児休業の取得者のうち、産後パパ育休の取得率は82.6%となっており、多くの労働者に活用されていることも明らかにされています。
【関連記事】
改正育児・介護休業法について解説しています。
企業が男性育休の取得を推進する4つのメリット

従業員エンゲージメントの向上
「従業員エンゲージメント」とは、従業員が企業に対して抱く貢献意欲や愛着等を表す指標です。男性育休を取得しやすい環境を整えることで、従業員との信頼関係が深まり、エンゲージメントの向上につながるのが大きなメリットです。
特に、これからさまざまなライフステージを迎える若手従業員にとって、男性も育休を取りやすい環境はポジティブな要素として映ります。仕事と育児の両立を踏まえて、自社でのキャリア形成を前向きに考えやすくなるため、定着率の向上にも結びつくでしょう。
また、男性の育休が推進されれば、女性の育休に対する心理的なハードルも低くなります。その結果、社内全体として好循環が生まれ、働きやすい職場づくりを進められます。
企業イメージの向上
前述のように、2025年4月からは、一定規模以上の企業に男性育休の取得率等の公表義務が課せられました。その結果、育休の取得状況は、企業イメージも左右する重要な要素となっています。
男性育休が進んでいる企業では、「従業員満足度が高い」「経営が安定している」といったプラスの評価を受けやすく、投資家を含めたステークホルダーにも前向きな印象を与えられる可能性があります。
採用力の強化
男性育休の取得推進は、採用力の強化にもつながります。厚生労働省の「若年層における育児休業等取得に対する意識調査」によれば、就職活動において重視する項目について、若年層の69.7%が「育休取得実績」と回答しています。
また、育休取得率が高い企業に対しては、「安定している」「社員思い」「先進的」「若手が活躍できる」といったポジティブなイメージを持つ回答者が多いのが特徴です。反対に、男性育休取得実績がない企業に対しては、61.0%が「就職したくない」と回答しています。
調査結果を見る限り、男性育休の取得は人材採用においても重要なポイントになっていることがわかります。
企業が男性育休の推進を行う際のポイント

自社で男性育休の推進を行うためには、全社的な取組が必要となります。ここでは、効果的に推進を行うためのポイントをご紹介します。
育休に関する制度を丁寧に周知する
男性従業員に育休を取得してもらうには、関連する制度の内容や申請方法等を丁寧に伝える必要があります。育児・介護休業法においても、2022年4月1日の法改正によって、育休に関する制度の個別周知・意向確認の措置が義務化されています。
具体的には、制度の内容と申出先、育児休業給付に関する仕組み、休業期間中の社会保険料の取扱い等を、面談・書面・電子メール等で伝えなければなりません。しかし、法律で定められている対象範囲は、妊娠した本人、あるいは配偶者の妊娠・出産等を申し出た従業員に限られています。
幅広く男性育休を取得してもらうためには、これから結婚・出産を控える従業員も含め、改めて全員に制度を周知することが重要です。全従業員を対象に仕組みを説明すれば、育休を取得した従業員と周囲との摩擦を予防することにもつながります。
経営層のメッセージや方針を明示する
厚生労働省の資料では、男性が出産・育児を目的とした休暇・休業を「取得しなかった理由」に関する調査が行われています。それによれば、取得しなかった理由として「会社で制度が整備されていない」「収入を減らしたくない」とともに「取得しづらい雰囲気」や「上司や職場の理解がない」といったものも上位を占めることが明らかにされています。
法改正が進む現在にあっても、男性育休に対する価値観は企業ごとにバラつきがあるのが実情です。育休取得への心理的なハードルを下げるためには、経営層や管理職層から、前向きなメッセージを明確に発信するのが効果的と言えるでしょう。
社内の体制を整備する
育休の取得を促進するには、社内の体制を整備し、休みを取りやすい環境を整えることも重要です。厚生労働省の調査によれば、男性が育休を取得しなかった理由のうち、「業務が繁忙であった」「自分にしかできない仕事を担当していた」等も上位に挙げられています。
この結果を踏まえると、休業によって業務に穴ができない体制を構築しなければ、男性育休の取得促進は難しいと考えられるでしょう。現場の改革を進め、業務の属人化や負担の偏りを解消することも、男性育休を進める大きな一歩となります。
また、小刻みでの休業に対応できるよう、フレックスタイム制やリモートワーク等を導入するのも有効な方法です。
【関連記事】
育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法の改正点について解説しています。
PDCAサイクルで施策の向上を図る
従業員の働き方は企業ごとに異なるため、初めから自社に合った取組を見極めるのは難しい面もあります。新たな制度を導入したら、PDCAサイクルを回して、取組のブラッシュアップを重ねることも重要です。
例えば、実際に育休制度を利用した男性従業員からフィードバックをもらい、良かった点と改善すべき点を洗い出してみるのも良いでしょう。人事部門と現場、従業員本人との感覚のズレを認識することで、より効果の高い施策を打ち出せるようになります。
助成金を活用する
男性育休の取得を進める上では、助成金の活用も視野に入れてみるのも一つの方法です。厚生労働省では、仕事と育児・介護等の両立をサポートする中小企業を対象に、「両立支援等助成金」を取り扱っています。
助成金は目的に応じた6つのコースに区分されており、男性の育休取得促進には「出生時両立支援コース」を活用できます。制度の概要は、育休を取得しやすい雇用環境や業務体制の整備をした上で、子の出生後8週間以内に開始する一定以上の育児休業を取得した男性従業員が出た中小企業に、国から助成金が支給されるというものです。
また、両立支援等助成金には、ほかにも「育児休業等支援コース」や「育休中等業務代替支援コース」等があり、育休取得のサポートに助成金を活用することができます。利用するにはそれぞれの受給要件を満たす必要があるため、厚生労働省が公表しているホームページや資料で具体的な仕組みを確認することが大切です。
男性育休を実現させた企業の事例

育休の取得を促進するためには、場当たり的な施策を打ち出すのではなく、計画的に取組を進めることが重要です。ここでは、厚生労働省の「令和5年度育児休業取得企業好事例集」から、男性育休の取得推進に成功している企業の事例と取組内容をご紹介します。
徹底した雰囲気・環境づくりで取得率向上
製造業・建設業を営むとある中小企業では、労働局からの提案により、「くるみん認定」の取得に向けて男性育休取得の推進に着手しました。推進にあたり、まず取り組んだのが社内ポスターの掲示です。
ポスターでは育休制度の基本的な仕組みとともに、「男性でも育休が取得できること」や「妻が専業主婦の世帯でも取得できること」等、内容を変えながら社内への周知を図りました。その後、男性育休への理解が浅い管理職がいたことを機に、管理職者全員を対象とした「イクボス研修」への参加を実施します。
イクボス研修とは、管理職者向けに都道府県等が行うセミナーのことです。同社では任意参加の従業員も含め、最終的に全体の1/3が参加しました。
周知徹底と研修の効果もあり、社内の雰囲気が着実に変わっていき、徐々に育休を希望する男性従業員が増えていきます。さらに、育休制度の説明時には、取得希望者と上司を同席させて認識のズレを解消する等、細やかな支援にも気を配りました。
その結果、男性育休の取得者が増加するとともに、介護休業にも対応できる柔軟な職場環境の実現に成功しました。
給与補償とサポート手当で男性育休取得率100%を達成
介護事業を営むとある社会福祉法人では、従業員のQOL向上を目的として、男性育休の取得推進に着手します。当初は育休を取得する男性従業員がいなかったため、まずはその理由について、アンケートをとるところからスタートしました。
「収入減少への心配」「周囲への迷惑」「制度を知らない」といった回答が多いことがわかります。そこで、育休取得者に対して独自の「給与補償制度」を設け、収入減少への不安を解消します。
さらに、育休取得者と同じ部署・チームで働く従業員に対し、1日500円の「子育て休業サポート手当」を支給することにしました。サポートに入る周囲の従業員にも、きちんとインセンティブを用意したことで、部署間・チーム間の不満や不公平感の防止につながります。
その結果、同社では男性育休取得率100%の実現に成功しました。さらに、職場環境の改善によって、「プラチナくるみん認定」の取得やメディアからの取材依頼といった副次的な効果も生まれ、企業イメージの向上にもつながりました。
トップによる明快なメッセージで社内の認識を変革
情報通信業を営むとある中小企業では、「くるみん認定」の取得に向けて男性育休の取得促進をスタートします。同社ではまず、子育て応援企業の風土をつくるため、ビジュアル面の取組に力を入れました。
例えば、育休中の従業員が子どもを連れてきた時には社長が抱っこして写真を撮り、「仕事と家庭の両立を応援している」というトップからのメッセージを明確に伝えるようにします。全社的に子育てを支援する姿勢を示したことで、社内では徐々に家庭や育児に関するコミュニケーションが増えていきます。
また、実務面においては、初めから育休を前提とした業務進行システムを構築し、無理なくチームで回せるような仕組みづくりを行いました。業務の属人化が解消されたことで、男性従業員も配偶者の出産の予定がわかった段階で、上司に相談するのが当たり前の風潮になっていきます。
その結果、男性育休取得率は100%を維持し、相乗効果でワークライフバランスへの意識も高まっていきました。同社の取組はメディアからも高く評価され、取材依頼や同業他社からの見学の申し入れ、業界セミナーへの登壇等、企業イメージの向上につながっています。
【2025年夏スタート】共育(トモイク)プロジェクトの概要

2025年の7月、厚生労働省は新たな共働き・共育て推進事業として「共育(トモイク)プロジェクト」のスタートを発表しました。従来の「イクメンプロジェクト」の後継事業として、主に男性の家事・育児参画の推進と、そのための長時間労働の是正を目的に導入されます。
イクメンプロジェクトは、男性の育休取得率向上に大きく貢献し、事業として一定以上の成果を残す結果となりました。一方で、男性の家事関連時間が女性に比べて少ない現状や、男性従業員の長時間労働が改善されない状態は、いまだに大きな課題として積み残されています。
そこで、共育プロジェクトでは企業へのアプローチを主軸として、雇用環境や職場風土の改善から、共育てをしやすい環境づくりを進めることを新たなゴールに設定しています。「脱ワンオペ」をキーワードに、社会全体で子育てを進めていくための仕組みづくりを行うチームとして、今後の取組が期待されています。
まとめ
男性育休の取得率は、近年飛躍的に向上しています。特に、産後パパ育休制度の導入によって、比較的に柔軟なスケジュールで休みをとれるようになった点は大きな後押しになっていると言えるでしょう。
それだけに、企業経営においては、男性育休の取得推進が採用力や対外的なイメージを左右する可能性も高まっています。既に成功している企業の事例も参考にしながら、自社の育休取得推進に活かせる取組を探り、働きやすい環境づくりを進めていきましょう。
【参考情報】
2023年6月23日付 内閣府 「男女共同参画白書 令和5年版」
2024年6月付 厚生労働省 「早わかり!男性の育児休業 ここがポイント」
2025年7月30日付 厚生労働省 「令和6年度雇用均等基本調査結果を公表します ~女性の管理職割合や育児休業取得率などに関する状況の公表~」
2025年9月10日付 厚生労働省 「若年層における育児休業等取得に対する意識調査」
2025年5月24日付 厚生労働省 「2025(令和7)年度 両立支援等助成金のご案内」
2023年付 厚生労働省 「令和5年度育児休業取得企業好事例集」
2025年7月4日付 厚生労働省 「共育(トモイク)プロジェクト開始のお知らせ」