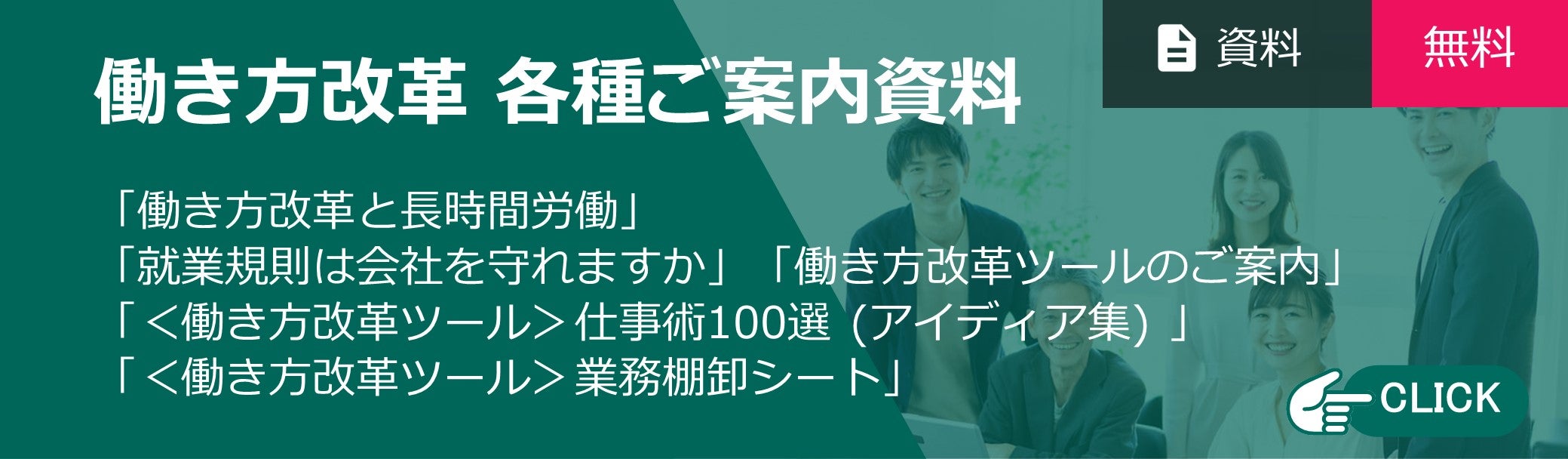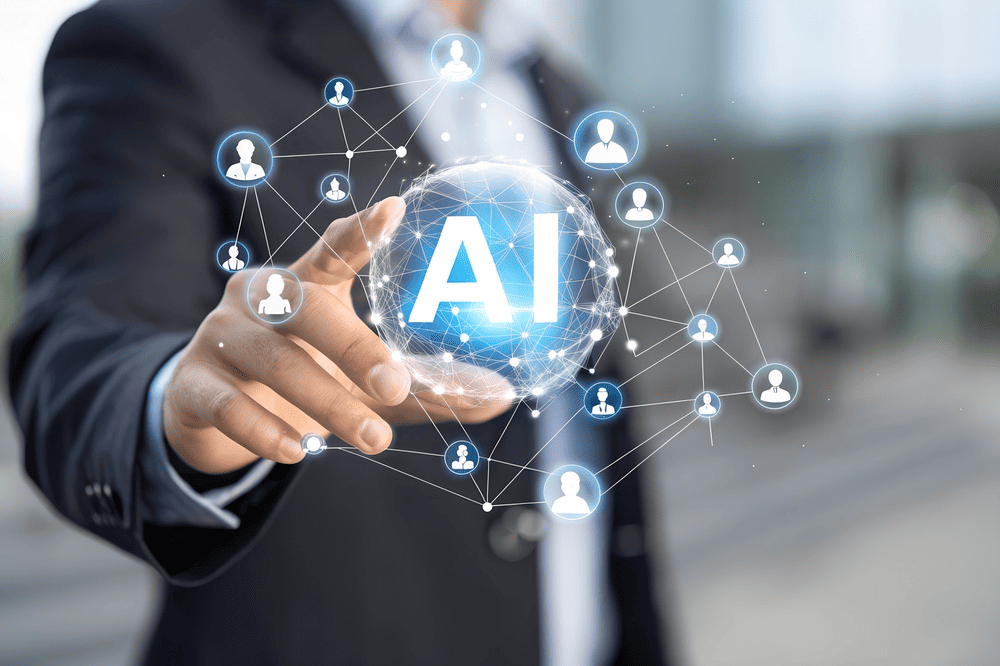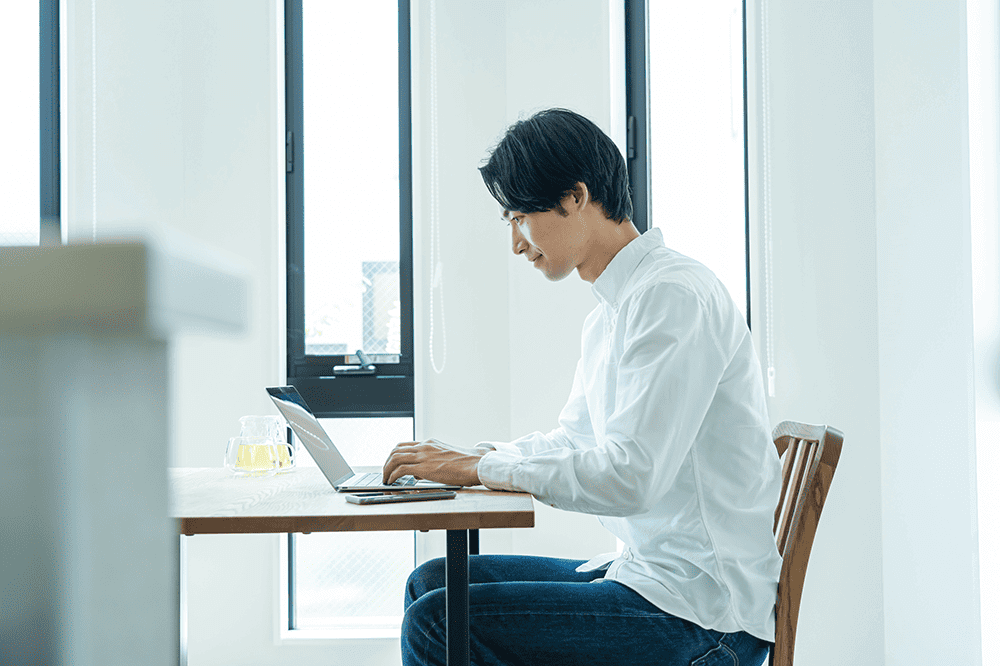週休2日制とは?企業が導入するメリットと課題、成功事例をまとめて紹介
公開日:2025年9月22日
人事労務・働き方改革

企業にとって、週休2日制の実現は従業員の満足度や定着率を左右する重要な課題と言えます。現在では、9割を超える企業が何らかの形で週休2日制を実現しており、働き方のスタンダードであると言っても過言ではありません。
今回は週休2日制の種類や企業が導入するメリット、実現に向けて乗り越えるべき課題を詳しく見ていきましょう。また、週休2日制の導入に成功している企業の取組も、事例を通じてご紹介します。
週休2日制の種類

週休2日制には、大きく分けて「週休2日制」と「完全週休2日制」の2つのパターンがあります。言葉が似ているため、両者が区別されないまま使われることも少なくありませんが、実際の働き方や休日数には大きな違いがあります。
ここではまず、両者の定義を確認しておきましょう。
週休2日制
週休2日制とは、「1か月に少なくとも1回以上、週2日の休みがある制度」を指します。月に1度以上であれば、週2日の休みがある週の数は問われません。
例えば、日曜日と曜日を問わない休日が月1日ある週休2日制を取り入れた場合、単純な年間休日は64日となります。そこに祝日や年末年始・お盆の休み等を加えると、実際の年間休日数は90日前後となるのが一般的です。
完全週休2日制
完全週休2日制とは、「すべての週に必ず2日の休みがある制度」を指します。完全週休2日制を採用する企業では、土日を休日とするケースが多いですが、休める曜日は必ずしも固定しなければならないわけではありません。
また、全社で一斉に休業するのが困難な場合は、従業員ごとに交代で休日を取らせることも可能です。いずれにしても、「必ず毎週2日休める」という点が、企業にとっても従業員にとっても重要なポイントとなります。
例えば、1日の労働時間を8時間とすると、完全週休2日制にすることで、1週間あたりの労働時間を40時間(労働基準法で定められている法定労働時間)に固定することができます。また、従業員にとっては、十分な休日があることで仕事へのモチベーションを保ちやすくなるでしょう。
なお、完全週休2日制の場合、祝日や年末年始、お盆等を加えると、年間休日数は125日前後となります。
週休2日制の導入状況

働き方改革の推進等により、週休2日制を導入する企業は着実に増えてきています。ここでは、厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査の概況」より、企業における週休2日制の導入状況を見ていきましょう。
週休2日制の導入割合
厚生労働省の調査によれば、何らかの週休2日制を導入している企業の割合は、「90.9%」となっており、ほとんどの企業で採用されていることがわかります。また、前年の同じ調査では85.4%であったことから、週休2日制の導入はさらに進んでいると考えられます。
なお、週休2日制の導入状況は、企業の規模によっても若干の違いが見られるのが特徴です。従業員数100人以上の企業では95%近くの導入率が平均であるのに対し、それ以下の規模の企業では89.0%とやや低めの水準となっています。
完全週休2日制の導入割合
一方、完全週休2日制を導入している企業の割合は、「56.7%」となっており、半数以上で採用されていることがわかります。完全週休2日制についても、前年調査では53.3%であったことから、週休2日制と同じく導入が進んでいる状況と言えるでしょう。
また、企業規模別に見ると、基本的には従業員数が多い企業ほど、完全週休2日制の導入割合が高い傾向にあります。従業員数1,000人以上の企業では、72.3%が完全週休2日制を採用しており、中堅以上の規模を持つ企業ではスタンダードな働き方となっているのが現状です。
休日に関するその他のデータ
企業ごとの休日数については特にルールがないため、なかには週3日の休日が設けられているケースもあります。ただし、同調査によれば、週休3日制を採用している企業は「1.6%」、完全週休3日制は「0.3%」となっており、実現されている企業はほとんどないと言えます。
このことから、休日のスタンダードは週休2日制、あるいは完全週休2日制であると考えられるでしょう。また、週休2日制・完全週休2日制の導入率はいずれも前年より高まっていることから、今後もますます一般的になっていくと言えます。
なお、年間休日総数の平均は「112.1日」となっています。前述のとおり、完全週休2日制で祝日や年末年始、お盆等を加味した年間休日総数が125日程度、週休2日制(月に1度だけ週休2日の週がある場合)で90日前後であるため、年間休日総数から見てもその中間がスタンダードであると考えられるでしょう。
企業が週休2日制を導入するメリット

現状においては、週休2日制は特に法律で義務化されているわけではなく、導入しなかったからと言って罰則等も発生しません。例えば、長時間労働が顕在化していた建設業では、週休2日制の義務化が話題に挙がることも多いですが、2025年時点では厳密な決まりは設けられていません。
ただし、建設業での週休2日制実現は、国土交通省によって強く推進されているのも現状です。週休2日制を実現するための支援制度や、応援ツール等も拡充されつつあり、社会全体としては休日数増加の流れが強まっていると言えるでしょう。
また、週休2日制を導入することには、企業側にとってもさまざまなメリットがあります。ここでは、企業が週休2日制を実現することで、どのようなメリットが得られるのかを詳しく見ていきましょう。
従業員満足度の向上
新たに週休2日制を導入することで、従業員満足度の向上を期待できるのが大きなメリットです。厚生労働省の「働き方・休み方改善指標」では、週労働時間と従業員満足度が以下のように反比例しているというデータが示されています。
データを踏まえれば、週労働時間が50時間未満の場合と、それ以上の場合で特に大きく満足度が変化することがわかります。週休2日制を導入すれば、極端に大きな残業が発生しない限り、この水準をクリアすることは十分に可能と言えるでしょう。
このように、週休2日制の実現は、従業員満足度を直接的に向上させる近道となり得るのです。また、適度な休日を確保できれば、心身の健康維持にもつながるため、モチベーションの維持や従業員の定着率向上にも寄与します。
【関連記事】
職場の働きやすさ・働きがいを高めて、生産性の向上や人手不足の解消につながる取組について解説しています。
人材採用における魅力の向上
休日数は人材採用のしやすさにも直接的な影響を与えます。前述のように、週休2日制は9割以上の企業で導入されているため、むしろ取り入れないことで、採用面では不利になってしまうと考えられます。
一方、完全週休2日制の導入割合は約半数であり、業界によっても実態は異なるため、導入できれば採用競争で優位性を確立できる可能性があるでしょう。また、近年では求人情報等に年間休日総数を明記する企業も増えており、平均以上の数字を提示できればプラスに働く可能性は高いと言えます。
週休2日制を導入する上での課題

スケジュールへの影響
既存の人員のまま週休2日制を新たに導入すれば、人的リソースが減少するため、スケジュールに影響をおよぼす可能性があります。もともとギリギリの人員で業務をこなしていた場合、対策がないまま休日だけを増やせば、リソースのカバーは難しくなってしまうでしょう。
また、急な仕様の変更やミス、体調不良といったイレギュラーな場面にも対応できなくなるため、週休2日制を導入するにはしっかりとした下準備が必要です。工期や納期の遅れが生じないためにも、1日あたりの作業時間を延ばす、あるいは納期を柔軟に延長してもらうといった工夫を凝らしましょう。
売上の減少・経済的負担の増加
人的リソースの減少により、会社として対応できる仕事量が減ってしまうため、売上の減少につながる恐れもあります。特に受注生産型の企業では、これまでよりも受注可能な水準が下がることで、取引に影響をおよぼしてしまうリスクもあるでしょう。
また、建設業等の場合は、工期が長くなれば建機のレンタル代が高くなるため、コスト増加につながる可能性も考えられます。週休2日制を導入する上では、売上やコスト面への影響も十分に考慮し、慎重に判断することが重要です。
従業員の収入の減少
業界によっては、従業員が日給制や日給月給制で働いている企業も少なくありません。この場合、週休2日制の導入によって単純に労働日数が減れば、各従業員の収入も低下してしまいます。
収入が減れば従業員やその家族の生活に大きな影響を与えるため、休みが増えるからといって、必ずしも全員から賛同されるとは限りません。週休2日制を取り入れる際には、収入の減少につながらないためにも、何らかの形でカバーできる方法を考えておく必要があります。
週休2日制を導入するためにすべきこと

週休2日制を導入するためには、企業それぞれに解消すべき課題が異なりますが、大まかな方向性としては3つのポイントが挙げられます。
【関連記事】
生産性の向上につながる健康経営について、取組のポイントについて解説しています。
生産性の向上
休日数が増えれば、基本的には労働時間が短くなるため、その分生産性の向上でカバーする必要があります。生産性にはさまざまな考え方がありますが、休日数の増加をめざす上では、1時間あたりの生産量を向上させるのが基本です。
生産性を向上させるためには、DXの推進によって「無駄な作業や廃棄ロスを削減する」「作業分析をしてハイパフォーマーのモデルケースを作る」「スムーズな情報共有とデータ管理を実現する」といった多様なアプローチが考えられます。また、単に作業効率を上げるだけでなく、「受注価格を引き上げる」「販売単価を上げる」といった価格転嫁の実現も重要な取組となります。
工期・納期の見直し、交渉
安定的に休日を確保するためには、人的リソースの減少を見越して、適切な工期・納期を設定する必要もあります。工期・納期の調整は、働き方改革の上でも重要な課題とされており、政策レベルでの取組も進められています。
例えば建設業界では、短納期による下請け企業の過度な負担を解消するため、2020年に建設業法が改正されました。これにより、工期に関する基準が制定され、著しく短い工期での請負契約は禁止されています。
適切な工期での見積もりを出せれば、過度な労働負荷の発生を防ぎ、休日を確保しやすい環境を整えられるでしょう。
週休2日制の導入成功事例

週休2日制の実現にあたっては、既に成功している企業の事例をもとに、参考になるヒントを探っていくのが近道です。ここでは、厚生労働省が取りまとめている「わたしの会社の働き方改革取組事例集」より、週休2日制の導入に成功した事例をピックアップしてご紹介します。
事例1.トップダウンで完全週休2日制を実現
卸売業界のある企業では、2018年から5か年計画で企業改革プロジェクトを立ち上げ、トップダウンで取組を進めていきました。プロジェクトは従業員の声を真摯に聞くことから始められ、そのなかで優先的に着手されたのが「完全週休2日制」と「時間単位年次有給休暇制度」の導入でした。
完全週休2日制の導入にあたり、同社では勤怠管理システム等を導入して作業効率を向上させます。時間にゆとりが生まれた結果、従業員自ら別の業務を率先して進めたり、後輩の育成に向き合ったりと、組織全体の動きが活性化していきます。
さらに、顧客にも働きかけて業務体制を見直し、最終的に完全週休2日制の実現を果たしました。その結果、年間休日数を15日増やすことに成功し、従業員満足度の向上にもつながりました。
また、ノー残業デーの設定や出退時間の調整によって業務体制をさらに見直し、数年間で月平均残業時間を25時間も削減することに成功しました。
事例2.業務効率化で年間休日120日以上を実現
情報サービス業を営むある企業では、従業員の健康を第一のテーマに掲げ、働きやすい環境を整える改革を進めました。その取組として行ったのが、徹底的に無駄を省いて生産性の向上を実現することです。
まずは会議の回数を減らすとともに、会議時間の削減をめざしてテレビ会議を活用します。さらに、テレワークも実現させながら生産性を高め、業務時間の大幅減に成功しました。
また、生産性の向上については、さまざまな角度からの従業員教育にも力を入れます。人材育成への投資を積極的に行うことで、社内全体の労働生産性の向上に成功しました。
その結果、完全週休2日制の導入とともに、年間休日120日以上の実現を果たします。また、残業についても事前申告制とし、ノー残業デーを設定することで労働時間そのものの見直しも図りました。
事例3.業界の壁を破り週休2日制の導入に成功
運送業界では長らくドライバーの長時間労働に支えられてきた経緯があることから、週休2日制の導入は大きな課題となってきました。とある企業でも、長時間労働と、それに伴う慢性的なドライバー不足に悩んでいたそうです。
そこで、「運送・物流業界の当たり前を見直し、若者が働きたいと思える魅力的な業界にする」との想いのもと、働き方改革に着手します。その取組の一つが、「リレー輸送」と「シャトル便」の確立です。
リレー輸送とは、1人あたりの労働時間8~9時間で輸送をつなぐ方式であり、シャトル便は基準である1日13時間の拘束時間を最大限利用した中距離対応の方式です。この2種類の輸配送方式を確立し、ドライバー自身が働き方を選べるようにしたことで、定着率は一気に向上していきました。
その結果、2020年には隔週土曜出勤の週休2日制から、完全週休2日制への移行に成功し、年間休日数は95日から119日へ飛躍的に増加します。さらに、その成果が認められた同社は、自動車運送事業で目覚ましい職場環境改善を果たした企業が認証される「働きやすい職場認証制度(国土交通省指定の「一般財団法人日本海事協会」が運営)」で、1つ星の評価を獲得しました。
まとめ
週休2日制の導入は、従業員自身の健康や意欲の向上につながるだけでなく、企業にもさまざまなメリットをもたらします。適度な休みが確保されれば、生産性の向上や採用力の強化が期待できるため、結果として自社の組織力を高めることにつながるケースも多いです。
しかし、新たに週休2日制を確立するためには、価格やスケジュール交渉といった課題を乗り越える必要もあります。導入に成功している企業の事例も参考にしながら、自社が実現できる方向性を丁寧に検討していくと良いでしょう。