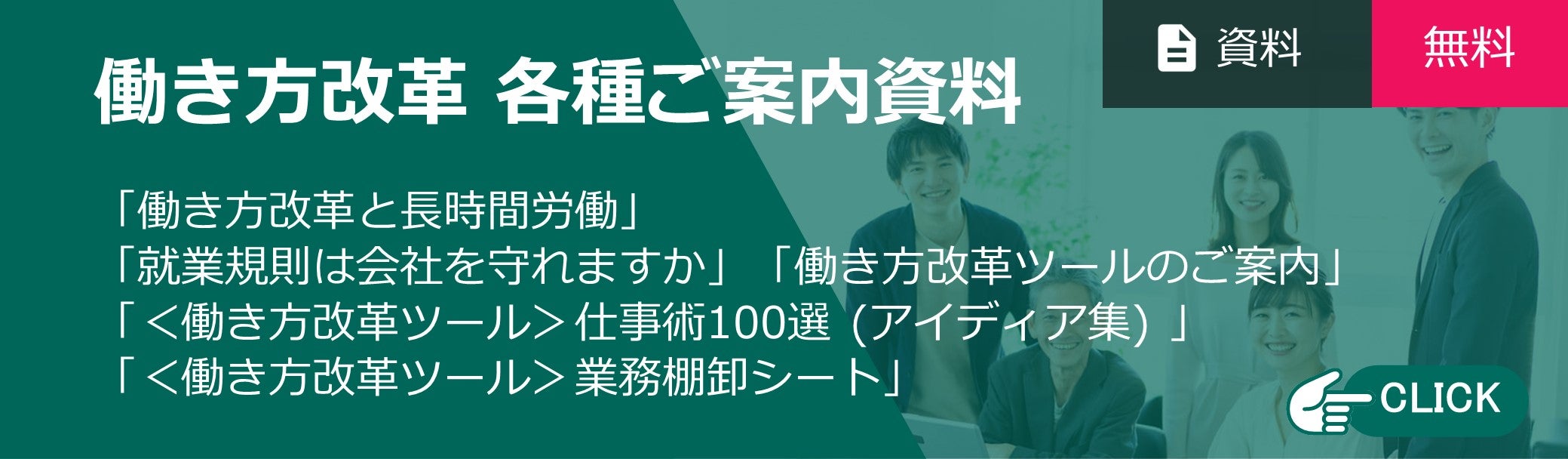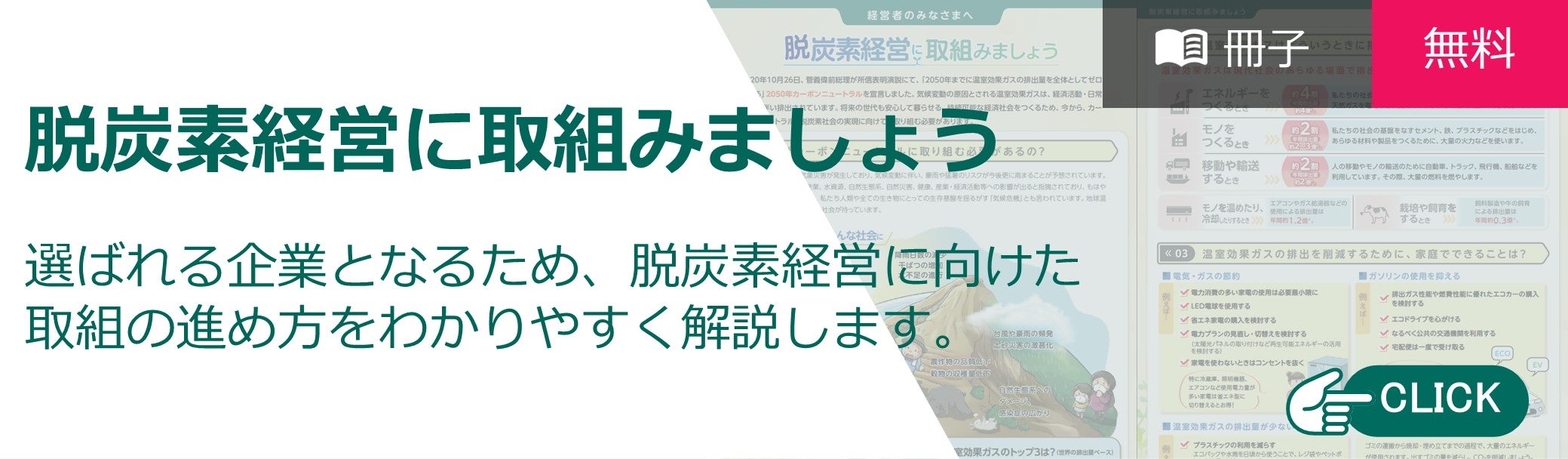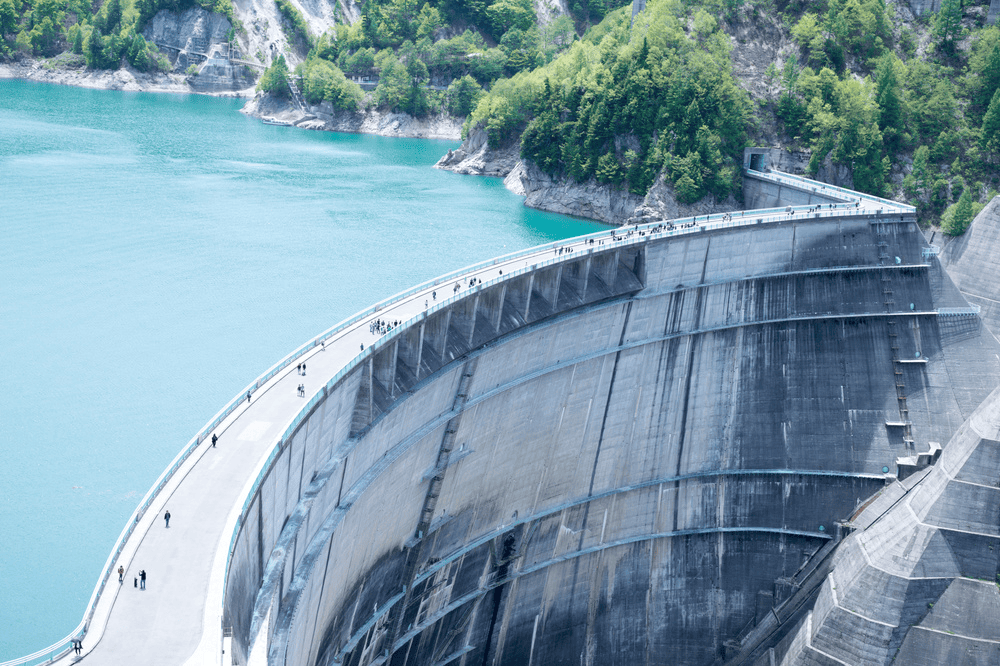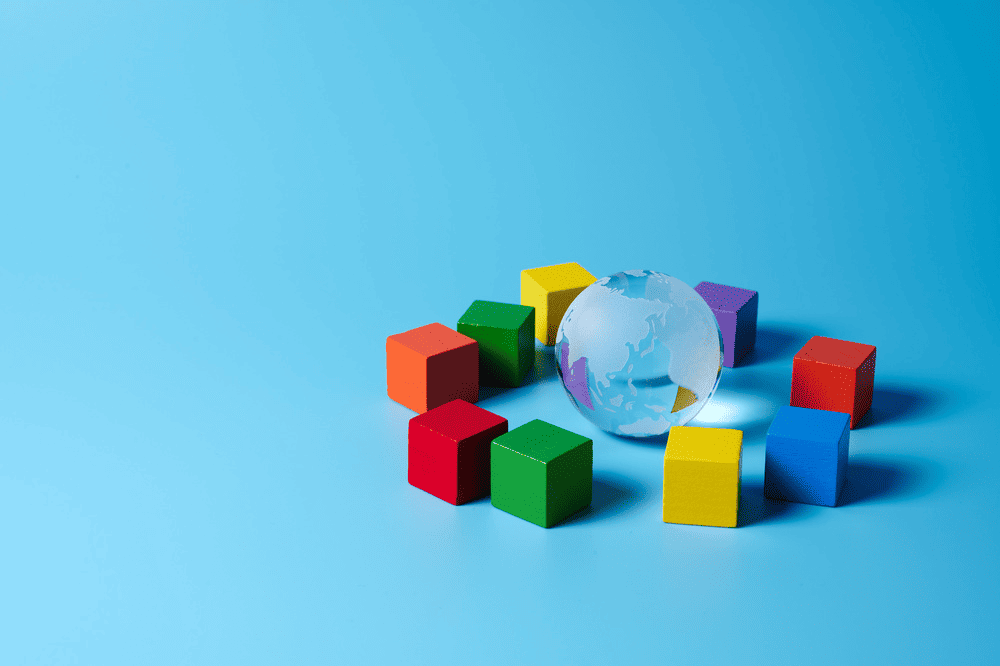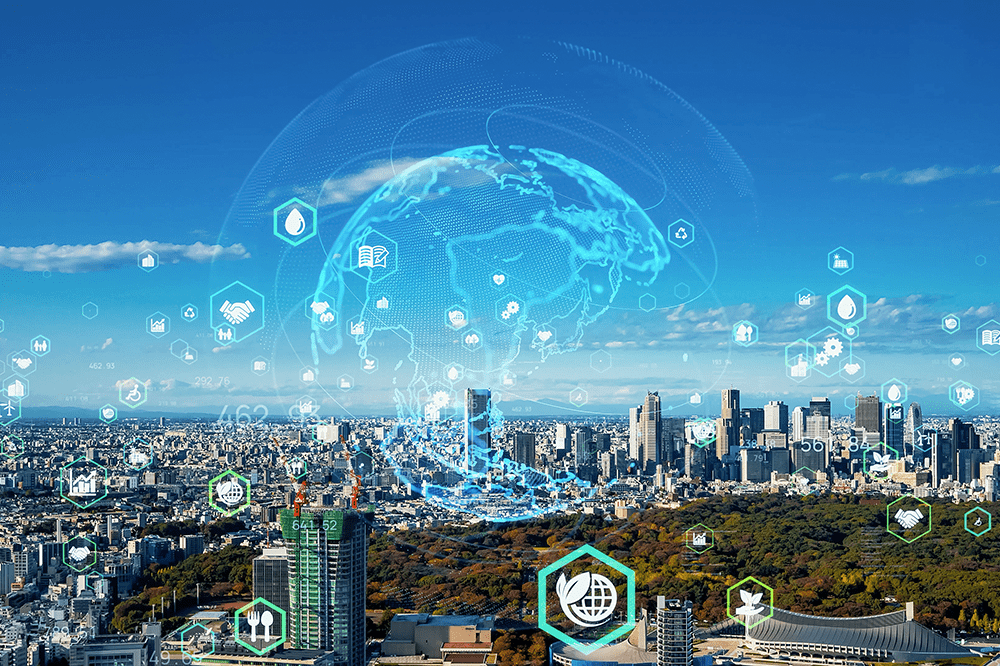ESG経営とは?SDGsとの違いと企業が実践すべき取組・事例を解説
公開日:2025年4月14日
SDGs

企業価値を向上させていくには、自社の短期的な利益の追求だけでなく、地域や社会も含めた幅広い経営戦略の実現が重要です。自然環境や地域社会に悪影響をおよぼせば、取引先や投資先の選択時に不利になってしまうため、長期的に見れば大きな損失につながります。
そこで重要となるのが、「ESG経営」の観点です。今回はESG経営の基本的な意味や重要性、企業における取組の事例等を詳しく見ていきましょう。
ESGとは

「ESG」とは環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance:企業統治)の頭文字を合わせた略語です。まずは、企業経営におけるESGの基本的な考え方・捉え方について確認しておきましょう。
ESGの基本的な概念
もともとESGは投資活動に関する概念であり、環境・社会・ガバナンスを考慮した投資活動や経営・事業活動を意味します。また、ESGの要素を考慮して行われる投資を「ESG投資」と言います。
ESGが国際的な注目を集めるようになったきっかけは、2006年に国連のアナン事務総長が提唱した「PRI」(Principles for Responsible Investment:責任投資原則)とされています。PRIは金融機関や保険会社のような機関投資家を対象に策定された行動指針であり、責任ある投資を行う上で、投資の意思決定プロセスにESGの課題を組み込むこと等が原則とされました。
もともと、国連がESGを推進する背景には、地球環境の変化や格差問題といった多様なリスクが関係していました。単なる短期的な利益追求型の投資では、こうしたリスクを加速化させてしまう恐れがあり、結果として経済全体への悪影響につながります。
そこで、投資という観点からも持続可能な社会の実現をめざす重要性が高まり、ESGについて言及したというのが一連の流れです。
ESG経営の捉え方
ESG経営とは、ESGに考慮した経営活動を行うことを指します。ESGに関する取組や企業の姿勢は、一義的には投資を呼び込む上で重要なポイントです。
企業がどのようにESGへ向き合うかによって、投資家からの評価が大きく左右されるため、特に上場企業においては欠かせない観点となっています。また、環境や社会へ配慮するスタンスは、取引先や顧客に対しても前向きな印象を与えやすくなるでしょう。
その上で、ESG経営を行うには継続した取組が求められ、中長期的な視野に立った方針やビジョンが必要となります。具体的には、「E:自社の事業分野を踏まえて環境問題とどう向き合うのか」「S:どのように豊かな社会の発展へ寄与するのか」「G:健全な経営を行うためにどのような自己管理体制を構築するのか」という大きな視点での施策が必要です。
ESGと関連する言葉との違い
ESGと関連性の深い言葉として、「SDGs」や「CSR」、「CSV」、「SRI」が挙げられます。これらはそれぞれ異なる概念を持つ言葉ですが、相互に関連し合っている部分もあり、ESGの追求がその他の概念を実現することにもつながります。
ここでは、類似する言葉の意味について、ESGとの違いを踏まえながら見ていきましょう。
SDGs(Sustainable Development Goals)
「SDGs」は特にESGと関連性が深い言葉であり、両者が同じ文脈で用いられる場面も多いと言えます。SDGsは2015年の国連サミットで採択された2030年までに達成すべき国際目標のことであり、持続可能な世界をめざすためのアプローチとして、17の目標と169のターゲットで構成されています。
SDGsは企業のみならず、国や世界全体として取り組むべき目標であり、その意味では対象が幅広い概念です。一方、ESGはSDGsを含めた目標を達成するために、企業や機関投資家が取るべき行動指針を指します。
つまり、ESGは企業がSDGsを進めるための具体的な取組であると言えるでしょう。そのため、企業がESG経営を行う際は、SDGsの取組とセットで進めるのが一般的です。
SDGs目標達成度における日本の評価について解説しています。
CSR(Corporate Social Responsibility)
CSRは1990年代から広がった考え方であり、「企業の社会的責任」と訳されることもあります。具体的には、企業が事業活動を行う上で、自社の利益のみならず社会的公正や環境等への配慮も組み込んだ「責任ある意思決定」を行うべきであるという考え方のことです。
CSRでは、消費者・従業員・投資家・地域社会等のステークホルダーに対して、企業がどのように責任ある行動をとるかが重視されます。例えば、従業員に対しては多様な働き方の実現や、性差のない労働環境の確立等が責任ある行動の例として挙げられます。
また、CSRではアカウンタビリティ(説明責任)を果たすことも重要視されるのが特徴です。ステークホルダーに対して企業の状況や財務内容を適切に報告し、透明性の高い経営を行うことも、企業の重要な責任として考えられています。
ESGは企業等が取るべき行動指針を表わすのに対し、CSRは具体的な意思決定を示す点を押さえておきましょう。
CSV(Creating Shared Value)
CSVを直訳すると「共有価値の創造」または「共通価値の創造」を意味します。2011年にCSRに代わる概念として、アメリカの経営学者であるマイケル・ポーターが提唱した考え方です。
CSVは事業を通じて社会的な価値(社会課題の解決や社会への貢献)と経済的な価値・利益の両方を創出するという点を重視するのが特徴です。CSVでは事業を通じて社会課題の解決を図り、同時に企業の利益を上げることも目標とします。
それに対して、CSRは必ずしも経済的な利益を生むことを目的とせず、社会的な責任を果たすことが目的であると言えます。
SRI(Socially Responsible Investment)
SRIは社会的責任を果たそうとする企業に対して、投資や融資等を通じて資金を供給する考え方のことです。社会的な意義を目的とした投資という点では、ESGと共通する部分も多く、実際に同様の意味で用いられるケースも少なくありません。
両者の違いを挙げるとすれば、SRIは社会的課題の「直接的な」解決がより重視されるのが特徴です。投資目的はあくまでも社会課題の解決にあるため、そもそも社会的な影響が小さな会社には積極的に投資を行う理由がありません。
反対に、投資や融資を行わないというネガティブな意思決定を行う際も、その企業が社会的に悪影響を与えているかどうかが判断基準となります。そのため、SRIの調査対象となるのは両極端な一部の企業のみであり、それ以外の一般的な企業はそもそも投資の対象とはなりません。
一方、ESGでは三つの基本要素を実現する企業であれば、規模が小さくても投資の対象となり得ます。適切な理念を持つ企業が成長すれば、中長期的に見て社会的な意義があると考えるため、SRIと比べるとより幅広い企業が対象となるのが特徴です。
中小企業におけるESGの取組

企業経営におけるESGの重要性は、社会の動きに合わせて着実に浸透しています。ここでは、中小企業におけるESGの取組について、目的や現状を詳しくご紹介します。
一般的に、ESGは投資による資金調達が重要となる大企業が取り組むべきものと考えられてきた面があります。しかし、実際には中小企業においても、ESG経営を進めることで多くの効果が期待されています。
ESG経営によって企業価値が向上すれば、投資家や金融機関から資金調達の機会を得やすくなるのは大企業と同様です。その上で、地域に根差して運営することが多い中小企業では、特に地域社会からの信頼性向上に重要な価値があります。
ESGへの積極的な取組が評価されれば、顧客や取引先の意思決定にプラスの影響をもたらすとともに、人材採用等の場面でも有利に働くでしょう。
帝国データバンクが行った調査結果について解説しています。
中小企業のESGへの取組状況
商工中金が2022年7月に行った「中小企業のESGへの取組状況に関する調査」によれば、ESGに「一つも取り組んでいない」と回答した中小企業はわずか2.9%に留まることが明らかにされています。有効回答数とされる5,231社のうち、ほとんどの企業が何らかの形でESG経営に取り組んでおり、重要な課題として認識されていることがわかります。
なかでも、特に注力されているのが「S.社会」に関する分野であり、具体的には「残業時間の削減」や「有給休暇の取得促進」といった点から着手する企業が多いです。また、「G.企業統治」に関する分野でも、「月次決算のスムーズな作成・財務会計管理体制の整備」については80%以上の企業が取り組んでいると回答しています。
一方、「E.環境」に関する分野は、中小企業の独力による取組が難しい面もあり、その他の分野と比べると着手は遅れている面があります。ただし、今後もっとも注力したい分野のなかでは、「E.環境」に属する「自社製品・サービスの環境面での付加価値の訴求」との回答がもっとも多いことから、関心度は十分に高いと言えるでしょう。
ESG投資の種類
ESG投資は海外ではサステナブル投資と表現されることが多く、基本的には同じ意味で用いられています。サステナブル投資の主な手法としては、次のようなものが挙げられます。
・ネガティブスクリーニング:ESGに反する業界をあらかじめ投資対象から除外する
・国際規範に基づくスクリーニング:国際規範を満たしていない企業を投資対象から除外する
・ポジティブスクリーニング:ESGの観点で優れている企業を投資対象にする
・サスティナビリティ・テーマ投資:特定のテーマに関する企業を投資対象にする
・インパクト・コミュニティ投資:貢献度等インパクトの強い企業を投資対象にする
・ESGインテグレーション:通常の財務分析にESG等の非財務情報を組み込んで投資する手法
・エンゲージメント:株主からESG経営に働きかける
ネガティブスクリーニングは、そもそもESGに反する特定の業界を除外するという考え方です。また、国際規範に基づくスクリーニングは、国連や国際労働機関等が提唱する規範をもとに、基準に達しない企業を除外する方法です。
ポジティブスクリーニングはESGの観点から優れた企業をピックアップして投資する方法であり、サスティナビリティ・テーマ投資は持続可能性に関する特定のテーマを限定して投資対象を絞り込みます。どちらもSDGsやESGに関する分野が重視されるのが特徴です。
コミュニティ投資とは社会問題の直接的な解決を図るための投資であり、特に貢献度の高い企業を絞り込んで投資することをインパクト・コミュニティ投資と呼びます。それ以外にも、財務分析のプロセスにESG要因を組み込んで投資するESGインテグレーションや、株主としてESGに働きかけるエンゲージメント等のさまざまな種類があります。
人的資本の注目度や取組水準、企業業績との関係性等について解説しています。
ESGの取組における課題

満足のいく形でESGを実践するには、課題と長期的に向き合うための体力や資力が必要となります。中小企業においては、大企業と比べて思うように施策が打ち出せず、ジレンマを抱えてしまうケースも少なくありません。
商工中金の「中小企業のESGへの取組状況に関する調査」によれば、ESGの取組について次のような課題が挙げられています。
・環境負荷削減活動のマンネリ化や数値による削減目標の限界
・ゴミの細かな分別に必要な保管場所や保管コストの確保が難しい
・大半のリサイクル商品は値段面で折り合いが合わないのが実態
・業界全体として従業員の確保に課題を抱えている
・ESGにかかるコストを価格に上乗せすると取引先の獲得時に不利になってしまう
・定義や価値基準を判断できる確実性のある指標がない
・社会貢献は長期目標であり施策結果がすぐ得られない
ESG経営を進めるにあたっては、多くの場合で資金面や提供価格等に課題が生じてしまうとされています。ESGで得られる経済的なメリットが表出するまでには時間がかかるため、それまで取組態勢をどのように維持するのかが、中小企業における重要なテーマと言えるでしょう。
ESG経営の事例を紹介

ESG経営に取り組む上では、既に実践している企業の事例を参考にしながら、自社に活かせるヒントを探ってみるのも有効です。ここでは、代表的な3社の事例を取り上げ、取組の内容や効果について見ていきましょう。
事例1:ジョイント・ベンチャーを創設し、雇用機会を創出
ある大手総合化学メーカーでは、既存の虫よけ網戸の技術を応用し、マラリア対策に役立つ防虫剤処理蚊帳を開発しました。2001年に世界保健機関(WHO)から世界初の長期残効型蚊帳として認定されると、アフリカの気候でも使いやすいように網目の形状を工夫し、通気性を高めて暑さ対策も行いました。
開発された商品は、さまざまな国際機関を通じて80ヵ国以上に供給され、特に製品を製造するタンザニアやベトナムでは、現地に新たな雇用を生み出す効果にもつながっています。なかでも、タンザニアではジョイント・ベンチャーを創設し、最大7,000人の雇用機会を生み出すなど、地域経済の発展に大きく貢献しています。
「マラリア感染率の減少」と「雇用の創出」という二つの課題を同時に解消した好事例と言えるでしょう。
事例2:ユニバーサルデザインを活かしたものづくり
ある大手消費財化学メーカーでは、早くから「ユニバーサルプロダクトデザイン」の実践に取り組んでおり、多くの人がわかりやすく安心して使える「人にやさしいモノづくり」を進めてきました。代表的なものとして、1991年には洗髪時に目をつぶっていても、シャンプーとリンスの容器を容易に識別できる「きざみ」を開発するなど、暮らしに身近な商品のブラッシュアップに力を入れています。
2010年に「UD(ユニバーサルデザイン)推進プロジェクト」を立ち上げると、さらにESG経営の観点が強まり、よきモノづくりを中心とした社会貢献、交流活動等にも注力されるようになります。例えば、2012年から実施されている「高齢者体験ワークショップ」は、従業員が要介護1相当の疑似体験装具を身につけ、高齢者への共感力を高める重要な機会です。
実際に高齢者の動きを体験することで、製品の使い勝手や表示の課題を発見し、高齢者のQOL(Quality Of Life:生活の質)を高めるモノづくりのきっかけとなっています。
事例3:社会全体の価値創造につなげる
世界に数々のグローバルブランドを持つ大手食品飲料メーカーでは、社会全体への価値の創造を目的とし、CSVをあらゆる行動の基本とする経営戦略を立てています。具体的な取組として挙げられるのが、調達から製造・流通・販売・消費まで、すべてのバリューチェーンにわたるサステナビリティ重視の施策の実現です。
例えば、調達のプロセスにおいては、自社のコーヒー栽培による温室効果ガス排出を削減し、土壌の健全性や肥沃度を高める「再生農業」に取り組んでいます。また、製造のプロセスにおいては、工場では購入電力のすべてを再生エネルギー由来のものに切り替え、年間5万トンもの温室効果ガスの削減につなげました。
さらに、流通においてもモーダルシフトによる中距離輸送の効率化を図り、温室効果ガスの削減を実現します。そして、販売の面では製品パッケージのプラスチック削減を行い、紙製パッケージの使用にも力を入れています。
このように、あらゆるバリューチェーンで一貫性のある施策を進めることで、企業全体としての社会的価値を高める結果につながっているのが特徴です。
まとめ
ESG経営とは「環境」「社会」「ガバナンス」の三つの視点から、企業の社会的な価値を高めるための経営を行うことを指します。ESGの取組は投資が行われる際にも重要な判断基準となっているため、特に上場企業では重要な施策の一つとされてきました。
しかし、近年では中小企業における注目度も高まっており、ほとんどの企業が何らかの形でESG経営を実践していることが明らかにされています。ESG経営では長期的な視点で着実に実行していくことが重要となるため、中小企業で実現するには、無理のない持続可能な計画が求められます。
他社の取組を参考にしながら、自社の業界や強みとする分野、企業規模等も踏まえて適切な経営戦略を構築しましょう。