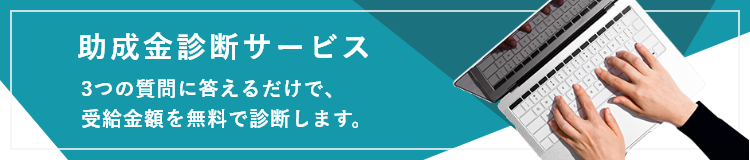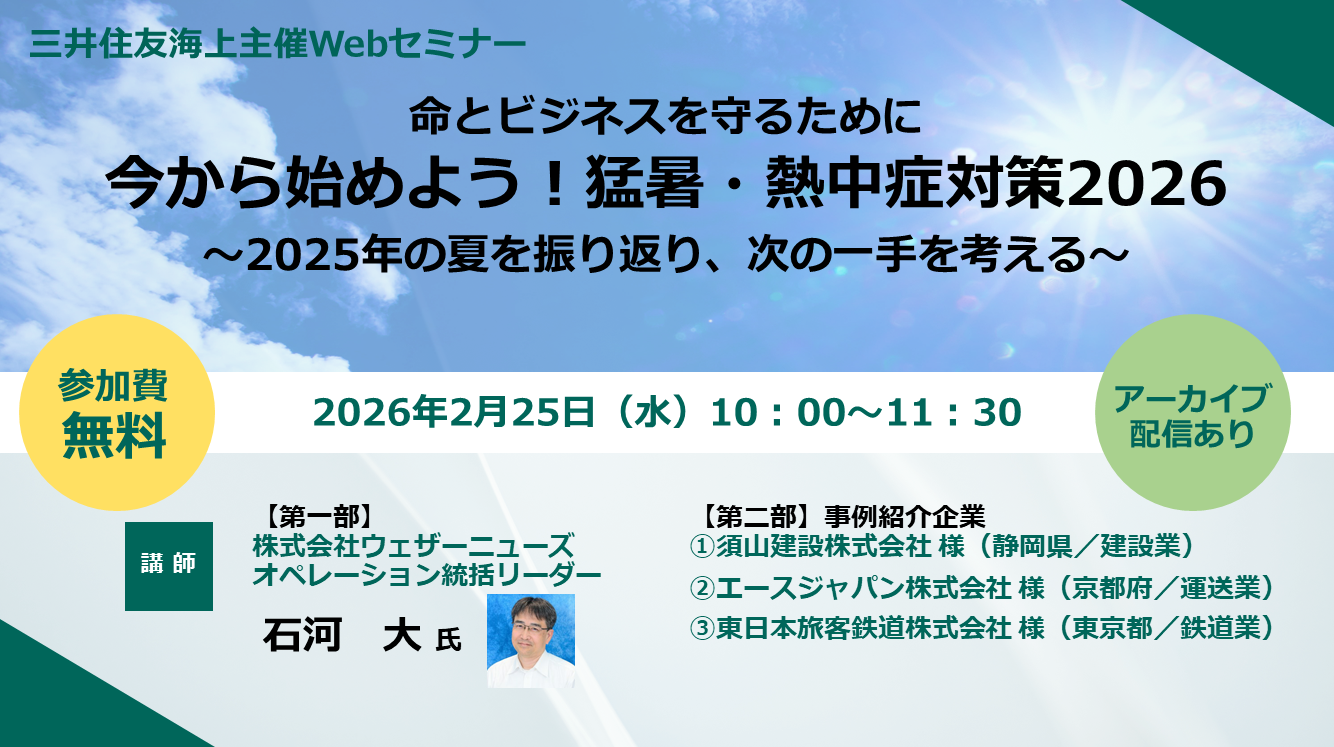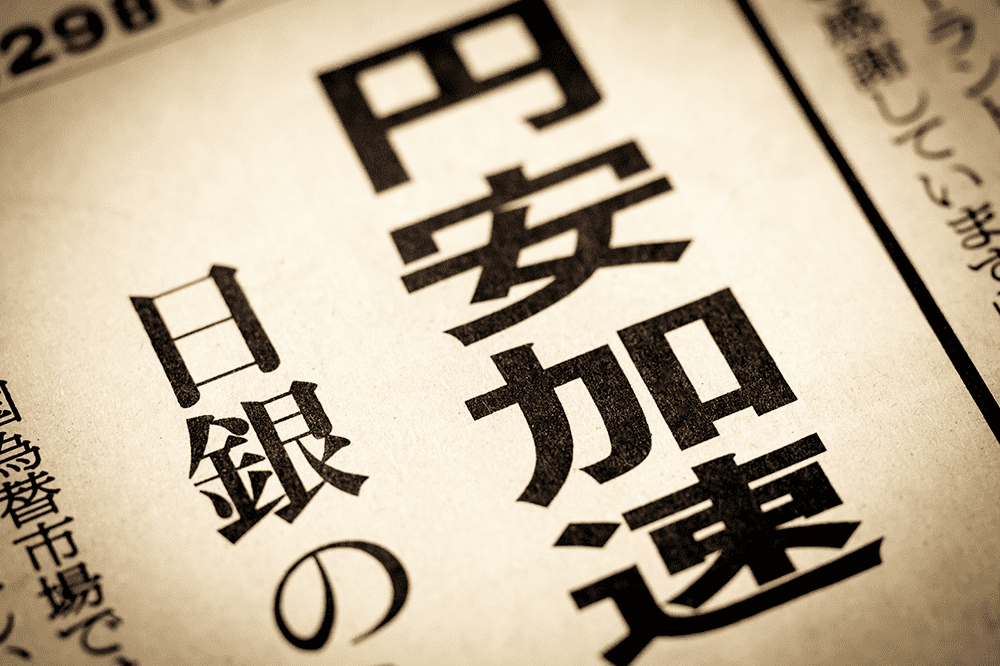労務相談とは?窓口としての社労士、弁護士の違いは?労務相談について解説
公開日:2025年1月29日
人事労務・働き方改革

労務相談とは、書いて字のとおり、労務に関する相談全般をいいます。 しかし、経営者の方や労務の実務に携わっている方にとっては、具体的にどのような内容が労務相談に該当し、どこに相談すべきか悩むことも多いのではないでしょうか。 本記事では労務相談を大きく分類した上で、判断に困った場合の相談先を解説します。
労務相談とは
労働相談と一言でいっても、大きく三つに分類できます。
①従業員と会社の間で行われる労務相談
②従業員と相談先の間で行われる労務相談
③会社と相談先の間で行われる労務相談
会社の相談先について知っておくべきなのはもちろんのこと、従業員が会社への相談後、もしくは相談に先立って相談する先を知っておくことで、労務トラブルの予防に役立ちます。
本記事では③に絞って解説を進めますが、労務相談において何より大切なポイントは、「判断に迷う場合は即答しない」ことです。
スマートフォンやスマートウォッチが普及している今日では、一昔前のボイスレコーダー同様クリアかつ手軽に音声を記録することが可能です。さらには音声のみならず、動画も手軽かつ鮮明に記録できることが、従業員の社内でのやり取りを記録することへのハードルを大幅に下げていることを認識しましょう。
うっかり間違った回答をしてしまうと、後々労働トラブルに発展した際に言い逃れができなくなります。
そればかりか、インターネットやSNSへ投稿されてしまうと、驚くほどの速さで拡散され、炎上しかねません。一度拡散されてしまった動画等はすべて削除するのが事実上不可能で、ネット上に半永久的に残ってしまいます。
そういった事態にならないよう、従業員からのあらゆる質問・相談について、判断に迷う場合はひとまず預かり、確認した上で回答しましょう。これが、社内における労務相談の鉄則です。
【関連記事】
デジタルタトゥーの概要や危険性、企業がとるべき対応策について解説しています。
労務相談の種類と相談先
ここからは、労務相談を大きくジャンル分けした上で、それぞれの代表例と問い合わせ先を紹介します。
労働条件その他労働基準法および関連法規に関すること
・職種、業務内容、契約期間、労働時間、休日、賃金等の労働条件
・就業規則に関すること
・残業時間や36協定等の労使協定
・最低賃金に関すること
これらの相談先は労働基準監督署の監督課(方面)です。
社会保険に関すること
ここでは従業員についての公的保険を総称して社会保険といいますが、社会保険は大きく次の四つに分類できます。
労災保険に関すること
・会社の労働保険(労災保険・雇用保険)の加入、労働保険料に関すること
・就業中、通勤途中のけが、就業に関連した傷病に関すること
・労災保険の申請に関すること
これらの相談先は労働基準監督署の労災課です。
労災の概要や判断基準、発生時の対応のほか、どのようなケースが労災に認定されるのか、具体的な事例をもとに解説しています。
雇用保険に関すること
・会社の雇用保険の加入に関すること
・従業員の雇用保険加入条件に関すること
・退職時の離職票発行に関すること
これらの相談先はハローワークの雇用保険適用課です。
・育児、介護休業中の給付に関することの相談先はハローワークの雇用継続課です。
・失業保険の受給に関すること
・再就職手当、就業促進定着手当に関すること
・従業員が持参した採用証明書、就労証明書等に関すること
これらの相談先はハローワークの雇用保険給付課です。
健康保険に関すること
・会社の健康保険加入に関すること
・従業員の健康保険加入条件、扶養家族の加入に関すること
・会社が納付する健康保険料に関すること
これらの相談先は日本年金機構です。
・傷病手当金(業務外の傷病)、出産手当金(産前産後休業中の給付)に関すること
・退職後の任意継続被保険者に関すること
これらの相談先は協会けんぽ 都道府県支部です。
※会社が健康保険組合、国民健康保険組合に加入している場合はそれぞれの担当窓口をご確認ください。
厚生年金保険に関すること
・会社の厚生年金保険加入に関すること
・従業員の厚生年金保険加入条件、扶養家族の加入に関すること
・会社が納付する厚生年金保険料に関すること
これらの相談先は日本年金機構です。
ハラスメントの定義や主な種類をご紹介した上で、発生する原因と必要な対策について解説しています。
専門家への相談
解説のとおり、労務相談と一言でいっても参照すべき法令、問い合わせ先となる行政機関は多岐にわたります。聞き方が不十分でうまく伝わらなかった場合、問い合わせ先が間違っていないにもかかわらず他の行政機関に誘導される可能性があり、最悪の場合たらい回しにもなりかねません。
そんなときに、これらの労務相談を一手に引き受けてくれるのが労務相談の専門家です。
社会保険労務士(社労士)
社会保険労務士は、労働基準法をはじめとする労働関連法規の専門家であり、各種社会保険制度にも精通したスペシャリストです。加えて給与計算を併せて受け持つことの多い社会保険労務士は、人事労務担当者の頼れるパートナーです。
もちろん、社会保険労務士にも得意分野とそうでないものもあり、中には行政機関への問い合わせを要し相談内容に即答を得られない場合もあります。その場合も、まずは社会保険労務士へ相談することで行政機関窓口のたらい回しを回避できます。
また、うまく説明できない相談も社会保険労務士が言語化して行政機関へ回答を求めてくれるため、いずれにしても労務相談の取りまとめ相談窓口として、社会保険労務士は心強い存在です。
社会保険労務士との契約は「労務相談」をベースに社会保険手続き、給与計算、就業規則等の作成、助成金の代行申請をオプションで加える形をとっているものが多いです。
また、労務相談の範囲もさまざまで、労働基準監督署に指摘されないよう法令遵守に限定した労務相談もあれば、社会保険手続きに関するものも含めた労務相談もあります。
一方で、社会保険労務士との顧問契約にあたって留意すべき点が、労働トラブルで裁判になった際、次に解説する弁護士のように事業主の代理人として法廷に立つことができない、という点です。裁判沙汰にならないよう、日頃から労務トラブルが起こらないように会社づくりをしていくことが社会保険労務士の業務の中心になります。
これから社会保険労務士との顧問契約を検討するにあたっては、上記の顧問契約の範囲等をしっかりと確認の上、進めていくことをおすすめします。
労働トラブルに強い弁護士
弁護士は、裁判で事業主の代理人として法廷に立つ心強い味方です。
同じ弁護士でも専門分野が分かれており、会社として顧問契約する場合は企業法務に強い弁護士であることが一般的です。また、企業法務を専門とする弁護士の場合、労働分野に特化しており労働トラブルにも強い場合が多くあります。
すでに顧問契約している弁護士がいる場合、以下の点について顧問契約の範囲内で可能であるか確認するとよいでしょう。
・社内の法務担当者のほか、人事労務担当者からの相談
・労務相談、労働トラブルへの対応
新たに顧問弁護士との顧問契約を検討する場合、顧問料と相談の上で労働分野にも強い弁護士と契約を結ぶことができれば、人事労務担当者の心強い味方になってくれます。
ただし、社会保険労務士とは異なり社会保険制度や手続きについては専門外であることがほとんどです。そのため、社会保険制度や社会保険手続き、給与計算は社内で問題なく実施できていることを前提とし、労務相談や法令について外部の相談窓口を求める場合、労働分野に強い弁護士は最適なパートナーとなります。
労務相談AIで対策は万全?
少し前に話題となったChatGPTを筆頭に、今日ではAIを導入した各種サービスメニューが充実しています。
これまでオペレーターとの電話が主流であった、携帯電話会社や生命保険会社、家電メーカー等への各種問い合わせも、まずはAIロボットが受付するシステムになっている会社が増えてきています。
そんなAIサービスにおいて、労務相談も例に漏れず、現在は社労士向けに労務相談の解決に役立つ法令や判例、周辺情報を提示してくれるAIサービスもリリースされています。
しかし、AIだけで労務相談が完結するわけではありません。AIの回答に専門的な知識が合わさって、よりスムーズに解決にたどり着く、というサービスモデルであることを理解しておく必要があります。
生成AIは日々急速に発展しており、精度も向上しているため、今後AIによる労務相談の精度も上がっていくことが期待できます。とはいえ、現状AIが苦手とする人間の感情を完全にカバーし、かつ過去の判例等を網羅し、99.9%の精度が約束されるまでにはまだ時間がかかるでしょう。
そのため、現状では困った時に頼りになる社会保険労務士、弁護士がいるというのがもっとも手っ取り早くかつ安心できる方法であると考えられますので、労務相談でお困りの場合はこれを機に専門家との顧問契約を検討してみてはいかがでしょうか。

日本社会保険労務士法人 社会保険労務士 山口 友佳
2009年、SATOグループ 「日本社会保険労務士法人」設立とともに入所。2010年社員に就任。労務相談部門責任者として中小企業、大企業に対する労務コンサルティングを担当。就業規則諸規程のコンサルティング、判例に基づいた実務的なアドバイス等、経験多数。