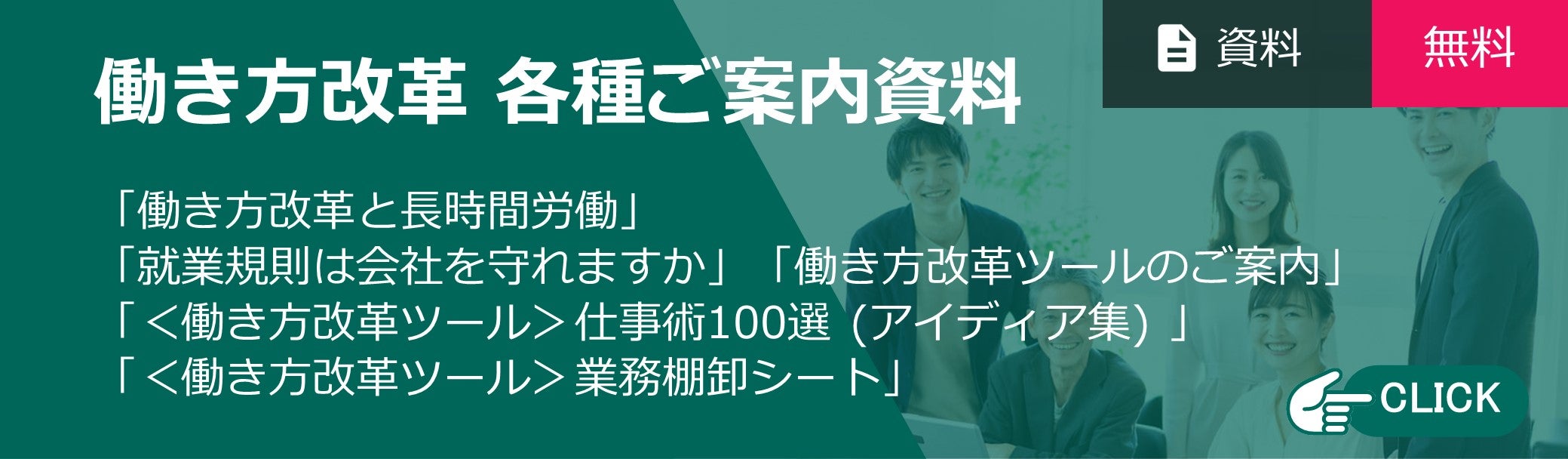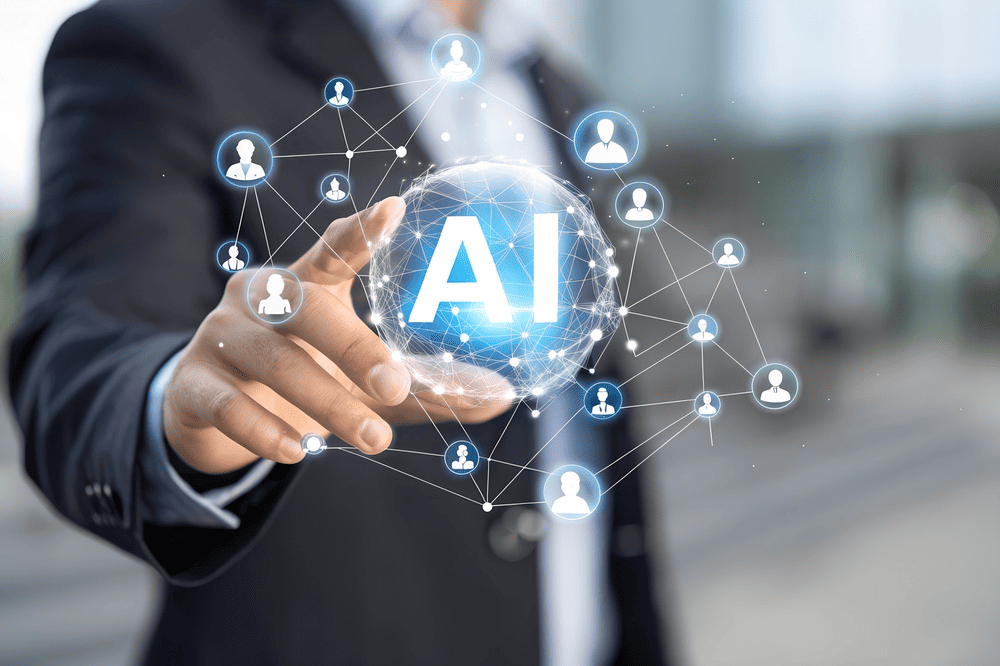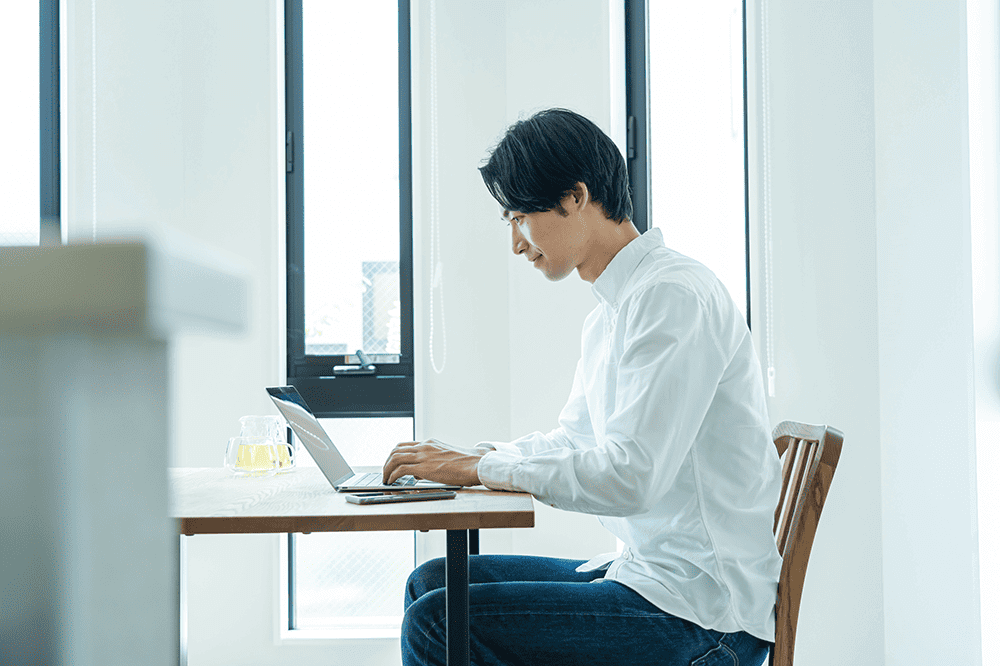人事評価とは?導入するメリットや手順、企業の事例を紹介
公開日:2025年3月17日
人事労務・働き方改革

人事評価は人材の配置や給与・昇進等を決める上で欠かせないプロセスです。どのように人材を評価するかによって、企業や組織の方向性まで決まってしまうため、評価手法や評価項目は慎重に決定する必要があります。
今回は人事評価の基本的な目的や効果、制度を導入する上で意識すべきポイント等をご紹介します。また、実際に人事評価制度の導入・見直しを行った企業の成功事例も併せて見ていきましょう。
人事評価の概要

「人事評価」は人事のさまざまな活動を支える基盤とも言える重要なプロセスです。ここではまず、人事評価の基本的な意味や目的について確認しておきましょう。
人事評価とは
人事評価とは、従業員の業務遂行能力や実績を一定期間に区切って評価する行為のことです。人事評価の結果は、給与や昇進・昇格等の待遇を決めたり、今後の人材育成の方向性を判断したりする上で重要な判断材料となります。
また、人事評価のやり方や判断基準、評価時に重点する項目等は、その企業が「どのように人を育てていくのか」を示すメッセージにもなり得ます。そうした意味では、人事労務管理の基礎にあたる重要な取組と言えるでしょう。
人事評価制度を導入する目的
人事評価制度は多くの企業で導入されており、おおむね三つの目的を備えています。一つめの目的は、従業員に対して客観的かつ公平な処遇を行うことにあります。
評価制度をしっかりと確立することで、評価者による偏った感覚や主観が入り込みにくくなり、従業員も自身の評価や待遇について納得感を得やすくなるでしょう。また、二つめは人事評価を人材育成等につなげていく目的が挙げられます。
適切な評価が行われていれば、人員配置や人材育成の判断もスムーズに行いやすくなります。従業員一人ひとりがどのような特性を持っているのか、どのように貢献しているのかが明らかになるため、より効率的な人事戦略を立てられるのです。
そして、三つめの目的として人事評価制度は、自社の経営理念や事業方針を明示するという役割も備えています。評価基準や評価項目は、企業が従業員に対して何を求めているのかを明文化したものでもあります。
そのため、評価の内容を通して、従業員は自身に期待される行動指針や目標を把握しやすくなるでしょう。
人事考課との違い
人事評価と類似した言葉に「人事考課」があり、実際に両者は同じような意味で用いられるケースも多いです。しかし、厳密に言えば、人事考課は昇級や昇進に関する査定のことを指し、従業員が備えている「能力」をベースに評価する点に特徴があります。
一方、人事評価は実際に対象期間で取り組んだ業務の成果にも焦点を当て、より広い視点で評価を行うのが特徴です。つまり、人事評価の枠組みの一つとして、人事考課が位置付けられると言えるでしょう。
例えば、人事評価の代表的な評価基準として挙げられるのが、「能力評価」「業績評価」「情意評価」の三つの項目です。能力評価とは対象者が持つスキルや経験に対する評価、業績評価は対象者が一定期間内に残した実績に対する評価、情意評価は従業員の意欲や姿勢、主体性等に対する評価を指します。
このうち、能力評価に重きを置いて行われるのが人事考課であり、基本的にその内容は公表されません。一方、業績評価や情意評価も含めて行われるのが人事評価であり、通常は本人に対するフィードバックが行われるほか、育成担当者等にも開示されるケースがあります。
人事評価制度を導入する四つのメリット

企業が適切な人事評価制度を導入することで、具体的にどのような効果が得られるのでしょうか。ここでは、導入のメリットを四つのポイントに分けて解説します。
人材の能力や適性を把握できる
きめ細やかな人事評価制度を確立できれば、従業員一人ひとりの能力や適性を丁寧に把握することが可能です。また、前回までの評価内容と比較すれば、個人の成長度合いも定点観測することができます。
例えば、昨年度と比べて著しい成長を遂げているメンバーがいれば、その要因が個人とチームのどちらにあるのかを確かめたり、きっかけとなった業務や研修を遡ったりすることもできます。望ましい成長を遂げるメンバー間に共通する要素が見つかれば、人材育成の重要なヒントとして活かせるでしょう。
このように、従業員の実情を詳細に分析すれば、一人ひとりに合った育成のプランを組み立てたり、適材適所が実現された人員配置を行ったりすることが可能となります。
帝国データバンクが行った調査結果について解説しています。
従業員のモチベーションを高められる
基準が明確になることで、評価に対する従業員の不公平感・不透明さが解消できるのも大きなメリットです。公平性が担保された状態で人事評価を実施すれば、従業員は自身が適切に評価されていると実感でき、仕事に対するモチベーションが高まりやすくなります。
どのような行動が評価の向上や報酬の増加につながるのかが明らかになれば、自身の役割に対する主体性が自然と生まれていくでしょう。また、適切な基準に基づく評価であれば、たとえマイナスの内容であったとしても納得しやすくなります。
改善すべきポイントがある従業員についても、しっかりとフィードバックを行うことで、信頼関係を損なわずに成長へのきっかけを与えられるでしょう。
従業員のモチベーションが低下することの影響や具体的に改善していくための方法等について解説しています。
経営理念や事業方針の浸透につながる
人事評価の内容を通じて、従業員には自然と自社の理念や方針が浸透していきます。どのような行動が評価されるのかを明示することで、自社が求める人材像がハッキリと伝わりやすくなるのです。
例えば、能力評価や業務評価だけでなく情意評価にも力点を置く基準になっていれば、従業員も仕事への意欲や姿勢が見られていることを理解できます。また、チームワークに関する項目を重視する場合は、企業がスタンドプレーよりも組織としての動きを求めていることがわかります。
このように、企業としての方向性を明確に示せるのも人事評価制度の効果です。
人事評価制度を導入するための五つの手順

新たに人事評価制度を取り入れる場合は、社内全体に影響を与えることを踏まえ、計画的に取り組む必要があります。人事評価の導入手順を五つのステップに分けて見ていきましょう。
経営理念や事業の方向性を明らかにする
これまで見てきたように、人事評価制度は企業の経営理念やビジョンに沿ったものである必要があります。そのため、まずは自社の経営理念や事業の方向性を見直し、言語化・視覚化を図ることが第一歩となります。
また、新たな制度を導入する上では、必要に応じて従業員へのヒアリング等を行い、自社の現状を把握することも重要です。
人事評価制度を導入する目的を示す
続いて、人事評価制度を導入する目的を明確にする必要があります。どのような目的を設定するかによって、評価方法や具体的な項目も大きく変わってくるため、経営層と人事部門による丁寧なすり合わせが求められます。
制度の対象者や評価サイクル等を決める
次に、導入する人事評価制度をどの範囲まで適用するのか、具体的な対象者を決めていきます。例えば、試用期間中の従業員やパートタイムの従業員を対象に含めるべきかどうかによって、細かな評価の方法にも違いが生まれます。
また、評価を行うサイクルについても明らかにしておくことが大切です。人事評価は半期に一度、あるいは1年に一度程度の頻度で実施されるのが一般的です。
具体的には、「前期・後期で分けて2回実施する」「冬季賞与前・夏季賞与前のタイミングに合わせて実施する」といった考え方で行われています。人事評価の目的に応じて、最適な実施タイミングを見極めましょう。
帝国データバンクが行った調査結果について解説しています。
評価者・評価方法を定める
人事評価制度の運用にあたっては、評価者と評価方法も定めておく必要があります。評価者については、ポジションごとにどの階層のメンバーが担当するのかを明確にします。
基本的には直属の上役にあたるポジションの担当者が評価を行うものですが、精度を高める上では、いくつかの階層に分けて設定するのも有効です。例えば、課長クラスであれば「第一次評価者」を部長に任せ、「第二次評価者」を社長が担い、さらに自己評価を加えた三つの階層で判断するといった具合です。
また、人事評価の目的によっては、部下や同僚といった間柄の相手も含めて評価者に設定する「360度評価」という評価手法を取り入れるケースもあります。評価者をどのように考えるかによって、人事評価のあり方が決まってしまうので、自社の実情に合わせて丁寧に検討しましょう。
評価方法については、前述した「能力評価」「業績評価」「情意評価」の3種類を用いるのが一般的ですが、細かな評価項目にはさまざまなパターンがあります。例えば、業績評価一つを見ても、「仕事の量」「仕事の質」「指導育成」「コスト削減」「目標管理」「イノベーション」といった多様な側面からのアプローチが可能です。
評価者によって評価にムラが生じないように、評価項目や判断基準はできるだけ精密に設定し、評価マニュアルを用意するなどの整備を行いましょう。
【関連記事】
コスト削減の捉え方や具体的な方法、注意点、事例等について解説しています。
ルールを策定して、従業員に周知を図る
評価者や評価方法が固まったら、運用ルールを策定し、従業員に説明するための資料を作成します。人事評価の目的を果たすためには、評価者だけでなく評価される全対象者にもきちんと意義や仕組みを理解してもらわなければなりません。
じっくりと周知徹底を図るとともに、どの従業員にも理解してもらえるように、できるだけシンプルなルールづくりをめざすことも重要です。また、説明会等で周知させる機会を設けたら、アンケートで従業員の意見をヒアリングしてみても良いでしょう。
特に現場の責任者等の意見を聞き、実情がきちんと反映されているかどうかをチェックすれば、評価制度の形式化を防ぐことにつながります。
人事評価制度を見直す際の三つのポイント

人事評価は報酬や人事異動といったさまざまな要素に直接的な影響を与えるため、企業や組織の現状に応じて、制度の見直しを行うことも大切です。ここでは、人事評価制度を見直す上で重視すべき三つのポイントについて解説します。
経営方針と人事評価制度の整合性
人事評価制度を見直す時には、経営理念や経営方針との整合性をチェックすることが大切です。自社が求める人材像や人材育成の方針と、現行の評価制度が十分にマッチしているかどうかを確認してみましょう。
また、自社がめざす組織のあり方と照らし合わせ、評価の手法を見直すことも重要となります。例えば、自律型組織の構築をめざすのであれば、評価制度も自律性を重んじたものに改善していく必要があります。
単純な業務量のみに重点を置いてしまえば、個人の創意工夫や挑戦が正しく評価されないため、なかなか自律性も育まれていきません。会社や組織として、自律的な行動を評価するというルールを明示することで、めざすべき人材像へ従業員の成長を促せるのです。
評価基準やマニュアルの変更
評価基準が不明確であれば、適正な評価が行えず、従業員が納得できるような説得力も生まれません。適切な基準がないまま評価を行えば、従業員の不満が溜まり、かえってモチベーションを損なう要因にもなってしまうでしょう。
また、評価方法等がきちんとマニュアル化されていなければ、評価者によって判断にバラつきが生じてしまいます。評価者の負担も大きくなるため、全体としての生産性を低下させる原因にもなるでしょう。
適切な評価を行うためにも、まずは基準やマニュアルにあいまいな部分がないかをチェックすることが大切です。その上で、基準や評価マニュアルについては、常に自社の現在の状況を反映させる必要もあります。
例えば、新たにリモートワークを導入する場合は、評価の方法や基準も適切な形に更新しなければなりません。また、事業規模の拡大により従業員数が増加した場合等も、必要に応じてマニュアルを見直すことが大切です。
【関連記事】
働き方の多様化が示す意味や企業にもたらすメリット、実現するための具体的な手段について解説しています。
従業員への周知
従業員への周知は、新たに制度を運用する上で欠かせない重要なプロセスです。人事評価制度はすべての従業員に関係するため、正しい認識を得た上で協力を求めなければなりません。
定期的な面談を通じて、従業員に人事評価制度を導入する目的や評価基準等をきちんと説明しましょう。
エンゲージメントの概要や測定方法、改善策等について解説しています。
人事評価制度を導入している企業の事例

人事評価制度は適切な形で運用すれば、組織の活性化や生産性向上に直結する重要な仕組みだと言えます。ここでは、導入に成功した企業の事例を三つピックアップし、具体的な取組方をご紹介します。
事例1:建築設計 自社が求める人材像を明確化
建築設計業を営む中小企業A社では、多様かつ高度な技能が求められる業務に対応するため、社内の資格取得の奨励と人材強化を目的として人事評価制度を整備しました。そして、自社が求める人材像に合わせ、職務遂行能力に応じて6等級に区分した職能資格制度を構築し、同時に人事考課マニュアルを制定しました。
職能資格制度により、能力に見合った格付けを行うことで、円滑な人事管理が可能となりました。そして、マニュアルに人事評価制度の目的やルールについて明記したことで、従業員全員が評価の意義や仕組みを理解できるようになりました。
その上で、同社の取組で特に重視されていたのは「運用のしやすさを優先して評価項目の複雑化を防ぐ」「日ごろから従業員と管理者間のコミュニケーションを図り、スムーズな運用を実現させる」「人事評価制度を動機付けの道具として捉える」という点です。わかりやすいシステムを構築し、仕組みを従業員にもきちんと理解してもらうことで、人事評価制度がモチベーションアップのきっかけとして機能したとされています。
従業員のモチベーションが低下することの影響や具体的に改善していくための方法等について解説しています。
事例2:総合商社 従業員の等級を細分化
家庭用の日用品を取り扱う総合商社B社では、新卒や若手の人材の育成強化に向けて、独自の人事評価制度を導入しました。具体的には、新卒者や若手人材を5年間で一人前に育て上げることを目的とした「プロフェッショナル教育」の一環として、評価のあり方が再定義されたという取組です。
それまでの同社では、営業部門では半年後にすぐ独り立ちに近い状態で経験を積ませる一方、商品部門では3年間の社内実習を行ってから商品開発担当者になれるなど、各部門がバラバラに育成を行っていました。そこで、各部門の育成制度を統一し、汎用的な知識や業務スキルの習得をめざすために人事制度にメスが入れられたのです。
同社では既に6段階の等級制度が導入されていたことから、一人前と認定される基準を3等級に設定し、まずはそこをめざして新卒・若手の育成計画を実行しました。前段階にあたる1・2等級を細分化し、具体的なステップを見える化することで、従業員それぞれが「一人前」までの道のりを自覚できるようにしたのです。
このように、細分化と見える化により、若手従業員のモチベーション向上を促す仕組みづくりが実現されているのが同社の大きな特徴です。
新入社員教育における課題やケア等について解説しています。
事例3:流通サービス 管理職の評価制度を変更
流通サービス業の運営を行っている上場企業のC社では、2年間にわたる人事制度の大幅改定により、管理職の賃金・評価のあり方を改革しました。それまで管理職を対象とする部門横断的な評価基準がなかったことから、共通の評価基準を設定し、賃金に反映させる仕組みを構築しました。
これは、管理職の評価制度を刷新することで管理体制や管理能力の向上を図り、企業全体の労働環境整備、法令遵守の仕組みを強化するのが狙いとされています。企業が求める管理体制を実現するために、評価制度そのものを刷新するという点に、この取組の大きな特徴があると言えるでしょう。
また、同社では十分な経験と資質を持ちながらも、「現場の第一線で働きたい」という従業員の声に応え、管理職以外のキャリアアップ制度として「エキスパート職」を新設しました。そして、複線型人事制度を導入するにあたって、新たに職業能力評価基準を活用し、評価制度を策定し直しました。
このように、人事体制の変化に合わせて、適切な評価制度へ更新することも重要なプロセスと言えます。
帝国データバンクが行った調査結果について解説しています。
まとめ
人事評価制度は、企業の人事管理を支える基盤であるとともに、企業が求める人材像を示したメッセージでもあります。どのような項目を評価するかによって、従業員は企業から求められている役割をしっかりと認識できるのです。
そして、従業員一人ひとりの努力や取組が的確に評価されれば、会社に対する信頼度や仕事へのモチベーションが向上していきます。人事評価制度を適切に運用していくためには、自社の理念や実情に合わせた基準や手法を検討することが大切です。
まずは基本的な目的とポイントをおさえて、自社の評価制度を丁寧に見直してみると良いでしょう。