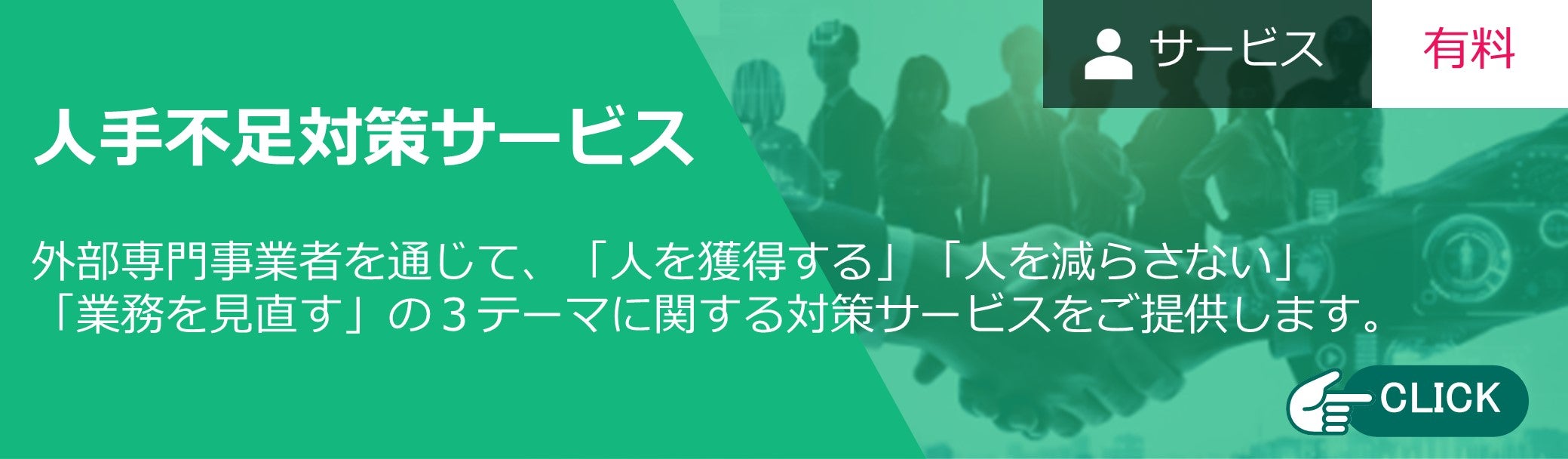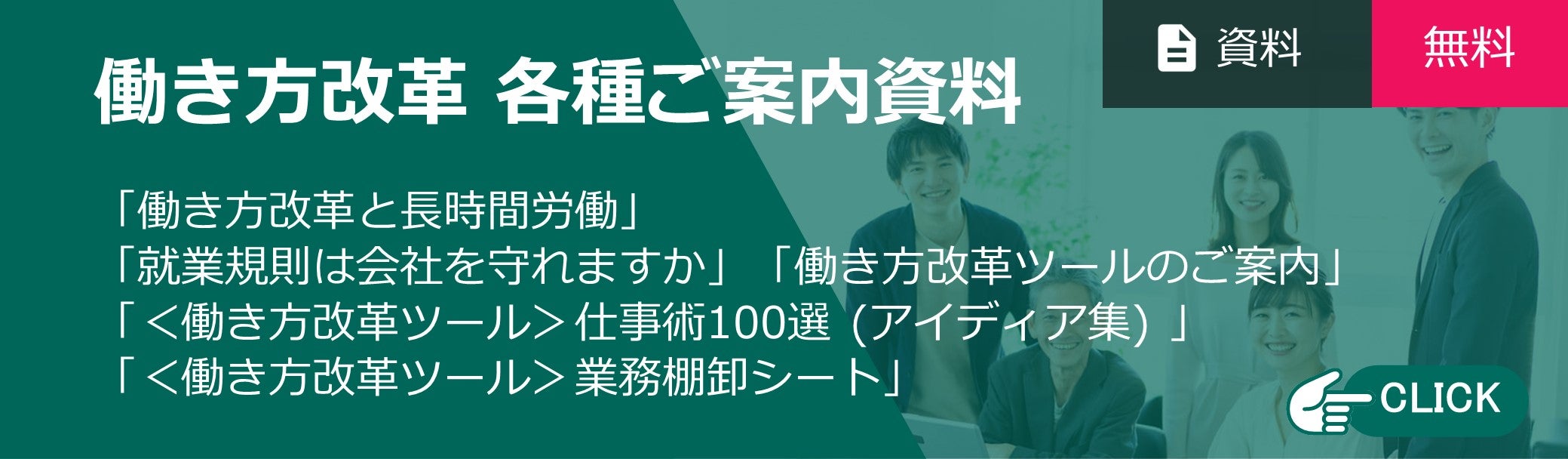採用戦略とは?立案の流れとポイントを事例とともに解説
公開日:2025年7月28日
人手不足

採用戦略とは、企業の将来も見据えながら、自社が求める人材を適切な形で獲得するための計画のことです。採用活動を進める上では、場当たり的な人材確保ではなく、長期で活躍してもらえる人材の獲得をめざす必要があります。
その土台となるのが採用戦略であり、現代では求職者の価値観や採用手法も多様化していることから、特に重要性が高まっています。今回は、採用戦略の重要性や立て方、中小企業における事例等を詳しく見ていきましょう。
採用戦略とは

「採用戦略」とは、企業が求める人材を効果的に確保するために立てる戦略を指します。より具体的に言えば、「どのような人材を何名採用するのか」「どのような採用チャネル・採用手法を用いるのか」を明確化し、採用活動の質を高めるための土台とも言えます。
人材採用では、単に高度なスキルや経験を持つ人材を採用するというだけでなく、自社にマッチする人材を適切な形で引き入れることが重要です。そのためには、経営計画や事業計画を踏まえながら、将来を見据えた人材採用を進めなければなりません。
そこで重要となるのが、確かなデータと分析に基づいた採用戦略です。明確な採用戦略があれば、限られた経営資源を最大限に有効活用し、効果的な採用活動が行えるようになります。
採用戦略の重要性
採用戦略を立てる一つのメリットは、自社にマッチする人材を見極めやすくなる点にあります。社内の状況と照らし合わせ、どのような条件の人材が理想的であるのかを明確化することで、選考の質を高めやすくなります。
マッチ度の高い人材を採用できれば、入社後もスムーズに活躍してもらうことができ、早期離職等のトラブルも予防できるでしょう。もう一つのメリットは、採用ターゲットを明確化することで、相性の良い採用チャネルや採用手法を選びやすくなる点にあります。
人材採用にかけられるコストは、当然ながら無制限というわけではありません。限られたリソースを最大限に活用するには、採用手法の取捨選択が必須です。
自社やターゲットに合った手法を戦略的に見極めることで、コストパーフォーマンスの最大化を図るのも採用戦略の重要な目的です。
リーダー人材の不足について解説しています。
採用戦略が重視されている背景
採用戦略の重要性が高まる背景には、労働人口の減少や価値観の変化といったさまざまな影響が考えられます。
人手不足に伴う採用競争の激化
現代の日本では、生産年齢人口の減少によって、構造的な人手不足が生じています。少子高齢化に伴い、とりわけ若年層の求人は売り手市場の状態が続いており、企業間での採用競争も激化しているのが現状です。
求人倍率が高まる状況にあって、各企業が採用における競争力を高めるには、確かな戦略が求められるようになっています。特に中小企業は知名度や体力の面で不利になりやすく、大手企業とわたり合うためには十分な工夫と独自性のある取組が必要とされています。
そのためにも、求人市場や自社の強み、競合他社の状況等を多角的に分析しながら、根拠のある採用戦略を練り上げていくことが重要です。
新卒社員の初任給について解説しています。
価値観の多様化
採用戦略が重視されるもう一つの理由は、働き手の価値観の変化です。現代では、働き方改革の推進等によって、考え方や労働環境が多様化しているのが特徴です。
例えば、働き方一つをとっても、リモートワークやフレックスタイム制、残業時間の短縮といったさまざまな選択肢が生まれています。また、厚生労働省の調査(※)によれば、若者(中高生・大学生)の労働価値観は、給与や出世等の外的報酬よりも、自己成長や興味・好奇心の追求といった内的報酬に対する欲求が強いという傾向が見られます。
さらに、20代~30代の労働者では、「好きな時間に好きな場所で働く」という自由な働き方を志向する傾向が明らかになっているのも特徴です。このように、働き手の価値観が変容する時代においては、企業側にも柔軟なスタンスが求められるようになっているのです。
加えて、人材サービスが多様化している点も、採用戦略が重要となる大きな理由です。近年では、転職に対するハードルも低くなっており、高度な能力を持つ人材がステップアップのために人材サービスを利用するケースもめずらしくありません。
サービスの多様化により、企業側で工夫できるポイントも増えているため、確かな採用戦略を持ってチャンスを逃さないことも重要となっています。
採用戦略の立て方を8つのステップで解説

採用戦略を立てる際には、一つひとつのプロセスを丁寧に進めていくことが重要です。ここでは、以下の8つのステップについて、詳しく見ていきましょう。
・経営計画・事業計画の把握
・要員計画の策定
・採用ターゲットの設計
・自社の強みの明確化
・採用チャネル・採用手法の選定
・採用スケジュール・KPIの設定
・体制の整備
・実行・効果検証
経営計画・事業計画の把握
採用戦略は、あくまでも経営計画・事業計画に紐づいたものでなければなりません。そのため、まずは自社の中長期的な計画について、内容を正しく把握する必要があります。
それには、経営者層とも緊密な連携を図りながら、人事と経営が一体となって戦略を話し合うのが理想です。また、採用戦略では、特に3~5年程度のスパンを見通した中期経営計画に基づき、必要な人材や予算を見極めていくのが基本です。
数年のうちに新たな事業を展開する予定があるのか、現在の部署を統合する可能性があるのか、新たな地域に商圏を広げるのか等、企業全体の計画を丁寧に把握していきましょう。
採用ターゲットの設計
要員計画が明らかになったら、自社が求める採用ターゲット(採用ペルソナ)を具体化していきます。採用ペルソナとは、採用したい人材を実在する人物のように細かく具体化したものです。
ここでは、採用ペルソナの一例をご紹介します。
・年令:30歳までの若手
・学歴・専攻:中堅私大で情報工学を専攻
・スキル:基本的なコミュニケーション能力、チームワークを苦にしない
・経歴:新卒で入社後3~5年で一定のエンジニア経験を積んでいる
・仕事で大事にすること:スキルを活かしながら地域に貢献する
・働き方の希望:給与よりもワークライフバランスを重視
・勤務条件:週1~2日程度のリモートワークを希望している
このように、採用したい人材像をできるだけ言語化しておくことで、採用チーム内での認識のズレが予防できます。その結果、選考の質やスピードも高めやすくなるでしょう。
人材採用版3C分析
採用ペルソナを考える上では、客観的な視点での分析も重要です。「3C分析」は、一般的にはマーケティングで用いられる分析手法ですが、人材採用にも活用することができます。
以下のように、ターゲットを「自社(Company)」「競合(Competitor)」「候補者(Candidate)」の3つの観点から分析し、3つが重なるポイントに自社のペルソナを見出すというシンプルな手法です。
・Company(自社):自社がめざす姿や今後の方向性、経営層が求める人材像、内部から見た自社の魅力
・Competitor(競合):競合が打ち出している魅力、採用ターゲット
・Candidate(候補者):外部から見た自社の魅力、過去の候補者の応募理由あるいは辞退理由
SWOT分析
採用ペルソナを策定する上では、自社の実情も的確に把握しておく必要があります。そのために活用できる分析手法が「SWOT分析」です。
SWOT分析とは、以下のように4つの象限から、自社を取り巻く内部と外部の環境を分析する手法です。
・Strength(強み):自社が持つ強み、競合と比べた時の相対的な魅力
・Weakness(弱み):自社が抱える弱み、競合と比べた時に劣るポイント
・Opportunity(機会):自社を取り巻く事業の機会、市場におけるチャンス
・Threat(脅威):自社を取り巻くリスク、法改正や規制、ニーズのネガティブな変化
SWOT分析を活用することで、自社の客観的な状況が明らかになり、採用ペルソナの設定に必要な情報を抽出できます。また、採用時のアピールポイントや、応募までに改善すべき点も明確になるでしょう。
自社の強みの明確化
採用ペルソナが明らかになったら、改めて自社の強みを明確化します。このプロセスにおける強みとは、従業員に与えられる魅力や価値のことです。
「企業が従業員にどのような価値を提供できるか」に主眼を置くフレームワークとして、「EVP」(Employee Value Proposition)の設計が挙げられます。採用戦略においては、その会社で働くメリットを従業員の立場から明らかにすることで、求職者への訴求ポイントを探るのがEVP設計の主な目的です。
具体的な進め方としては、まず「給与や待遇」「キャリア」「働き方」「やりがい」「社会とのつながり」といったポイントについて、アンケート等で従業員の声を集めます。その後、他社と差別化できるポイントを洗い出し、EVPの決定・構築を行います。
採用チャネル・採用手法の選定
採用ペルソナと自社の強みが固まったら、それらに合わせて適切な採用チャネル・採用手法を選定していきます。主な採用チャネルとしては、次のようなものが挙げられます。
・人材紹介
・求人広告
・ダイレクトソーシング
・採用イベント
・リファラル採用
・採用オウンドメディアの運営
・アルムナイ採用
人材紹介や求人広告は1人あたりの採用コストは高くなる一方、運用工数は少なく、質・量ともに十分な母集団にアプローチできるのが魅力です。また、ピンポイントで必要な人材にアプローチをするのであれば、ダイレクトソーシングを活用してみるのも良いでしょう。
一方、今後も安定的に採用活動を行うのであれば、採用オウンドメディアを立ち上げ、自社が主体となって情報発信を続けていくことも重要です。運用工数はかかってしまいますが、オフィスの日常風景や先輩社員の声等を自由に発信できるため、高い訴求力が期待できます。
従業員の紹介によるリファラル採用や、かつて自社で働いていた従業員を対象とするアルムナイ採用も併用しながら、最適な採用チャネルの組合せを検討しましょう。
SNSを活用した採用手法について解説しています。
【関連記事】
リファラル採用の実施手順や成功させるポイントについて解説しています。
【関連記事】
アルムナイの概要や採用手順、注意点について解説しています。
採用スケジュール・KPIの設定
続いて、要員計画や採用チャネルに応じて、採用スケジュールを設定します。この時、施策の効果検証を行うためにも、採用KPIを明確化しておくことが重要です。
代表的なKPIとしては、応募数、面接通過率、内定承諾率、定着率、1人あたりの採用単価等が挙げられます。大量採用するのか、長く働いてくれる人材をピンポイントで探すのかによっても重視すべき目標は異なるため、自社の状況に合わせて細かく検討しましょう。
体制の整備
おおまかな戦略が固まったら、選んだ採用チャネル・採用手法に応じて、必要な運営体制を整備します。特に採用オウンドメディアを運営したり、自社で採用イベントを行ったりする場合は、工数も多くなりやすいため注意が必要です。
募集要項の作成や募集活動、書類選考、面接、アフターフォローまでのプロセスを洗い出し、既存業務とのバランスを考慮しながら、社内での役割分担を決めましょう。その上で、スケジュールと照らし合わせ、進行管理の仕組みを整えれば実行段階へと進めます。
実行・効果検証
求人市場の動きは細かく変動していくため、当初の採用戦略が必ずしもうまく機能するとは限りません。実行に移す際には、KPIをもとに効果検証を行いながら、施策の妥当性を確かめていくことが大切です。
このように、採用戦略では、PDCAサイクルを回しながら精度を高めていくことが前提となります。それだけに、実行にあたっては、長期的に取り組める計画を立てる必要があります。
特に中小企業の場合は、初めから大きなコストをかけるよりも、スモールスタートで試行錯誤を重ねていくほうが良いケースも多いです。柔軟に調整できるように、リソースにはゆとりを持たせておくことを意識しましょう。
エンゲージメントを向上させるメリットや測定方法等について解説しています。
中小企業における採用戦略の好事例

中小企業における採用戦略は、自社の魅力をうまく引き出せるように、企業独自の工夫を凝らしていくことが成功のカギとなります。リソースに制限がある分、自由度の高さが強みでもあるため、時には思い切ったアクションを起こしてみるのも良いでしょう。
ここでは、厚生労働省が取りまとめている「地域で活躍する中小企業の採用と定着成功事例集」より、採用戦略における優れた事例をご紹介します。
多様な人材に活躍の土台を整備
採用戦略では、採用活動と並行して、自社の魅力向上に力を入れることも大切です。運輸業界のとある企業では、これまで採用実績のなかった育児中の女性求職者からの応募をきっかけに、子育て世代の女性を含めた多様な人材の活躍を後押しする「ダイバーシティ経営」に取り組みました。
能力に応じて、短時間勤務者の正社員登用やプロジェクトリーダーへの登用を可能にしたり、外国人従業員の正社員採用に力を入れたりと、柔軟な雇用環境を実現していきます。さらに、健康経営の実施や長時間労働の是正に取り組み、従業員満足度の向上にも力を入れました。
その結果、多彩なスキルを持つ人材の応募が集まり、社内の活性化が進むという結果につながりました。また、地域密着事業をブランディングにつなげることで、地域の課題解決に関心の高い人材からの応募も増加しています。
【関連記事】
企業が働き方の多様化を推進するメリットや具体例等について解説しています。
採用ターゲットを意識した情報発信
中小企業の人材採用では、自社の採用ターゲットに合わせたきめ細かな情報発信も重要となります。とある離島の運行会社では、観光需要の増加に対応するために、フルタイムに縛られない柔軟な雇用環境の実現に着手しました。
そして、高齢者や主婦層の求職者には時短勤務を、季節労働者には短期間就労の提案を行うなど、ターゲットに合った求人ページを作成します。また、県外出身の資格保有者に対しては、職場環境を事前に把握できるように、採用オウンドメディアでリアルな働き方を発信しました。
加えて、離島という地域特性を活かし、SNS等で高頻度の発信を続けています。県外出身者の関心を捉えるキャッチコピーを精査し、定期的な発信を行うことで、着実に応募者数が増えていきました。
さらに、事前の情報発信を丁寧に行った結果、「採用した人材の移住後のミスマッチ」という離島ならではの課題解消にも成功しています。
高年齢労働者の現状や職場づくりについて解説しています。
【関連記事】
健康経営が求められる背景やポイントについて解説しています。
副業人材の活用
採用戦略では、要員計画の段階で、本当に新規採用が必要なのかを十分に精査することも重要です。ピンポイントな人手不足には、柔軟に副業人材の活用を考えてみるのも一つと言えるでしょう。
製造業のとある企業では、販路拡大をめざすにあたってECサイトの活用に挑戦するも、担当者の離職により大きな壁に直面しました。そんな時、県が開催するセミナーを通じ、全国のプロフェッショナルな人材を副業人材として採用し、オンラインで活用できるサービスを知ります。
そこで、経験豊富なITスキルの保有者やデザイナー等を副業人材として採用し、社内の新たな部署に就いてもらうことにしました。部署には若手従業員を配属し、副業人材からオンラインで指導を受けながら、OJTでECサイトの構築を進めました。
さらに、副業人材の「高校生の採用にはSNSの活用が必須」という意見を受け入れ、アドバイスを受けながら運用を進めていきます。その結果、毎年3~4名の高校生を順調に採用することに成功しています。
【関連記事】
副業人材を活用するメリットや注意点について解説しています。
まとめ
効果的な採用戦略を立てられれば、自社の強みや魅力をしっかりと引き出し、納得のいく採用活動が行えるようになります。そのためにも、まずは社内の実情を丁寧に分析し、要員計画や採用ターゲット、適切な採用チャネルを一つずつ見極めることが大切です。
また、他社の成功事例を参考にしながら、自社に活かせるヒントを探ってみるのも有効です。そして何より、採用戦略は自社の経営計画や事業計画に基づき、実情に合わせて立案していく必要があります。
人事部だけでなく、経営層や現場の担当者とも連携を図りながら、じっくりと自社に合った採用戦略を組み立てましょう。