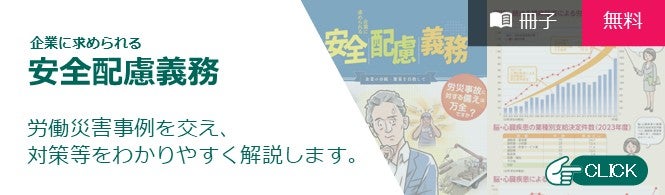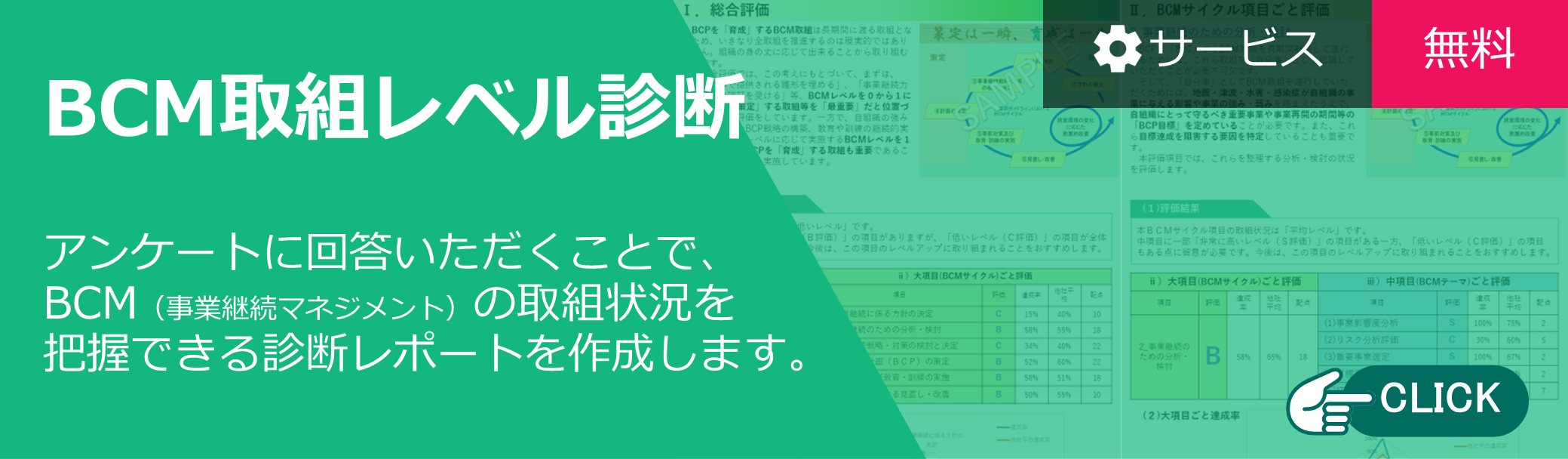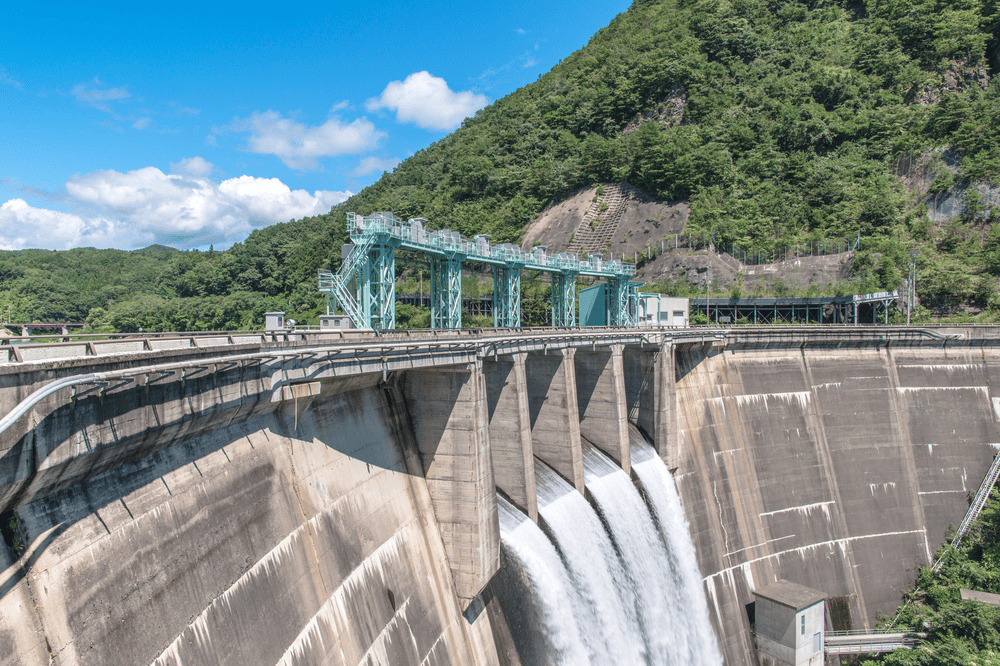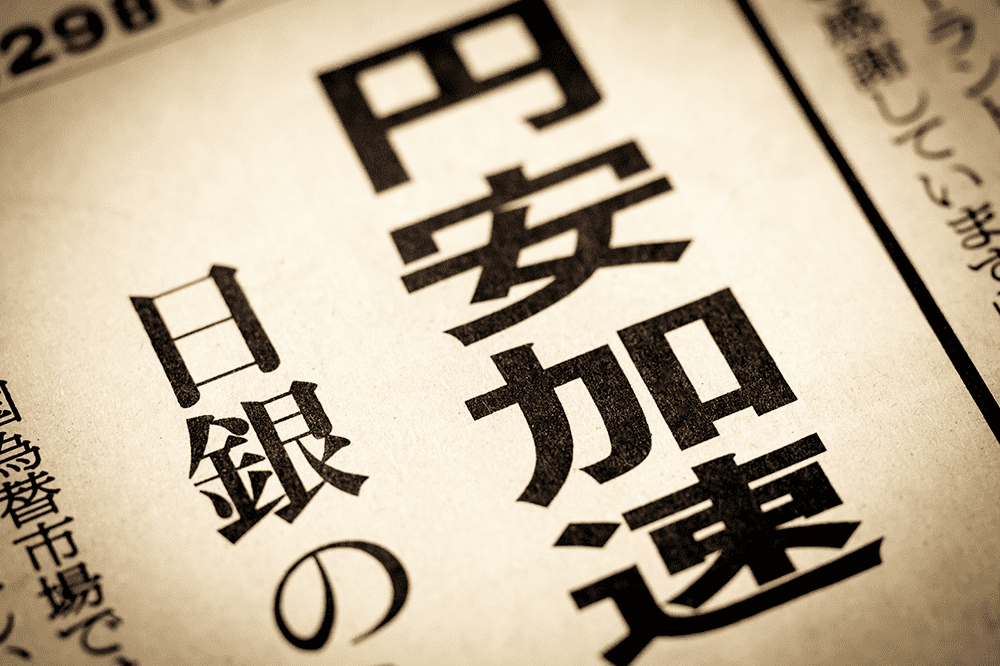企業に求められる救護の対応力向上へ向けた取組
公開日:2023年9月25日
自然災害・事業継続
.jpeg)
■大規模災害発生により事業所で負傷者が発生した場合、事業所は医師や看護師等の専門家の助けを得にくいことが想定されるため、自ら救護活動を遂行することが求められています。
■そのため、予め救護対応の計画を立てておくことは重要ですが、本編では、事前の習得が必要とされる、特に『負傷者搬送』と『応急手当』にフォーカスし、その課題や見直しのポイントを考察します。
■また、策定した救護対応の実効性を上げるために実施することが推奨される救護訓練の実施例を紹介のうえ、訓練のポイントを整理します。
企業における救護対応計画の必要性
“救護”とは、負傷者を救助し、保護・看護することであるため、本来は医師や看護師、救急救命士などの専門家が対応することが望ましいです。しかし大規模災害発生時には、119番通報をしても、平時のように救急車を呼び寄せることは困難なうえ1)、医師や看護師など専門家が常駐している拠点(事業所)も少ないのが現状です。このような現状であっても、企業には従業員の安全確保に全力を尽くすことが求められています。したがって、単に重要事業の実施・継続と早期復旧の為の人的リソースの確保だけでなく、人的資本の確保と災害時における安全配慮義務の観点からも取組を進めることが重要です。
一方で、平時には企業が社員に人命救助や救護活動を求めることがないため、突発的に発生する有事に必要な活動ができない可能性は高いです。また、昨今ではリモートワーク推進により、自衛消防組織の編成自体が難しい企業もあると考えられます。そのため、自社の出勤状態などを考慮した救護対応の計画(災害時における企業の自衛消防活動や対策本部活動において応急救護や負傷者対応、医療機関への搬送などを規定した計画書や手順書)を立てておくことが望ましいです。
しかし、専門家がいない企業においては、特に、知見がなければ習得できない事項について計画を立てることは困難です。そのため本稿においては、特に事前に知見の習得が必要とされる「応急手当」と「負傷者の搬送」にフォーカスし、専門家を有していない企業での取組について、事例を交えて解説します。
事業継続力強化計画の基本的な仕組みや策定するメリット、具体的な策定手順などを解説します。
救護対応計画の訓練の必要性
有事に「応急手当」や「負傷者の搬送」の実効性を確保するには、前述の課題への対応が不可欠です。また、救護のための「救急セット」や担架を準備している企業は多いですが、実際に他人の手や足に包帯を巻いたり、担架に人を乗せて運んだりする経験が無ければ、計画されたことをスムーズに実行することは困難と思われます。したがって、計画したことを有事に実行できるようにするには、訓練や演習を繰り返し実施することが有効です。
なお、訓練を実施するなかで、「一般人が手当てをすることでケガが悪化した場合に責任を問われないのか」といった、法的責任に関する質問がありました。結論としては、市民が善意で実施した応急手当の結果について、故意による重大な過失がない限り法的に責任を問われることはありません2)3)。そのため、大規模災害発生時やケガ人を見かけた場合には、その場にある物や人を使い、できる限りのことをしていただくよう伝えました。ただし、法的責任は問われないものの、自分の行為によって他人に損害を与えてしまうような結果は望ましくなく、手当てした社員の心の傷として残ってしまうこともあります。また、負傷者を助けるために受傷してしまうようなことも、安全配慮の観点からも防がなくてはなりません。そのため、平時から救護対応訓練は繰り返し実施することが重要です。
【関連記事】
安全配慮義務違反に当てはまるケースや防止策、企業のリスクと責任等について解説しています。
救護対応計画の訓練実例
(1)訓練概要
訓練の概要、タイムテーブルは以下のとおりです(図1)。訓練手法は実践的な演習を中心に行います。ただし、演習に先立ち、地震発生時にオフィスにおいてどのようなケガが発生しうるかをイメージしていただくため、アイスブレイクとして参加者同士でディスカッションをしたのちに、演習に入ることも有効です。講師は対応方法を説明するにとどめ、ほとんどの時間を演習に費やし、応急救護を担う組織の活動をイメージしてもらうことを柱に進めるよう企画しました。
.png)
(2)訓練の様子と参加者の感想
①応急手当
応急手当のパートでは「出血している」という状況を提示し、ガーゼや包帯を実際に他人に使用する体験していただきました(図2、図3)。訓練上の工夫として、幅に差がある包帯を配布したところ、「なぜ幅が違うのか」という質問がありました。また、包帯はどうやって巻くのか、傷に対して包帯をどこから巻き始めればよいのかなど、積極的に疑問が寄せられました。考えていたよりも力の入れ方や腕の支え方など難しく、「やってみないとわからないものですね」との感想があがりました。
.png)
②負傷者の搬送
負傷者の搬送は、実際に配備されている簡易担架を組み立てる体験とし、ドアを開けて会議室を出てUターンするという短い距離の搬送体験としました(図4、図5)。搬送を担当した参加者からは「比較的簡単に組み立てることができた」「この担架で階段を下るのは絶対に無理だ」「長距離の移動は重くて無理だ」という意見が出ました。また、負傷者役として担架に乗った参加者からは「非常に怖かった」という意見が得られました。
【関連記事】
平成 29 年に『水防法』が改正され、要配慮者利用施設の「避難確保計画の作成・報告」および「避難訓練の実施」が、令和 3 年には「避難訓練結果の報告」についても義務化されました。避難確保計画の課題と取組のポイントについて解説します。
救護対応計画の訓練実施のポイント
紹介しました応急手当の訓練の内容は、包帯を巻く、ガーゼを当てる程度のものでした。しかしながら包帯一つとっても、それをどう扱えばよいのかについては、実際に「巻く」という行為をしなければ疑問すら浮かばないのが平時の状態なのです。高度に専門的な内容を扱う必要はなく、簡単なものを題材とし、実際にやってみるような時間を設けることが重要です。
また、負傷者の搬送訓練のように全員が体験できないものについては、デモンストレーションに参加した人の感想をその場で全員に共有することがポイントです。訓練後のアンケートで回収する予定であっても、その場で共有いただく時間を取ることをお勧めします。その場での感想の共有は、搬送を体験していない参加者の代理体験につながり、「搬送備品はこれでよいのか」「新しいものを購入すべきか」「搬送を担当するメンバーは何人必要か」といった、救護対応計画立案や見直しにつながる対話の発生を促進できます。
このような救護対応訓練が必要なことは、多くのお客さまにご理解いただけていると考えています。しかし新型コロナウイルス感染症の影響もあって、ここ数年の教育・訓練実施が難しくなっているとも考えられます。まずはオフィスから屋外へ搬送するまでをイメージするために、設置している担架を持って搬送経路を歩いてみてはどうでしょうか。これだけでも具体的な搬送経路が思いついたり、障害物となるものが明らかになることもあります。まずは救護活動で使用すると計画しているものを担当者全員でさわり、使ってみることから始めていただき、より実践的な計画の立案、見直しへつなげてください。
MS&ADインターリスク総研株式会社発行のBCMニュース2023年4月(NO.5)を基に作成したものです。


.png)
.jpg)