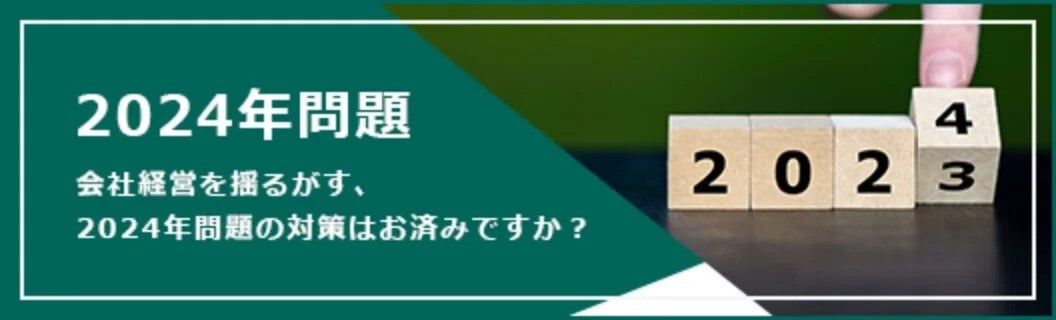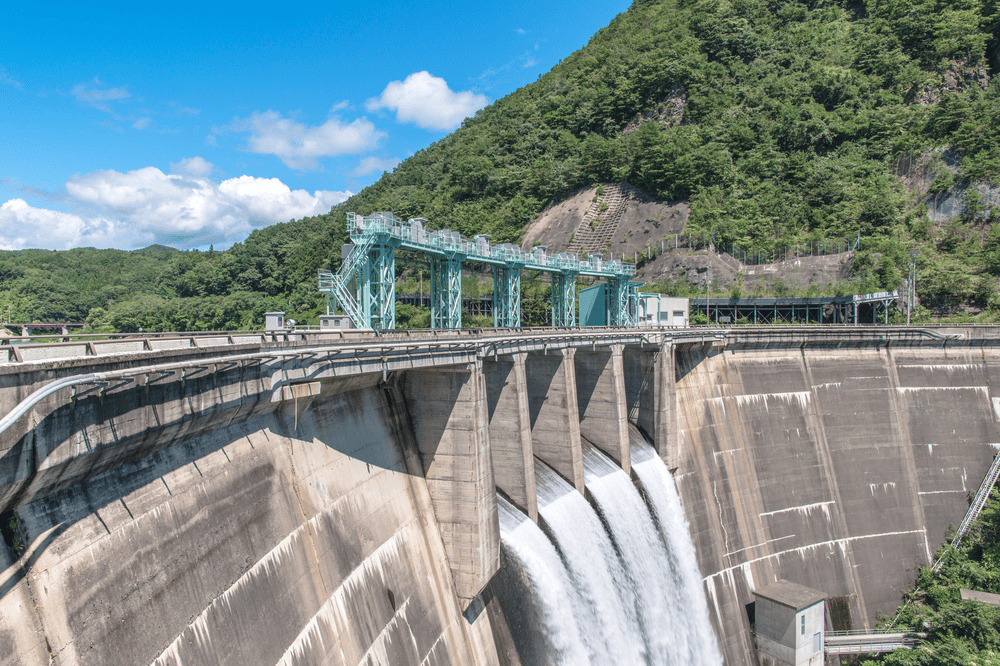サプライチェーンマネジメント(SCM)とは?仕組みや導入のメリット、活用できる補助金制度を紹介
公開日:2025年8月25日
自然災害・事業継続
助成金・補助金

サプライチェーンマネジメントとは、個別の企業やプロセスだけでなく、調達から販売までのサプライチェーン全体を運営管理するという概念です。近年ではさまざまな理由からサプライチェーンマネジメントの重要性が注目されており、関連する補助金等も整備されています。
今回はサプライチェーンマネジメントの基本的な仕組みやメリット、導入する方法等を詳しく見ていきましょう。
サプライチェーンマネジメント(SCM)とは?

「サプライチェーン」とは、原材料を仕入れてから製品として完成させ、消費者に届けるまでの一連の流れのことです。具体的には原材料や部品の「調達」、商品の「製造」、「在庫管理」「物流・流通」「販売」の5つのプロセスを指します。
サプライチェーンマネジメント(以下SCM)とは、これらの流れを全体で管理し、最適な形で運営していくための取組です。サプライチェーンにおいては、仕入れから製造、運送、倉庫管理、小売りまで、さまざまな企業・部門が連携することとなります。
通常であれば、各企業がバラバラの状態で運営されており、それぞれが自社の利潤を追求する「部分最適」で経営が行われます。そのため、ときには利害が一致せず、チェーン内の摩擦や衝突が生まれる可能性もあるでしょう。
それに対して、サプライチェーン全体で手を結び、「全体最適」の視点で利潤を求めるのがSCMです。全体最適で各企業の役割を果たすことにより、サプライチェーン全体の効率化が図られ、競争力の強化につながるのが主な効果です。
サプライチェーンのリスクマネジメントについて解説しています。
SCMが注目されている理由

SCMという考え方が生まれたのは1980年代のアメリカとされており、それほど新しい概念ではありません。ここでは、現代の日本のビジネス環境において、なぜSCMが注目されているのか、その理由を4つのポイントから見ていきましょう。
グローバル化と技術革新
現在では、企業のグローバル化と技術革新により、サプライチェーン全体の柔軟性が求められるようになっています。特に2000年代初頭に、ITを活用したビジネスが主流になると、企業を取り巻く環境は目まぐるしく変化していきました。
多様なビジネスモデルが生まれる一方で、既存の技術が廃れていくのも早く、現代の企業経営では環境への素早い対応が求められるようになっています。こうした先行き不透明な状況にあっては、SCMの観点で企業運営を行い、調達・生産管理・流通の柔軟性を高めることが重要となります。
ビッグデータの利活用
ITの進歩によるビジネスモデルの変化は、ビッグデータの重要性をさらに高める結果となっています。例えば、ECサイトの普及等により、膨大な顧客データをどのように活用するのかが、企業の競争力を左右するようになりました。
多種多様なデータを利用できるようになったことは、IT分野のみならず、製造分野においても大きな変革をもたらします。データの使い方によっては、需要や流行の予測を適切に行いつつ、速やかに製造・供給に活かし、より適切な生産・流通プロセスを実現することも可能です。
このように、ビジネスモデル全体の変化も、SCMの重要性が高まっている理由の一つと言えるでしょう。
サイバーセキュリティの脆弱性について解説しています。
コンプライアンス対応
近年では、企業の社会的責任として、コンプライアンスへの対応が特に重要な要素となっています。製造業においては、製品の製造から流通までの透明性を高め、説明責任を果たせるようにしておくことがコンプライアンス対応の土台と言えます。
SCMによって各プロセスの連携が強化されていれば、自然と全工程の透明性が高まり、問題が発生した時にもすぐに対応しやすくなるでしょう。また、株主や顧客といったステークホルダーに対して、企業のアカウンタビリティ(説明責任)を果たすことにもつながります。
災害リスクへの対策
現在、SCMの重要性として特に注目されているのが、災害リスクへの対策です。これまでに発生した震災やコロナ禍では、サプライチェーンが寸断されたことで、経済活動に大きな被害が出ました。
例えば、内閣府の資料では、東日本大震災の影響でその後5年間に倒産した1,898件のうち、9割以上にあたる1,718件は、「被災地外にもおよぶ間接損害によるもの」とされています。地震や津波による直接的な損害よりも、それ以外の理由による倒産が圧倒的に多いことからも、企業における災害リスクは多岐にわたることが明らかです。
特に製造業では、納入先の被災や生産計画の変更といったサプライチェーンへのダメージが、倒産の主な原因となっていたことも示されています。このように、非常事態に備えたリスクマネジメントの一貫として、SCMの注目度が高まっているという側面も強いです。
SCMを導入するメリット

SCMを導入することで、サプライチェーンの各プロセスにはさまざまなメリットが生まれます。ここでは、調達・生産・販売物流の3つのプロセスに分けて、SCMの導入によって得られる効果を解説します。
調達プロセス:コスト管理で競争優位性を確立しやすい
調達プロセスにおけるメリットは、原材料を安定的かつコスト面で有利に仕入れられるようになる点が挙げられます。例えば、仕入先と発注元の連携が密に行われていれば、輸送の効率化が実現されます。
ムダをできるだけ排除して、効率的に調達プロセスを実行することで、無理なくコストを下げられる可能性があるでしょう。また、両者に確かな信頼性があれば、納品時の検品作業も合理化しやすくなります。
さらに、質の高い材料や特殊な素材を用いる場合でも、SCMがきちんと行われていれば、安定的に仕入れを行うことが可能です。その結果、コストだけでなく品質面においても、企業の競争優位性を確立しやすくなるでしょう。
生産プロセス:ニーズへの対応力が向上する
生産プロセスにおけるメリットとしては、高品質の製品を低コストで生産できる環境が整えられる点にあります。発注から販売までのプロセスが明確化されるため、一つひとつの生産工程を最適化でき、少ないリソースでも高いパフォーマンスを発揮できるようになるでしょう。
さらに、販売によって得られた顧客データを生産に活かせば、ニーズを柔軟に反映させながら生産工程を調整することも可能です。サプライチェーン全体として、スピーディな環境対応力が身に付けば、より一層競争力を高めることができます。
また、そのほかのメリットとして、製品そのものの安全性や規制への適合性等を管理しやすくなる点も挙げられます。仕入れから販売までの流れに一貫性が生まれることで、責任の所在が明らかになるため、品質管理のクオリティ向上も期待できるのです。
販売・物流プロセス:商材や顧客に応じた販売チャネルを構築しやすい
販売・物流プロセスにおいては、商材や顧客のニーズに合わせ、柔軟に販売チャネルを組み合わせやすくなるのがメリットです。例えば、一般消費者向けに製品を販売するケースであれば、ECサイトを構築してSCMのシステムと連携させ、リアルタイムで配送できる体制を整えることもできます。
つまり、購入までのプロセスを一気通貫で管理すれば、顧客サービスの向上も図れるということです。また、SCMが行われていれば、製品の逆流も問題なく行えるため、返品プロセスの質も高めやすくなります。
スムーズな返品対応とデータ収集により、顧客満足度を高めつつ、生産への反映が行えるため、製品そのもののクオリティ向上にもつながるでしょう。
SCMのデメリット

SCMのデメリットは、システム構築の難しさにあります。調達から生産、配送、在庫管理といった幅広い業務を管理する必要があるため、仕組みの構築には大きな労力が発生してしまいます。
また、プロセスが複雑になりすぎると、非効率になってしまう恐れもあるため、適切な管理システムの構築が重要となります。それには、全体を統括できるだけの経験とスキルを持った人材も必要です。
特に中小企業にとっては、日常業務外で一時的に多大なリソースを奪われてしまうため、思いがあっても実現が難しいというケースはめずらしくありません。導入を検討する際には、SCMの難しさを理解した上で、専門性の高いスキルを持った人材を集められるかどうかなども踏まえながら、慎重に判断することが大切です。
SCMを導入する5つのステップ

SCMの範囲を決定する
冒頭でもご紹介したように、SCMでは部分最適から全体最適へ発想を転換する必要があります。自社のみならず、サプライチェーン全体の運営がスムーズに進むように、広い視野を持たなければなりません。
その上で、SCMにおいてはまず、「どの範囲までを全体とするのか」がキーポイントとなります。例えば、「業界全体」を一つのサプライチェーンと捉える場合や、「地域の経済活動」をサプライチェーンと捉える場合等、自社の状況や環境によって考え方はさまざまです。
そのため、まずはSCMを導入する目的を明確にした上で、対象範囲を明らかにすることが大切となります。
参加メンバー(企業)を選定する
続いて、実際にSCMを構成するメンバー(企業)を選定していきます。例えば、自社が生産工程を担う企業なのであれば、ほかに調達や物流、販売を担う企業を選ぶのが基本です。
その上で、SCMの企業を選ぶ際には、「担当する範囲について、他の企業には真似できない高付加価値を適切なタイミングで供給できる」「全体としての付加価値創出に貢献できる」という2点が重要な条件と言えます。これらの観点からパートナー企業をピックアップし、サプライチェーンへの参加を要請します。
リーダー企業を決める
サプライチェーンは複数の企業の集合体であるため、イニシアチブをとる企業が必要となります。参加企業が確定したら、自社も含めたサプライチェーン全体を見渡し、適切なリーダー企業を選定しましょう。
リーダー企業を見極める際には、「適切なビジネスプロセスを描ける」「SCMに関する明確なビジョンを持つ」といった観点を重視します。また、リーダー企業には人的リソースの消費等の負担が生じるため、公平性の観点から、その他の企業がサポートできる体制を整えることも大切です。
SCMインフラを構築する
リーダー企業が決まったら、SCMを構築・運営するのに必要なインフラを整備していきます。まずは情報共有のためのネットワークを構築する必要があるため、各企業と意見をすり合わせながら、適切なシステムを選定しましょう。
SCMのシステムには、多様な業種・業態に適用できるマルチタイプのものから、特定の業界に特化したタイプのものまで多くの種類があります。さまざまなシステムの特徴を比較しながら、サプライチェーンの目的に合うものを選ぶことが大切です。
サプライチェーンのセキュリティ強化の取組について解説しています。
運営と情報共有に関するルールを確立する
SCMを機能させるには、細やかな情報共有を行いながら、プロセス間の確かな信頼関係を構築していく必要があります。サプライチェーンはとても幅広い業務をカバーするため、仕入れに関する状況の変化や物価の影響、売れ行きや店頭在庫、生産リードタイムの変更等、共有すべきデータも多岐にわたります。
すべての企業が必要なタイミングで必要なデータにアクセスできるよう、リアルタイムでの情報共有を心がけ、情報の透明性を確保できるようなルールを策定しましょう。また、リーダー企業は、サプライチェーンのリスクをどのように各企業へ分散させていくかを考慮することも重要です。
特定の企業に負担やリスクの偏りが生まれないよう、バランスを保ちながら運営できる仕組みを構築しましょう。
SCMの導入事例

SCMの導入を検討する際には、既に成功している企業の事例を参考にしてみるのも有効です。ここでは、経済産業省の「サプライチェーンイノベーション大賞2024」から、SCMの成功事例を2つピックアップしてご紹介します。
パートナーとの連携により物流の2024年問題に対応
食品卸売・運送業を営むとある企業では、「物流の2024年問題」に対応するために、サプライチェーンの連携強化に取り組みました。物流の2024年問題とは、トラックドライバーの時間外労働に上限規制が適用されたことによる、人手不足や輸送力低下等の諸問題です。
同社ではまず、全体の取組として動態管理端末を導入し、配送の可視化を行います。すべてのプロセスに透明性を持たせることで、問題が生じた時でも課題の所在が明らかになりました。
その結果、パートナー企業と課題が共有しやすくなり、協業しながら改善できる仕組みができたとされています。さらに、サプライチェーンでの「一貫パレチゼーション」により、納品業務を関東エリアのみで年間9,180時間も削減させることに成功させました。
一貫パレチゼーションとは、貨物を生産者から消費者までパレットに載せたまま輸送する方式のことであり、輸送や荷役、保管業務を効率化させる仕組みです。サプライチェーン全体での意思疎通と共通認識が求められる方式であるため、SCMの代表的な効果と言えるでしょう。
さらに、同社は取引先とのパートナーシップを構築し、賃金引上げ等を盛り込んだマルチステークホルダー方針を策定します。「不合理な原価低減要請を行わない」「災害時に一方的な負担を押し付けない」等の基本方針を固めたことで、サプライチェーンの結束が固まり、全体として協業しやすい仕組みが整えられました。
こうした取組が評価され、同社はサプライチェーンイノベーション大賞2024で優秀賞を受賞しています。
【関連記事】
2024年問題の対応策について解説しています。
物流デジタル化によりサプライチェーン全体での物流の最適化・効率化に成功
サプライチェーンイノベーション大賞2024で大賞を受賞したのは、複数の日用品メーカーが手を組んで行っている、大掛かりな物流デジタル化への取組です。この事例の要旨は、「業界標準の物流情報基盤」を整備し、それまでアナログ(伝票等)でやりとりされていた物流情報をデジタル化するというものです。
具体的には、「ロジスティクスEDI」を構築し、事前出荷情報(ASN)に基づく検品レス・伝票レスの実現を進めます。それにより、作業時間や資源のムダを省き、業界全体の生産性を向上させるという狙いです。
システムの導入により、伝票発行に関わるさまざまな業務が効率化され、1日あたり約3割の削減につながるとされています。さらに、プリンターや伝票保管スペースの削減等、ペーパーレス化によるメリットも生まれます。
そのほかにも、「SKU(受発注や在庫管理における最小管理単位)あたり約5割の作業時間削減」「納品車両の滞留短縮」といった効果も見込め、業界全体の物流課題の解消が期待されています。
SCMに関する補助金制度

今回ご紹介したように、SCMは大掛かりな取組であるため、仕組みを確立するのには大きな労力とコストがかかります。中小企業が独力で取り組むのは難しい側面もあるため、補助金等の利用を検討してみるのも一つの方法です。
事業再構築補助金
「事業再構築補助金」とは、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために活用できる補助金制度です。制度の一つである「サプライチェーン強靭化枠」という枠組みでは、製造業の中小企業を対象に、国内サプライチェーンの強靭化や地域産業の活性化の支援が行われています。
ただし、サプライチェーン強靭化枠については公募が行われない回もあるため、事前に仕組みや要件を詳しく確認することが大切です。
GXサプライチェーン構築支援事業
GX(グリーントランスフォーメーション)分野における国内製造サプライチェーンを支援するための事業です。事業期間は2029年3月31日までを予定しており、比較的に長いスパンでの利用計画を立てやすいのが特徴です。
補助対象要件は「ペロブスカイト太陽電池または浮体式等風力発電設備」の製品の生産に関わる設備投資を行う事業であることであり、設備機械装置・建物等取得費、システム購入費等が補助対象となります。
まとめ
サプライチェーンマネジメント(SCM)は、調達から生産、販売までのプロセスの連携を強化し、全体としての生産性を高めていく大掛かりな取組です。地域や業界内の企業と強力なサプライチェーンが構築されれば、自社を含めたサプライチェーン全体の競争力を高めることができるでしょう。
そのためにはまず、SCMの重要性やメリット、導入方法について適切に理解を進める必要があります。その上で、長期的な視点に立って協力企業を選定し、じっくりと信頼関係を育てていくことが重要です。