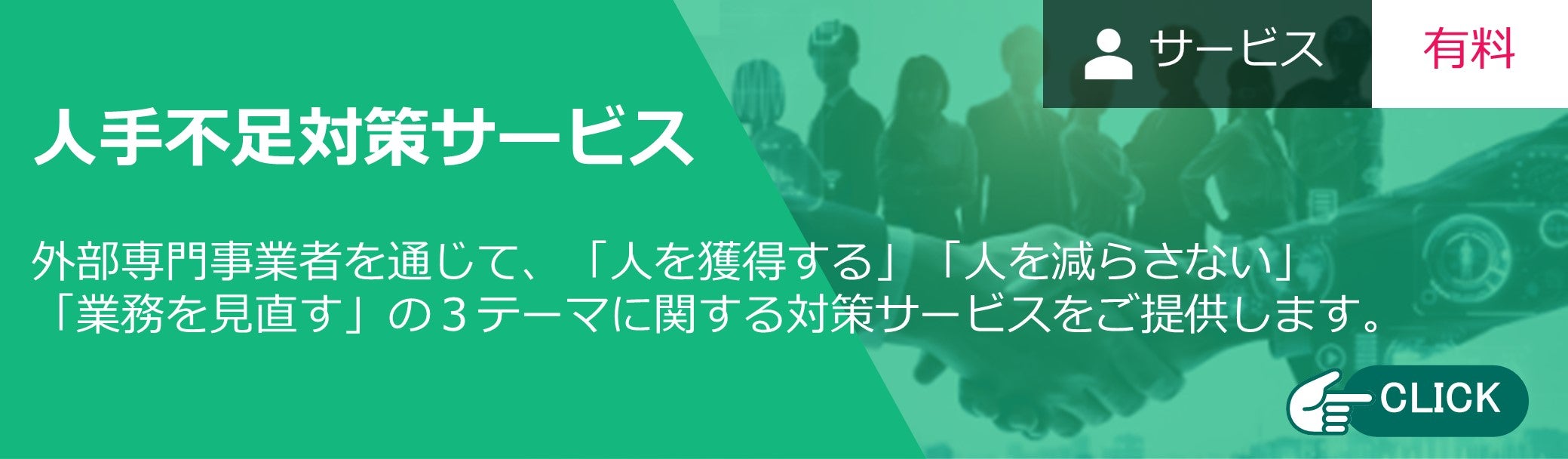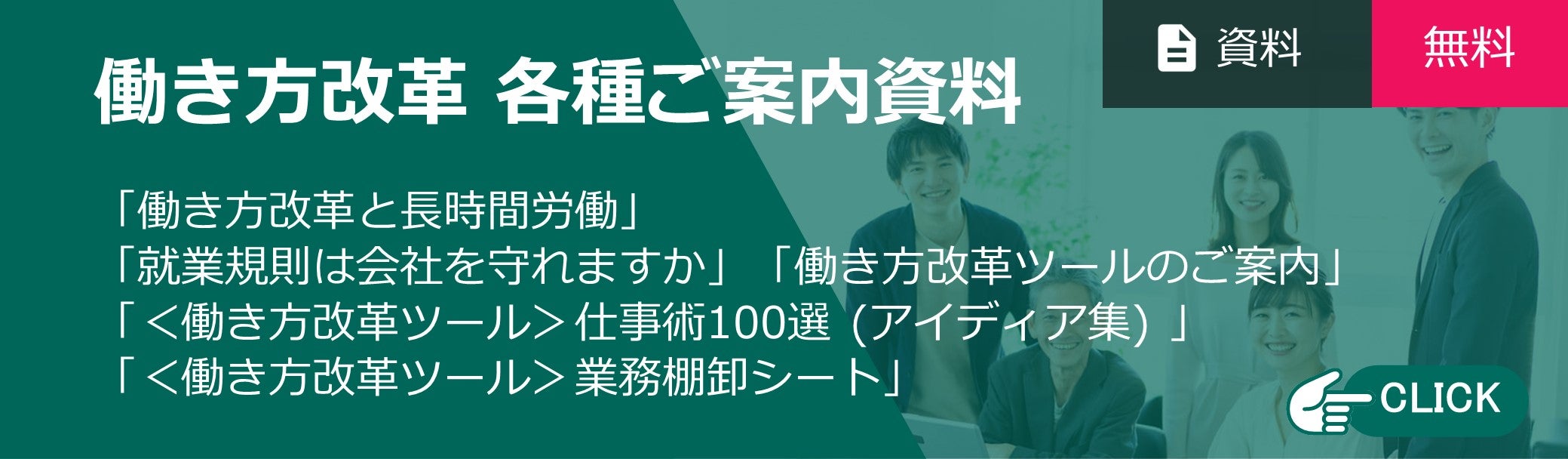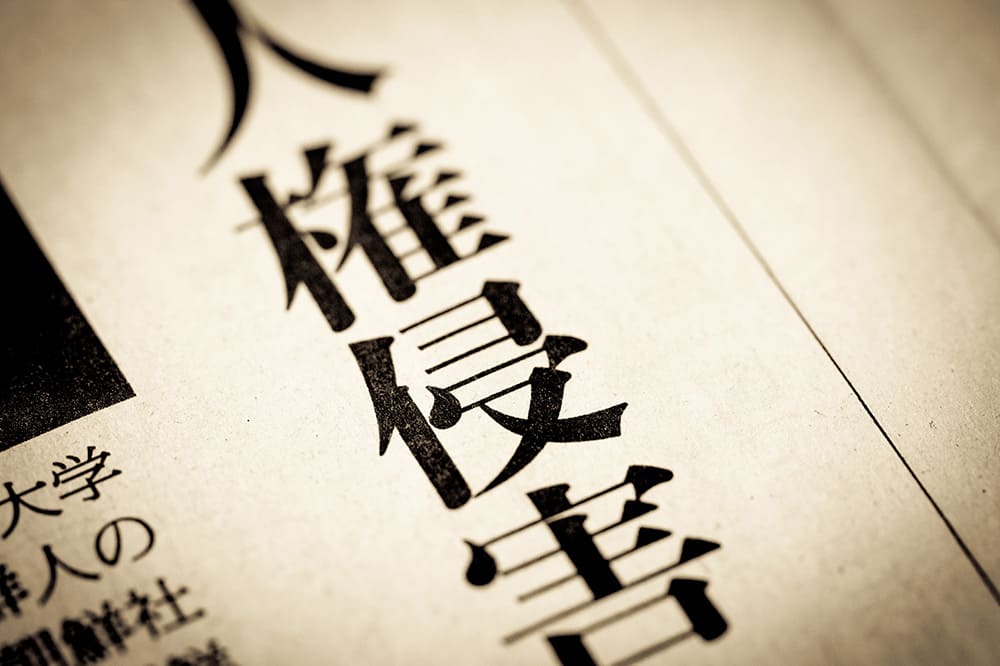LGBTQとは?意味や種類、課題と企業の取組事例を解説
公開日:2024年12月2日
人権

「LGBTQ」への関心度は年々高まりを見せています。特に2023年6月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(通称:LGBT理解増進法)が公布・施行されたことは、社会的な注目度を強める契機となりました。
ビジネスシーンにおいても、主要な経営資源である「ヒト」に関連していることから、重要性の高いテーマとして取り扱われるようになっています。この記事ではLGBTQの基本的な捉え方を確認した上で、企業における取組の重要性と、具体的な実施方法についてご紹介します。
LGBTQの概要

「LGBTQ」について正しく理解するためには、基本的な意味や性別に関する捉え方、関連する用語等を押さえておく必要があります。LGBTQに関する調査はいくつか実施されており、結果に違いはありますが全人口に占めるLGBTQの割合は7~9%程度と考えられています。
つまり、30人規模の職場であれば、2~3人程度の割合でセクシャルマイノリティがいるといえるでしょう。従業員数の多い大企業だけでなく、中堅・中小企業においても関係してくるものであるため、基本となる部分への理解が欠かせないと言えます。
LGBTQの意味
LGBTQとは性的マイノリティの方を表わす総称の一種であり、以下の6つの頭文字をとった用語です。
・レズビアン(L):性自認が女性で女性に恋愛感情を抱く人(=女性同性愛者)
・ゲイ(G):性自認が男性で男性に恋愛感情を抱く人(=男性同性愛者)
・バイセクシュアル(B):男性にも女性にも恋愛感情を抱く人(両性愛者)
・トランスジェンダー(T):出生時に割り当てられた性別と異なる性自認を持つ人
・クエスチョニング(Q):自身のセクシュアリティを決められない、あるいは意図的に定めない人
・クィア(Q):規範的でないとされる性のあり方を幅広くとらえた表現
なお、上記のLGBTQにカテゴライズされない性のあり方を包括的に含めて、「LGBTQ+」と表現されることもあります。そこには、「性のあり方は特定のカテゴリに区分されるものではなく、グラデーションになっている」という前提があると考えられます。
いずれにしても、「性別は男性と女性のみである」という従来の規範では捉えきれない、多様な性のあり方を前提としているのがLGBTQの特徴です。
性のあり方を構成する要素
性のあり方について考える上では、「性的指向(Sexual Orientation)」と「性自認(Gender Identity)」の二つに分けて捉えるのが一般的です。性的指向とは、本人の恋愛感情や性的な関心が、どの性別へ向いているのかを示す言葉です。
また、性自認は本人が自身の性別をどのように認識しているのかを示します。
LGBTQに関連する言葉
前述した「性的指向(Sexual Orientation)」と「性自認(Gender Identity)」は、それぞれの頭文字をとって「SOGI(ソジ)」と表現されることもあります。SOGIはLGBTQに限らず、すべての人が持っている普遍的なものです。
そのため、SOGIと表現されるときには、性のあり方を「特定の人のみに配慮が必要な問題」と捉えるのではなく、「すべての人の人権に根差した課題」として捉えるべきであるという考え方が根底にあります。例えば、「労働施策総合推進法」では、「SOGIハラスメント」や「アウティング」の禁止等が企業に対して義務づけられています。
これらは、LGBTQの人のみを対象にしているというよりも、全員の人権を守るルールと言うことができるでしょう。また、LGBTQに関連する用語として、近年では「Ally(アライ)」という言葉も使われるようになっています。
AllyはLGBTQ等の性的少数者を支援したいと考えている人を指し、LGBTQの当事者以外でも積極的に支援するケースが増えています。
LGBTQ当事者が抱えやすい課題

LGBTQに関する法律や制度はまだ整備され始めたばかりであり、社会全体として適切な理解が進んでいるとは言えません。ビジネスの場においても、性的マイノリティであるがゆえに悩みやトラブルを抱えてしまうケースは少なくないでしょう。
ここでは、仕事に関してLGBTQの当事者が抱えやすい課題を三つに分けて見ていきましょう。
職場内で相談先がない
職場における代表的な悩みとして挙げられるのが、「適切な相談先がない」というものです。LGBTQに該当する人は全体から見れば少数派であり、会社全体の規範として、必ずしも寄り添った制度が確立されているとは限りません。
それだけに、仕事においては不都合が生じる場面も多くなりがちですが、トラブルや困り事を相談する先を見つけるのも難しいという側面があります。なぜなら、性のあり方は目に見えにくく、本人からのカミングアウトがなければ問題の直接的な解決にはつながりにくいためです。
一方で、職場内に相談先がない、あるいは存在していても担当者が理解をしてくれないことを恐れて相談しにくいといった状況も生まれやすいため、八方ふさがりになってしまうケースが多いと言えます。特に、本人の同意なくSOGIに関する事柄を他言する「アウティング」を恐れ、相談すること自体に抵抗を感じてしまう場合も少なくありません。
日常的なストレスを感じる
LGBTQの当事者にとって、カミングアウトには大きなリスクがつきまといます。職場の理解が十分に進んでいない場合、自身のSOGIを打ち明けることで、異動や退職勧奨等の不利益を被る恐れがあると感じられてしまうのです。
また、従業員本人が自任する性とは異なる制服の着用を求められたり、トイレや更衣室の利用で問題が発生したりする等、特定の性を押し付けられてストレスを感じるケースもあります。さらに、結婚休暇の適用において、通常は結婚が異性愛者の男女間のものであることが前提として、制度設計されている場合が多いと言えます。
そのため、国内において同性婚が法的に認められていない現状においては、同性のカップルには結婚休暇が付与されないといった問題も生じているでしょう。たとえ、目に見える不利益はなかったとしても、人間関係に影響を及ぼしたり、キャリア形成で不利になったりする可能性がないとは言えません。
職場で家庭や恋愛等の話題が出るときには、本心を隠すように振る舞わなければならず、日常的なストレスを感じやすいのも大きな課題です。
ハラスメントの被害に遭う恐れがある
LGBTQの当事者は、性的マイノリティであることに起因したハラスメントの被害に遭いやすい側面もあります。「本人の意思に反して配置転換を迫られてしまう」等の不利益な処遇のほかに、「ひどいハラスメントによって適応障害を発症してしまう」といったケースもあり、メンタルヘルスへの影響も見過ごせない課題となっています。
ハラスメントの定義や主な種類、発生する原因と必要な対策について解説しています。
LGBTQに関する施策を企業が取り組むメリット

LGBTQに関する課題を解消するためには、企業側も適切な理解のもとに環境整備を進める必要があります。ここでは、LGBTQに関する施策に取り組む重要性について、三つのメリットをご紹介します。
企業イメージがアップする
さまざまなバックグラウンドを持つ人材を雇用し、活躍の場を整えることで、ダイバーシティの推進に積極的に取り組んでいるという前向きな姿勢を示せます。人権尊重の意識が高い企業として認知されれば、社会に対する企業やブランドのイメージを向上させることにつながります。
その結果、企業全体の信頼性も高まり、取引先の拡大や投資の呼び込み等で有利に働くこともあるでしょう。また、多様な人材を企業として受け入れることは、SDGsの取組にも結び付いていきます。
SDGsには前提として、「No one left behind(誰一人取り残さない)」という共通理念があります。SDGsの具体的な行動目標には文化的・宗教的な背景への配慮からLGBTQに関する内容は記載されていませんが、世界中のセクシャルマイノリティの人たちを誰一人取り残さないという考えに含まれているというのが前提です。
SDGsの目標を達成するには、企業としてLGBTQへの支援やサポート体制の構築等も、必要なものとして考えられています。そのため、積極的な取組を行う企業に対して、社会的な評価が高まっていくと言えるでしょう。
帝国データバンクが行った調査結果について解説しています。
労働生産性が高まる
個人のSOGIにとらわれず、多様な人材を受け入れれば、新たなスキルやノウハウを確保できる機会が広がります。さらに、LGBTQフレンドリーな環境が整えられていれば、どのような背景を持つ人でも安心して働けるため、職場の風通しがよくなります。
社内コミュニケーションが活性化することで、日常的な業務の効率化が図られ、労働生産性の向上につながる可能性もあるでしょう。また、さまざまな価値観を持つ人材が活躍することで、既存の商品・サービスに対して新たな視点が加わるのも大きな利点です。
多様な意見を柔軟に交し合うことで、思いがけないビジネスチャンスの創出につながるケースもあります。
多様な人材の確保につながる
LGBTQの人が働きやすい職場づくりを行うことは、人手不足を解消するきっかけになる場合もあります。積極的な取組によって企業イメージが向上すれば、採用活動においても優位性を確立しやすくなり、多様な人材からの応募が期待できます。
また、さまざまな立場にある人が安心して働けることで、既存の従業員の満足度も高まり、結果として人材の定着率向上にもつながるでしょう。
各認定制度の概要や認定のメリットについて解説しています。
LGBTQにおける企業が取り組むべき施策と事例

それでは、LGBTQの寄り添った職場づくりを行う上で、企業は実際にどのような施策を打ち出すべきなのでしょうか。ここでは、厚生労働省が公表している「多様な人材が活躍できる職場環境に関する企業の事例集~性的マイノリティに関する取組事例~」をもとに、企業が取り組むべき施策をご紹介します。
経団連による企業行動憲章アンケートの結果について解説しています。
方針の策定と体制の整備
LGBTQに関する施策を進めるには、当事者や周囲のメンバーだけでなく、全社の課題として組織的に取り組む必要があります。そのため、まずは企業の方針として「多様な人材が活躍できる職場環境づくり」を明確に打ち出し、取組に一貫性を持たせることが大切です。
また、厚生労働省の資料では、「就業規則や企業行動憲章にSOGIに関する差別禁止を明記する」「人事担当部局からSOGIに関する担当者を選出して取組を推進する」「トップが社内外に向けてダイバーシティ宣言を行い、企業としてのスタンスを明示する」といった事例が紹介されています。
理解の増進に関する取組
方針の策定と体制の構築を行ったら、社内のメンバーに向けて丁寧に理解を促すことが大切です。従業員や管理職、経営層がLGBTQについて基本的な知識を持つことが重要となるため、企業には研修等を通じた継続的な啓発活動が求められます。
理解増進に向けた取組事例としては、「全社を対象に研修やeラーニングを実施した」「外部講師を招いてセミナーを行い、企業としての本気度を自社の従業員に感じ取ってもらった」「カミングアウトがあった場合の対応等を想定して管理職向けの研修を行った」といったものが紹介されています。
相談窓口の設置
「相談先がない」という課題を解消するために、LGBTQ当事者が必要に応じて相談できる体制を整えておくのも重要な施策です。具体的な取組事例としては、「社内に専用の窓口を設置する」「従来の窓口で相談できることを明示する」「当事者団体に外部の相談窓口を委託する」といったものが挙げられています。
また、相談体制が形骸化するのを防ぐために、「相談相手の性別に希望がある場合に備えて多様な担当者を用意する」等の利用しやすいシステムを整えることも大切です。
採用や労務管理における施策
採用については、特定の人を排除しないよう、公正な採用基準や採用方法に基づいた採用活動を行う必要があります。そして、配置や昇進・昇格等においても、不当な扱いが行われないようにルールを制定することが大切です。
採用活動における取組事例としては、「採用ポリシーに差別の禁止を明記している」「エントリーシートに性別欄を設けない」「配偶者の有無を尋ねる必要がある場合は配偶者とパートナーの文言を併記する」「面接時のマニュアルを作成する」といったものが紹介されています。また、労務管理については「人事異動にあたって差別を行わないことを明記する」「ハラスメント等による不利益・不快感を与える行動が懲戒理由になり得ることを明記する」等の取組が挙げられています。
また、社内で施策を実施するためのリソースが不足している場合は、外部との連携も重要です。「MSコンパス×無料de顧問」なら、月額顧問料が無料で社労士に労務相談を行えますので、ぜひ活用してみてください。
福利厚生の対応
福利厚生についても、本人のSOGIを理由に不利益や差別が生じないように注意する必要があります。具体的な事例としては、「同性のパートナーがいる従業員に対して、結婚祝い金や家賃補助等の福利厚生制度を適用させる」「各種制度を利用する際にカミングアウトにつながらないように工夫する」等、さまざまな企業で同性パートナーを配偶者に含める動きが見られています。
【関連記事】
福利厚生を充実させるメリットと注意点等について解説しています。
働きやすい職場環境の整備
トランスジェンダーの従業員に対しては、個別の事情に合わせた対応が必要となります。例えば、「入社後にホルモン療法を進めるなかで見た目が変化していくことに備えた対応を行う」「性別に関係なく制服をパンツスタイルに統一する」「トイレや更衣室に関して適切なルールを策定する」といったものが挙げられます。
ただし、取組を進める上ではほかの従業員の理解も得ておかなければならないため、当事者だけでなく周囲にも丁寧なサポートを行うことが重要です。
まとめ
企業がLGBTQに寄り添うことで、多様な人材が活躍できる場となり、生産性の向上やイノベーションの創出につながりやすくなるといったメリットが生まれます。また、対外的なイメージが向上するため、取引先や顧客層の拡大、投資の確保、人材採用の母集団獲得等にも良い影響をもたらすでしょう。
取組を進める上では、経営層や管理職層がLGBTQに対して正しく理解するのはもちろん、社内全体にも推進していく意識を浸透させていく必要があります。LGBTQに関する方針の策定や体制の確立、継続的な研修の実施といった地道な取組を着実に実践し、社内の意識変革を図りましょう。