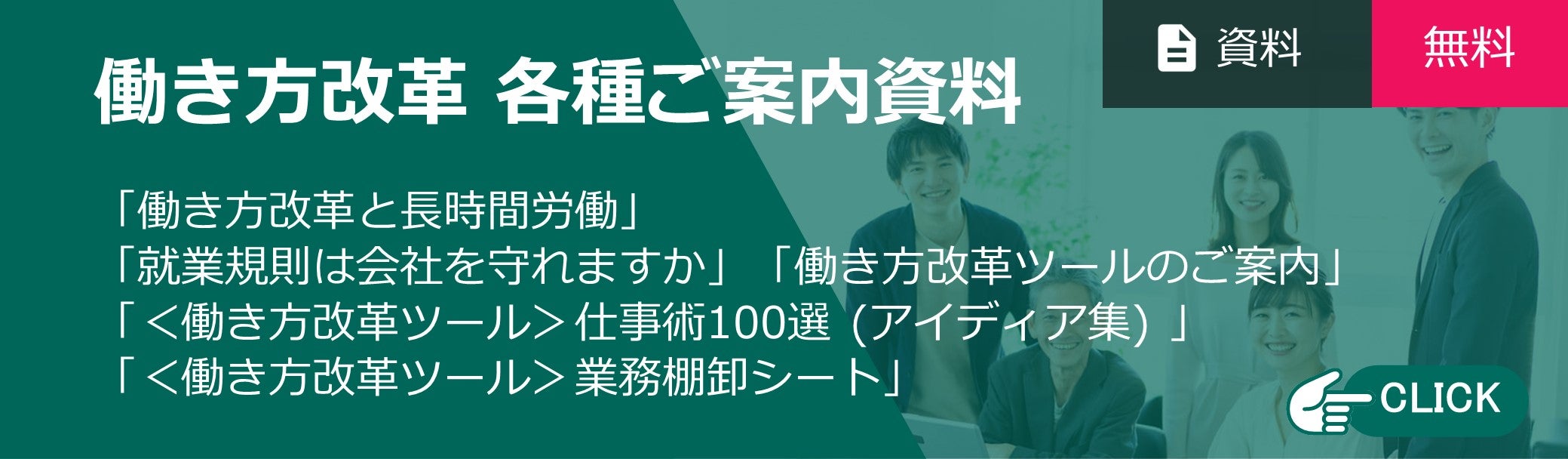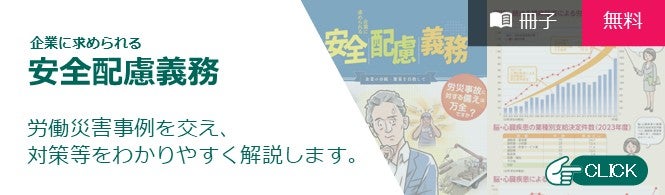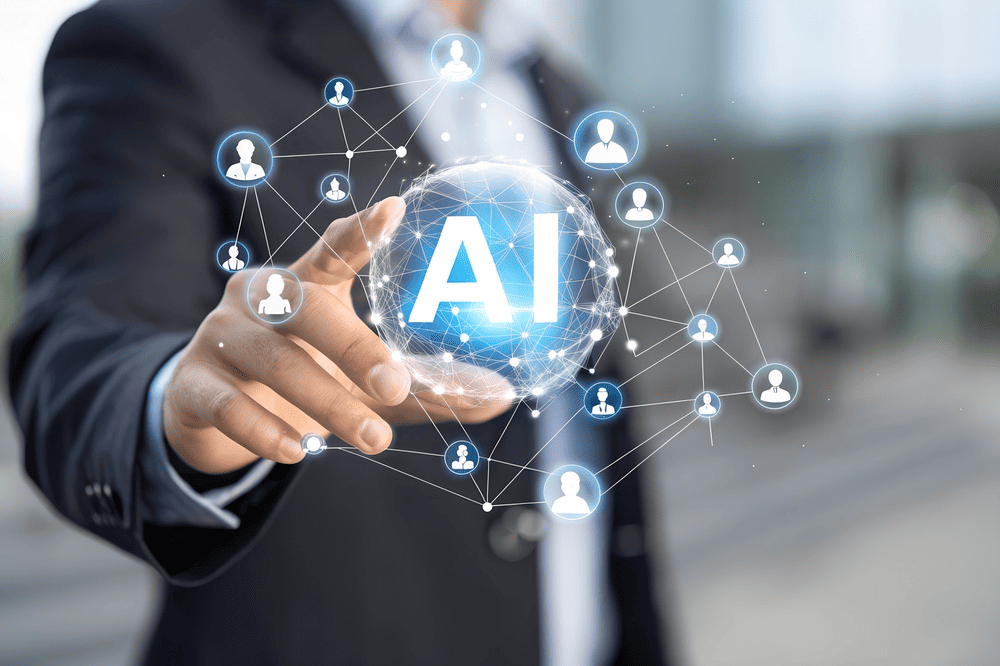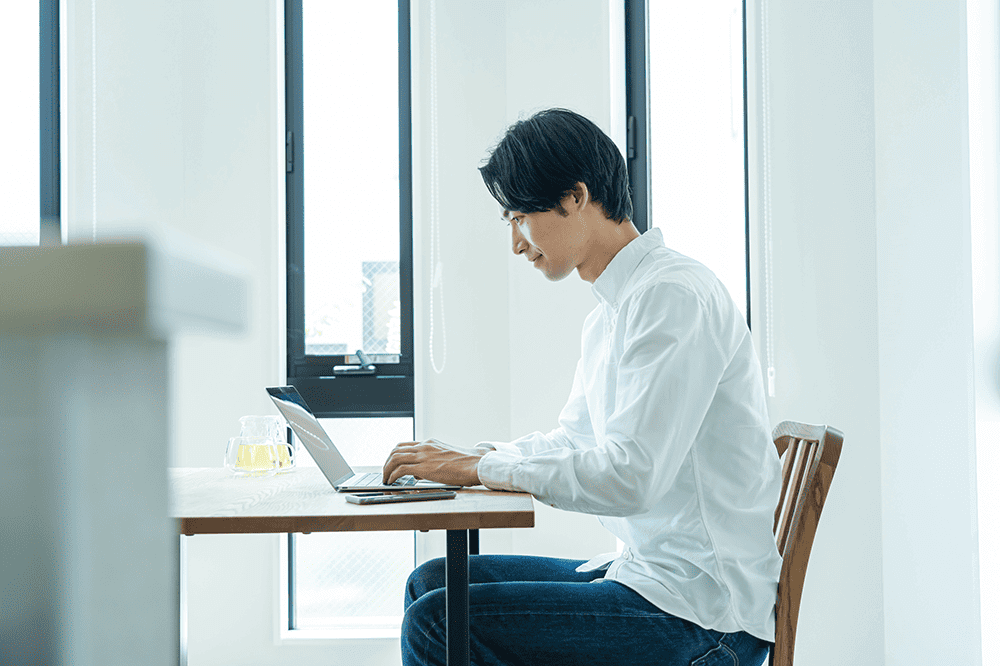不当解雇とは?適正な解雇との違いや条件を詳しく解説
公開日:2025年4月21日
人事労務・働き方改革

従業員の雇用は労働契約に基づいて行われているため、解雇をするにあたっても適切な手続を踏まえる必要があります。法律に適合しない部分があれば、不当解雇とみなされ、企業側に大きな責任が発生するリスクもあるので注意が必要です。
この記事では、解雇に関する基本的なルールを確認した上で、不当解雇とみなされてしまった時のリスクや、不当解雇を避けるための注意点をご紹介します。
不当解雇とは
不当解雇とは、法律や就業規則等の決まりを守らずに、一方的な都合で労働者を解雇する行為を指します。日本の法律では、従業員を解雇する際の条件が厳格に決められており、事業者の一方的な都合で辞めさせることはできません。
例えば、労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されています。不当解雇であるかどうかを最終的に決定するのは裁判所ですが、基本的には解雇の客観性や合理性、社会通念等が判断基準となります。
例えば、国籍や性別を理由にした解雇、労働組合に加入したことを理由とする解雇等は、不当解雇に該当する可能性が高いと言えるでしょう。
労災相談の種類と相談先や相談ポイント等について解説しています。
解雇の主な種類

一口に解雇と言っても、事情や性質によって扱われ方は大きく異なります。解雇には大きく分けて「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」の3種類があり、それぞれ関係する法規制も変わってくるので注意が必要です。
普通解雇
普通解雇とは、整理解雇、懲戒解雇以外の解雇を指し、主に労働契約の継続が困難な場合に認められます。普通解雇には「正当な理由」が必要であり、例えば単に能力が不足しているという理由のみでは、社会通念上正当とは認められません。
具体的な例としては、「勤務成績が著しく悪く、指導を行っても改善の見込みがない」「健康上の理由で、長期にわたり職場復帰が見込めない」といった十分に客観性・合理性のある理由が必要です。また、「著しく協調性に欠けるため業務に支障をきたし、さらに改善の見込みがない時」も正当な解雇理由の一つとして挙げられます。
日本の裁判所では、正当な解雇理由があったと判断されるハードルは高く、解雇を行う事業者側がきちんと正当性を証明する必要があります。
整理解雇
整理解雇とは、企業の経営悪化等により、経営の合理化を図る上で人員整理を行うことを目的とした解雇のことです。整理解雇は普通解雇や懲戒解雇と異なり、労働者には明確な非がないのにもかかわらず、企業の都合で解雇が行われるのが特徴です。
そのため、解雇が正当と認められるためには、少なくとも以下の四つの条件はすべて満たさなければならないとされています。
整理解雇の四つの要件
・整理解雇することに客観的な必要があること
・解雇を回避するために最大限の努力を行ったこと
・解雇の対象となる人選の基準、運用が合理的に行われていること
・労使間で十分に協議を行ったこと
つまり、「人員削減の必要性が本当にあるのかどうか」「解雇の方法や人選に合理性があるか」「解雇を避けるために適切な対処が行われていたか」が重要なポイントになるということです。例えば、企業が人員整理を回避する方法には、「新規採用の停止」や「役員報酬の削減」「一時帰休」「配置転換や出向」といったさまざまな選択肢があります。
また、場合によっては希望退職者を募り、退職者にはある程度の優遇措置を設けるのも有効な方法です。これらのアプローチを行っても経営状況が改善できない場合に、はじめて解雇が現実的な手段になり得るというのが、整理解雇の基本的な考え方と言えるでしょう。
【関連記事】
役員退職金の基本的な捉え方や計算方法、具体例、注意点等について解説しています。
懲戒解雇
懲戒解雇とは、従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行った時に、懲戒処分として行うための解雇のことです。懲戒解雇は懲戒処分のなかでももっとも重い制裁であり、退職金の不支給等のペナルティが加わるケースも少なくありません。
そのため、対象となる行為も、横領や贈賄といった極めて重大なものに限られます。また、懲戒解雇については、前述した労働契約法第16条のほかに、労働契約法第15条と労働基準法第89条も関係し、厳格なルールが規定されています。
特に労働基準法第89条では、「10人以上の労働者を常時雇用する使用者は、制裁に関する定めを決める・変更する場合は就業規則を作成し、行政官庁に届けなければならない」とされているので注意が必要です。
法律で禁じられている解雇
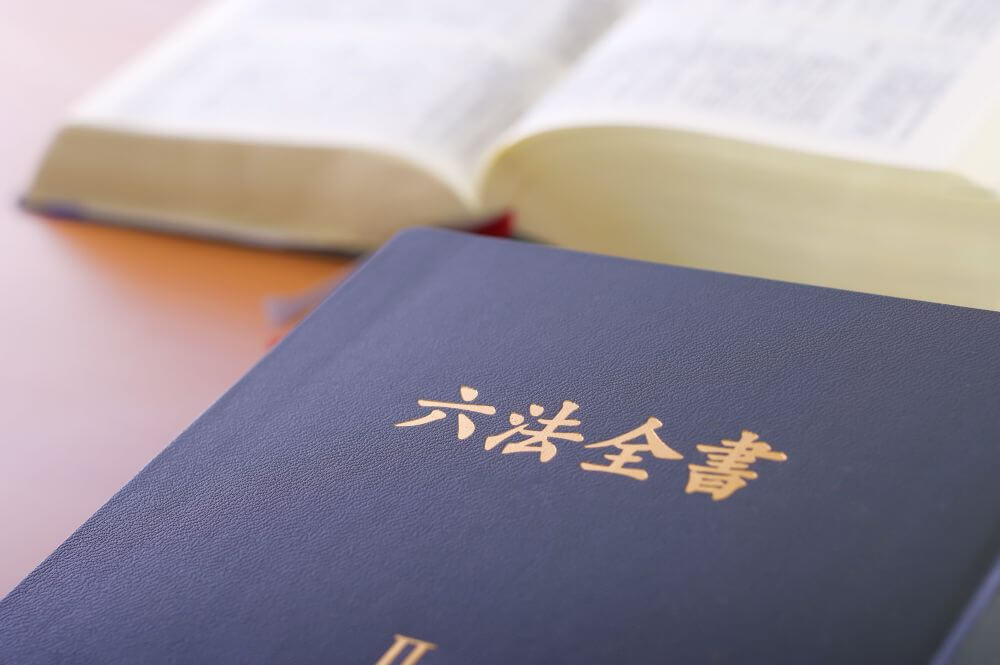
解雇に関する決まりは、さまざまな法律にまたがって規定されているため、単独の法律のみではなく横断的に理解しておく必要があります。ここでは、法律で禁じられている解雇について、具体的なルールを確認しておきましょう。
■労働基準法
労働基準法においては、以下のケースにおける解雇が禁止されています。
・業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇(第19条1項)
・産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇(第19条1項)
・労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇(第104条2項)
業務災害による療養中やその直後、産前産後の休業期間とその直後は、万が一解雇が行われると就職活動に大きな影響が出てしまうため、法律で禁止されています。ただし、労働災害のなかでも通勤災害は私傷病として扱われ、解雇制限の対象とはなりません。
また、従業員が企業の法令違反を労働基準監督署に通報したこと等を理由とする解雇も法律で禁止されています。
労災の概要や判断基準、発生時の対応のほか、どのようなケースが労災に認定されるのか、具体的な事例をもとに解説しています。
■労働組合法
労働組合法では、以下のケースにおける解雇の禁止が規定されています。
・労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇(第7条)
労働組合への結成・加入は労働者の権利であり、企業の都合で一方的に制限することはできません。労働組合はそもそも労働者を守るための仕組みであることから、加入や結成、組合員としての正当な権利の行使を理由に解雇することは禁じられています。
■男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法では、次のケースにおける解雇が禁じられています。
・労働者の性別を理由とする解雇(第6条)
・女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇(第9条)
雇用における男女の均等な機会を確保するためには、性別を理由とした不利益な取扱いが行われないようにルールを設ける必要があります。そのため、性別を理由とする解雇や、女性特有の問題である妊娠や出産を理由とした解雇は、法律で明確に禁じられています。
■育児・介護休業法
育児・介護休業法では、以下のケースにおける解雇が禁じられています。
・労働者が育児・介護休業等を申し出たこと、又は育児・介護休業等をしたことを理由とする解雇(第10条)
つまり、従業員が育児や介護に関する休業を取得したことを理由に解雇をする「育休切り」は明確に禁止されているということです。また、第10条における対象制度は、育児休業や介護休業だけでなく、子の看護休暇や介護休暇等にも広く適用されるため注意が必要です。
従業員の解雇における基本的なルール

労働基準法では、従業員の解雇を行う時の基本的なルールが定められています。不当解雇とみなされないためには、法律の規定と内容を踏まえた上で、正しい手続を行う必要があります。
ここでは、解雇におけるルールを三つに分けて見ていきましょう。
解雇事由を明示する必要がある
常時雇用する従業員数が10人を超える企業では、就業規則と労働契約書(労働条件通知書)に解雇の事由を明示しておく必要があります。正当性のある解雇と判断されるためには、どんな時に解雇される可能性があるのかをあらかじめ示しておき、その要件に合致しているかどうかを十分に見極めなければなりません。
就業規則等に定められていない事由で解雇が行われれば、不当解雇とみなされて無効になる恐れがあります。なお、この要件は法律改正により平成16(2004)年1月から新たに設けられたものである点に注意が必要です。
平成16年以前に定められた就業規則等には、具体的な解雇事由が記載されていない場合もあるため、見直しをしておくことが重要です。
【関連記事】
労働基準法により義務付けられている労働条件の書面明示事項の追加について解説しています。
【関連記事】
労働基準法により義務付けられている労働条件の書面明示事項の追加について解説しています。
解雇権の濫用の場合は無効となる
解雇権の濫用とは、冒頭でも触れたように「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」の解雇を指します。解雇の事由が就業規則や労働契約書に明示されており、その内容に合致した場合であっても、解雇そのものに合理性がなければ正当性は認められません。
例えば、「体調が悪く連絡できないまま無断欠勤をした」といったやむを得ない理由があった場合は、仮に無断欠勤を解雇事由に設定していたとしても、それだけを理由に解雇をすることはできません。また、単に「商品を壊した」「服装がだらしない」といった理由による解雇も、社会通念上相当とは認められない場合が多いです。
服装については個人的な自由に属する事柄であるため、業務に支障が出ない限りは、基本的に解雇事由としては認められません。仮に業務に支障をきたしたとしても、指導や配置転換等の対策を講じないまま直ちに解雇すれば、不当解雇とみなされる可能性があります。
解雇をする時は予告しなければならない
原則として、従業員を解雇する際には、解雇しようとする従業員本人に対して「30日前まで」に予告をしなければなりません。予告そのものは口頭でも有効となりますが、口約束はトラブルの原因となる恐れもあるため、書面で残しておくのが一般的です。
解雇する日と具体的な理由を明記した「解雇通知書」を作成し、コピーを本人に渡すのが望ましいと言えるでしょう。また、従業員から作成を求められた場合は、解雇理由を記載した書面を作成して本人に渡さなければなりません。
なお、やむを得ない事情があるケースでは、予告を行わずに解雇することも可能です。ただし、予告なしで解雇を実行する場合は、「解雇予告手当」として最低30日分の平均賃金を支払う必要があるので注意しましょう。
不当解雇と判断された場合の企業の対応

裁判によって不当解雇と判定された場合、企業にはどのような対応が求められるのでしょうか。ここでは、不当解雇によって企業が負うべき責任を三つに分けて見ていきましょう。
従業員を復職させる必要がある
裁判によって不当解雇と判断された場合、解雇は「無効」となり、初めからなかったものとして解釈されます。そのため、解雇した従業員とは雇用契約が途切れずに続いている状態となります。
企業は従業員を直ちに復職させて、引続き給与を支払わなければなりません。
バックペイを支払わなければならない
不当解雇と判断された場合、解雇自体がそもそもなかったものとみなされ、無効になるまでの間も賃金が発生していることになります。そのため、企業は給与を支払わなかった期間をさかのぼって、本来受け取れるはずであった給与を全額支払わなければなりません。
これを「バックペイ」と言い、不当解雇で発生する大きなリスクの一つとして捉えられています。通常、解雇を言い渡した従業員が裁判を起こした場合、判決が出るまでには1年以上の月日を要します。
その期間の給与となると、金額面での損失は大きくなるため、解雇の判断・手続は特に慎重に進めることが重要です。
損害賠償も支払うケースがある
不当解雇の状況によっては、バックペイとは別に損害賠償の支払いを命じられることもあります。通常はバックペイの支払いによって、従業員が負った「解雇による精神的苦痛」は解消されたと判断され、企業の責任も復職とバックペイのみにとどまるケースが多いです。
しかし、従業員が精神的な苦痛を負ってしまい、バックペイの支払いでも解決が図れないと判断されれば、追加で損害賠償責任が発生する可能性もあります。例えば、「十分な証拠がないまま懲戒解雇を行い、その理由を公表して解雇された本人の名誉を損なわせた」といった事例では、裁判所の判断で実際に損害賠償責任が生じています。
ハラスメントによる労災認定について解説しています。
裁判となった場合の企業の守り方

万が一解雇をした従業員から不当解雇を訴えられた時、企業はどのように対処すべきなのでしょうか。結論から言えば、すぐに専門家である弁護士に相談することが重要です。
ここでは、弁護士に相談すべき理由やそのタイミングについて解説します。
労災相談の種類と相談先や相談ポイント等について解説しています。
弁護士に相談をするタイミング
解雇した従業員から不当解雇の主張を受けた時には、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。その理由は、万が一不当解雇と判断された時のバックペイを小さく抑えるためです。
バックペイは復職までの期間の賃金をカバーする必要があるため、解雇から月日が経過すればするほど負担が大きくなります。早い時点で弁護士に相談をすれば、裁判になる前に解雇トラブルを解決してもらえる可能性があるため、損失も小さく抑えられるでしょう。
また、リスクを防止するには、そもそも解雇前に相談をしておき、不当解雇にあたる要素がないかアドバイスを受けるのが望ましいです。
不当解雇の裁判における流れ
不当解雇を理由に従業員が裁判を起こした場合には、企業側もきちんと求められた手続を進めて対処しなければなりません。不当解雇に関する裁判は「地位確認訴訟」と呼ばれており、基本的に次のような流れで進んでいきます。
1.訴状が送達される
2.裁判所での主張
3.証人尋問
4.裁判所からの和解案の提示
5.判決
訴状が届いたら、企業側と従業員側の双方が書面で主張を出し合い、お互いの主張が済んだ段階で証人尋問が行われます。ただし、地位確認訴訟で解決を図るには長い期間がかかり、その間に解雇された従業員が新たな就職先を見つけるケースも少なくありません。
仮に不当解雇と認められたとしても、復職を希望する可能性は低いため、途中で未払い賃金の精算等を条件に和解へ至ることもあります。裁判所からの和解案を受けてもどちらかが応じない場合は、最終的に判決が下されることとなります。
不当解雇に関する裁判例

解雇に関する企業の向き合い方として、特に重要となるのは「不当解雇に該当する要素を避ける」という視点です。それには、関連する法律の論点を正しく理解するとともに、過去の事例にも触れておく必要があります。
最後に、不当解雇に関する代表的な裁判例を三つご紹介します。
事例1:電力会社A社の事例
一つめは、裁判により不当解雇の訴えが棄却されたケースをご紹介します。A社に勤務していた身体障害等級一級の嘱託社員Xが、生体腎移植手術後に入退院を繰り返し、術後3年が経過した退院後もほとんど出社しないまま解雇となった結果、不当解雇として訴えた事例です。
A社は高頻度で断続的な欠勤があった3年以上の期間と、まったく出社がなかった2か月間にわたって賃金を支給していました。しかし、その後も出社が見られなかったため、就業規則に定めた「心身虚弱のため業務に耐えられない場合」に該当するとし、予告解雇を行いました。
それに対して、X側が不当解雇であるとし、定年までの期間の生活保障を求めたのが本件のあらましです。判示では本件の解雇には相当な解雇理由が存在し、その手段も不相当なものではないことから、「解雇権の濫用にはあたらない」とし、X側の訴えを棄却しました。
事例2:ゲーム会社B社の事例
続いて、不当解雇の訴えが認められたケースについて見ていきましょう。B社に大学院卒の正社員として採用された従業員Yが、労働能率が劣り、向上の見込みがなく、積極性や協調性にも問題があったことを理由に解雇され、不当解雇として訴えた事例です。
訴えの趣旨は、Yが解雇を無効とし、従業員としての地位保全と、賃金仮払いの仮処分を申し立てたというものです。判示ではまず、B社の就業規則における解雇事由が「精神・身体の障害により業務に堪えない時」「会社の経営上やむを得ない事由がある時」極めて限定的であることが確認されます。
さらに、Yはあくまで平均的な水準に達していないだけで、著しく労働能率が劣っているとは言えないことから、「本件の解雇が直ちに有効になるわけではない」とし、解雇は無効とされました。
事例3:電気機器メーカーC社の事例
最後に、うつ病を発症した従業員の解雇が不当解雇とみなされた事例について見ていきましょう。大手電機機器メーカーCに入社した従業員Zは、激務により精神の不調をきたし、業務軽減を申し入れても受け入れられないままうつ病を発症し、休職へと至りました。
休職期間が満了したところで企業に解雇を言い渡されたところ、Zが過重な業務によるうつが原因であるとし、不当解雇を訴えたというのが本件の概要です。Zは自身の従業員としての地位の確認と、解雇後の賃金、損害賠償等を求めて提訴しました。
不当解雇の有無については、東京地裁・東京高裁ともに「解雇は無効である」とし、解雇から判決までのペイバックを行う必要があるとの見解が一致しました。一方で、損害賠償については一審と二審で裁判所の見解が一致せず、判決確定までに提訴から12年もの歳月がかかります。
東京地裁では、CがZの業務を軽減しなかったことが「安全配慮義務違反」にあたるとしました。しかし、東京高裁ではZが病気の事実をCに報告しなかったことを理由に、2割分の過失相殺を認めます。
これに対して、最高裁ではCがYの変化に気づける状況にあったとし、過失相殺を認めないものとして東京高裁に差し戻しを行いました。その結果、最終的には東京高裁により「過失相殺は認めない」「未払い賃金・休業損害の大幅な増額」という判断が行われました。
【関連記事】
安全配慮義務違反に当てはまるケースや防止策、企業のリスクと責任、等について解説しています。
まとめ
解雇は従業員に与える影響が大きいため、法律によって厳格なルールが定められています。法に適合しない要素があれば、不当解雇として企業側に大きな責任が発生するリスクもあるため、解雇の判断・手続には十分に注意が必要です。
解雇に関するルールはさまざまな法規制にまたがって決められているため、各論点を的確におさえるとともに、専門家である弁護士に相談しながら手続を進めることが大切です。
【参考情報】
2025年2月12日付 厚生労働省 「労働基準法に関するQ&A 解雇」
2025年2月12日付 厚生労働省 「労働契約の終了に関するルール」
2025年2月12日付 e-Gov法令検索 「労働契約法」
東京労働局 「しっかりマスター労働基準法 解雇編」
厚生労働省 「個別的労働紛争の調整事例と解説(9)企業秩序と懲戒 懲戒解雇の有効性」
2025年2月12日付 厚生労働省 「不当労働行為救済制度とは」
厚生労働省 「職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!」
2025年2月12日付 e-Gov法令検索 「労働基準法」
2025年2月12日付 e-Gov法令検索 「労働組合法」
2025年2月12日付 e-Gov法令検索 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
2025年2月12日付 e-Gov法令検索 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
2025年2月12日付 厚生労働省 「労働条件に関する総合情報サイト 確かめよう労働条件」