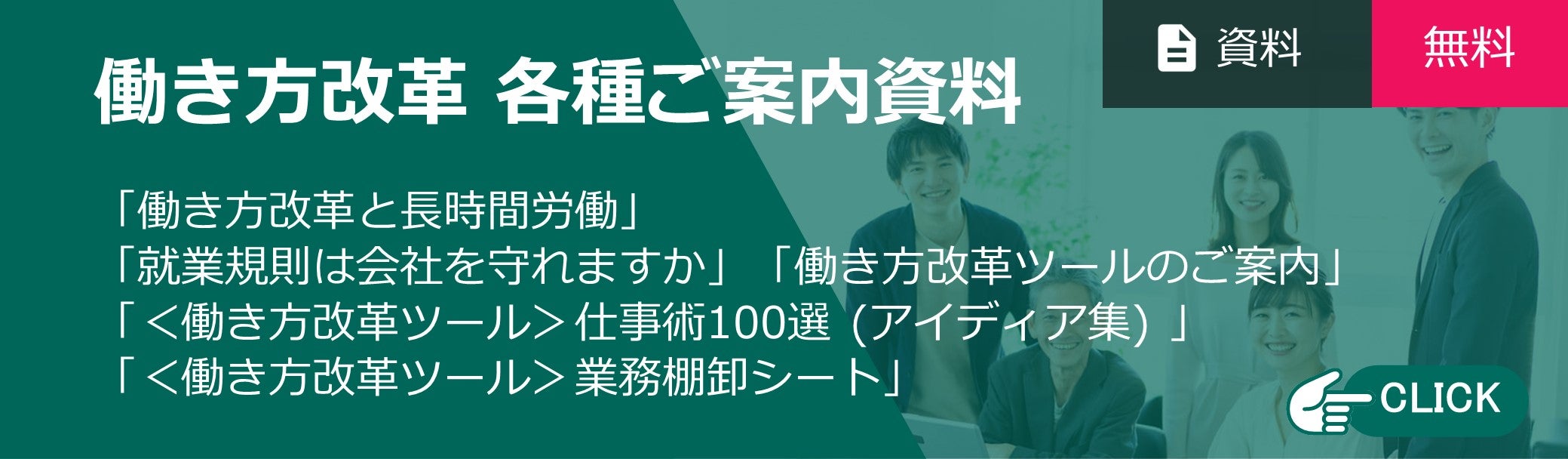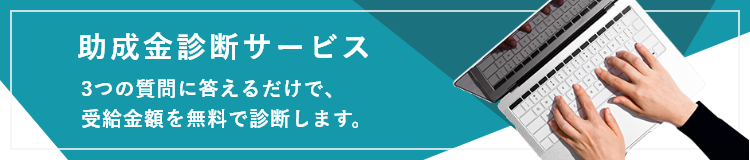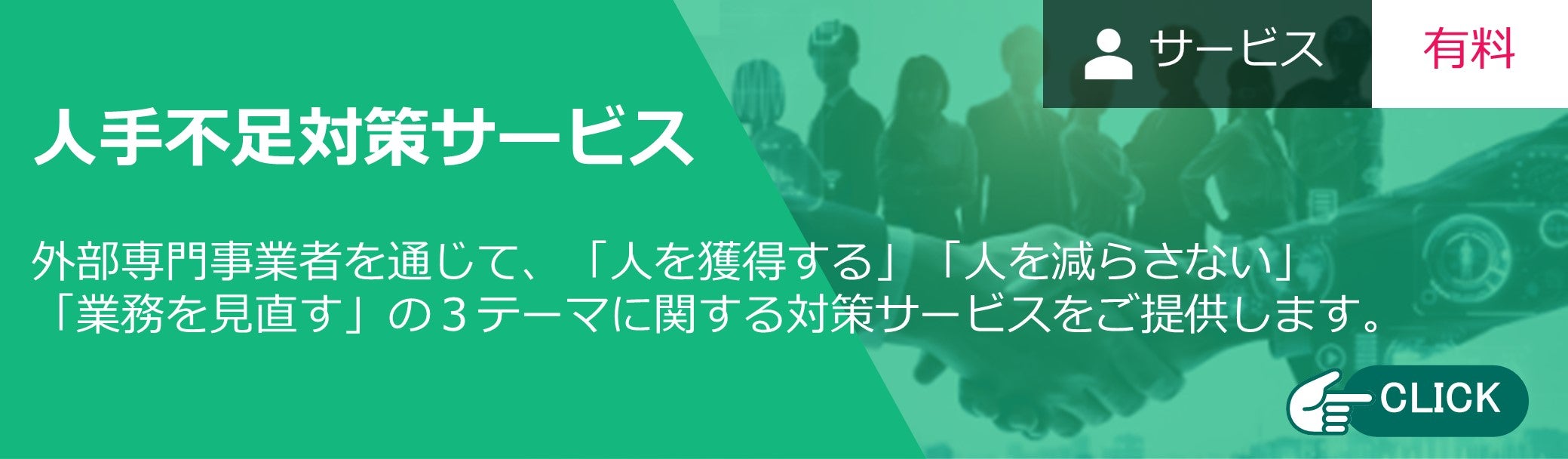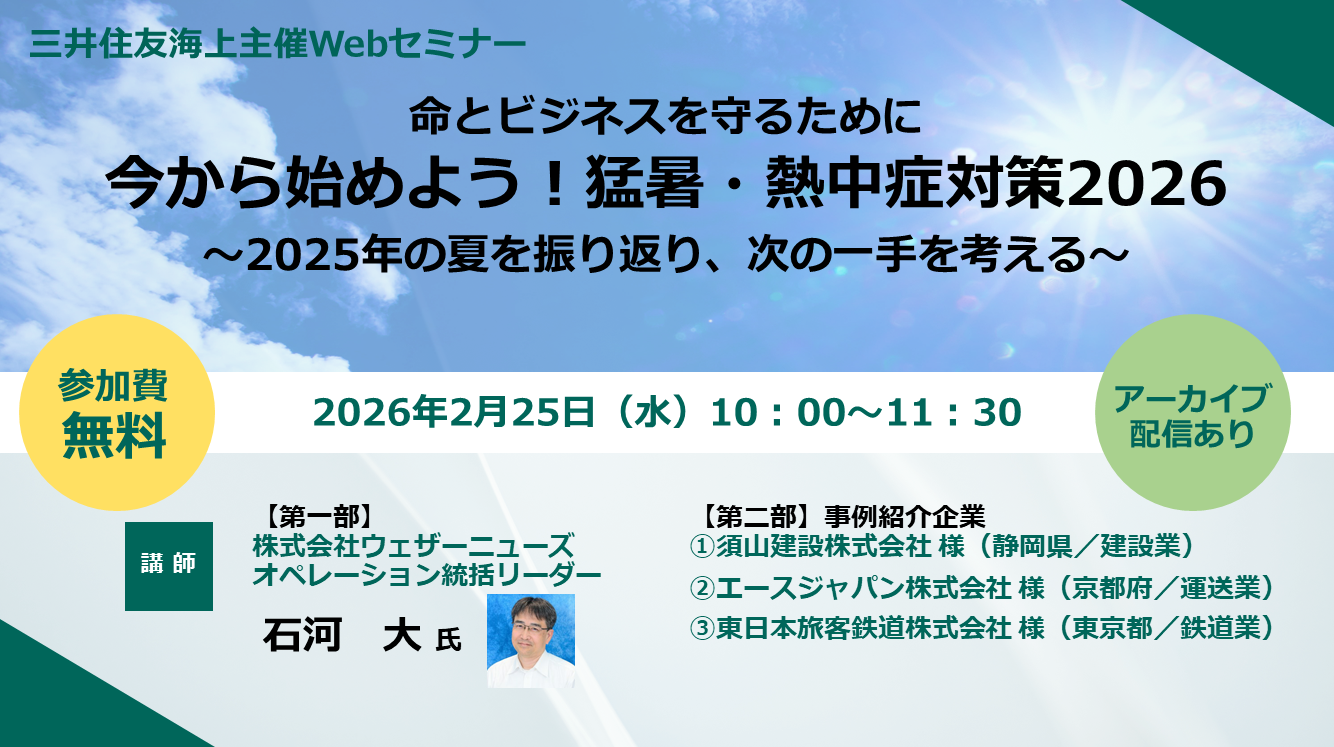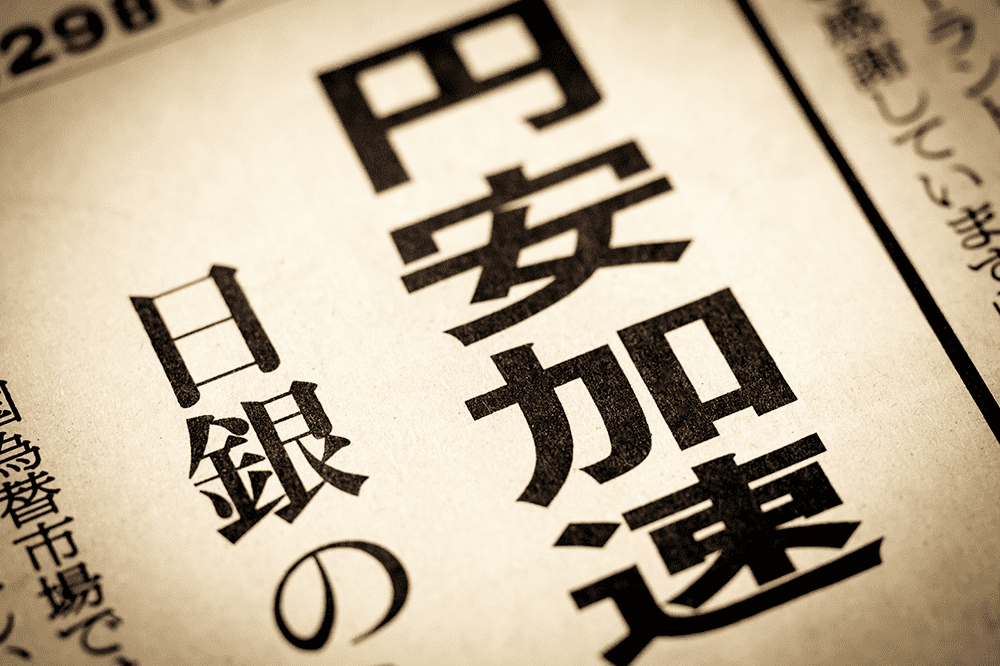働き方の多様化とは?導入するメリットと具体例を解説
公開日:2024年11月11日
人事労務・働き方改革

働き方改革やワークライフバランス向上の推進に伴い、企業における「働き方の多様化」にも注目が集まっています。生産年齢人口が減少する日本社会において、働き方の多様化は多様な人材を活用する施策として、国レベルでも重要な施策に位置付けられています。
今回は、働き方の多様化が示す意味や企業にもたらすメリット、実現するための具体的な手段について見ていきましょう。
働き方の多様化とは

働き方改革の推進に伴い、多くの企業で多様な働き方の実現を進める動きが見られるようになっています。企業や労働者を取り巻く環境は着実に変化しており、いわゆる「働き方の多様化」は、人材確保や生産性にも関わる重要なテーマになりつつあります。
ここではまず、働き方の多様化の基本的な意味について見ていきましょう。
働き方の多様化の意味
働き方の多様化とは、働く側の事情に応じて柔軟な働き方を実現することを指します。現代ではライフスタイルそのものが多様化しており、仕事に対する価値観も個人や家庭によって多種多様と言えます。
従来のように、「決まった時間にオフィスに出勤する」「既定の枠組みのなかでキャリアを形成する」といった画一化された働き方ではなく、きめ細やかなニーズに合わせた柔軟な働き方が求められているのです。その代表例として挙げられるのが、「リモートワークの普及」です。
働く場所を限定せず、状況に応じた柔軟な働き方ができることで、多様な人材を活用できるようになります。また、自由度が高まることで仕事へのやりがいを感じられやすくなり、生産性の向上にもつながっていくと考えられています。
コロナ禍を経て社内ネットワークへリモートアクセスする機会は急増し、アクセス管理に用いられるID・パスワードを狙うサイバー攻撃が増加しています。ID・パスワード管理の課題や多要素認証の概要・種類等について解説しています。
働き方の多様化が求められる理由
働き方の多様化が求められる背景には、少子化に伴う労働人口の減少が関係していると言えます。多くの業界や企業にとって、人手不足が深刻な経営課題となるなかで、働く場としての魅力ある職場づくりが求められているのです。
例えば、リモートワークや時短勤務等の柔軟な働き方が可能であれば、遠方の人材や育児・介護との両立を望む人材にも自由に活躍してもらえます。このように、多様な背景を持つ人材を活用することで、人手不足の解消だけでなく生産性の向上にもつなげていくというのが働き方の多様化の狙いです。
また、現代では終身雇用制度や年功序列が形骸化している面もあり、キャリアに対する考え方が変化しています。一つの企業で定年まで勤め上げるのではなく、キャリアアップをめざして転職を志したり、副業・兼業に挑戦したりするケースも増えているのです。
こうしたキャリア形成の多様化も、働き方の多様化につながっていると言えるでしょう。
キャリアアップ助成金の基本的な仕組み、申請条件、助成額、申請までの流れについて解説しています。
企業が働き方の多様化を推進するメリット

働き方の多様化が実現されれば、労働者はライフスタイルに応じた柔軟なキャリアを築きやすくなるなどのメリットが得られます。一方で、企業側にとってもさまざまな効果が期待できる面があります。
ここでは、働き方の多様化に伴う企業側のメリットを3つに分けて見ていきましょう。
人手不足の解消につながる
多様な働き方が可能になれば、労務環境の改善によって新たな人材を呼び込みやすくなります。働き方の柔軟性が高い会社は、求職者からすれば「ワークライフバランスを向上させやすい」「自分の個性や価値観を認めてもらいやすい」「従業員を大切にしている」といったプラスイメージを持ちます。
そのため、採用市場で競争優位性を確立しやすくなり、人手不足の解消につながるのです。また、働く人にとって魅力のある職場となれば、既存の従業員のエンゲージメントも高まり、さらなる定着率の向上も期待できます。
エンゲージメントの概要や測定方法、改善策等について解説しています。
社内コミュニケーションが活発になる
労働環境の改善や多様な働き方の実現に着手することで、さまざまな背景を持った人材が集まりやすい環境が整えられます。例えば、社内に育児と仕事を両立する女性の管理職が増えれば、同じように育児に取り組む若手の女性人材が集まりやすくなるでしょう。
その結果、社内のコミュニケーションが活発になり、組織としての団結力強化につながります。また、副業・兼業を認めれば、自社にはないスキルや資格を持った人材を確保できる機会も広がります。
新たな視点を持つ人材が加われば、社内にさまざまな変化が生まれ、コミュニケーションの質がますます高まっていくでしょう。
【関連記事】
リファラル採用の基本的な捉え方や実施手順、成功に導くためのポイント等について解説しています。
生産性を高められる
働き方の多様化は、生産性の向上にもつながります。リモートワークによる通勤時間の削減や、ITツールの活用による場所にとらわれない働き方を通じて従業員のストレスが軽減されれば、自然とモチベーションを維持しやすくなるでしょう。
そして、仕事への意欲が高まることで、業務効率や生産性が向上し、組織としての好循環を生み出しやすくなります。また、多様な雇用のあり方を受け入れれば、高度な専門性を持った人材も呼び込みやすくなり、イノベーションの土壌づくりも進みます。
多様な人材によって新たな製品・サービスが創出されれば、事業拡大による企業全体の成長にもつながるでしょう。
従業員のモチベーションが低下することの影響や具体的に改善していくための方法等について解説しています。
多様な働き方の具体例

一口に働き方の多様化といっても、具体的な取組方は企業によっても異なります。ここでは、多様な働き方につながる代表的な施策を8つご紹介します。
リモートワーク
リモートワークとは、オフィスから離れた場所で業務を行うことを指します。具体的にはICTの活用によって、オンラインでのスムーズな連携を図り、在宅勤務またはサテライトオフィス等での勤務を可能にする取組のことです。
リモートワークが実現されれば、通勤時間が削減されるため、自由に使える「可処分時間」が増えます。その結果、仕事とプライベートの両立がしやすくなるのが大きなメリットです。
また、働く場所に縛られないため、企業側にとってはさまざまな背景を持つ人材を活用できるのが利点となります。
副業・兼業
副業や兼業を認めることで、従業員は自由に収入を増やしたり、本業を足場にしながら新たな挑戦が行えたりするようになります。また、多様な経験やスキルを得るチャンスが生まれるため、キャリアの幅を広げる機会にもなるでしょう。
一方で、企業側から見ても、身につけたスキルやノウハウを本業に活かしてもらえるというメリットがあります。
【関連記事】
副業・兼業に対する変換のほか、基本的な考え方や労務管理について解説しています。
フレックスタイム制
「フレックスタイム制」とは、従業員の裁量で始業・就業の時間を決められる制度のことです。企業によって導入の仕方は異なり、例えばもっとも業務が集中しやすい時間帯は「コアタイム」として勤務を義務付け、それ以外の時間帯で自由にシフトを組んでもらうといった方法もあります。
フレキシブルな働き方ができることで、「ワークライフバランスが向上する」「生産性の高い時間帯に絞って業務ができる」といったメリットが生まれます。
時差出勤
時差出勤には、通勤ラッシュや渋滞等を避けられるという効果があります。従業員の通勤負担の軽減を望んでいても、業務の性質上リモートワークの実現が難しい場合等では、時差出勤で対応するのも有効な方法です。
短時間勤務
短時間勤務は従業員の希望に応じて、通常よりも時間を短縮して働くことを認める制度です。時短勤務とも呼ばれ、育児や介護に取り組む従業員も継続して働きやすくなります。
なお、育児・介護休業法により、3歳未満の子を養育する労働者に対しては、原則として1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務制度を整えることが事業者に義務付けられています。また、介護や育児等で一定の要件に該当する従業員から短時間勤務の申し出が合った場合も、原則として企業側が拒むことはできないとされています。
制度の整備そのものは法律で義務付けられているので、企業側としては、短時間勤務を申し出やすい環境をつくれるかどうかが重要なポイントです。具体的には、「短時間勤務による業務負担の発生を受け入れられるリソースの確保」「負担が増える従業員への配慮、手当の拡充」等が挙げられます。
【関連記事】
2024年5月に公布された「育児・介護休業法」及び「次世代育成支援対策推進法」の改正について解説しています。
勤務間インターバル
「勤務間インターバル」とは、勤務終了から翌日の出社までの間に、一定時間以上のインターバルを設けるという制度です。何らかの事情で勤務終了時刻が遅れてしまった場合には、翌日の始業時刻を繰り下げて決められたインターバルを確保します。
また、始業時刻を固定する代わりに、一定時刻以降の残業を禁止することで安定したインターバルを確保するといった方法も考えられます。いずれの場合においても、業務環境や取引状況に左右されず、労働者が必ず一定の休息時間を確保できるようにするのが目的です。
【関連記事】
労働環境改善に向け「勤務間インターバル制度」導入によるメリット、課題点や対応策等について解説しています。
業務委託
多様な人材に活躍してもらうという点では、業務委託も有力な手段となり得ます。雇用契約を結ぶわけではないため、個別の案件に応じて専門性の高い人材に業務を依頼できるのがメリットです。
ただし、業務を遂行する時間や場所、仕事の進め方等を細かく指定すると「労働者性」を有するとみなされ、トラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。
【関連記事】
委任契約と請負契約の違いや注意点について解説しています。
ジョブ型雇用制度・メンバーシップ型雇用
「ジョブ型雇用制度」とは、業務内容や責任の範囲、必要なスキル、勤務条件等をあらかじめ明確にした上で雇用を行う制度のことです。職務が明確化されることから、中途採用におけるミスマッチが起こりにくく、スムーズに必要な人材を確保しやすくなるのがメリットと言えます。
それに対して、終身雇用を前提とし、業務内容や勤務地等も限定せずに雇用契約を結ぶのが「メンバーシップ型雇用」です。先に人材を確保し、育成をしながら業務や役割を割り当てていく方法であり、従来の日本企業における基本的な雇用スタイルが該当します。
多様な働き方を実現するには、両者の雇用方法の違いを踏まえて、必要に応じて併用することも重要となります。
働き方の多様化進める上でのポイント

働き方の多様化を促進していくためには、十分な環境整備を行う必要があります。ここでは、特に重要となるポイントを3つに分けてご紹介します。
ITツールの導入と活用
業務の効率化やリモートワークの実施を図るには、ITツールの活用が欠かせません。遠隔地で滞りなく業務を進めるには、Web会議ツールやタスク管理ツール等を適切に導入する必要があります。
また、コミュニケーションを図りやすくするために、チャットツールも利用できるようにしておけると安心です。どのようなツールが適しているかは業務内容や従業員のITスキルによっても異なるため、自社の実情に合った方法を見極めましょう。
デジタル人材育成のポイントと育成方法等について解説しています。
従業員への説明
多様な働き方を認める上では、従業員への十分な説明とフォローを行う必要があります。例えば、短時間勤務を導入するのであれば、フルタイムで働く従業員に不満が生じないよう、制度の仕組みや狙いを丁寧に説明することが大切です。
その上で、実質的に負担が増加してしまう担当者については、手当等の形でフォローを行うと良いでしょう。また、リモートワークを導入する際には、勤怠管理のルールやセキュリティ上の注意点等を細かく共有しておくことが重要です。
まとめ
働き方改革の推進や仕事への価値観の変化により、「働き方の多様化」は企業における重要なテーマの一つになっています。人手不足が続く現代にあって、多様な働き方を実現できる企業は、幅広い人材を柔軟に活用できるという点で競争優位性を確立しやすくなるでしょう。
その上で、働き方の多様化につながる取組にはさまざまなアプローチがあります。適した方法は企業の状況や業務内容によっても異なるので、従業員にも意見をヒアリングしながら、自社の実情に合った施策を導入しましょう。